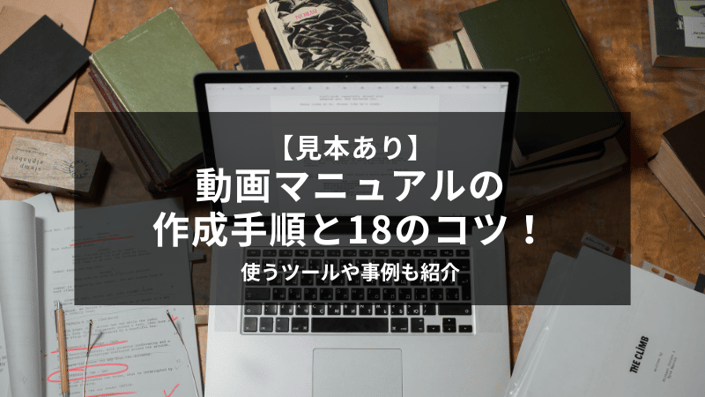

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開するtebikiサポートチームです。
この記事では、動画マニュアルの作成手順を「事例」や「サンプル動画」を紹介しながら解説します。動画マニュアルの作成~運用を数多くの業界で支援してきた私たちのノウハウを凝縮して解説しているので、より具体的で実践的な作り方が知れると思います。
本題に入る前に重要なことをお伝えすると、動画マニュアルはツールによってできること・できないことに差があります。ツールによって機能や使い勝手が大きく異なるので、最初にある程度、使用するツールの目星をつけておいた方が後々失敗せずに済む、というのが弊社の経験則としてお伝えできます。
そこで「動画マニュアル作成ツール9社の比較ガイド(pdf)」では、代表的な9ツールを徹底比較し、各社の特徴や選び方のポイントを分かりやすく解説しているので、本資料を見ながらツールを選んでおくことをおすすめします。
目次
- 1. 動画マニュアルとはどんなもの?サンプル動画で紹介
1-1. 例①:製造業で使われている動画マニュアル
1-2. 例②:サービス・小売業で使われている動画マニュアル
1-3. 例③:営業で使われている動画マニュアル
2.【見本あり】動画マニュアルの作成手順
2-1. 【一番重要】動画マニュアル作成の目的(数値目標)を定める
2-2. 動画マニュアルの活用シーンを5W1Hで整理する
2-3. 動画マニュアル化する業務の優先度をつける
2-4. 動画マニュアル作成プロジェクトの責任者を決める
2-5. 動画マニュアルの構成案/台本を作成する
2-6. 撮影に必要な機材を準備する
2-7. 動画を撮影する
2-8. 動画を編集する
2-9. 作成した動画を一元管理する
3. 押さえておきたい動画マニュアル作成「18のコツ」
3-1. 準備段階における3つのコツ
3-2. 撮影時における6つのコツ
3-3. 編集時における6つのコツ
3-4. 管理やメンテナンスにおける3つのコツ
4. 何で作るべき?動画マニュアル作成ソフト/ツールの選び方
4-1. 動画編集未経験者でも簡単に作れるか?
4-2. 必要な機能やサポートが揃っているか?
4-3. 動画マニュアルの管理もセットで行えるか?
4-4. 費用対効果が伴っているか?
5. 【無料/有料ツール別】主な動画マニュアル作成ソフト一覧と比較
5-1. 無料で動画マニュアルを作れるソフトやアプリ
5-2. 代表的な動画マニュアル作成ソフト一覧とおすすめツール
6. 動画マニュアルの作成や運用を成功させている企業事例
6-1. 業務手順を動画で標準化!作業ミスによる品質不良を9割削減:児玉化学工業株式会社
6-2. 動画マニュアル作成時間が75%削減!:タマムラデリカ株式会社
6-3. 従業員の業務品質の標準化と多能工化を実現:東急リゾーツ&ステイ株式会社 - 7. 注意点:映像制作会社への外注/代行依頼はおすすめしません
8.まとめ
動画マニュアルとはどんなもの?サンプル動画で紹介
動画マニュアルとは、「一目で業務内容や作業手順が理解できる動画」です。紙や文書マニュアルよりも分かりやすく、煩わしい文字情報を見なくともある程度の内容が把握できる点が特徴であり、動画マニュアルのメリットと言えます。
特に、複雑な業務プロセスや言語化しにくい技術解説が含まれるマニュアルは、動画マニュアルが向いています。文字よりも「実際の動き」を見たほうが理解しやすい業務が多い業界は、動画マニュアルの導入が進んでいます。
<動画マニュアルが向いている業界の代表例>
- 製造業
- 物流業
- 建設業
- 小売業・サービス業 など
そこでここからは、企業や現場で実際に活用されている動画マニュアルのサンプルを紹介します。これから動画マニュアルを作成する際の、クオリティの参考例として見てみてください。
例①:製造業で使われている動画マニュアル
まずは、製造業で使用されている動画マニュアルの一例を紹介します。
自動車部品や住宅設備等のプラスチック成形品を手掛ける製造企業である「児玉化学工業株式会社」では、現場従業員が以下の動画マニュアル「ヤスリでバリを取る業務プロセスの解説」をスマホで撮影・編集し、技術をスムーズに共有しています。
▼動画マニュアルの例:製造業▼
(音量にご注意ください)
※「tebiki」で10分で作成
一目で「何をどうすればいいか」が把握でき、文字では伝えにくい動きもすべて理解できるようになっています。
以下も併せてご覧ください。
例②:サービス・小売業で使われている動画マニュアル
続いてサービスや小売業における動画マニュアルの紹介です。
例えば、小売業の「株式会社いなげや」では、セルフレジの操作方法を動画マニュアルで解説しており、新入社員が動画でいつでも研修や手順が見られるようにしています。
▼動画マニュアルの例:小売業▼
(音量にご注意ください)
※「tebiki」で作成
このような一連の流れを文字で伝えるのは難しいですが、動画であれば動き方のイメージが分かるのでスムーズな教育が可能になります。
以下も併せてご覧ください。
>>小売業の店舗教育に動画マニュアルを活用すべき理由とは?を見てみる
例③:営業で使われている動画マニュアル
セールス活動の進め方も、動画マニュアルで教育が可能です。
例えば人材紹介等を手掛ける「テンプスタッフフォーラム株式会社」は、訪問営業の商談の進め方について動画マニュアルで教育しています。
▼動画マニュアルの例:営業▼
(音量にご注意ください)
※「tebiki」で作成
他の動画マニュアルのサンプルも見てみたい方は、「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(pdf)」で公開しています。自社での活用イメージを膨らませてみてください。
>>>「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(pdf)」を見てみる
【見本あり】動画マニュアルの作成手順
動画マニュアルの作成や運用でつまづかない動画マニュアルの作成手順について、サンプル動画も交えながら具体的にご紹介していきます。
- 【一番重要】動画マニュアル作成の目的(数値目標)を定める
- 動画マニュアルの活用シーンを5W1Hで整理する
- 動画マニュアル化する業務の優先度をつける
- 動画マニュアル作成プロジェクトの責任者を決める
- 動画マニュアルの構成案/台本を作成する
- 撮影に必要な機材を準備する
- 動画を撮影する
- 動画を編集する
- 作成した動画を一元管理する
※ボリュームの都合上、本記事には書ききれなかったノウハウや作成のコツが凝縮された資料「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」では、動画マニュアルの作成手順を画像付きで解説しています。
記事よりも見やすい内容になっているので、動画マニュアルの作成手順や導入イメージをじっくり考えたい方は以下からダウンロードしてみてください。
【一番重要】動画マニュアル作成の目的(数値目標)を定める
実はここが一番重要なのですが、動画マニュアルを作る前に、まずは「動画マニュアルによって達成したい数値目標」を定めましょう。目標設定をすることで社内や部門、チーム単位など、動画マニュアルを推進するメンバーの目線を揃えることができます。
なにより、目標が明確であればあるほど、作成すべき動画マニュアルの企画や映像のクオリティをどこまで詰めるべきかが明確になり、後の作成がスムーズに進行します。
具体的には以下のような内容です。
- 新人に対するOJTの〇割を動画に置き換える
- マニュアルや手順書作成工数を〇割削減する
- 製造現場の事故やケガを〇件まで減らす
- 業務品質を標準化させて作業ミスを〇割削減する
逆に、「動画マニュアルを〇本作る」というような「行動目標」は、目標としてふさわしくありません。行動目標は「作成自体が目的化」しやすく、本来の目的(教育改善)から逸れる失敗ケースが実態として多いからです。
例えば製造業の「株式会社アルバック」はボンディング工程の製作時間の短縮を目標に、動画マニュアルを導入しました。結果的に目標を上回る成果が出、現場全体の生産性向上を実現したのです。
東北工場でのボンディング工程の製作時間を78分短縮することができました。これは当初の目標だった九州工場の水準を上回る結果でした。1日あたりの生産可能枚数も167%となり、67%の生産向上を達成しました。
さらに、この取り組みを通じて、これまでテキストや画像のマニュアルでは十分に伝えきれなかった暗黙知やノウハウが、動画を通じて言語化・可視化されました。
※同社の動画マニュアル導入インタビュー事例はこちらをクリック
とはいえ目標が多すぎると負担の増加や優先度のバラつきが生じるため、目標は多くても1~2程度にとどめ、まずは小さく始めてみましょう。
例えば一部の部署や、一部の業務領域だけに動画マニュアルを導入する、というようなイメージです。
動画マニュアルの活用シーンを5W1Hで整理する
目標を定めたら次は、動画マニュアルの活用場面を定めます。
有名な「エビングハウスの忘却曲線」をご覧いただくと分かる通り、人は一度で見た内容を100%理解することはできず、復習を重ねていくことで初めて記憶として定着します。動画マニュアルも同様に、継続的に活用するシーンを事前に整理することがオススメです。

活用シーンを整理するためには、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)の視点で整理します。
事前に整理を行っておくことで、使用者も動画マニュアルをどのように使ったらよいか分かりやすくなるため、目標達成につながる活用を推進することが可能です。
5W1Hによる整理方法の具体例を解説しましょう。例えば、物流業や小売業でよく使われる「ロール台車」の運び方に関する業務を動画マニュアル化する場合、以下のような活用シーンが考えられます。
▼5W1Hで活用シーンを整理した例▼
|
いつ |
どこで |
誰が |
何を |
なぜ |
どのように |
|
朝礼時に |
事務所で |
新入社員が |
正しい作業手順を学ぶ |
作業ミスを未然に防ぐため |
事務所にあるタブレットで |
|
勤務開始前に |
バックヤードで |
店舗スタッフが |
チェッカー業務を確認する |
不具合対応を行うため |
備え付けのPCで |
|
作業開始前に |
現場で |
新入社員が |
ロール台車の扱い方/危険性を理解する |
誤った使い方による事故や労災を防ぐため |
社用のスマートフォンで |
このように、動画マニュアルがどのような場面で活用されるのかを整理してみてください。
5W1Hで活用シーンを考えることと並行して、そもそも「現場で使われる」ために不可欠な、「カンコツが伝わる」作業標準書の作成ポイントも押さえておきましょう。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
動画マニュアル化する業務の優先度をつける
いきなり全ての業務を動画化することはオススメしません。動画マニュアル導入に失敗するよくあるケースとして、最初から完全・完璧を目指そうとするとプロジェクトが頓挫しがちです。
したがって、動画マニュアル化しやすいもの(作成難易度が小さいもの)や、使用頻度が多いもの/作成による業務改善のインパクトが大きいもの(重要度)といった視点で、作成の優先度をつけていくことをオススメします。
具体的には、下のような表を作り、「優先1」に振り分けられた業務から動画マニュアル化してください。

動画マニュアル作成プロジェクトの責任者を決める
作成する動画マニュアルが定まったら、実際に構成案や台本を作成するステップに入ります。ここではまず、作成を先導する責任者を決めることが重要です。
「プロジェクトメンバーみんなで頑張る!」という形では、責任と権限の所在があいまいとなって作成が上手く進まないことが多いです。最初は責任者を置き、作成の段取りが形になってきたタイミングで、作成するメンバーを徐々に増やしていく形を推奨します。
責任者に置くべき人など、責任者の決め方については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも併せてご覧ください。
▼関連記事▼
マニュアルは誰が作るのが正解?新人や派遣に依頼して良いのか
動画マニュアルの構成案/台本を作成する
動画化するマニュアルや作成者が決まったら、構成案/台本を作成していきます。
構成案・台本作成の見本として、物流業や小売業等でよく扱われる「ロール台車の運び方」を例にしながら解説します。

※ロール台車のイメージ
必要な要素を洗い出す
「活用シーンを5W1Hで整理する」で洗い出したように、このマニュアルの目的は【ロール台車の扱い方/危険性を理解し、誤った使い方による事故や労災を防ぐ】ことにあります。まずは、この目的の達成に必要な要素を整理しましょう。
整理するコツとして、作業のポイントや注意点を明確にすることが挙げられます。過去に起きたミスやヒヤリハットなどを参考にするとよいでしょう。
|
必要なもの |
ロール台車 |
|
作業の流れ |
ロール台車の準備、ロール台車を移動する、ロール台車を片付ける |
|
作業のポイント |
ロール台車を使用後は必ず所定の場所へ片付ける |
|
作業の注意点 |
ロール台車が空でも移動時は1段目を開く(閉じると台車が倒れやすく危険) |
|
注意が必要な作業 |
ロール台車の一段目を閉じる、1段目を閉じた状態でロール台車を移動する |
構成案を作成する
洗い出した要素を時系列順に並べて、動画マニュアルの構成案を作成します。
構成をしっかりと固めずに撮影を進めてしまうと、編集中に「こんな素材が必要だった」「このアングルでは分からない」といった手戻りが発生することがありますのでご注意ください。
動画の長さは短く簡潔に、およそ1分程度を目安に構成を考えてみましょう。構成段階で長くなる見込みであれば、作業単位/注意点(正しい手順/NG例を分ける)といった項目で分割して作成することがオススメです。1分程度を推奨する理由は、後述の「動画の長さは1分程度にする」で具体的に解説しています。
構成案のイメージは以下の表をご覧ください。
|
カット |
工程/作業内容 |
撮影内容 |
|
1 |
オープニング |
正面から全体を撮影、今回の動画マニュアルについて説明する |
|
2 |
NG例:ロール台車の移動 |
正面から全体を撮影、台車が倒れやすいことを実演する |
|
3 |
ロール台車の1段目を開く |
正面から全体を撮影、1段目が見えやすいように意識する |
|
4 |
正しいロール台車の動かし方 |
正面から全体を撮影、どこを掴んで移動するか実演する |
台本を作成する
作成した構成案から、どこでどんなセリフやナレーションを入れるか/画像や資料を差し込むか、台本に落とし込みます。
モデル役/ナレーション役となる方は、いざ撮影するという場合に緊張してしまうケースもあるでしょう。事前にセリフを決めておくことで、安心して撮影を進められます。
また、事前に動画マニュアルのイメージを作り込むことに繋がるので、編集時の手戻りを防ぐ効果もあります。動画マニュアルの作成に慣れるまでは、しっかりと準備をした上で撮影に望むことをオススメします。
台本のイメージは以下の表をご覧ください。
|
カット |
工程/作業内容 |
セリフ |
|
1 |
オープニング |
ロールを移動/用意する時は必ず1段目を開きましょう |
|
2 |
NG例:ロール台車の移動 |
閉めた状態で移動するとロールが倒れてきてケガをしてしまいます |
|
3 |
ロール台車の1段目を開く |
必ず1段目を開いておくようにしましょう |
|
4 |
正しいロール台車の動かし方 |
【実演するのでセリフ無し】 |
撮影に必要な機材を準備する
動画の撮影には様々な機材が必要ですが、最初から全ての機材を揃える必要はありません。まずはカメラなど必要最低限を揃えて身近にあるものを活用しつつ、追加で必要だと感じた機材を後から揃えていきましょう。
動画マニュアルの目的は「業務の改善」にあるので、見栄えにこだわって高価な機材などを揃えないように気を付けましょう。その機材があることで、より伝わりやすい動画マニュアルを作れて業務改善につながるか?という判断軸は機材を準備しましょう。
最低限揃えておきたい機材は以下の4つです。
- カメラ
- 外付けマイク
- 三脚やジンバル
- 編集ソフト
具体的におすすめな製品などは、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらをご覧ください。
▼関連記事▼
【動画マニュアルの必要機材】おすすめカメラや撮影のコツも(初心者~プロまで)
動画を撮影する
準備した構成案と台本に沿って撮影を行います。撮影時には周辺環境を整えることも忘れずに準備しましょう。
例えば、工場内では機器の騒音が入ることがあり、周囲の騒音が激しいと説明のために入れた音声が聞き取り難くなるため、マイクが必要になります。
また、暗すぎたり、明るすぎたりする動画は視聴しにくいです。明るすぎる場合は明度を調整すればいいだけですが、暗すぎる場合はライトをつけて撮影しなければなりません。撮影前に撮影場所を下見しないと、撮影当日に困るため事前に確認をしましょう。動画の明るさ(彩度)を調整する方法は、別記事「動画の明るさ(彩度)を調整する方法」をご覧ください。
撮影時のコツについては、後ほど本記事内「撮影時における6つのコツ」で詳しくご紹介しているので併せてご覧ください。
動画を編集する
動画の撮影が完了し、マニュアルの素材が揃ったら編集作業を行いましょう。
以下は、動画マニュアルの編集でよく行う編集の一覧です。マニュアルで伝えたいこと、分かりやすさに応じてそれぞれ使い分けましょう。編集時のコツは、後ほど「編集時における6つのコツ」で詳しく解説しているのでそちらをご覧ください。
- 字幕の挿入
- ナレーションを入れる
- 〇や✕といった図形の差し込み
- 別の画像/動画の差し込み
- 不要な映像のカット
- 映像の一時停止
ここまでの手順を踏まえて作成された、サンプルの「ロール台車の運び方」の動画マニュアルは以下になります。短い動画ながらも、誤った手順/正しい手順が共に理解できるわかりやすい動画マニュアルに仕上がっています。
▼サンプル動画:ロール台車の運び方▼
※音量にご注意ください
※「tebiki」で作成
他の動画マニュアルのサンプルも見てみたい方は、「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(pdf)」で公開しています。自社での活用イメージを膨らませてみてください。
>>>「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(pdf)」を見てみる
編集のコツは、後述する『撮影時における6つのコツ』で詳細に解説しているので、ぜひご覧ください。
動画マニュアル作成はここまでで一旦完了ですが、管理体制も運用において非常に大切な要素です。次のステップでは、作成した動画マニュアルのオススメ管理方法について解説していきます。
作成した動画を一元管理する
動画マニュアルは作って終わりではありません。
事前に設定したような活用シーン通りに運用できる管理体制を整え、目標を達成できるかが一番大切です。実際、過去に動画マニュアルの運用がうまくいかなかった現場では、この管理~運用面で課題を抱えていました。
結論、動画マニュアルの管理には「動画の管理機能が備わっている動画マニュアル作成ツール」の使用がオススメです。その理由として、現場教育のヒントを発信する情報メディア「現場改善ラボ」が実施した【動画マニュアル内製化の実態調査(N=100)】にて、「動画マニュアルの作成がうまくいかなかった理由」で1番多かった回答が「動画の管理がうまくいかなかった」だったからです。
具体的な失敗例としては、『動画のデータ量が大きくすぐ保存上限に達する』『フォルダ管理が難しくて探せない』『バージョン管理ができない』といったものが挙げられました。
また、管理がうまくいかなかった方の管理方法を見てみると、70%の方が「社内サーバー」を使用している実態も明らかになりました。そのため、動画マニュアルを一元管理する方法として、社内サーバーはオススメできません。
『ならYouTubeを活用すればいいのでは?』と感じる方もいらっしゃると思います。多くの動画をアップロードできる、字幕の翻訳ができるメリットがある一方、以下のデメリットがあるため会社の動画マニュアルを管理する方法としては向いていません。
- 広告が表示されるため業務に適さない
- 教育の管理ができない
- セキュリティ上のリスクがある
動画マニュアル運用でYouTube活用をするメリットとデメリットは、別記事「YouTubeで動画マニュアルは運用できる?メリットやデメリット、留意点などをご説明」でより詳しく解説しています。
押さえておきたい動画マニュアル作成「18のコツ」
ここまで、動画マニュアルを作成する流れを具体的に解説してきました。
繰り返しになりますが、動画マニュアルはただ作成することが目的ではなく「誰が見てもわかりやすく内容が理解できる」状態にすることが重要です。ここからは、誰が見てもわかりやすいと感じられる動画マニュアルを作るコツを、段階別に計18個ご紹介します。
※ボリュームの都合上、本記事には書ききれなかったノウハウや作成のコツが凝縮された資料「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」では、動画マニュアルの作成手順を画像付きで解説しています。記事よりも見やすい内容になっているので、動画マニュアルの作成手順や導入イメージをじっくり考えたい方は以下からダウンロードしてみてください。
準備段階における3つのコツ
「動きがあるからこそ伝わる業務」から作成する
紙マニュアルで伝わっている業務まで動画マニュアルにする必要はありません。必要に応じて紙と動画を組み合わせて効率的にマニュアルを作成しましょう。
例えば以下の動画は、物流企業である「株式会社近鉄コスモス」が作成した「正しいハンドリフト操作の解説動画」ですが、言語化が難しいこのような動きも映像でシンプルかつ分かりやすい内容になっています。
▼ハンドリフトの操作を解説する動画マニュアル(音量にご注意ください)▼
※本動画は「tebiki」で作成されています
ハンドリフト操作という細かい工程に焦点をあてた動画マニュアルとなっており、たった40秒で説明が完結しています。
「何を知って欲しいのか」を意識しながら構成を考える
紙マニュアルの課題と各動画のシーンで何をわかって欲しいのかを意識すると、全体構成や撮影アングルなどが浮かんできます。
モデルは「人材育成の中心者」にする
誰がモデル役にふさわしいかの判断は、「人材教育の中心となっている1人のトレーナー」です。
業務に癖がある方を選抜してしまうと、トレーニーはその癖をそのまま引き継いでしまいます。モデル役の選抜には細心の注意を払いましょう。
撮影時における6つのコツ
手ブレしないようにカメラを持つ
カメラを手で持って撮影をする場合、脇を締めて腕や手が揺れないように持つのがコツです。もしくは三脚を利用すると安定した状態で撮影ができます。
食品スーパーのいなげやでは、動画マニュアルの撮影時に三脚を使用しているとのこと。手ブレがなくなり「見る側のストレスが無くなったと思います」とお話しくださいました。ブレがある動画マニュアルは注目すべき点が分かりにくいだけでなく、使用者の集中も削ぐような要素となります。
いなげやの動画マニュアル導入経緯から導入効果については、以下のインタビュー記事をご覧ください。
▼関連記事▼
小売業の動画マニュアル導入事例 | スーパー133店舗の現場で動画を活用。レジ打ち、接客時の応酬話法、クレジットカード運用など教育をスピーディに実施。
カメラのズーム機能は使わない
作業をしている手元の動きなど拡大して伝えたい場合は、カメラをズームするのではなく、自分の身体/カメラを撮影対象に近づけて撮影するようにしましょう。全体の様子を伝える「引き」の映像、伝えたい部分に注目させる「寄り」の映像、この2つを使い分けることがコツです。
ズーム機能を使うと、手の小さなブレでも映像には大きなブレで残ります。また、ズームをすればするほど画質が荒くなり、撮影対象が見えにくくなるため動画マニュアルの撮影には使わないことを推奨します。
画質は720pでも十分
1mm単位の緻密な作業を動画マニュアルにする場合は別ですが、問題ない場合は動画のファイル容量を下げるために、720pで撮影するのがおすすめです。
4Kなど、容量が重たい動画では再生や保存、取り回し等が大変です。なるべくファイル容量は小さくしましょう。
▼関連記事▼
・スマートフォンで動画撮影:画質設定 720pと1080pの違い
アングルを変えて何度か撮影する
作業全体の流れを説明したいときは「引き」、細かな手元の作業を説明したいときは「寄り」にすると、見る側が理解しやすいので、撮影時はこの「引き」と「寄り」を意識しましょう。
当たり前な手順も撮影する
動画作成者からすると、当たり前に感じることも動画マニュアルに盛り込むことをオススメします。特に新人教育向けの動画マニュアルでは、経験者が知っていて当たり前のことも知らないケースが多いです。
初めて作業をする人でも、動画マニュアルを見ながら1人で作業ができるように視聴者目線で作成することがコツです。
あえてNG例も盛り込む
「マニュアル=正しい手順のみを盛り込む」と考えがちですが、動画マニュアルでは正しい手順だけでなく、あえて誤ったNG例を盛り込むことで、よりわかりやすく動画になります。
正しい業務のやり方と併せて、正しくない業務のやり方も撮影し、少し大げさに事故を起こしてしまった動画を見せることで、社員に危機意識が芽生えマニュアルを遵守しようという心がけが生まれます。
例えば工作機械の製造販売を行う「新日本工機株式会社」では、動画マニュアルで「現場あるあるなミス」をNG例として先に見せたうえで正しい手順の動画を見せることで、正しい手順/NG手順どちらの理解も促しています。
▼例:NG作業手順を解説する動画マニュアル▼
※「tebiki」で作成
同社のような製造業では、動画マニュアルの導入が特に増えています。詳しくは、「製造業における動画マニュアル活用事例集(pdf)」をご覧ください。記事では紹介していない、製造業における動画マニュアルの活用イメージや事例がまとめられています。
>>>「製造業における動画マニュアル活用事例集(pdf)」を見てみる
編集時における6つのコツ
動画の長さは1分程度の短さに
長い動画マニュアルを作っても途中で長いと飽きられて、見られなくなってしまう可能性があります。
長い動画の場合は、内容にメリハリをつけて、注目して欲しい箇所とそうでない箇所の緩急をつけて視聴に集中してもらう工夫が必要であり、動画マニュアル作成の初心者にはハードルが高いです。
また、業務の一部変更によって業務全体の動画マニュアルを撮影し直さないといけなくなる場合がありますので、動画が長いとその分撮影し直す長さも長くなります。そのため、動画の長さは1分をおすすめしています。
総合建設業である株式会社安藤・間では、「可能な限り短く、シンプルに」ということを意識して動画マニュアルの作成を行っています。その結果、わかりやすいマニュアルを作成でき、時間を取られていた問い合わせ対応業務が約7割削減されたそうです。
安藤・間の動画マニュアル導入経緯から導入効果については、以下のインタビュー記事をご覧ください。
▼関連記事▼
動画マニュアル導入事例 │「利用者からの問合せ」や「新システムの普及展開」に関わる工数を8割削減!
※ちなみに同社が導入した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、動画の分割機能が備わっています。大きな作業工程を動画におさめたあと、ひとつひとつ小さく分割して動画マニュアル化する、という簡単かつ効率的な作業が可能です。
見栄えにこだわりすぎない
動画=テレビ番組やYouTubeのように高品質なものをイメージするかもしれませんが、動画マニュアルにおいては高品質よりわかりやすさの方が優先です。
見栄えにこだわっていると、いつの間にか動画を作ること自体が目的となり、相手に伝わるかどうかが抜けてしまうケースがあります。動画の見栄えは、シンプルでわかりやすければ十分です。デザインや見栄えに時間をかけるよりも、マニュアルの内容を充実させることに時間をかけることをオススメします。
▼関連記事▼
新人教育マニュアルの作り込みすぎに注意!「相手に伝わるか」で作成時間を決める
テロップ・字幕は簡潔にする
テロップはポイントごとの要約的な短文がおすすめです。長文のテロップにすると、動画で伝えたい動きに集中し難かったり、動画が見え難くなることがあります。
テロップでは新人が見ても理解できるように、専門用語を用いないようにすることもコツです。
テロップや字幕を入れる作業は基本的に手間がかかりますが、動画内で動画マニュアル作成ツールであれば、非常にスピーディに作業を進められます。
ちなみに「tebiki現場教育」は、動画の撮影中に収録された音声から自動で字幕を生成するので、編集者は誤字脱字の修正、表示位置の調整をするだけで作業が完了します。
もし、機械音が大きい製造現場のように、音声を入れづらい撮影環境の場合は、編集時に音声収録をすることでナレーションを上書きすることが可能です。実際の動作は映像で見せつつ、ポイントはナレーションで補足する使い方もできます。
ナレーションを入れる
テロップを簡潔にする代わりに、ナレーションで作業内容を補足します。これによって、動きのある業務は目で視覚的に理解し、補足情報は耳で理解できる質の良い動画マニュアルが作成できます。
音声のポイントとして、きれいに録音する/滑舌よくシンプルに話す/抑揚をつけるといったことが挙げられます。
介護老人福祉施設を展開している社会福祉法人若竹大寿会では、ナレーションとテロップをうまく活用し、情報量が多い動画マニュアルを作成しています。実際の動画マニュアルが見たい方は、以下からご覧ください。
注目箇所は矢印や一時停止で目立たせる
長くなってしまった動画にはメリハリをつけないと、集中して視聴してもらえません。図形やスタンプ等を用いて、情報を強調・補足するような動画マニュアルが作れるとより良いです。
また、外国人従業員が多い職場の場合、用いる記号はチェックマークや✕といった、言葉や文化の違いがあっても意味がわかるものを使用しましょう。例えば正しい手順にはマル、間違った手順にはバツなど、動画に図形を挿入することで簡単に見やすい動画マニュアルが完成します。その動画例を以下に掲載します。※実際に企業で活用されている動画マニュアルです。
▼記号を使った動画マニュアルサンプル▼
(音量にご注意ください)
※「tebiki」で作成
動画だけでなくドキュメントも残す
後ほど「動画マニュアルより紙マニュアルが効果的なケース」でもご紹介していますが、状況によっては文字ベースのマニュアルも併用した方がいい場合もあります。とくに動画マニュアルの導入したてのタイミングは、従来の形式に慣れていた社員から抵抗が起こりやすいです。
動画マニュアル活用を進める際は、最初からすべて動画化するのではなく、ドキュメントを併用しつつも「動画マニュアルを見なくてはいけない仕組み」を整えることで、触れる機会を設けて徐々に慣れさせていくことがコツです。
管理やメンテナンスにおける3つのコツ
動画マニュアルの保管先は統一する
各動画マニュアルの保管先がバラバラだと、動画マニュアルを見つけるのが手間に感じ、自分のパソコンに動画ファイルを複製して保管する社員が現れ始めます。
各社員のパソコンに動画が保管されると、動画マニュアルが更新されても気づかずに古い動画マニュアルを見続けて、作業ミスを誘発する恐れがあります。
常に特定の場所に最新のマニュアルを保管し、アクセスしやすくすることで、古いバージョンの動画マニュアルを見て、間違った作業をしてしまうのを防ぐことができます。
※「tebiki現場教育」は、作成した動画マニュアルはすべて同一サーバー上に保管されるうえに、アップロードの制限は一切ないので、社内サーバーを圧迫することなく動画マニュアルの量産が可能です。
動画ファイルの保管先はフォルダで通知
動画ファイルの保管先を社員に通知する時におすすめなのが、保管先をファイルパスではなく、ファイルパスでの通知です。
ファイルから動画マニュアルへたどってもらえば、更新通知に気づかなくても、どれが最新の動画マニュアルか確認してからアクセスしてもらうことができ、古いバージョンの動画マニュアルを見られてしまう可能性がぐっと下がります。
更新時は古い動画ファイルの扱いに留意
更新の連絡に気づかなかった社員がリンクで動画ファイルにアクセスしていると、古い動画マニュアルを見続けてしまう可能性があります。
そのため、古いバージョンの動画マニュアルは削除するかファイル名を変更する、または保管先を変更するなどの対応が必要です。
おすすめなのは、最新の動画ファイルの名前を常に一定にして、古いバージョンの動画マニュアルのファイル名を変更する運用です。社員が更新に気づかなくても、動画マニュアルに直リンクで見ていても、常に最新の動画マニュアルに自然とアクセスされます。
ここまで動画マニュアル作成時のコツを段階別にご紹介しました。『数が多い…』と感じたかもしれませんが、適切な動画マニュアル作成ソフトやツールを用いることで、ご紹介した作成/運用のコツをかんたんに反映することができます。
次章では、動画マニュアル作成ソフトやツールの選び方をご紹介します。
何で作るべき?動画マニュアル作成ソフト/ツールの選び方
動画マニュアル作成ソフトとは、一般的な動画編集ソフトよりも手間なくマニュアル動画を制作できるツールです。
動画マニュアル作成ソフトの場合、ビジネスシーンの使用において必要な機能が厳選され、シンプルな操作性を実現できているため、わかりやすい動画マニュアルの作成を手助けする存在になります。
本章では動画編集の工程など、動画マニュアルを作る手段であるソフト/ツールの選び方を詳しくご紹介します。主に、以下の4つの視点で動画マニュアル作成ソフト/ツールを選ぶことをオススメします。
- 動画編集未経験者でも簡単に作れるか?
- 必要な機能やサポートが揃っているか?
- 動画の管理もセットで行えるか?
- 費用対効果が伴っているか?
ツールによって機能や使い勝手が大きく異なるので、最初にある程度、使用するツールの目星をつけておいた方が後々失敗せずに済みます。
そこで「動画マニュアル作成ツール9社の比較ガイド(pdf)」では、代表的な9ツールを徹底比較し、各社の特徴や選び方のポイントを分かりやすく解説しているので、本資料を見ながらツールを選んでおくことをおすすめします。
動画編集未経験者でも簡単に作れるか?
動画マニュアルをメインで作るのは、基本的にはマニュアル化する業務の理解/知見が深い人を推奨しています。
なぜなら、業務に知見がある人の方が編集時に強調すべき点を動画マニュアルに落とし込めるからです。そのため、動画編集をしたことがない方でも、直感的に操作ができるソフトか事前に確認しましょう。
「社内に動画編集できる人がいるから任せていいのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、作成者が属人化すると業務負荷が特定の人に集中する弊害が生じます。そのため、動画マニュアルは誰でも作れるように未経験者でも操作が簡単なツールを選びましょう。
▼関連記事▼
マニュアルは誰が作るのが正解?新人や派遣に依頼して良いのか
必要な機能やサポートが揃っているか?
動画マニュアル作成や管理を行う上で、自社が取り組みたいことによって必要な機能が変わってくるでしょう。
特に、はじめて動画マニュアルを作る方は、運用支援もサポートしてもらえるような体制があると安心です。自社にとってどんな機能が必要か?それを叶えられるソフト/ツールはどれか?という視点で選びましょう。
参考として、別記事「動画マニュアル作成ソフト14選を比較!無料ツールや事例も解説」でご紹介している、機能面の比較項目を以下に記載します。
- 動画マニュアルのアップロード本数に上限はあるか?
- 数百本近く作成したときの検索性はどうなるか?
- 公開範囲を設定できるか?
- 更新したら、バージョン管理ができるか?
- 動画マニュアルの閲覧状況を可視化できるか?
- オフライン環境下でも閲覧できるか?
- 早送りやスロー再生ができるか?
- 5秒スキップなど見たい作業をピンポイントで見返せるか?
- アフターフォローの回数や期間はどれくらいか?
動画マニュアルの管理もセットで行えるか?
先ほど「作成した動画を一元管理する」でご紹介したように、動画マニュアルは作って終わりではなく、管理体制も整えることで効果的な運用が実現できます。ぜひ、ソフト/ツールの選び方でも管理面の機能に注目しましょう。
特に「動画のアップロード本数の上限」や「管理画面の分かりやすさ」に注目することをオススメします。
費用対効果が伴っているか?
動画マニュアル作成に特化したソフトやツールを導入する場合、金銭的なコストが発生します。単純なツールの費用が高い/低いで判断するのではなく、想定される導入効果と照らし合わせて確認をしましょう。費用対効果をシミュレーションする場合、以下のような要素で洗い出すことをオススメします。
- 新人に対する教育工数:〇時間/月
- 社内問い合わせ対応:〇時間/月
- 紙や文書マニュアルの作成工数:〇時間/月
上記のような業務に割かれている人件費を掛け合わせることで、動画マニュアル作成ツール導入による費用対効果を簡易的にシミュレーションできます。また、上記の時間を価値を生む活動に集中できていた場合の売上も、機会損失コストという形で洗い出すことで、より精緻な費用対効果を洗い出せます。
ツールやソフトの選び方が分かったところで、次は「代表的な動画マニュアル作成ソフトの一覧」を紹介します。
>>動画マニュアルが作れる!無料の動画編集ソフト比較表を見てみる
【無料/有料ツール別】主な動画マニュアル作成ソフト一覧と比較
先ほどご紹介した動画マニュアル作成ソフト/ツールの選び方を踏まえて、ここからは具体的な作成ソフトの一覧と比較をしていきましょう。無料/有料ツール別にご紹介します。
無料で動画マニュアルを作れるソフトやアプリ
まずは無料で動画マニュアルを作れる手段をご紹介します。無料ツールは複数あるので比較が大変です。そこで、代表的な無料ツール一覧の特徴や使い勝手を1枚にまとめた比較表(pdf)をご覧ください。以下からダウンロードが可能です。
>>動画マニュアルが作れる!無料の動画編集ソフト比較表を見てみる
無料ソフト・ツールの場合、機能面が限定的/作成者が属人化しやすい/管理~運用面の課題を解消できないことは念頭に置いておきましょう。
今回は動画マニュアル作成で使える、代表的な無料ソフト/アプリとして以下の4つをご紹介します。
- パワーポイント/Googleスライド
- Zoom
- Windowsフォトアプリ(Microsoftフォト)
- iMovie
パワーポイント/Googleスライド
皆さんも身近でお使いになっているパワーポイントやGoogleスライドを使うと、比較的簡単に動画マニュアルの作成が可能です。プレゼンテーション形式で収録することで、簡易的な動画マニュアルを作成することが可能です。
パワーポイントで動画マニュアルを作成する手順は、資料「パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順(pdf)」で解説しています。2分の解説動画もついているので、本資料を参考にしながら動画マニュアルを作るのも1つの手でしょう。
>>>「パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順(pdf)」を見てみる
Zoom
パワーポイントやGoogleスライドを活用し、Zoomで収録をすることで研修動画の整備が可能です。Zoomによる収録方法は以下の記事で詳しく解説しています。
▼関連記事▼
Zoomを活用してパワーポイントのプレゼンを録画する方法
Windowsフォトアプリ(Microsoftフォト)
Windowsフォトアプリを活用することで、撮影した動画を編集することが可能です。(Windows11をお使いの方は「Microsoftフォト」です)基本的な動画のカットやスローモーション、字幕作成など、動画マニュアル作成に必要最低限な機能が揃っています。
Windowsフォトアプリを活用した動画編集方法は、以下のページで具体的に解説しています。
iMovie
iMovieもWindowsフォトアプリ同様に、動画マニュアル作成に必要な機能が揃っているソフトです。iMovieを活用した動画編集方法は、以下のページで解説しています。
代表的な動画マニュアル作成ソフト一覧とおすすめツール
動画マニュアルの作成や管理が行える代表的なツールは以下の10個です。
- tebiki
- VideoStep
- VideoTouch
- ABILI Clip
- Teachme Biz
- COCOMITE
- Dojo
- トースターチーム
- viaPlatz
- shouin+
参考記事:動画マニュアル作成ソフト14選を比較!無料ツールや事例も解説
これだけ多いと、どれを選んだらいいか迷ってしまうと思います。そこで「動画マニュアル作成ツール比較ガイド(pdf)」では、上記を含む代表的な動画マニュアル作成ツールを徹底比較し、各社の特徴や選び方のポイントを分かりやすく解説しているので、本資料を見ながらツールを選んでおくことをおすすめします。
動画マニュアルの作成や運用を成功させている企業事例
ここからは、動画マニュアルの作成や運用を成功させ業務改善を進めている企業事例を3社ご紹介します。今回ご紹介している事例は、全て現場教育システム「tebiki」を活用しているケースです。
『より多くの動画マニュアル活用事例』を見たいという方には、さまざまな活用成功事例を1冊に凝縮した以下のガイドブックも併せてご覧ください。
>>tebikiを用いた「動画マニュアルによる業務改善事例集」を見てみる
業務手順を動画で標準化!作業ミスによる品質不良を9割削減:児玉化学工業株式会社
児玉化学工業株式会社は、プラスチック材料を活用した住宅設備や自動車向けの設備を製造している会社です。製造現場で動画マニュアルを活用したことで、業務手順が従業員に理解されやすくなり作業ミスによる品質不良が9割削減しています。
▼インタビュー動画:児玉化学工業株式会社▼
|
動画マニュアル活用前の課題 |
動画マニュアル活用後の効果 |
|
・紙のマニュアルや手順書では作業内容が伝わらない |
・作業を視覚的に伝えられ作業ミスが大幅に減る |
児玉化学工業株式会社の具体的な動画マニュアル活用事例を知りたい方は、以下のインタビュー記事を併せてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
手順書作成の工数は紙の1/3になったと思います。動画で作るのはかんたんだし、学ぶ側にもわかりやすいですよね。
動画マニュアル作成時間が75%削減!:タマムラデリカ株式会社
タマムラデリカ株式会社は、大手コンビニエンスストアの専門工場として食品の開発製造を行う会社です。教育改善を目的に動画マニュアル活用に取り組む中、tebikiを活用したことで動画マニュアル作成時間が従来の75%まで短縮しています。
▼インタビュー動画:タマムラデリカ株式会社▼
|
動画マニュアル活用前の課題 |
動画マニュアル活用後の効果 |
|
・動画編集ソフトは作業が難しく作成が追い付かない |
・tebiki活用で動画作成が1時間⇒15分に短縮 |
タマムラデリカ株式会社の具体的な動画マニュアル活用事例を知りたい方は、以下のインタビュー記事を併せてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
動画マニュアル作成時間が75%削減!教育体制を強化し、お客様に喜ばれる商品を提供したい
従業員の業務品質の標準化と多能工化を実現:東急リゾーツ&ステイ株式会社
東急リゾーツ&ステイ株式会社は、ホテルやゴルフ場、別荘地など全国100を超えるレジャー施設を運営している会社です。動画マニュアルを活用することで、各従業員の業務品質を標準化しつつさまざまなオペレーションを1人がこなせる状態を目指し、働き方改革実現に向けた環境を整えています。
|
動画マニュアル活用前の課題 |
動画マニュアル活用後の効果 |
|
・業態や従業員ごとにサービスレベルのバラつきがあった |
・業態や施設ごとにことなっていたマニュアルを統一化 |
東急リゾーツ&ステイ株式会社の具体的な動画マニュアル活用事例を知りたい方は、以下のインタビュー記事を併せてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
従業員数2,500人超・全国100を超える施設で業務の平準化と多能工化を推進。
ここまで、内製化を前提とした動画マニュアルの活用についてご紹介してきました。皆さんの中には『手間がかかるから外注や代行のほうがいいかも?』とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし私たちは、動画マニュアルの作成を映像制作会社に委託することは適さないと考えています。次章ではその理由について詳しくご紹介します。
注意点:映像制作会社への外注/代行依頼はおすすめしません
動画マニュアル制作の外注や代行をおすすめできない理由として、大きく以下の3つが挙げられます。
- 動画化する作業のコツやポイントを作業者以外は正しく伝えられない
- 完成した動画マニュアルが現場で実際に役立つまでには改善が必要
- 作業手順に変更があった際に追加コストが発生する
自前で内製すると手間がかかるデメリットはあるものの、上記のような外注/代行のデメリットと比較すると小さいものといえます。
また、動画マニュアルの内製で取り組むか、外注で取り組むかの比較ポイントの1つがコストです。映像/動画制作会社に外注する際、費用項目は企画/制作/編集の3つに大きく分けられます。
動画マニュアルの場合、合計すると30万円~50万円を予算相場と見ておくとよいでしょう。これは一般的な動画マニュアル作成ツールの月額と比較しても高い部類といえるため、費用対効果が出しにくいと私たちは考えています。
これらの観点から、自社の業務改善につなげるための動画マニュアル作成には、内製化で改善を重ねていくことが大切で、費用対効果も出しやすくなります。
▼関連記事▼
・動画・映像制作会社の料金相場|費用を抑えるポイントもまとめ
今回の記事では、初心者でも失敗しない動画マニュアル制作ノウハウについて、数々の動画マニュアル運用を支援してきた私たちtebikiのノウハウを凝縮してご紹介しました。
動画マニュアルには、現場のノウハウを見える化できる、短時間で理解できる、外国人スタッフでも理解しやすいといったメリットがたくさんあります。記事内で解説した動画マニュアルの作り方やコツ、ツールの選び方を参考にすれば、現場で活用されるわかりやすい動画マニュアルを作成できます。
また、tebikiには、動画編集だけでなく、社内共有にも便利な機能が備わっています。動画マニュアルの作成に役立つtebikiを活用し、動画マニュアルを作成してみてはいかがでしょうか。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。




