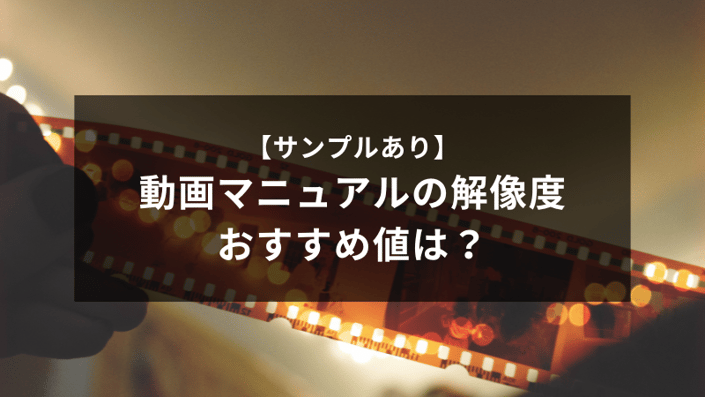
目次
- 1. 動画マニュアルの最適な解像度は?
1-1. 「高画質であれば良い」は間違い!その理由とは
1-2. 動画解像度の選び方は「用途」で決める
1-3. 代表的な動画解像度一覧
1-4. 動画を見て「720p」と「1080p」の違いを確認
2. 実際に企業で活用されている動画マニュアルをチェック
3. 動画の解像度を設定する方法
3-1. iPhoneの場合
3-2. Androidの場合
4. 撮影した動画の解像度の調べ方
5. 720pと1080pの動画容量はどれくらい?
6. 保存容量を気にせず簡単に動画マニュアルを作るなら「tebiki」
6-1. 動画の容量や本数の制限なし
6-2. スキルがなくても動画編集できる
6-3. そのほか、翻訳機能や教育管理機能も搭載で使い勝手抜群!
7. tebikiによって動画マニュアルを作成/運用した事例
7-1. 株式会社GEEKLY
7-2. 株式会社ハングリータイガー
7-3. サラヤ株式会社
8. そもそも動画の解像度とは?
8-1. 「解像度」と「動画サイズ」の違いは?
8-2. よく見る「p」ってどういう意味?
9. まとめ
動画マニュアルの最適な解像度は?
動画マニュアルの最適な解像度は、HD(High Definition)画質と呼ばれる1280p×720pがおすすめです。
動画マニュアルは、映画のような美しい映像にする必要はありません。かといって、画面が粗くぼやけてしまうようでは、マニュアルとして成り立ちません。動画マニュアルの視聴は、タブレット/スマートフォン/パソコンなどの端末で行われることが多いため、これらの端末できちんと見られるレベルの1280p×720pの解像度がおすすめです。
解像度について知りたい方は、後述する『そもそも動画の解像度とは?』をご覧ください。
「高画質であれば良い」は間違い!その理由とは
一般的に、高画質は1920p×1080pのフルHD以上を指すことが多い。「1280p×720pよりも高画質であればいいだろう」と必要以上に高解像度で撮影した場合、次のようなデメリットが生じます。
動画がスムーズに再生できない可能性がある
高画質の動画はデータ量が大きくなるため、端末が動画を読み込むのに時間がかかってしまい、スムーズに再生できないおそれがあります。
視聴環境によって高画質で再生できない可能性がある
高画質の動画はデータ量が多いため、通信環境によっては再生できないか、もしくは低画質での再生になる可能性があります。また、データ量が多いと通信量を多く消費するというデメリットも生じるでしょう。
動画の書き出しやアップロードに時間がかかる
動画の編集におけるデメリットです。高画質の動画は、編集ソフトによってはデータ書き出しやアップロードに時間がかかる可能性があります。
保存容量が大きく、ストレージを圧迫する
高画質になると保存容量が大きくなり、サーバーやクラウドのストレージを大きく圧迫するおそれがあります。その結果、ストレージ増設による余計なコストがかかってしまうかもしれません。
動画解像度の選び方は「用途」で決める
集合研修などで大きなスクリーンに投影する動画であれば、高解像度での撮影が良いでしょう。作業手順を伝えるためにモバイル端末で視聴する動画であれば、1280p×720p程度の解像度がおすすめです。
このように、動画マニュアルの活用シーンや用途をもとに、解像度を決めると良いでしょう。
スマートフォンの解像度の初期設定は、1440p×1080pになっているケースが多いです。動画マニュアルを撮影する際は設定を確認しましょう。解像度の変更方法は、『動画の解像度を設定する方法』で後述します。
代表的な動画解像度一覧
現在のおもな動画解像度はこのようなラインナップとなっています。これらのほか、YouTubeでは「144(256p×144p)」「360(640p×360p)」といった低解像度へ設定することが可能です。
|
画質の通称 |
横×縦の解像度 |
画素数 |
|
8K |
7680×4320(16:9) |
33,177,600 |
|
4K |
3840×2160(16:9) |
8,294,400 |
|
フルHD |
1920×1080(16:9) |
2,073,600 |
|
HD |
1280×720(16:9) |
921,600 |
|
SD |
720×480(16:9) |
345,600 2,073,600 |
動画を見て「720p」と「1080p」の違いを確認
▼「720p」と「1080p」の違い▼
前半部分は、1080pで撮影したもの、後半部分は720pで撮影したものです。
ご覧いただくとどちらの画質もさほど違いはないことがお分かりいただけるでしょう。もちろんデータ容量は、720pで撮影した方が抑えられるため、どの端末でもスムーズに再生できるはずです。
それぞれの詳しいデータ容量については、後述する『720pと1080pの動画容量はどれくらい?』で解説します。
実際に企業で活用されている動画マニュアルをチェック
動画マニュアル作成ツールtebikiを使って作成した動画マニュアルのサンプルをご紹介します。
▼動画マニュアルサンプル:サラヤ株式会社▼
(音量にご注意ください)
このように、高画質ではなくても、業務の手順は把握できるため問題なく活用できます。
より多くのサンプル動画を見たい方は、以下の記事も併せてご覧ください。全65個のサンプル動画と、業種別の導入時の事例をご紹介しており、どのように動画マニュアルが活用されているかをご覧いただけます。
▼関連記事▼
【業界別26社】動画マニュアルの事例とサンプルを多数ご紹介!参考ポイントや作り方も解説
動画の解像度を設定する方法
スマートフォン(iPhone/Android)で解像度を設定する方法をご紹介します。スマートフォン以外のカメラについては機器によってそれぞれ設定方法が異なるため、取扱説明書を確認してみてください。
iPhoneの場合
- 「設定」画面を開きます
- 「カメラ」→「ビデオ撮影」で、設定したい解像度を選択します
Androidの場合
Androidについては機種によって設定方法が若干異なりますので、一例としてご紹介します。
- ビデオカメラを起動し「設定」画面を開きます。
- 「動画サイズ」画面を開き、設定したい解像度を選択します。
以下の記事では、スマートフォンでの解像度の設定方法を動画でわかりやすくご紹介していますのでぜひご覧ください。
▼関連記事▼
スマホ/タブレットでビデオ撮影の解像度を変更して動画サイズ(容量)を小さくする方法
撮影した動画の解像度の調べ方
動画をパソコンに取り込んだ場合は、動画ファイルを右クリックし、ファイル情報(プロパティ)から確認できます。スマートフォン上で調べる場合は、ご利用のアプリ上で動画ファイルのファイル情報を開いて確認しましょう。
解像度は、「1280p×720p」「フレーム幅1280/フレーム高720」といった表記で表示されます。
720pと1080pの動画容量はどれくらい?
実際にスマートフォンを使って、720pと1080pの2種類の画質で撮影し、比較してみました。
|
720p |
1080p |
|
|
Android |
225MB |
600MB |
|
iPhone |
200MB |
300MB |
上表のように、720pと1080pではデータ容量に差があることをご確認いただけます。また、使用機種によっても、動画容量は変動します。
以下の記事では、スマートフォン(iPhone/Android)で動画を撮影した場合、機種と解像度と所要時間によってデータ容量がどうなったかを実際に計測した結果を詳しくご紹介しています。動画容量が気になる方は、こちらも併せてご覧ください。
▼関連記事▼
1本の動画の長さ(分数)と容量(MB)の目安と計算方法
保存容量を気にせず簡単に動画マニュアルを作るなら「tebiki」
マニュアルは業務の手順や流れを説明する、業務に欠かせない存在です。そのため、「データ容量の上限があるから、すべての業務をマニュアル化できない……」といった事態は避けたいもの。
そこで、おすすめしたいのが、データ容量を気にせずに、簡単に動画マニュアルを作れるtebikiです。なぜおすすめなのか、その理由を3つご紹介します。
▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼
動画の容量や本数の制限なし
近年、動画マニュアルの作成に活用されているのが動画マニュアル作成ツールですが、保存する動画の総容量によって料金が異なるサービスもあります。しかし、tebikiは、容量や動画数に制限がありません!
動画マニュアルを何本作成しても料金は変わらないため、数千本のマニュアルを作成し、活用されている企業もいらっしゃいます。また、業務の手順だけでなく、安全管理など社員全員へ共有したい重要情報の共有手段として用いて生産性向上を実現している企業もあります。
スキルがなくても動画編集できる
tebikiは、誰でも簡単に動画を作れるように開発されました。業務の様子をスマートフォンで撮影し、ボタン1つでツールに動画を取り込み、不要な部分をカットしたら動画マニュアルが完成! 操作が簡単だからこそ、「導入から1年で1,500本以上の動画マニュアルを作成できた」という事例もあります。
社内でマニュアルを作成する際、業務に詳しい人が担当することが多いですが、業務に詳しい人が動画編集にも詳しいとは限りません。「動画編集やパソコンの扱いに詳しい人がいない」といった職場でも「tebikiを使ってみたら簡単に編集できた」「tebikiは操作マニュアルを読まなくても直感的に操作できた」という声をいただいています。
▼tebikiでの動画マニュアル作成基本手順▼
動画の作成時間を削減するために、動画内の音声を自動的に字幕化する機能 /字幕を読み上げナレーション化する機能もあり、スムーズな動画作成をサポートしています。
そのほか、翻訳機能や教育管理機能も搭載で使い勝手抜群!
デスクレス産業において外国人雇用が増えている今、tebikiでは、字幕を自動的に100か国語へ翻訳する機能があるため、外国人スタッフの多い職場でも活用されています。
文字のマニュアルを多言語へ翻訳する作業が大きな負担となっていた企業からは「翻訳作業がゼロになった」との声をいただいており、海外拠点にもタイムラグなく情報共有できているそうです。
そのほかにも、次のような機能で、人材教育を徹底的にサポートしています。
- レポート機能:誰が何時間動画を視聴しているのか学習進捗を管理
- テスト機能 :動画内容をミニテストにして習熟度をチェック
- タスク機能 :特定のユーザーに動画視聴を指示
上記でご紹介した以外にも、tebikiには現場教育の効果を最大限に引き出す機能がたくさん搭載されています。機能面や無料で続くサポート体制について詳しく知りたい方は、以下の「3分でわかる!tebiki」も併せてご覧ください。
tebikiによって動画マニュアルを作成/運用した事例
動画マニュアル作成ツールtebikiを導入し、たくさんの動画マニュアルを作成して、業務にお役立ていただいている事例を3社ご紹介します。
より多くの導入事例を読みたい方は、以下の導入事例集もご覧ください。異なる7つの業種で、企業が「どのような課題を抱えて、どのように解決したのか」がわかりやすく紹介されています。
動画内製化の課題を解決!導入1年で1,300本以上作成&総視聴時間は550時間超:株式会社GEEKLY
人材紹介事業を展開する株式会社GEEKLYでは、OJT指導を中心とした人材教育を実施していました。ただ、OJT指導では教え方のバラつきや指導者の負担が課題となっていたため、わかりやすく伝えられる動画マニュアルの内製に着手しました。
内製化に着手したはいいものの、データ保存方法が部署によって違ってしまい探しづらい点や、YouTubeでの共有ではアカウント管理者の退職により動画が削除されるなどから、改めて動画作成のサービスを探し、tebikiを導入。
操作性の高さから、導入1年で1,300本以上の動画マニュアルを作成! 人材教育に取り入れたところ、教え方のバラつきが解消されただけでなく、OJTの約7割を動画マニュアルに置き換え、負担軽減に成功しました。
「今後も営業方法の改善など多くの動画マニュアルを作成したい」と意気込みを語る株式会社GEEKLYのインタビューは、次の記事から詳しくご覧ください。
▼関連記事▼
1年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!
IT知識がなくても「直感」で動画作成できる:株式会社ハングリータイガー
ハンバーグとステーキの専門店を運営する株式会社ハングリータイガーでは、紙のマニュアルにて人材教育を行っていました。しかし、調理や接客など動作のノウハウは伝えづらく、効率的に人材教育できる動画マニュアルを内製しました。
ただ、動画編集は一定のITスキルがないと難しく、マニュアルの作成・更新業務がスキルのある担当者に集中。また、YouTubeでの共有では、公開設定に神経を使うなどデメリットもあり、内製化を断念しました。
編集が簡単にできそうなtebikiを見つけ、サービスデモを見たところ、「スキルがなくても、動画マニュアルを作成できる」と確信。tebikiは月額数万円から利用でき、解約までずっと無料のサポートがつくためコストパフォーマンスの面でも納得感がありました。今では「tebikiを見ておいて」の一言で、未経験者も現場に出る一歩手前までレベルアップできる体制になっています。
キッチンにもマニュアルを持ち込めるようになり、安全教育や多能工化にも活用しさらなる生産性向上を目指す株式会社ハングリータイガーの事例について、詳しくは次の記事をご参照ください。
▼関連記事▼
飲食業の動画マニュアル│接客の所作や動きを伝えるには動画がベスト
半年で400動画作成!tebikiは現場で使うための必要条件をすべてクリア:サラヤ株式会社
世界の「衛生・環境・健康」に貢献しつづけるサラヤ株式会社では、製造過程の標準作業手順書を紙で作成していましたが、微妙なニュアンスが伝わりにくく作業や製品の品質のバラつきにつながっていました。
製品品質の維持は、製造業にとって至上命題。動画マニュアルソフトの自主開発に取り組むも、誰にも使いやすいソフトを開発するには費用や工数の面で難しく、複数サービスを検討した結果tebikiを導入しました。
tebikiは初めて触った人でもすぐに使い方がわかるほど編集操作が簡単で、動画の読み込みも時間がかからず、自動翻訳により一瞬で翻訳が完了。再生においても利用端末に制限がないといった点も魅力に感じていただけています。
海外工場でも活用したところ、「再生もスムーズで、活用頻度や理解度も把握できている」と語るサラヤ株式会社のインタビューについては、次の記事をご覧ください。
▼関連記事▼
医薬品メーカーの動画マニュアル導入事例 | 消毒剤のトップシェアメーカーでSOPを動画で作成。動画標準で力量の均一化、安全性の向上、品質の向上を実現
そもそも動画の解像度とは?
動画の解像度とは、「対象の動画がどれほどの画素数で分割されているのか」といった密度を表したものです。画素数の数が大きいほど密度が高く画質がきめ細やかである、ということになります
解像度は、動画の画質や鮮明さを決定する重要な要素となります。
「解像度」と「動画サイズ」の違いは?
解像度とともに耳にするのが「動画サイズ」という言葉です。動画の容量という意味で使う場合は解像度と同じ意味であるものの、多くは動画画面のサイズを意味しており、「アスペクト比」を説明する際に用いられます。
アスペクト比は「横:縦」で表現され、動画の画面形状を示します。たとえば16:9だと横長の画面となり、4:3だと正方形に近い画面ということです。「動画サイズの変更」とは、たとえば16:9の横長の動画をSNSに適した9:16の縦長のアスペクト比へ変更することを指します。
よく見る「p」ってどういう意味?
動画マニュアルにおすすめの解像度として「1280p×720p」と述べましたが、この「p」はどのような意味なのでしょうか。
これはプログレッシブスキャン(progressive scan)の頭文字であり、画面上の水平の線である「走査線」を1つずつ描画することで動画が表示されます。この方法はプログレッシブ方式と呼ばれますが、テレビ放送で用いられる負荷の少ないインターレース方式での解像度は「i」(interlace)、印刷した写真の解像度は「dpi」(dot per inch)といった文字となります。
まとめ
動画マニュアルの最適な解像度は、HD(High Definition)画質と呼ばれる1280p×720pです。解像度は、動画マニュアルの使用シーンや用途に合わせて決めましょう。
動画マニュアルは紙のマニュアルと比べるとデータ容量が大きくなりますが、わかりやすさやマニュアルの作りやすさの面では優れています。保存容量を気にせず簡単に動画マニュアルを作るなら、動画マニュアル作成ツールtebikiをおすすめします。
tebikiを導入した企業の事例や動画サンプルをぜひご覧いただき、無料トライアルで実際の動画編集画面や操作感を確かめてみてください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。







