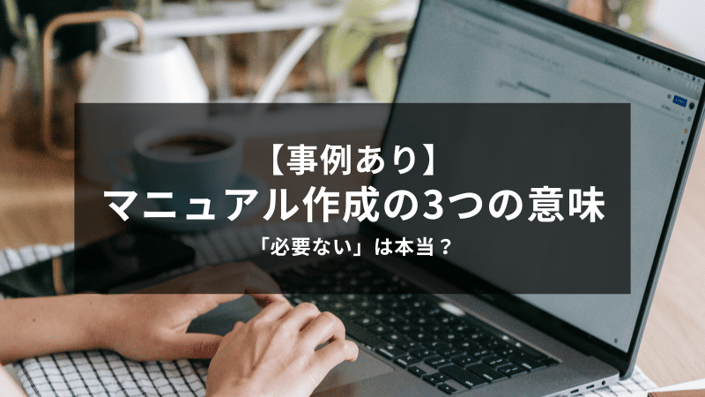
目次
- 1. マニュアル作成には、どんな意味や目的がある?
1-1. 業務内容の標準化による品質向上
1-2. 社員教育プロセスの効率化
1-3. ナレッジの共有
2. マニュアル作成による「メリット」
2-1. 社員教育の時間/コストを削減できる
2-2. 作業品質/作業効率が向上する
2-3. 復習が可能になる
2-4. スムーズに引継ぎが行える
2-5. 個人に依存するリスクが軽減できる
3. 必要ないという声も…マニュアル作成の「デメリット」
3-1. マニュアル作成に時間がかかる
3-2. マニュアルを作っても活用されない
3-3. マニュアル通りの動きしかできなくなる
4. 社内で活用されるマニュアル作成のポイント
4-1. マニュアルの目的や目標を設定する
4-2. 写真や動画を用いて、視覚的にわかりやすくする
4-3. 誰が読んでもスムーズに読めるようにする
5. マニュアル作成の意味を高める運用のポイント
5-1. マニュアルが使われる仕組みを作る
5-2. マニュアルの管理場所/方法を明確にする
5-3. 現場の声を取り入れながら定期的に更新する
6. 学習効果を高めたいなら、動画マニュアルがおすすめ
6-1. 文書マニュアルよりも見てもらいやすい
6-2. 複雑な動きもそのまま伝えられる
6-3. マニュアルの作成負担が少ない
6-4. 学習の効率性を向上できる
7. 動画マニュアルtebikiなら、作成から運用まで誰でも簡単!
7-1. マニュアル作成/動画編集がとにかく簡単
7-2. 一元管理だからこそ見たいマニュアルがすぐ見つかる
7-3. タスク機能やテスト機能によって、学習定着率を向上できる
7-4. 100か国語への翻訳をボタン1つで自動で行える
7-5. アクセス履歴や習熟度進捗の可視化も可能
8. 動画マニュアルの効果がわかるtebikiの導入事例
8-1. 株式会社GEEKLY
8-2. 新日本工機株式会社
8-3. 東急リゾーツ&ステイ株式会社
9. そもそも、マニュアルとは?
9-1. マニュアルと手順書の違い
9-2. マニュアル作りが上手い人の特徴
10. まとめ
マニュアル作成には、どんな意味や目的がある?
マニュアル作成の意味や目的を一言で表すと、「教育する仕組みを作る」だと言えます。マニュアルは、業務における教科書です。そのため、マニュアルをもとに業務を進めることで、ミスや作業手順不順守を防ぐことができ、品質向上や効率化の効果が期待できます。
マニュアルを活用せずにOJT中心の教育をすると、教育担当者に負荷が集中して、本来の業務に注力できなくなってしまいます。さらに、教育内容にバラツキが生じるといった課題が生じかねません。効果的かつ効率的に社員教育を行いたいのなら、マニュアル整備を行いましょう。
以下に、マニュアル作成の意味をより詳しくご紹介します。
業務内容の標準化による品質向上
作業内容が標準化されたマニュアルを使用することで、すべての従業員が同じ手順で業務を行えるようになります。これにより、作業の一貫性が保たれ、品質のバラつきを削減でき、結果として顧客満足度を向上させることが可能です。
社員教育プロセスの効率化
新入社員や異動してきた従業員に対して、標準化されたマニュアルを用いて教育を行えば、指導者が付きっ切りで教育を行う必要がなくなり、短期間で必要なスキルや知識を習得させることができるでしょう。
とくに、以下のような企業は、マニュアル作成/整備を進めるのがおすすめです。
- 新人受入の機会が多い企業
- OJT教育に依存して教育工数が膨大になっている企業
社員教育のプロセスを効率化できれば、ベテラン社員による機会損失の削減/新規サービス実行への時間へ転化などが可能になり、業績向上にもつながると考えられます。
ナレッジの共有
マニュアル作成を行い、業務に関する重要な情報や手順を共有できる体制を整えれば、作業の属人化を解消させることに役立ちます。
また、経験豊富な従業員の知識やノウハウをマニュアルに残すことで、新しい従業員や他のチームメンバーがその知識を学び、活用することができます。これにより、組織全体の知識レベルが向上します。
マニュアル作成による「メリット」
マニュアル作成を進めることで、さまざまな教育効果を期待できます。ここでは、代表的な5つのメリットをご紹介します。
社員教育の時間/コストを削減できる
マニュアルに沿って自習してもらうことで、一から教える必要がなくなり、教育にかかる時間やコストを大幅に削減できます。教育にかかる時間が短縮することで、新人社員の早期戦力化も期待できるでしょう。
作業品質/作業効率が向上する
標準化された手順に従うことで、誰でも同じ品質の作業を行えるようになります。その結果、生産性の向上につながるでしょう。
復習が可能になる
業務内容や手順をまとめておくことで、必要なときにいつでも確認できます。
たとえば、久しぶりに行う作業を実行する際にマニュアルを見返すことで、正確な手順や注意点を再確認でき、作業の品質と効率を保つことが可能です。さらに、マニュアルを定期的に見返すことで、知識の定着を図ることもできるでしょう。
スムーズに引継ぎが行える
業務内容や手順をまとめておくことで、引継ぎの際に必要な情報を漏れなく伝えることが可能です。また、引継ぎ期間が短くても、マニュアルを参考にすることでスムーズに業務を開始できるようになります。
個人に依存するリスクが軽減できる
業務のノウハウやコツをマニュアルとしてまとめることで、特定の個人に頼らずに業務を遂行でき、属人化の解消につながります。たとえば、ベテランの社員が退職や異動した際にも、マニュアルがあることで業務品質を維持することが可能です。
必要ないという声も…マニュアル作成の「デメリット」
マニュアルに頼りすぎると臨機応変な対応ができなくなるなどの理由から、「マニュアルは必要ない」と言われることがあります。たしかに、顧客対応やクリエイティブな業務では、標準化されたマニュアルでは対応しきれないこともあるかもしれません。ここでは、マニュアル作成のデメリットをご紹介します。
マニュアル作成に時間がかかる
マニュアルを作成するためには、業務の手順を明らかにして、わかりやすく記述する必要があるため、多くの時間を要します。中には、文章ベースのマニュアル作成に「1ページ1時間」ほど時間を費やしている企業も……。さらに、マニュアルは1度作成すればそれで終わりではなく、定期的に内容を更新する必要があります。そのため、「時間がかかるなら必要ない」と考える人もいるのだと考えられます。
マニュアルを効率的に作成したいのなら、マニュアル作成ツールを活用するのがおすすめです。以下の記事で、おすすめのマニュアル作成ツールのご紹介をしていますので、併せてご覧ください。
▼関連記事▼
【無料あり】マニュアル作成ツール比較12選│失敗しない選び方も
マニュアルを作っても活用されない
せっかく時間をかけてマニュアルを作成しても、活用されずに形骸化する可能性があります。これでは作成しても意味がなく、「結局不要だったじゃないか」と言われてしまうでしょう。
活用されないマニュアルの特徴としては、以下の通りです。
- 内容がわかりにくい
- 最新の情報が載っていない
- 管理場所や管理方法が認知されていない
マニュアルの効果を最大限発揮させるには、実務に適した内容にし、マニュアルの存在を周知させる必要があります。現場にマニュアルを定着させる方法を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
▼関連記事▼
マニュアルの「定着」4STEP!効果的な周知方法とは?
マニュアル通りの動きしかできなくなる
マニュアルに頼りすぎてしまうと、臨機応変な対応ができなくなる恐れがあります。これを、「マニュアル人間」と呼ぶことがありますが、柔軟性や創造性に欠けると見なされ、自発的に考えて行動する能力が低いと評価されてしまいます。
マニュアル通りの動きをしっかり行えることは、むしろ高く評価されるべき特性とも言えます。そのため、マニュアルの内容を意識しながらも、状況判断力を養う教育も行うと良いでしょう。
社内で活用されるマニュアル作成のポイント
社内で活用されるマニュアルを作成するには、わかりやすく見やすいマニュアルである必要があります。そのためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
わかりやすいマニュアル作成の方法は、別記事『【見本あり】わかりやすいマニュアル作成の5つのポイント。構成やレイアウトは?』か、以下のマニュアル作成ガイドも併せてご活用ください。
マニュアルの目的や目標を設定する
目的や目標が明確でないと、マニュアルが必要とされる場面や使用方法が曖昧になり、効果的に活用されません。
そのため、目的や目標を明確に設定し、目標達成に必要な手順やチェックリストをマニュアルに組み込むと良いでしょう。これにより、マニュアルが実用的なものとなり、業務効率や作業品質の向上が期待できます。
マニュアルの目的/目標設定例
- すべての作業員が同じ手順で製品を組み立てられるようにする
- 作業ミスを減らして不良品の発生を防ぐ
- 入社後3ヶ月以内に基本的な業務を習得する
- 自分のペースで学習できるようにする など
マニュアル作成における目標設定方法を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。職種別に目標設定例文もご紹介しているので、参考にしていただけますと幸いです。
▼関連記事▼
【例文つき】マニュアル作成での目標設定方法とは?重要性やコツも解説
写真や動画を用いて、視覚的にわかりやすくする

視覚的な情報は文字よりも理解しやすく、記憶にも残りやすいです。そのため、言葉で伝えにくい部分は写真や動画を用いて視覚的に伝えると良いでしょう。たとえば、機械の操作方法を説明する際に、文章だけでなく実際の操作手順を写真や動画で示すことで、スムーズに理解できるようになります。
誰が読んでもスムーズに読めるようにする
専門用語や難しい言葉を避け、簡潔でわかりやすい文章を心がけることで、誰でも理解できるマニュアルになります。また、一文を短くしたり段落や見出しを適切に配置することで、文章の読みやすさも向上します。
マニュアル作成の意味を高める運用のポイント
マニュアルの効果を最大限発揮するには、作った後の運用も重要です。「作ったはいいけど、誰にも見られずに形骸化している」という企業の多くは、運用や管理に力を入れていないことが多いです。ここでは、活用を促す運用のポイントをご紹介します。
運用方法や整備方法を詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。マニュアルが形骸化する理由などもご紹介しているので、すでに形だけになってしまっているという方は必見です。
▼関連記事▼
形骸化させないマニュアル整備の進め方は?活用される更新・運用方法を解説
マニュアルが使われる仕組みを作る
せっかく作成したマニュアルも、使用されなければ意味がありません。そのため、以下のような「マニュアルが使われる仕組みづくり」を行いましょう。
- マニュアルの存在を社内に周知する
- マニュアル活用による業務効率向上事例を共有する
- チェックシートとマニュアルを紐づける など
マニュアルが形骸化している企業の従業員の中には、「そもそもマニュアルの存在を知らなかった」という方もいます。社内に存在を周知させるために、メールや社内ポータルでマニュアル公開の共有をするのも1つの方法です。
マニュアルの管理場所/方法を明確にする
マニュアルが適切に管理されていないと、必要なときに見つけられず、業務で活用されなくなってしまいます。そのため、「どこにどのマニュアルがあるか」「マニュアルは誰が更新するのか」などを明確にし、従業員がスムーズにアクセスできる環境を整えることが大切です。
現場の声を取り入れながら定期的に更新する
現場で実際に働いている人の意見を反映させることで、より実用的で役立つマニュアルを作成できます。具体的には、以下のことをヒアリングして更新しましょう。
- わかりにくい箇所はないか
- 情報は古くなっていないか
- より効率的に行える方法はないか など
従業員にどのようなマニュアルが欲しいか聞いて、新しく作る方法も有効です。社内で一体となって、業務効率や品質を向上できるよう、マニュアル作成/運用に取り組みましょう。
学習効果を高めたいなら、動画マニュアルがおすすめ
文書ベースのマニュアルを活用している企業が多いかと思いますが、教育工数をより削減しながらわかりやすいマニュアルを目指すなら動画マニュアルがおすすめです。ここでは、動画マニュアルの効果やメリットをご紹介します。
「紙マニュアルと動画マニュアルの比較をしたい」という方は、以下の記事も併せてご覧ください。それぞれのメリットやデメリット、動画マニュアルの導入事例などもご紹介しています。
▼関連記事▼
【動画vs紙】どっちのマニュアルがいい?メリットとデメリットを徹底比較
文書マニュアルよりも見てもらいやすい
分厚い文書マニュアルを読むよりも、動画を見る方が心理的ハードルが低いため、マニュアルの活用頻度を上げられます。そのため、自学自習を促進する効果も期待できるでしょう。
複雑な動きもそのまま伝えられる

文章や口頭では伝えにくいコツが必要な作業でも、動画なら「動きをそのまま」伝えることが可能です。そのため、新人社員でも熟練の技を再現することが可能になり、早期独り立ちにつながるでしょう。
実際に動画マニュアルを導入している企業からは、「活躍している社員の高いスキルを共有することで、社員レベルの底上げにつながっている」という声が挙がっています。
マニュアルの作成負担が少ない
文書ベースのマニュアルでわかりやすさを求めると、写真や図を多用する必要があり、作成にかなりの時間を要してしまいます。しかし、動画だと、普段の業務の様子を撮影するだけで作業内容を伝えられるため、効率的にマニュアルを作成することが可能です。
紙マニュアルから動画マニュアルに切り替えた企業では、「マニュアルの作成時間を75%削減できた」という事例もあるほど。作成工数に悩んでいる方は、動画マニュアルの導入を検討してみてください。
学習の効率性を向上できる
動画が伝えられる情報量は、写真や文章より遥かに多いです。そのため、短時間の学習でより多くの情報のインプットが可能になり、効率的な学習を叶えてくれます。長い文章を読むのに抵抗感がある人にとっては、文字を読む必要がないというのも、大きなメリットになりえますよね。
また、動画マニュアルの場合、時間や場所を問わず、マニュアル閲覧ができます。そのため、出張先や移動中でも動画を視聴できるため、自学自習を推進する効果が期待できます。
動画マニュアルの教育効果をより詳しく知りたい方は、以下の資料も併せてご覧ください。紙マニュアルのあるある課題から動画マニュアルのメリットを網羅的にご紹介した1冊となっており、検討資料として活用しやすいでしょう。
動画マニュアルtebikiなら、作成から運用まで誰でも簡単!
動画マニュアルの有効性はご説明しましたが、いざ作ろうと思っても、編集や管理が大変で作成が頓挫してしまう恐れがあります。そこで、効率的かつ効果的に動画マニュアルを作成するツールとして、tebikiがおすすめです。以下に、tebikiの特長をご紹介します。
マニュアル作成/動画編集がとにかく簡単
tebikiを使うと、以下の3ステップで動画マニュアルの作成が可能です。

tebikiは「簡単であること」に重きを置いて開発されたサービスであるため、動画編集経験がない人はもちろんのこと、パソコン操作が苦手な人でも、使い始めたその日から動画マニュアルの作成が行えます。編集に時間がかかる字幕生成を自動で行う機能も搭載されているため、1つの動画をサッと15分程度で作成している企業の方も多いです。
さらに、動画マニュアルだけでなく、文書ベースのマニュアル作成も可能! 用途や目的に合わせて、動画と文書を使い分けて、効果的な現場教育を行うことができます。
実際の操作画面や使い勝手を見てみたいという方は、こちらからお問い合わせください。
一元管理だからこそ見たいマニュアルがすぐ見つかる
tebikiのデータはクラウド上に一元管理されるため、マニュアルのファイルが散見することがありません。検索性の高さも好評をいただいており、マニュアル名/説明文/タグから、見たいマニュアルを網羅的にワード検索できるため、マニュアルの内製化でありがちな「見たいマニュアルがどこにあるかわからない」という問題を解消できます。
フォルダ分けをして、マニュアルを整理することも可能。部署やチームごとにマニュアルを整理し、業務を効率化するのに役立ちます。
タスク機能やテスト機能によって、学習定着率を向上できる
tebikiには動画作成や管理の機能だけでなく、「タスク機能」や「テスト機能」も搭載されています。これにより、マニュアルを作った後の動きもカバーでき、学習の定着率が向上するでしょう。
|
タスク機能 |
「〇日までに画面操作マニュアルを閲覧してください」というようなマニュアルの閲覧指示を、指定のユーザーに送る機能。 |
|
テスト機能 |
記述式や選択式からオリジナルのテストを作成できる機能。回答を指定しておけば、自動採点して、合否を出すこともできます。 |
100か国語への翻訳をボタン1つで自動で行える
動画の再生画面で、言語切り替えボタンを押せば、翻訳したい言語へ一瞬で切り替わります。これにより、外国籍のスタッフは母国語で教育を受けられるため、技術が定着しやすくなります。

アクセス履歴や習熟度進捗の可視化も可能
マニュアルのアクセス履歴や社員ごとの習熟度を、表やグラフで可視化するレポート機能も搭載されています。そのため、人気コンテンツを分析しながら、より効果的な動画作成が可能です。

tebikiの特長やより詳しい機能を知りたい方は、以下からサービス説明資料をご覧ください。機能性だけではなく、導入からずっと続く安心のサポート体制についてのご紹介もしています。
動画マニュアルの効果がわかるtebikiの導入事例
動画マニュアルtebikiを導入して、大きな効果を出している企業の事例をご紹介します。それぞれ業種や抱える課題が異なる中で、どのような効果を出しているのかチェックしていきましょう。
より多くの企業事例と効果を知りたい方は、『【業界別26社】動画マニュアルの事例とサンプルを多数ご紹介!参考ポイントや作り方も解説』という記事か、以下の導入事例集もご覧ください。
教育工数を7割削減、動画マニュアル効果で会社全体の営業成績も向上:株式会社GEEKLY
IT・WEB・ゲーム業界に特化した人材紹介を行っている株式会社GEEKLYでは、新人教育の際にトレーナーごとの教え方に差があり、新人の営業成績にばらつきが生じるという問題を抱えていました。そこで、教育内容の統一化とトレーナーの負担軽減のためにtebikiを導入し、1年で1,300本以上の動画マニュアルを作成。
OJTの7割近くを動画マニュアルに置き換えたことで、新人の理解度が均一化され、業務内容や営業品質のばらつきが解消されました。また、新人1人あたりの教育時間を150時間から45時間に短縮し、年間で約3,700時間の教育工数を削減することに成功しました。
株式会社GEEKLYの導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
▼関連記事▼
年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!
導入1年で1,500本以上の動画を作成。効率的なマニュアル整備で作業品質が安定:新日本工機株式会社
▼動画マニュアル『tebiki』導入事例インタビュー:新日本工機株式会社▼
工作機械や産業機械の製造販売を行っている新日本工機株式会社では、作業手順の標準化が進まず、作業者によって作業の品質にばらつきが生じるという問題を抱えていました。そこで、作業手順の標準化を進め、品質管理を徹底するためにtebikiを導入。
導入から1年で1,500本以上の動画マニュアルを作成することで、現場作業の標準化を実現しました。また、教育現場で作業手順や注意点を伝える際にもtebikiを活用することで、作業品質が安定し、作業のばらつきが解消されました。
新日本工機株式会社の導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
▼関連記事▼
人が育つ環境づくりとして動画マニュアルtebikiを活用。技術の蓄積と作業品質の安定を実現
動画マニュアル導入によって、業務負荷低減/新規サービス実行への時間へ転化:東急リゾーツ&ステイ株式会社
ホテル・ゴルフ場・スキー場・別荘地などの施設運営を手掛ける東急リゾーツ&ステイ株式会社では、サービスのバラつきや従業員の業務負荷が問題となっていました。そこで、運営オペレーションの標準化と可視化を目的に、tebikiを導入しました。
操作が簡単だからこそ、導入から2年で9,000本以上の動画マニュアルを作成。動画マニュアルにより、業務の統一管理を実現しました。また、動画マニュアルによって効率的に業務を学べるようになり、サービスの質が向上したという効果も。その結果、各施設での業務のバラつきが解消され、労働時間の短縮と新たなサービス取組み時間への転化に成功しました。
東急リゾーツ&ステイ株式会社の導入事例を詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
▼関連記事▼
従業員数2,500人超・全国100を超える施設で業務の平準化と多能工化を推進
他にも幅広く、「業界別の事例とサンプル動画を見てみたい」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▼関連記事▼
【動画マニュアル事例集】業界別26社のサンプルを多数紹介
そもそも、マニュアルとは?
そもそもマニュアルとは、「特定の業務の作業手順を具体的にまとめたもの」とされています。
前述した『マニュアル作成には、どんな意味や目的がある?』でもご紹介した通り、品質向上/教育の効率化/ナレッジ共有などのメリットが期待できます。
マニュアルと手順書の違い
マニュアルと手順書では掲載する内容が異なります。
マニュアルは作業手順だけでなく、業務の背景や目的などを解説します。一方で、手順書は具体的な作業手順を詳細に説明する文書なので、業務の背景や目的などは含みません。
用語の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
▼関連記事▼
マニュアルとは:「作業手順書」「SOP」等の類語との意味の違いや英語の呼び方など
マニュアル作りが上手い人の特徴
マニュアル作りが上手い人は、読み手を意識することに長けています。たとえば、初心者向けのマニュアルを作成する際には、スムーズに作業内容を理解してもらうために専門用語を避けて簡単な言葉で解説します。
マニュアル作成が上手い人の特徴は、以下の記事で詳しく解説しています。上達するためのコツがつまっている記事になっていますので、こちらも併せてご覧ください。
▼関連記事▼
【即上達】マニュアル作成が上手い人の5つの特徴!コツやおすすめツールも
まとめ
マニュアル作成の意味やメリットを解説しました。マニュアルを作成することで、作業内容を標準化し、品質を向上させることが可能です。そのため、業務効率や作業品質を向上させたい方は、目的に合ったマニュアルを作成し、継続的に運用するのがおすすめです。
学習効果を高めたい方は、「tebiki」を活用して動画マニュアルを活用するのがおすすめです。動きだけでなく、表情や声のトーンなども伝えられるため、複雑な作業や動作もスムーズに伝えられます。また、動きを撮影するだけで作業内容を伝えられるため、マニュアル作成の負担も軽減できます。作成だけでなく管理や分析も簡単に行えるので、効率よくマニュアル運用をしたい方は「tebiki」を活用してみてください。
動画マニュアルに興味がある方は、以下からtebikiの機能や導入事例をご確認ください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。









