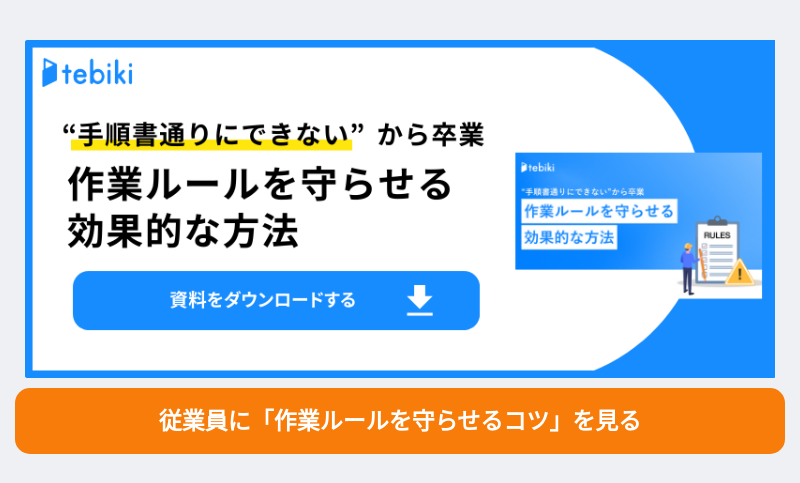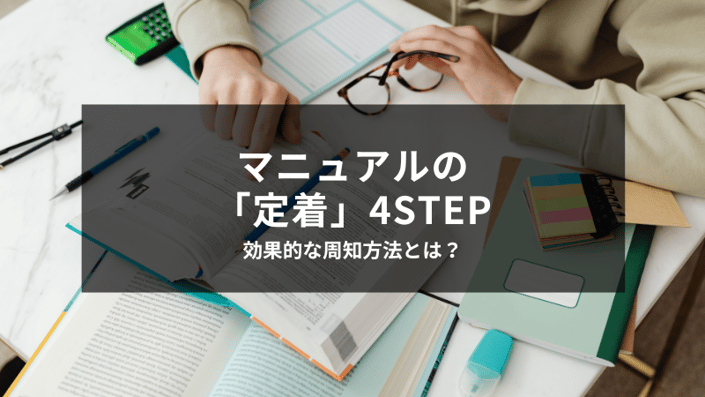

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開するTebiki株式会社です。
業務効率や生産性の向上、品質を維持させるためには、現場のルールを正しく守ってもらうことが重要です。しかし、「中々現場のルールが定着しない...。」と悩んでいる方も少なくないでしょう。
そこで、この記事では、マニュアルで現場のルールを定着させる方法を解説します。ルールを定着させるための効果的な周知方法や定着しないことで発生するリスクなどについても紹介するので課題を感じている方は最後までご覧ください。
現場のルールを定着させるには、わかりやすいマニュアルである必要があります。教育効果を出すためのマニュアル作成のコツを知りたい方は、以下のガイドを参考にしてください。これまで何社ものマニュアル整備をサポートしてきたtebikiだからこそわかる「作成の秘訣」が詰まった1冊になっています。
目次
- 1. マニュアルで現場のルールを定着させる4つのSTEP
1-1. STEP① マニュアルの内容/フォーマットを見直す
1-2. STEP② マニュアルが活用される仕組みを作る
1-3. STEP③ 管理/運用ルールを定める
1-4. STEP④ 定期的に更新を行う
2. マニュアルで現場のルールを定着させる効果的な周知方法
2-1. なぜそのルールがあるのかを明確に伝える
2-2. 従業員が「確実に見る」仕組みを作る
2-3. ベテラン従業員を巻き込む
2-4. ルールの理解度テストを定期的に実施する
2-5. ルールを守っている従業員を評価する
3. ルールを定着させるために「動画マニュアル」の活用も手段のひとつ
4. 動画マニュアルの作成には「tebiki」がおすすめ
4-1. スマホひとつで簡単に作成できる
4-2. アクセス履歴や習熟度の進捗が一目でわかる
4-3. タスク機能で従業員に対してルールの周知を定期的に実施できる
4-4. 検索性が高く、見たいマニュアルがすぐ見つかる
4-5. 100ヶ国語以上に自動翻訳でき、外国人従業員にも利用できる
5. 現場で重宝されているtebikiの導入事例
5-1. OJTの約7割をtebikiに置き換えて定着!教育工数の削減&営業品質のバラツキが解消:株式会社GEEKLY
5-2. 操作が簡単だからこそ現場に浸透。月30万円の教育コストを削減:サッポログループ物流株式会社
5-3. 読まれない紙マニュアルから、現場で使われる動画マニュアルに:株式会社安藤・間
6. 現場で定めたルールが定着しない理由
6-1. ルールがあること自体を認識していない
6-2. ルールを守る重要性が伝わっていない
6-3. 従業員の慣れや怠慢によって形骸化している
7. 現場にルールが定着しないことで起こりうるリスク
7-1. 労働災害に発展する
7-2. 品質不良のリスクがある
7-3. 業務が標準化されずに、業務効率化が低下する
8. 【まとめ】現場でのルール定着には動画マニュアルの活用がおすすめ
マニュアルで現場のルールを定着させる4つのSTEP
マニュアルで現場のルールを定着させるためには、以下の4つのSTEPを行いましょう。
STEP① マニュアルの内容/フォーマットを見直す
マニュアルの内容が複雑だったり見づらかったりすると、従業員に活用してもらえません。そのため、まずはわかりやすいマニュアルにするため、内容やフォーマットを見直すと良いでしょう。
▼内容やフォーマットの見直し方▼
|
内容 |
・マニュアルを使う人にヒアリングする |
|
フォーマット |
・伝えたい内容に合わせる |
わかりやすいマニュアル作成のコツを知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。文章だけではなく、構成やレイアウトデザインのポイントも解説しています。
▼関連記事▼
見本テンプレ付!わかりやすいマニュアルの作り方とコツ。構成、レイアウト、作成ツールは?
STEP② マニュアルが活用される仕組みを作る
マニュアルを配布するだけでは、現場に定着せず形骸化してしまいます。そのため、以下のようなマニュアルが活用される仕組みを作ると良いでしょう。
- マニュアルの使い方や管理方法を教える
- チェックリストを用いて、マニュアルの活用を促す
マニュアルが活用される仕組みづくりの具体的な方法については、次章『マニュアルで現場のルールを定着させる効果的な周知方法』でご紹介します。
STEP③ 管理/運用ルールを定める
「どこにどのマニュアルがあるかわからない」状態だと、必要なときに閲覧できず、活用されないままになってしまいます。管理方法や運用ルールを明確にして、全従業員がマニュアルにすぐアクセスできる環境を整えることが重要です。
STEP④ 定期的に更新を行う
マニュアルの内容が古いと、現場で使われなくなってしまいます。マニュアルは、決算期や繁忙期を避けて半年に1回/年に1回といったペースで定期的に更新を行いましょう。
マニュアルの更新に適したタイミングや改訂方法は、以下の記事で詳しく解説しています。改訂履歴の書き方や改訂手順なども解説しているので、更新前に参考にしてください。
▼関連記事▼
【マニュアル改訂方法】表紙の書き方から履歴の残し方まで!目的も解説
マニュアルで現場のルールを定着させる効果的な周知方法
マニュアルで現場のルールに定着させるには、大前提として従業員にマニュアルの存在を周知させる必要があります。形骸化してしまうマニュアルの特徴の1つとして「マニュアルの存在を知らなかった」ということも挙げられるので、全従業員に知ってもらえるよう、以下の周知方法を行ってください。
なぜそのルールがあるのかを明確に伝える
いくらルールを定めても従業員が腹落ちしないと、ルールを軽視してしまい、遵守されない可能性があります。そのため、なぜそのルールがあるのか、なぜ守る必要があるのかなどを明確に周知するようにしましょう。
ルールを設定している意味合いを理解してもらうことで、従業員ごとに現場にあるルールを守る重要性の認識を統一することができます。
従業員が「確実に見る」仕組みを作る
マニュアルがあっても従業員が存在を認識していないと意味がありません。また、口頭で「マニュアルを見ておいてね」と口頭で伝えておいても、日々の業務をこなしている従業員が確実に見てくれる保証はありません。
例えば、「業務の開始時に必ずマニュアルを確認する」などの確実に見る仕組みを設定することで、マニュアルを閲覧する習慣が身につき、ルールの遵守率も向上するでしょう。
このような仕組みづくりを行うことで、不明点がある場合は「人に聞く」のではなく「マニュアルを参照する」という習慣がつき、効率的な教育体制を構築/質問を受けていたベテラン社員の機会損失の削減が可能になります。
ベテラン従業員を巻き込む
従業員の中でも社歴の長いベテラン従業員は現場内でも影響力があるため、ベテラン従業員に「マニュアルを周知してもらう」「ルール定着に協力してもらう」などは効果的な周知方法の一つです。
いきなり定着するのはハードルが高いため、どの従業員が良い意味で声が大きい(影響力がある)のかを考え、小さい範囲から定着を進めていきましょう。
ルールの理解度テストを定期的に実施する
従業員に業務内容のテストを実施し、「テスト対策としてマニュアルを参照して勉強してください」とアナウンスすれば、マニュアルを見たことがない/マニュアルの存在を知らないという人も、マニュアルを見ながら学習するでしょう。とくに、評価や報酬が関連付けられている場合、学習意欲が向上する傾向があります。
定期的にチェックテストを行えば、従業員は継続的にマニュアルの内容を復習し、周知だけではなく定着も促せます。
ルールを守っている従業員を評価する
朝礼や張り紙などでルールを守っている人を称えて評価することもルールを周知する上で大切です。当事者にとっても、気分が良く、ルールに関する話題が増えるために意識も強くなるでしょう。
金銭的なインセンティブを付与する必要まではありませんが、従業員がルール遵守の意欲向上に寄与する対価を与えるのも検討してみてください。
ルールを定着させるために「動画マニュアル」の活用も手段のひとつ
ルール定着に向けて文書のマニュアルを活用しているケースも多いかもしれませんが、わかりやすさを求めるのであれば「動画マニュアル」がおすすめです。
動画マニュアルは文書のマニュアルと比べて閲覧する心理的なハードルが低く、文章を読むことに抵抗がある従業員でも目と耳でスムーズに情報を得ることができます。また、短い時間で濃い情報を伝わることも期待できます。
マニュアルを作成する業務負担の面でも、テキストで説明する文書マニュアルと比べて、撮影するだけの動画マニュアルのほうが負担が少なく、効率的に作成することができるでしょう。
動画マニュアルについてもっと詳しく知りたい方は、紙マニュアルの課題や動画マニュアルのメリットを詳しく解説している以下の資料も併せてご覧ください。
動画マニュアルの作成には「tebiki」がおすすめ
「動画マニュアルで現場のルールを定着させたい」と検討している方は、様々な現場で導入されている「tebiki」がおすすめです。パソコンの操作に不慣れな方でもカンタンに動画編集ができ、公開作業や管理までもとてもカンタンにできます。
ここからはそんな「tebiki」の特徴を紹介していきます。
▼tebiki現場教育紹介動画▼
- スマホひとつで簡単に作成できる
- アクセス履歴や習熟度の進捗が一目でわかる
- タスク機能で従業員に対してルールの周知を定期的に実施できる
- 検索性が高く、見たいマニュアルがすぐ見つかる
- 100ヶ国語以上に自動翻訳でき、外国人従業員にも利用できる
スマホひとつで簡単に作成できる
tebikiは簡単に動画マニュアルを作成できるように、編集の工数がかかる字幕の作成を自動で行える機能を搭載しています。そのため、tebikiでは、以下の3ステップで動画マニュアルを作成できます。
- スマホなどで撮影
- 撮影した動画をtebiki上に保存
- 自動生成された字幕を確認

動画マニュアルだけでなく、文書ベースのマニュアルも作成可能なため、作業内容や用途に応じて使い分けることも可能です。導入いただいている企業にtebikiのおすすめポイントを伺うと、多くの方に「操作の簡単さ」と言っていただけるほど、tebikiは簡単さが魅力なツールとなっています。
アクセス履歴や習熟度の進捗が一目でわかる
tebikiでは、動画マニュアルを作成できるだけではなく、アクセス履歴や習熟度をグラフで可視化できるため、マニュアル運用を効率よく進めることが可能です。また、理解度テストを実施する機能も搭載されているため、教育の効果検証も簡単に行えます。

より詳しく知りたい方は、tebikiのサービス概要や導入サポートなどをまとめた資料もご覧ください。機能の詳細やサポート体制などのご紹介もしています。
タスク機能で従業員に対してルールの周知を定期的に実施できる
「このマニュアルをいつまでに閲覧してください」という閲覧指示を期限つきで設定できるため、新しく作ったマニュアルの周知やルールの定着が効率的に行えるでしょう。閲覧したかどうかは、各マニュアルついている「できるボタン」を押してもらうことで管理できます。
また、作成した動画マニュアルをコースにしてグルーピングできるため、新人が入ってきてもコースの閲覧をタスクとして出しておけばルールの定着につながるでしょう。
検索性が高く、見たいマニュアルがすぐ見つかる
tebikiで作成したマニュアルは、クラウド上で一元管理されます。そのため、「見たいマニュアルがどこにあるかわからない」という状態を防止できます。また、検索性の高さも魅力で、マニュアルタイトル/説明文/タグなどからキーワード検索が可能です。
マニュアル一つひとつをQRコード化することもできるため、探さずとも瞬時にマニュアルを閲覧できます。
▼tebikiで作ったマニュアルをQRコード化している事例▼
(株式会社テック長沢の導入事例より)

100ヶ国語以上に自動翻訳でき、外国人従業員にも利用できる
tebikiは100ヶ国語以上の言語に対応しており、ボタン1つで翻訳が可能です。そのため、外国人スタッフが多い職場でも、スムーズにマニュアル運用を進められるでしょう。実際に、tebikiを導入している企業からは「翻訳工数がゼロになった」「教育の定着度が向上した」などの嬉しい声をいただいています。

現場で重宝されているtebikiの導入事例
現場でtebikiを活用し、効果的な教育が行えている事例を3選ご紹介します。教育効果だけではなく、コスト削減や業績向上などの効果も出ている事例なので、運用方法や教育方法の参考にしてください。
より多くの企業事例を読みたい方は、『【業界別26社】動画マニュアルの事例とサンプルを多数ご紹介』という記事か、以下の導入事例集も併せてお読みください。
OJTの約7割をtebikiに置き換えて定着!教育工数の削減&営業品質のバラツキが解消:株式会社GEEKLY
IT・WEB・ゲーム業界に特化した人材紹介を行っている株式会社GEEKLYでは、教え方のバラツキにより、新入社員の理解に差が生まれるという問題を抱えていました。そこで、教育内容を統一するためにtebikiを導入し、1年で1,300本以上の動画マニュアルを作成。
OJTの7割近くを動画マニュアルに置き換えることで、業務内容や営業品質のバラツキを解消することに成功しました。年間にするとOJTの時間を約3,700時間削減できたため、トレーナーが他の業務に集中できるようになり、目標未達の状態から脱却できました。
株式会社GEEKLYの導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
▼インタビュー記事▼
年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上
操作が簡単だからこそ現場に浸透。月30万円の教育コストを削減:サッポログループ物流株式会社
食料品の輸配送を行っているサッポログループ物流株会社では、動きを伴う作業をうまく伝えられず、業務が属人化してしまうという問題を抱えていました。そこで、tebikiで動画マニュアルを作成し、業務内容やノウハウを可視化することに。
その結果、業務がわかりやすく伝えられるようになり、効率よく技術伝承を進めることに成功しました。また、従来の紙マニュアルよりと比べると3割程度の時間でマニュアル作成できるようになったため、作成の負担も大幅に軽減しました。
サッポログループ物流株式会社の導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
物流現場の動画マニュアル導入事例│物流現場のノウハウを動画で可視化!ロジスティクスの生産性を上げるため人材教育の課題に挑む
読まれない紙マニュアルから、現場で使われる動画マニュアルに:株式会社安藤・間
土木事業や建築事業を行っている株式会社安藤・間では、国内外300以上の現場で利用されている現場サポートシステムの使い方を周知できず、大量の問い合わせに対応しなければならないという問題を抱えていました。そこで、利用者がアクセスしやすく簡単に社内展開できるtebikiを導入。
システムの操作方法を解説した1〜2分程度の動画を作成することで、問い合わせの数を7割程度削減することに成功しました。また、tebikiで動画マニュアルを展開できるため、動画マニュアルを掲載する社内ポータル作成や保守業務が不要になり、マニュアル運用のコストを約8割も削減できました。
株式会社安藤・間の導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
▼インタビュー記事▼
動画マニュアル導入事例 │「利用者からの問合せ」や「新システムの普及展開」に関わる工数を8割削減!
現場で定めたルールが定着しない理由
そもそも現場でルールを定めているにもかかわらず、なぜルールが定着しないのでしょうか?ここでは、現場で定めたルールが定着しない理由について紹介していきます。
規定の作業手順書に沿って作業をしてくれないと悩んでいる方は、以下の資料をご覧ください。手順書通りにできない理由やルールを守ってもらうためのポイントをわかりやすくまとめています。
ルールがあること自体を認識していない
管理側がルールを定めていても、従業員がルールがあること自体を認識していないケースがあり、このような状態だとルールは普及しません。
これは、ルールを策定すること自体が目的となっていて、その後の浸透まで考えられていないのが原因です。「マニュアルで現場のルールを定着させる効果的な周知方法」で紹介したように、ルールを周知する方法を検討してみてください。
ルールを守る重要性が伝わっていない
従業員がルールを守る重要性を理解していないのも定着しない理由の一つです。ルールを設定するだけではなく、「なぜそのルールがあるのか」「ルールを守らないことでどのようなリスクがあるのか」などもセットで考えてみましょう。
特に危険が伴うような作業の場合には、ちょっとしたミスが大きな事故に発展する可能性もあるので、ルールを守る重要性をしっかりと伝える必要があります。
従業員の慣れや怠慢によって形骸化している
社歴や年齢、経験など従業員によって異なり、特に社歴が長く経験豊富なベテラン社員は、慣れによってルールの存在は知っているものの、ないがしろにしているなどの形骸化しているケースがあります。
形骸化を回避するためにも、「ルールを定期的に見直して更新する」「定期的にルールを周知する」など、常にルールを認識する働きかけが重要です。
現場にルールが定着しないことで起こりうるリスク
定めたルールが定着しないことによって、長期的に考えると大きなリスクに発展する可能性があります。
労働災害に発展する
主に製造現場においては、日常的な業務の中で様々なリスクが潜んでおり、些細なルールの不遵守が大事故に発展してしまい労働災害を引き起こす可能性があります。
一例として、厚生労働省の令和5年労働災害発生状況の分析等によると、製造業における労働災害での死亡者数は他業種と比べて最も多く、27,194人にも及びます。最悪の場合、死亡事故につながるので、日常的なルールを守った上で業務にあたるような働きかけが大切と言えるでしょう。
品質不良のリスクがある
ルールが定着しないことによって、作業の品質にバラツキが生じてしまう可能性があり、結果として品質不良に陥るリスクも考えられます。「4M」に当てはめると「Man」の要素がルールの不定着による品質不良の原因です。
- Material(材料)
- Man(人)
- Machine(機械)
- Method(方法)
人による品質不良を防ぐためにも、「新人従業員の作業ルール」「体調管理のルール」「作業負荷のルール」などの設定や整備が必要と言えるでしょう。
業務が標準化されずに、業務効率化が低下する
現場には経験年数や年齢が異なる様々な従業員が作業にあたっているため、基準となるルールを定着させないと業務が標準化されない可能性があります。
標準化されずにそれぞれのスキルや経験をもとにした「カン」「コツ」に頼ってしまい、従業員ごとの習熟度が均一化されずに属人化してしまい、結果として業務効率の低下を招くリスクがあるのです。
なお、動画マニュアル作成ツールのtebikiを活用し、新人の教育品質質の均一化を実現した「ソニテック株式会社」のような事例もあります。以下より記事をご覧ください。
▼インタビュー記事▼
3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現
【まとめ】現場でのルール定着には動画マニュアルの活用がおすすめ
現場でルールを定着させるためには、わかりやすいマニュアルであるかどうかを見直した上で、マニュアルが活用される仕組みを作ることが重要です。ただ、作っただけでは意味がないため、「マニュアルで現場のルールを定着させる効果的な周知方法」でご紹介したことを参考にしつつ、定着をするように取り組んでみてください。
なお、わかりやすいマニュアルを作成したいと考えている方には、紙ではなく、動画マニュアルがおすすめです。
動画マニュアルを作成するツールは数多くあるので、どのサービスが良いのか悩んでいる方は動画マニュアル作成ソフトを比較しているこちらの記事もチェックしてみてください。
また、以下の資料ではより詳しく動画マニュアルソフトの比較や事例からわかる動画マニュアル活用の課題などをご紹介しております。併せてご覧ください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。