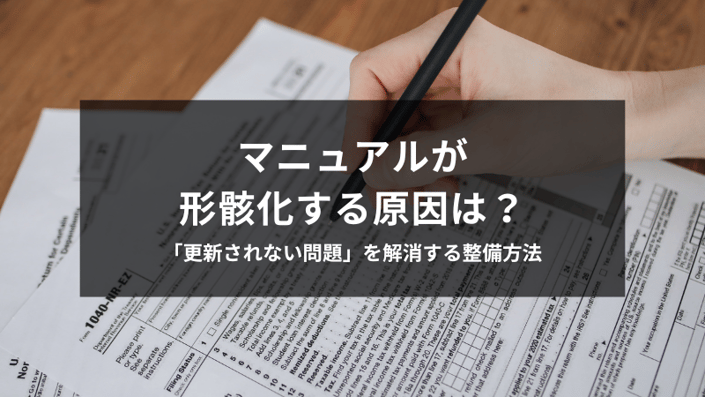

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開するTebiki株式会社です。
「マニュアルはあるけれど、更新されないために形骸化してしまっている」という方、意外と多いものです。マニュアルが形骸化してしまう状況には理由があります。この記事では、形骸化する理由やマニュアルが活用されるためのポイントをご紹介し、どのようなマニュアルなら形骸化せず活用され続けるのか解説します。
なお、マニュアルの形骸化を防止している企業では、マニュアルの動画化が進んでいます。実際に使われない・形骸化を防止している企業の好事例をまとめた資料も用意していますので以下をクリックしてあわせてご覧ください。
>>動画の活用で「使われないマニュアル」を卒業した企業の事例集を見てみる
目次
- 1. なぜ?「マニュアルが形骸化」「更新されない」原因
1-1. マニュアルを守る重要性が軽視されている
1-2. マニュアルがわかりにくい
1-3. 保管場所や保管方法が周知されていない
1-4. 更新ルールが存在しない
1-5. 更新作業が煩雑で、修正に手間がかかる
2. マニュアルを形骸化させないためのポイント
2-1. マニュアルが活用される風土をつくる
2-2. 現場の声を反映させてマニュアルを作る
2-3. マニュアル運用ルールを決める/見直す
3. マニュアルの形骸化を解消し、「現場で使われる」マニュアルを整備した企業事例
3-1. タマムラデリカ株式会社
3-2. 御幸毛織株式会社
3-3. MSSステンレスセンター株式会社
4. 【結論】 マニュアルが形骸化していない企業の共通点は「一目見れば理解できるマニュアル」が採用されている
4-1. 動画マニュアルが簡単に作れる「tebiki現場教育」
5. マニュアルの形骸化がもたらす脅威
5-1. トラブルや事故のリスクが増加する
5-2. 手順が標準化せず業務効率が悪化
5-3. OJT頼みの教育になり現場負担の増加 - 6. まとめ
なぜ?「マニュアルが形骸化」「更新されない」原因
そもそも形骸化とは「内容がなく形だけのものになる状態」を指します。マニュアルが形骸化すると「更新されない」状態になり、ますます現状と乖離し、使いにくさを増すばかり。つまり、形骸化したマニュアルを放置すればするほど負の連鎖を生み出します。
ここでは、「マニュアルが形骸化する原因」や「更新されなくなる原因」をご紹介します。
「形骸化しないマニュアルの作り方」には一定のポイントが存在しますが、それらが解説された資料「マニュアル整備の教科書」は以下からダウンロード可能です。常にマニュアルが読まれ、更新される現場環境を作りたい担当者の方は特にご覧ください。
>>「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書を見てみる
マニュアルを守る重要性が軽視されている
せっかくマニュアルがあっても現場の従業員がマニュアルの重要性を理解していなかったり、マニュアルを見ず自分流の慣れた手順で作業してしまったりするとマニュアルはただ存在するだけで活用されず、結果的に業務品質の悪化やトラブル発生といった問題を引き起こすきっかけになってしまいます。
「自分流の慣れた手順」こそが、繰り返される「不安全行動」そのものです。その根本原因を、行動科学に基づいて解明し、断ち切る方法を解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
こうしたマニュアル使用者への周知に関する問題の解決策は、後述する『マニュアルを形骸化させないためのポイント』で解説します。
マニュアルがわかりにくい
わかりにくいマニュアルの場合、「マニュアルを見ても分からない」という認識になり形骸化してしまいます。わかりにくいマニュアルに共通している特徴は以下の通りです。
- 内容が専門的すぎる
- 文字だけの説明で作業が想像できない
- 検索性が低くて、知りたい内容が探し出せない など
言い換えると、マニュアルが形骸化していない現場の共通点は「一目見ただけで理解できる」マニュアルが整備されている点です。例えば、合成樹脂加工や産業機器の製造などを行っている児玉化学工業株式会社では、「ドリルで穴のバリをとる」作業を動画で可視化し、誰が見ても同じ手順で作業できるよう、マニュアルの整備を進めています。
分かりやすいマニュアルを作り形骸化を防ぐには、動画であってもそうでなくても、一定の「コツ」が必要です。分かりやすいマニュアル作成に必要な情報をギュッとまとめたPDF資料「成功に導く『わかりやすいコツ』つき!はじめてのマニュアル作成ガイド」を参考にすると、形骸化しないマニュアル整備のヒントが得られます。以下のリンクからダウンロードできるので、本資料を開きながら作成してみてください。
>>>「成功に導く『わかりやすいコツ』つき!はじめてのマニュアル作成ガイド」を読んでみる
保管場所や保管方法が周知されていない
保管する場所や方法が明確に定まっていないことで、見たいマニュアルがどこにあるのかわからず使いたいときに使えない、というマニュアルの管理に関する理由です。
似たような紙のマニュアルやWordファイルが複数あったり、保存場所がバラバラだったりすると、見るべきマニュアルがどれなのかわからなくなります。いざ新しい従業員が来たときに間違ったマニュアルを渡してしまってミスや失敗が発生し、「マニュアルは使わないでおこう」という意識が広がってしまいます。
更新ルールが存在しない
更新頻度 / 更新方法 / 更新後のマニュアルの承認フローなどの更新ルールが明確に定められていない場合、「いつ」「誰が」「どのように」更新すれば良いのか分からず、責任の所在も曖昧なまま、更新作業は先延ばしにされがちです。
その結果、マニュアルは時間とともに陳腐化し、現状と乖離し「形骸化したマニュアル」へと変貌してしまいます。
>>作業手順書が形骸化する原因「本当に意味のある」手順書を作るには?を見てみる
更新作業が煩雑で、修正に手間がかかる
特に、紙媒体のマニュアルや、複雑なレイアウトのマニュアルは、修正箇所を探すだけでも一苦労。修正内容を反映するのも手間と時間がかかってしまうため、担当者は更新作業を「面倒だ」と感じ、後回しにしてしまいがちです。
結果として、マニュアルは常に最新の状態を保てず、現状と乖離した情報が放置され、形骸化の一途を辿ります。
なお、煩雑な更新作業や複雑な修正といった「マニュアルの整備工数」を大幅に削減するには、紙ではなく「電子(データ)マニュアル」を活用すると改善されることが多いです。
例えば電子マニュアルの1つである「動画マニュアル」は、オンライン上の共有フォルダに動画データを格納するだけで、全国各地の拠点にリアルタイムで共有が可能です。更新する際も、共有フォルダの動画データのみを更新すれば全国のマニュアルも自動で更新(上書き)されるので、マニュアルの整備工数を大幅に削減できます。
動画マニュアルを活用している株式会社大商金山牧場では、拠点ごとに把握しきれなかった手順書が動画マニュアルの活用で一元管理できるようになっています。マニュアル整備の工数削減および高品質な手順書の全拠点へのスムーズな展開を可能にし、教育レベルを底上げしています。
マニュアル形骸化の抜本的改善が図れた「動画」を活用している現場は、同社以外にも多数存在します。そんな動画マニュアルによって現場教育を整備する方法がまとめられた資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法(PDF)」は、以下をクリックしてダウンロードできます。
>>動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法を見てみる
マニュアルを形骸化させないためのポイント
マニュアルを単なる「お飾り」ではなく、組織全体の成長を支える「生きた教材」とするためには、作成段階から運用まで、徹底した工夫が必要です。ここでは、マニュアルを形骸化させず、常に活用される状態を保つための3つの重要なポイントを解説します。
なお、形骸化させないためのポイントを理解したい方は、図解を用いて詳しく解説されている資料「「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書」をご覧ください。本記事よりも分かりやすく・重要な情報を絞ってまとめられているので、要点だけ知りたい方は特に参考にすると良いでしょう。
マニュアルが活用される風土をつくる
マニュアルを形骸化させないためには、まず組織全体で「マニュアルを活用する」という文化を醸成することが不可欠です。マニュアルは、単に業務手順をまとめたものではなく、知識やノウハウを共有し、組織全体の能力を底上げするための重要なツールであるという認識を共有する必要があります。
具体的には、以下の2つを実践すると良いでしょう。
マニュアルの必要性を浸透させる
マニュアルは必要な業務知識や成功例・失敗例などを集積した、いわば企業の財産です。新人時代に読んで終わりにするものではなく、従業員の異動などでの転入時、引き継ぎでも活用できるものですから、従業員間でコツやノウハウを共有するためのツールとして「みんなで情報を持ち寄り充実させていこう」という意識を浸透させましょう。
「みんなでマニュアルを充実させる」という理想とは裏腹に、多くの現場ではまず「手順書通りにできない」のが現実です。その現実から卒業するための、効果的な方法を解説します。
>>“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法を見てみる
従業員全員がマニュアルを「必然的に」見る仕組みを作る
マニュアルが従業員全員に必然的にみられるような仕組みを作りましょう。例えば、業務中や業務終了後の勉強会などマニュアルを見る「タイミング」を増やしたり、スマートフォンやタブレット端末など見る「手段」を増やしたり、マニュアルの更新担当者を当番制にするなど見る「人」を増やしたりします。細かい業務もマニュアル化し、マニュアルの「数」を増やすことも一法です。
例えば、産業機械などの製造・販売をしている新日本工機株式会社では、作業手順の説明だけではなく新人の実践的な教育で、動画マニュアルを閲覧してから作業に取り掛かるフローを確立し、マニュアルを確実に見る仕組みを構築しています。仕組みを構築したことにより、作業標準化を実現し作業品質の安定化につながっています。
同社の取り組みを詳細に知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
>>新日本工機株式会社のインタビュー記事を読んでみる現場の声を反映させてマニュアルを作る
実際の現場を理解していない状態で作成されたマニュアルは、現場の実態と乖離しやすく、現場で活用されることはありません。そのため、現場で実際に業務を行っている従業員の声を反映させて、マニュアルの実用性を高めると良いでしょう。
▼現場の声を反映させたマニュアル作りのHOW TO▼
- 作業のコツを理解している人が作成/更新する
- マニュアルに対するフィードバックを収集する仕組みを作る
- 現場の従業員にヒアリングを行う
現場の声を反映し、作業の「カンコツ」を盛り込むことで初めて、手順書は「現場で使われる」ものになります。そのための具体的な作成ポイントがこちらです。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
なお、マニュアルの作成や改訂時、現場担当者・管理者・新人など誰が主導して作成すべきなのか悩んでいる方は、「マニュアルは誰が作るのが正解?新人や派遣に作成を依頼しても良い?」の記事をご覧ください。
マニュアル運用ルールを決める/見直す
運用ルールがない状態では、マニュアルの更新が滞り、情報が陳腐化してしまうだけでなく、担当者の責任が曖昧になり、誰もマニュアルの管理に主体的に関わろうとしなくなる恐れがあります。形骸化を防ぐためには、適切な運用ルールを定めましょう。
具体的な運用ルールとしては、以下のようなものを定めることが推奨されます。
▼マニュアルの運用ルール例▼
|
更新頻度 |
マニュアルの内容を定期的に見直し、更新する頻度を定める(例:半年に1回、年に1回) |
|
更新担当者 |
マニュアルの更新を担当する人を明確に定める |
|
更新方法 |
マニュアルの更新手順を定める(例:修正依頼書を作成、承認を得てから修正) |
|
承認フロー |
更新されたマニュアルを承認する人を定める |
|
マニュアルの周知方法 |
マニュアルの変更があった際に、関係者に周知する方法を定める |
|
マニュアルのアクセス方法 |
従業員がいつでも必要な時にマニュアルにアクセスできるように、アクセス方法を定める |
>>「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書を見てみる
マニュアルの運用や更新に関するポイントをより詳しく知りたい方は、以下の関連記事もぜひご覧ください。
▼関連記事▼
作業手順書の見直し・改訂のタイミングは?手順や見直さないリスクを解説
【マニュアル改訂方法】表紙の書き方から履歴の残し方まで!目的も解説
マニュアルの形骸化を解消し、「現場で使われる」マニュアルを整備した企業事例
ここでは、マニュアルの形骸化を解消し、活用されるマニュアルを整備した企業の好事例を紹介していきます。どのような方法が効果的なのか参考にしてみてください。
タマムラデリカ株式会社
中華麺や軽食惣菜などの開発製造を手掛けている食品メーカーのタマムラデリカ株式会社。同社では、紙マニュアルとOJTを中心にした教育を実施していたものの、マニュアルでは詳細な動き・ニュアンスが伝わらず、マニュアルが活用されない課題を抱えていました。
この課題を解消すべく、動画マニュアルを導入。紙マニュアルと比べて細かいニュアンスが伝わるようになり、繰り返し動画を見返せるため、マニュアルの活用頻度の増加につながっています。また、これまでルールを間違って覚えていた従業員に対して、動画マニュアルで再教育したところルールを正しく理解できてミス削減にもつながったとのことです。同社の詳細な事例は以下のインタビュー記事をご覧ください。
御幸毛織株式会社
オーダースーツ事業、ユニフォーム事業など紡績から縫製、販売まで一貫して服飾に携わっている御幸毛織株式会社。同社では、40代・50代のベテラン社員の技をいかに若手へ継承するために、紙ベースで教育を行っていたものの、細かな動きや絶妙なニュアンスなどが伝わらず、マニュアルが形骸化する課題を抱えていました。
この課題を解消すべく、動画マニュアルを導入し、紙ベースで運用していたマニュアルの動画化を推進。動画マニュアルの活用によって、作業手順が伝わりやすくなりミスやトラブルが減少し、安全教育にも効果がでていると実感しています。また、マニュアルの利用が活発化したことで、ベテラン従業員しかできなかった業務を誰でもできるようになり、属人化解消にも寄与しています。同社の詳細な事例は以下のインタビュー記事をご覧ください。
MSSステンレスセンター株式会社
熱間・冷間圧延ステンレス鋼板や鋼帯の加工/販売に携わっているMSSステンレスセンター株式会社。同社では、マニュアル作成や改訂に手間がかかり、現場で改訂が行われずにマニュアルが形骸化してしまう課題を抱えていました。結果として、教育内容にバラつきが生じていたようです。
この課題を解消すべく、動画マニュアルを導入。現場の従業員が自発的に動画の撮影・編集を行い、動画マニュアルの作成や改訂が活発化する効果を実感しています。また、紙とは違い、タブレット上ですぐに動画マニュアルを視聴できるので、繰り返しマニュアルを視聴することも習慣化しているとのことです。同社の詳細な事例は以下のインタビュー記事をご覧ください。
>>MSSステンレスセンター株式会社のインタビュー記事を読んでみる
ここまで紹介してきた企業以外でも、マニュアルの形骸化を防止することを目的の1つとして、動画マニュアルを活用している企業は数多くあります。実際に活用されている動画マニュアルのサンプルをまとめた資料も用意していますので、活用イメージをより具体的にしたい方は、以下をクリックしてご覧ください。
>>実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集を見てみる
【結論】 マニュアルが形骸化していない企業の共通点は「一目見れば理解できるマニュアル」が採用されている
「マニュアルの形骸化を解消し、「現場で使われる」マニュアルを整備した企業事例」で紹介した企業の好事例から、マニュアルの形骸化を解消している企業には、「一目見れば理解できるマニュアル」が採用されているのがわかります。
一目で理解できるマニュアルは、紙で実現するのは難しく、事例で紹介した企業のいずれも動画を活用してマニュアルを作成しています。紙ではなく、動画でマニュアルを作成するメリットは以下の通りです。
- 閲覧するハードルが低くなり、活用が促進される
- 視聴者によって理解にばらつきが生まれにくい
- 教育工数/作成工数が削減される
- 全拠点で同時更新/即時共有ができる
紙・動画それぞれの特徴の比較を詳しく知りたい方は、「【紙と比較】動画マニュアル特有のメリットとデメリット」の記事もご覧ください。
動画マニュアルが簡単に作れる「tebiki現場教育」
「tebiki現場教育」は、動画の撮影〜編集がかんたんにでき、誰でも動画マニュアルを作成できるツールです。属人化しやすい編集作業も直感的な操作性で工数を最小限に抑えられます。実際にtebiki現場教育を活用している企業の中には、導入からわずか半年の間に400本もの動画を作成した実績もあります。
また、以下のようなマニュアルを形骸化させない特徴があるのもポイントです。
- 字幕は音声によって自動生成され、かつ100カ国以上の言語へ自動翻訳できる
- キーワード検索により短時間で必要な動画を探すことができる
- レポート機能でマニュアル活用状況が可視化される
- テスト機能で使用者の理解度をチェックできる
tebiki現場教育の詳しい案内や具体的な機能、動画マニュアルの基礎知識について以下をクリックすると資料を無料でダウンロードできます。動画マニュアルの導入を検討されている方やtebikiについて詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。
マニュアルの形骸化がもたらす脅威
マニュアルが現場で使われずに形骸化することで、以下のような問題が発生するリスクがあります。
こうした問題を起こさせないためには、形骸化しないわかりやすいマニュアル作りが欠かせません。活用されるマニュアルを整備する方法を知りたい方は、以下のリンクをクリックして「マニュアル整備の教科書」をご覧ください。
>>【無料で資料を読む】現場で本当に活きるマニュアルの作り方とは?
トラブルや事故のリスクが増加する
マニュアルは業務に必要な知識を集約したものであり、職場で起きたこれまでの失敗例をふまえたコツを伝える手段でもあります。マニュアルを使わないとそれらの大切な情報が伝わらず、従業員が怪我や事故に遭遇したり、取引先や顧客へきちんとしたサービスを届けられなくなる可能性があります。
大きなトラブルや問題になればなるほど、社会的な信頼が損なわれてしまうことになりかねません。このような最悪なケースを未然に防ぐためにも、マニュアル化が形骸化しないように取り組む必要があります。
マニュアルが形骸化し、過去の失敗が共有されないことで繰り返される「不安全行動」を、行動科学の力で根本から防ぐ方法を解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
手順が標準化せず業務効率が悪化
マニュアルがあれば、標準的な業務手順や業務範囲を定め、共有することができます。ところがマニュアルを使わないと人によって手順や業務の範囲がまちまちになってしまい、作業の質を一定水準以上に保てなかったり、サービスレベルがバラついたりしてしまうことにつながります。他にも、不良品率が上がったり過剰サービスをしてしまったりなど、生産性の低下につながるおそれもあります。このような業務のムダを防ぐためにもマニュアルによる標準化が大切です。
OJT頼みの教育になり現場負担の増加
新人教育でマニュアルを使わず、先輩従業員によるOJT指導がメインとなると、人が入れ替わる時期に現場に負担がかかってしまいます。マニュアルがあれば、先輩従業員が忙しい時間帯でも新人が基礎的内容を自習することができます。マニュアルがないと先輩が不在では何もできなくなり、早期戦力化につながりにくくなります。
また、OJTで一度教わっただけではすべて覚えきれずあとで不明点を確認したい場合に、先輩が多忙で聞くことができず、つい独断でやって失敗してしまうことも。その失敗の修正や新人への指導で現場の負担が大きくなってしまいます。
これらの脅威を排除するためには、形骸化しないためのマニュアル作りや運用体制の構築が重要です。排除する手段として、紙ではなく動画を活用したマニュアル作成がおすすめ。「「現場で使われる」マニュアルを整備した企業事例」でも紹介したように、動画の活用でマニュアルの形骸化を防止している企業は数多くあります。
OJT頼みの教育が引き起こす「現場負担の増加」という悪循環を断ち切り、担当者の負担を激減させる「OJT教育の新常識」を解説します。
>>OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識を見てみる
まとめ
マニュアルは作成するだけでもかなりの工数が発生するため、マニュアルが誰にも使われずに形骸化してしまうと、作成にかけた時間がムダになってしまう可能性があります。そのため、作成・活用する段階で、形骸化しないための工夫を凝らすのが大切です。
形骸化を防止する有効な対策としては、動画マニュアルをかんたんに作成できる「tebiki現場教育」の活用がおすすめ。一目見れば誰でも理解できるマニュアルを作成できます。ぜひ、tebiki現場教育を活用して、マニュアルが活発に活用される環境を構築してみてください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。




