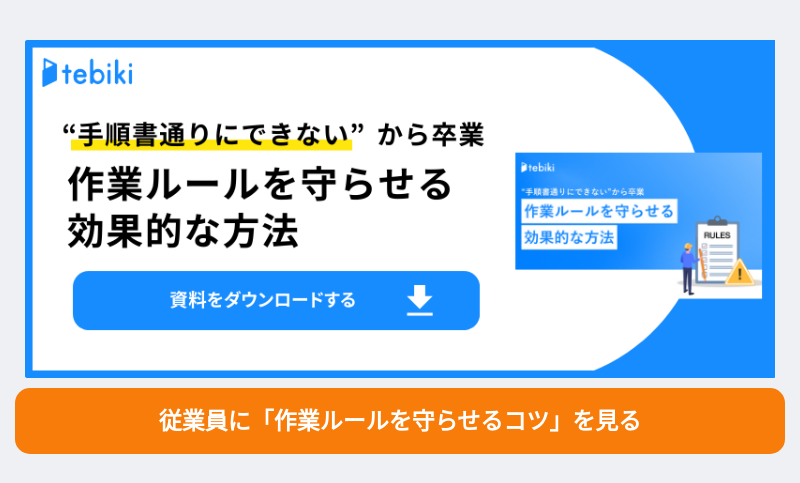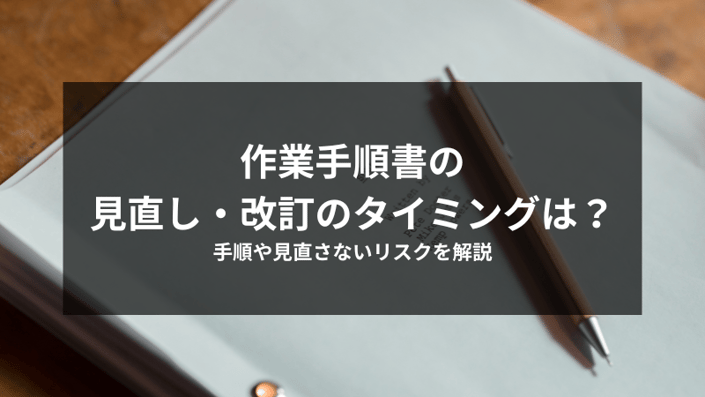

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開するTebiki株式会社です。
業務の手順をわかりやすくまとめた作業手順書。「修正箇所があっても全体の見直しや改訂ができない...。」という方も多いのではないでしょうか?
作業手順書を見直さないままでは、少しずつ実際の業務と作業手順書の内容が乖離していき、作業のバラつきや不良品の増加、業務中の事故などが発生するリスクがあります。
そこで今回は、作業手順書を見直し改訂すべきタイミングや見直さない場合のリスク、見直しが進まない理由や効率的に進める手順について詳しく解説します。作業手順書の見直しをしようと思っていてもなかなか着手できていない方、どのタイミングで見直すべきなのかを知りたい方はぜひご覧ください。
目次
- 1. 作業手順書の見直しタイミングはいつ?
1-1. 作業ルールや手順に変更や修正があった時
1-2. 期日を決めて定期的に実施
1-3. 品質不良や事故などが発生した時
2. 作業手順書の見直し・改訂を行わないリスク
2-1. 「古い作業手順書」として形骸化する
2-2. 多能工化できずに属人化する
2-3. 手順にバラつきが生じてムダやミスが増える
2-4. 品質不良や労災の引き金になる
3. 作業手順書を動画にすると見直し・改訂の工数が減らせる
3-1. 全ての拠点で同時更新・即時共有ができる
3-2. 作業手順書の管理コストを削減できる
3-3. 複雑な業務手順を動画で視覚的に説明できる
4. 手順書の作成には動画マニュアル作成ツール「tebiki」がおすすめ
5. 作業手順書の見直しや改訂が進まない理由
5-1. OJTに依存しすぎた教育のため作業手順書を活用していない
5-2. 取りまとめる担当者やルールが定まっていない
5-3. 現場が忙しすぎて手順書をブラッシュアップする暇がない
5-4. 社内承認や差し替えの手間がかかる
6. 作業手順書の見直し・改訂を効率的に進める5つの手順
6-1. ステップ1.改善点や要望をヒアリングする
6-2. ステップ2.改訂目的を明確にする
6-3. ステップ3.改訂作業を行い、改訂履歴を作成する
6-4. ステップ4.問題がないか作業観察を行う
6-5. ステップ5.定期的な見直しを行う - 7. まとめ
作業手順書の見直しタイミングはいつ?
作業手順書は業務の標準的なやり方を説明するものであり、特に新人や引き継ぐ人へ業務を説明する際には最新の状態にしておきたいものです。
そのため、見直しや改訂は以下のタイミングで行うことをオススメします。
作業ルールや手順に変更や修正があった時
作業手順書に記載されている内容から、作業ルールや手順が変更された場合、早急に見直しを実施して改訂しましょう。手順書と実際の作業に相違があると、品質不良はもちろん生産性の低下など様々なリスクが考えられます。
また、作業手順書の内容が更新されない状態が続いてしまうと、手順書が形骸化してしまい、従業員ごとの感覚で作業が行われてしまうことも。私たちが運営する「現場改善ラボ」で、製造業に従事する会員318名を中心に【作業手順書の形骸化に関する実態調査】を行ったところ、手順書が形骸化する背景で最も多かったのは「作業手順書を更新する時間がない」という結果もあります。

形骸化しないためにも、常に最新の状態にアップデートしておくことが大切です。その他、手順書の運用/管理のポイントについて詳しくまとめている資料「カンコツが伝わる!『現場で使われる』作業手順書のポイント」をご用意しておりますので、併せてご確認ください。
期日を決めて定期的に実施
手順やルールに変更がない場合でも、定期的に手順書の見直しを実施して更新していくサイクルを作ることも大切です。定期的に更新することで、手順書の形骸化を防ぐことができます。
なお、手順書の更新・改訂を実施したタイミングで従業員への周知も忘れずに行いましょう。
品質不良や事故などが発生した時
作業において、品質不良、事故などがあった時に、作業内容の見直しに加えて作業手順書の見直し・改訂も実施しましょう。
特に品質不良が発生する主な原因を分類すると「ヒューマンエラー」「材料不良」「管理体制不備」の3つに分けられ、その中でも「ヒューマンエラー」に起因する品質不良は改善がしやすく、改善インパクトが大きいです。
ヒューマンエラーの発生として多いのは、「手順不遵守」であり、この不遵守については、作業手順書を正しく作成〜管理することで改善が見込めます。以下の資料で詳しく説明しているので、気になる方は以下の資料をダウンロードしてご覧ください。
>>「手順不遵守に起因する品質不良対策の考え方と対策」を見てみる
作業手順書の見直し・改訂を行わないリスク
作業手順書の見直しや改訂をしていないと、作業手順書の内容が実際の業務と乖離している可能性があります。それによって以下のようなリスクが生じる恐れがあります。
「古い作業手順書」として形骸化する
作業手順書を改訂しないままで実際の業務との乖離が進むと、新人への指導に作業手順書を使わなくなっていきます。作業手順書を使わずに教えられた新人は、やがて後輩を教える際に、やはりように同じように作業手順書を使わずに教えるようになります。
こうして作業手順書が形骸化し、誰も読まなくなるおそれがあります。このような古い作業手順書は悪い作業手順書の一例です。「製造業における「良い作業手順書」と「悪い作業手順書」の違い」で良い例・悪い例をご紹介しているので併せてご覧ください。
作業手順書が形骸化してしまう理由や形骸化を解消する方法を詳しく知りたい方は「作業手順書が形骸化する原因「本当に意味のある」手順書を作るには?」の資料も併せてご覧ください。
多能工化できずに属人化する
作業手順書の見直し・改訂が行われないと、作業手順書と実務で内容に乖離が生まれてしまい、作業が属人化してベテラン従業員のみができる作業が生まれます。このように属人化が進むと、従業員ごとのカンコツによって作業が行われるため、業務の標準化が進まなくなってしまい悪い循環が生じることも。
また、属人化することで手順や数値が明確に定義されないカンコツを要する作業が発生してしまい、新人への技術伝承ができず人材育成にも影響を及ぼす可能性も考えられます。
伝わらない・属人化している作業を標準化するうえでは、標準化する方法を具体的に紹介している以下の資料をご覧ください。
>>>“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解
手順にバラつきが生じてムダやミスが増える
手順にバラツキが生まれ、ムダな作業や過去にミスが多かった作業を再発する可能性も考えられます。
例えば、改善された手順が作業手順書に反映されていない場合、改善後の手順を知らない人はムダな作業をしたり、過去にミスが起きた工程で同じミスを起こしたりするなどです。さらに、作業手順書を更新しないと、他の人に教える際に改善前の手順を教えてしまう可能性もあります。
このようなムダやミスを増やさないようにするためにも、従業員に作業ルールを守ってもらうような工夫が大切です。
以下の資料では、「手順書通りにできない理由」「作業手順を守ってもらう方法」などをわかりやすく紹介しています。手順書の作成や管理で悩んでいる方はぜひ資料をご覧ください。
品質不良や労災の引き金になる
製品の品質不良や労災が発生するリスクがあります。例えば製造業では、従業員の衛生や安全を守りつつ効率的で生産性の高い、標準となる手順があります。
標準的な手順を作業手順書に定めていても、変更に即した修正を行っていないと、変更前の手順で製品を製造してしまい不良品率が上がったり、製造工程での事故で従業員がケガをするおそれがあります。
作業手順書を動画にすると見直し・改訂の工数が減らせる
作業手順書を効率的に見直し・改訂するためには、紙で作成するのではなく、手順書自体を動画にする方法があります。動画マニュアル作成ツールを利用し、作業の風景を撮影し、編集して作業手順書として利用するイメージです。
ここでは、作業手順書を動画にすることで、なぜ見直す工数を削減できるのか詳しく紹介していきます。
全ての拠点で同時更新・即時共有ができる
紙の作業手順書の場合、見直しを実施して更新・改訂を行うと特定の拠点でしか共有することができません。拠点が複数ある場合には、各拠点に更新した旨を通知し、拠点ごとに手順書を印刷・周知する必要があります。
一方、紙ではなく動画化すれば、特定のドライブにデータをアップロードするだけで全ての拠点に共有できるので、更新した内容をすぐに伝えることが可能です。
動画マニュアル作成ツール「tebiki」を活用している株式会社大商金山牧場では、拠点ごとに把握しきれなかった手順書がtebikiの活用で一元管理でき、質の高い手順書を各拠点に展開できて教育レベルの底上げにつながっていると効果を実感しています。事例を詳しく知りたい方は、以下より併せてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
衛生管理教育を徹底し、食肉の安全性を確実なものとするために動画マニュアルを活用!
作業手順書の管理コストを削減できる
紙の作業手順書は作業工程が追加されるごとに増えてしまうため、手順書をまとめておくファイルが非常に分厚くなってしまいます。どこにどの情報があるのかを整理したり、手順ごとにファイルを分けたりなどの管理コストが発生するのです。
動画マニュアルの場合は、Web上に動画を保管しておけるので、紙での管理と比べて圧倒的に管理工数を削減することができます。視聴したいマニュアルにすぐアクセスできるので、利用する従業員にもストレスがかかりません。
また、PCだけではなく、スマートフォンやタブレットなど様々な端末で管理することも可能です。タブレットで作業手順書を作成する手順をまとめている以下の記事もご覧ください。
▼関連記事▼
作業手順書は「タブレット」で電子化できる?作成手順やおすすめツールを紹介
複雑な業務手順を動画で視覚的に説明できる
紙の手順書では、複雑な作業をテキストや写真、イラストなどで表現する必要があり、従業員に理解してもらうために定期的な見直しが発生することもあるでしょう。
一方で動画を利用することで、作業風景をカメラで撮影し補足となる説明をいれるだけで、紙と比べてとてもカンタンに手順書の作成が可能です。ルールや手順の変更で改訂する際も、動画で撮り直しするだけで完了です。
手順書の作成には動画マニュアル作成ツール「tebiki」がおすすめ
動画マニュアル作成ツールとは、動画によるマニュアルや手順書の作成に適したツールであり、動画の編集から手順書の作成まで一貫して行うことができます。様々ある動画マニュアル作成ツールの中でも「tebiki」は、スマートフォンで撮影した動画を簡単に編集でき、誰でも動画の手順書を作れるのでおすすめです。
字幕が自動生成され、動画の切り取りや図形の挿入も直感的に行えるなど、高度な動画編集技術を学んだことのない現場の従業員も、動画の作業手順書を作ることができます。
他にも、100ヵ国語への自動翻訳機能や、誰が何時間どの動画を視聴したかをレポートで確認できるといったメリットもあり、製造業や物流業、小売業や飲食業などで広く活用されています。tebikiのサービスについてより詳しく知りたい方は以下よりサービス資料をダウンロードいただけます。
作業手順書の見直しや改訂が進まない理由
作業手順書の見直しや改訂をすべきだとわかっていてもなかなか着手できない理由は、どのようなものでしょうか。主な理由を4つ挙げ、解消するヒントをご紹介します。
OJTに依存しすぎた教育のため作業手順書を活用していない
本来、新人教育や引き継ぎ時には作業手順書を活用するとスムーズになりますが、先輩従業員が作業手順書を使わずにOJTで教えてしまう状況だと、仕事を覚えた後は作業手順書を見なくなり、従業員があまり意識を向けなくなります。
作業手順書は「業務の標準的な手順を記載し、業務の共有に活用するものである」という役割を再認識し、新人教育や引き継ぎでOJTと並行して活用することを徹底しましょう。
取りまとめる担当者やルールが定まっていない
作業手順書の見直し・改訂を取りまとめる担当者やルール、実施するタイミングが定まっていないと、よりよい手順書へ向けた改善はなかなか進みません。
そのような場合、まずは作業手順書の見直しが重要であることを再認識した上で、例えばチームやグループ内で2名を取りまとめ担当に任命し、見直しのルールやタイミングを話し合う中心的な役割を担ってもらいます。社内の業務の繁閑期から判断しやすい、定期的な見直しタイミングを決めてみるとよいでしょう。
現場が忙しすぎて手順書をブラッシュアップする暇がない
現場が忙しすぎて余裕がなく、作業手順書を見直す時間が取れないということが背景にあるケースも考えられます。
時間が取れない中でも、1日だけ「作業手順書を見ながら仕事をする日」を作り、作業手順書と実際の業務で違っていることがないか確認しながら業務を進めてみましょう。改訂がすぐできなくても、まずは見直すことが重要です。
内容がかなり古くなっているなど気づきがあると「何とかして作業手順書を改訂する時間を作ろう」という意識やモチベーションが高まります。
ブラッシュアップできない原因として、どんな手順書がわかりやすいのかという点を理解できずにどのように修正すればよいのかが不透明な可能性もあります。以下の記事では、わかりやすい手順書作成のコツをまとめているので併せてご確認ください。
▼関連記事▼
【テンプレあり】作業手順書のわかりやすい作り方!作成例も紹介
社内承認や差し替えの手間がかかる
見直し・改訂を行うのに、上席の社内承認が必要だったり、全営業所や工場に配備されているために差し替えるのに時間や手間がかかったりするものです。
手間がかかるから見直さないままでは、作業手順書が実際の業務と乖離してしまい、ブラックボックス化につながります。このまま見直し・改訂を行わずにいるとムダの発生や生産性の低下、品質不良に陥り、経営課題に結びつく可能性もあるため、手間をかけてでも取り組む必要があります。
作業手順書の見直し・改訂を効率的に進める5つの手順
作業手順書の見直しや改訂を効率的に進める手順を、5つのステップでご紹介します。
紙ベースの作業手順書の運用は、作成/管理/回収/修正/配布と多くの工数が発生するため、見直し・改訂のタイミングで『作業手順書のペーパーレス化』もご検討ください。
▼関連記事▼
【事例と方法】作業手順書・作業指示書のペーパーレス化!メリットやツール選定のポイント
ステップ1.改善点や要望をヒアリングする
作業手順書を使用している現場の従業員に改善点や要望をヒアリングし、見直す材料を集めます。
ヒアリングする内容としては、業務内容の変更に伴い修正すべきところ、表現の面で改善してほしいところや、内容の面で追加・削除してほしいところなどです。複数の目で見直すと一度にいろいろな意見を集められますので、できるだけ多くの従業員からヒアリングしましょう。
ステップ2.改訂目的を明確にする
ステップ1で集めた材料から、今回改訂する目的を定めます。
例えば業務内容が大きく変更していたなら、業務に沿った内容へ改訂することが優先的な目的です。もしくは、軽微な変更だけであれば、新人受け入れを意識した改訂を目的となるでしょう。
他にも、半年のサイクルのように定期的に行うならば「8月には変更点のみの改訂、2月には新人を意識した全面的な改訂」というようにあらかじめ目的を決めておいてもいいでしょう。
ステップ3.改訂作業を行い、改訂履歴を作成する
ステップ2で決めた目的にしたがって作業手順書を見直し、改訂作業を実施します。
作業手順書の見直しポイントに、ヒアリング時に付箋を貼るなどして、抜け漏れのないよう注意しながら改訂していきます。同時に、改訂した箇所については、改訂箇所・時期・理由などを別表に記録し、改訂履歴も作成していきましょう。
担当者2名で行い、一人が改訂作業を行ったらもう一人が再鑑するなど、複数人で推進すると集中的に効率よく進められます。
ステップ4.問題がないか作業観察を行う
改訂した内容に問題がないか、実際の業務を作業手順書に沿って実践し、確認します。
ステップ2で決めた目的を達成しているかを意識しながら「内容が間違っていないか」「表現が理解しやすいか」「体裁が見やすいか」の3つの視点から確認するとよいでしょう。
ステップ5.定期的な見直しを行う
今後も引き続き見直し・改訂作業を継続するために、定期的な見直しタイミングを決めておきます。例えば「5月・11月の第3週に行う」と具体的に決め、次回の担当者も決めておくとよいでしょう。
なお、本章で紹介した内容はあくまでも概要です。より詳しい手順書整備の手順を知りたい方は、手順書の管理や運用のポイントまで紹介している「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント」も併せてご覧ください。
まとめ
忙しくて見直し・改訂をする時間がないかもしれませんが、見直さないままでは少しずつ業務実態と手順書の内容がずれていき、使いづらい手順書となって形骸化したり、正しい業務を従業員間で共有できないことで生産性が低下したりするリスクがあります。内容が変わったタイミングや定期的なタイミングに見直していきましょう。
なお、手順書を動画化することで、見直しや改訂の手間を削減でき、従業員にとっても見やすいため、管理者と閲覧者の双方に効果が見込めます。おすすめの動画マニュアル作成ツール「tebiki」をご紹介しましたが、こうした誰もが使いやすいツールであれば、すぐに内容を修正できるため、見直し・改訂の工数を削減できます。
ぜひ、この記事を読んでいただいたことをきっかけとして、作業手順書の見直し・改訂に取り組んでみてください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。