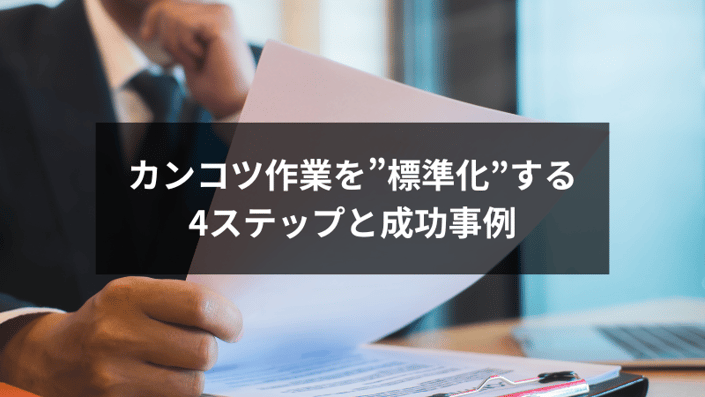

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する、tebikiサポートチームです。
カンコツとは、熟練作業員の経験と勘に基づく、手順や数値が明確に定義されていない作業のことです。 長年の経験から培われた「勘」と「コツ」によって成り立つ作業で、マニュアル化が難しく、言葉や図だけでは伝えきれない、職人技のような要素が強く含まれています。
本記事では、カンコツ作業を伝承する難しさと、標準化して教える方法まで解説します。本記事の内容を分かりやすく整理したPDF資料もご用意していますので、以下のリンクをクリックして併せてご覧ください。
>>「カンコツ作業を標準化する最適解」をPDF資料で見てみる
目次
- 1. カンコツとは?
2. カンコツが伝わりづらい4つの理由
2-1. カンコツの伝え方/教え方がわからない
2-2. 忙しくて教える時間や余裕がない
2-3. 「飲み込みが悪い」「カンが鈍い」と評価しがち
2-4. 教えてもらうことや質問することに躊躇してしまう
3. カンコツ作業を標準化する基本的な4つの手順
3-1. カンコツを整理/分類する
3-2. カンコツ作業を分析する
3-3. 作業の目的や判断基準を明確にする
3-4. 作業手順書や技能マニュアルに落とし込む
4. カンコツ作業の標準化に成功した事例と活用ツール
4-1. カンコツ作業の標準化を推進する2つの好事例
4-2. カンコツ作業の標準化で活用されているツール - 5. まとめ
カンコツとは?
「カンコツ」とは、熟練作業員によって長年の経験や勘に基づいて行う、手順や数値が明確に定義されていない作業のことです。 言い換えれば、暗黙知に基づく、非標準化された作業と言えるでしょう。
▼カンコツ作業の例▼
|
製造業 |
部品の磨き、溶接、塗装など、熟練工の感覚に頼る部分が多い作業。微妙な力加減や角度調整が求められ、数値化が困難なケースが多い。 |
|
建設業 |
コンクリートの打ち方、左官工事、溶接など、経験に基づいた微妙な調整が求められる作業。材料の状態や天候にも左右され、標準化が難しい。 |
|
食品加工業 |
食品の選別、味見、焼き加減の調整など、感覚的な判断が求められる作業。 熟練者でも、言葉で正確に伝えることが難しい場合が多い。 |
マニュアル化が難しく、言葉や図だけでは伝えきれない、職人技のような要素が強く含まれています。 そのため、若い世代への技術伝承が難しく、人材育成における大きな課題となっています。
こうした課題を解消するためにも、「カンコツ作業の標準化」に取り組む必要があるのです。
>>「伝わらない」「属人化している」カンコツ作業を標準化する最適解を見る
カンコツが伝わりづらい4つの理由
カンコツ作業を伝えるために、作業手順書を整備したり、OJTなど手取り足取り業務内容を伝える育成手法が行われるケースが多いものの、『カンコツ作業がうまく伝わらない…』というお悩みをよく伺います。
このお悩みを深掘りしていくと、カンコツ作業が伝わらない背景として以下の〇つが主な理由だと私たちは考えています。
カンコツの伝え方/教え方がわからない
前述の通り、カンコツとは「熟練者の長年の経験や勘に基づく作業」です。熟練者視点では、長年の蓄積で無意識的に行っている動作であるため、初心者や中級者向けに分かりやすく、作業を体系的に伝えることが難しいです。
このような言語化はすべての熟練者が上手く行えるとは限らず、結果的に『作業を見て学べ』のような教え方になり、正しく作業内容が伝わらないケースがあります。
そこで、オーダースーツの製造・販売を行う御幸毛織株式会社では、服飾の個性を引き出すカンコツ作業が要求されるなか、動画マニュアルを活用して視覚的にカンコツ作業を分かりやすく伝え、業務の属人化解消や技術伝承を推進しています。
同社のように、言語化が難しく教えるハードルが高いカンコツ作業に、動画マニュアルを活用することは効果的な手段の1つです。御幸毛織株式会社の取り組み事例は、以下のインタビュー記事から詳細をご覧いただけます。
>>明治時代創業の繊維会社が挑む技術伝承!ITテクノロジーを駆使して伝統芸を若手へ伝達
以下の資料も併せてご覧ください。
>>カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
忙しくて教える時間や余裕がない
熟練者が、新人に技術を教えるための時間が十分に取れない状況はよくあることです。日々の仕事に追われ、教育や指導に割く時間が限られてしまうからです。
たとえば、熟練者が会社から指示された目標に追われている場合、新人への技術指導に必要な時間を確保することが難しい状況になるでしょう。結果として新人の習熟期間が伸び、新人の戦力化に時間がかかってしまいます。
熟練者が「教える時間がない」ことで新人育成が進まない…その問題は、OJT担当者の負担を激減させる「OJT教育の新常識」で解決できます。
>>OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識を見てみる
同様のケースとして、新人を待たせてしまう時間が度々発生していた日本クロージャー株式会社では、トレーナーが不在でも新人が作業内容の基礎を学習できる教育カリキュラムを整備し、新人が手持ち無沙汰にならずに基礎知識を学べる体制を整備しています。
同社の取り組み内容は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
>>「新人を20~30分待たせる状況」を解消した教育改善事例を見てみる
「飲み込みが悪い」「カンが鈍い」と評価しがち
熟練者が新人を指導する際、「飲み込みが悪い」「カンが鈍い」といった評価をしてしまうことがあります。熟練者が無意識のうちに習得した技術を、新人が理解できないことに対する失望から生じる傾向です。
熟練者は長年の経験を通じて自然と身につけた技術を、同じように新人も短期間で習得できると考えがちです。この誤解は、熟練者と新人の間のコミュニケーションのギャップを生む原因となり、技術伝承の妨げになります。また、誤解による評価で、新人のモチベーションが低下する可能性もあるでしょう。
熟練者と新人の認識のズレこそ、技術伝承を阻む最大の壁です。その壁を乗り越え、「技術伝承を成功させる」ためのポイントがこちらです。
教えてもらうことや質問することに躊躇してしまう
新人が疑問や不明点を質問することを遠慮し、自身で解決しようとすることがあります。
この背景の1つとして『先輩社員が忙しそうで、質問をすると迷惑がかかるのでは』と考えてしまうケースがあります。新人が質問をためらうことで、重要な技術の習得が遅れ、結果として効率が低下することを招きかねません。
また、別の背景として『トレーナーによって言っている内容が違う』という不信感から生じるケースも少なくありません。実際、うどんをはじめとする多種多様な冷凍食品を製造・販売するテーブルマーク株式会社では、新人に対して教える作業内容が従業員間で統一されておらず、新人が悩んでしまう場面が実際にあったようです。
今回ご紹介した4つの理由はあくまでも一例ですが、さまざまな理由から「カンコツ作業が伝わりにくい」「カンコツ作業の標準化が進みにくい実態がお分かりいただけると思います。このような実態に対して、ご紹介した事例のように動画マニュアルを活用することも効果的です。
カンコツ作業を伝える手段として、動画マニュアルはどれほど効果的なのか?詳細は別紙のガイドブックで事例も交えて詳しく解説しています。以下をクリックすると、ガイドブックをご覧いただけますので、本記事と併せてご活用ください。
>>「カンコツ作業を標準化する最適解」をPDF資料で見てみる
カンコツ作業を標準化する基本的な4つの手順
カンコツ作業を伝える難しさにはさまざまな理由があり、早急に改善することは至難の技です。
しかしカンコツ作業は、企業活動における高付加価値を支えている部分も少なくなく、適切に技術として伝えていくこと、つまり標準化に取り組むことが大切です。ここからは、カンコツ作業の標準化を進めていく基本的な4つの手順を解説します。
- カンコツを整理/分類する
- カンコツ作業を分析する
- 作業の目的や判断基準を明確にする
- 作業手順書や技能マニュアルに落とし込む
伝えにくいカンコツ作業を「標準化する最適解」をまとめたガイドブックも公開していますので、以下のリンクをクリックして参考資料もご活用ください。
>>“伝わらないカンコツ作業”を標準化する最適解を見る
カンコツを整理/分類する
前提として、カンコツとは「熟練者の経験や勘に基づく作業」です。このような業務ノウハウは、暗黙知とも表現されます。
カンコツを正しく整理/分類するためにも、暗黙知の言語化は避けては通れません。暗黙知を言語化し、カンコツ作業として整理/分類するためには、まず「暗黙知の4階層モデル」に沿った洗い出しを行いましょう。

▼暗黙知の4階層モデル▼
|
階層の概要 |
例 |
|
|
第1階層 |
外から見えて、言語化が可能な階層 →もっとも伝達しやすい |
特定の機械の操作方法や安全手順など |
|
第2階層 |
外からは見えないが、言語化はできる階層 →個人の経験や判断基準などで、外からは直接観察はできないものの、言葉で表現可能 |
ヒヤリハットが発生しそうな状況での判断の仕方や問題解決策など |
|
第3階層 |
作業者は無自覚であるが言語化ができる階層 →インタビュー/観察を通じて知識を引き出し、文書化することが可能 |
作業者が経験から無意識に行っているコツなど |
|
第4階層 |
作業者が無意識に行い、言語化ができない階層 →もっとも伝達が難しい暗黙知 |
作業者自身もその存在に気づいていないことが多い。まさしく熟練工が長年の経験で得た「カンコツ」などが該当 |
第1層から第4層までの違いを理解し、粒度によって整理/分類することで、カンコツ作業をより実用的な形で後継者に伝えることができます。
カンコツ作業を分析する
カンコツ作業を効果的に伝えるためには、その作業を詳細に分析することが重要です。
なぜなら、ベテランの経験や知識は言葉だと表現しづらい暗黙知になっているため、明確にすることが必要だからです。分析の方法としては、以下がおすすめです。
- ベテラン作業員に対して、作業内容のヒアリングやインタビューを行う
- ベテラン作業員の作業風景を動画で撮影する
- 作業工程をチャートで可視化し、どの部分が暗黙知なのか特定する など
複数の視点から客観的に作業の順番や動作を分析することで、技術を他の作業員にも伝えやすくなります。カンコツ作業の分析について、熟練者と新人がうまくコミュニケーションを重ね、効果的に行っている事例として御幸毛織株式会社の取り組みをご紹介します。
同社では、カンコツ作業のような熟練技術を伝承する手段として、動画マニュアルを活用しています。動画の作成は新人が行い、業務のポイントや内容に対するフィードバックを熟練者が行う形で、カンコツ作業の標準化に取り組んでいます。
世代間のギャップや熟練者の業務負荷など、カンコツ作業の標準化で発生しやすい悩みを仕組みで解消し、上手く改善している好事例といえるでしょう。
御幸毛織株式会社の取り組み事例は、以下のリンクをクリックして詳細をご覧ください。
>>明治時代創業の繊維会社が挑む技術伝承!ITテクノロジーを駆使して伝統芸を若手へ伝達
作業の目的や判断基準を明確にする
作業手順の根拠や理由を明確にすることは、カンコツや暗黙知の伝達において極めて重要です。なぜなら、作業員が手順の背後にある目的や理由を理解することでより深くその作業を理解し、適切な判断ができるようになるからです。
たとえば、品質管理のプロセスを教える際は、「その手順が品質を保つためになぜ重要なのか」を理解することで、作業員の自律的な品質管理能力を向上させます。作業手順と作業目的などは1セットで教育しましょう。
作業手順書や技能マニュアルに落とし込む
ここまでカンコツをわかりやすく伝えるためのポイントとして、『整理/分類』『分析』『目的や判断基準の明確化』をお伝えしました。こちらが終わったら、いよいよ暗黙知となっている事柄を作業手順書に落とし込んでいきましょう。
作業手順書やマニュアルは、「作業員がいつでも参照できる知識の源泉」と捉えて、作業を行う誰もが/いつでも/どこでも閲覧できるようにしてください。教育負担を減らしながら、効率的な教育を行えるでしょう。
現場で活用される作業手順書の作り方はこちらの別記事か、以下のガイドブックをご覧ください。作業手順書やマニュアルをわかりやすく作るコツやポイントが詰まった内容なので、以下をクリックして参考資料としてご活用ください。
>>カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
カンコツ作業の標準化に成功した事例と活用ツール
ここまで、カンコツ作業を伝えにくい理由や、カンコツ作業の標準化を推進する手順について網羅的に解説していきました。
最後に、実際にカンコツ作業の標準化に成功している好事例と、成功企業で活用されている共有ツールを解説します。
以下の資料も併せてご覧ください。
カンコツ作業の標準化を推進する2つの好事例
御幸毛織株式会社
御幸毛織株式会社は1905年創業の繊維会社で、紡績から縫製、販売まで一貫して行っている企業です。
同社では、40代と50代のベテラン社員の技をいかに若手へ継承するかが課題でした。紙のマニュアルでは細かな動きや微妙なニュアンスが伝わりづらく、動画マニュアルを社内で作成しようとしたものの、その難しさや作成担当者の負担を懸念し実現まで至らなかったという状況に。
そこで動画マニュアルを活用することで、動画による作業手順の可視化や業務標準化を実現し、効率的な研修と業務の属人化の削減に成功しました。加えて、マニュアル作成の工数も3割~4割削減でき、紙マニュアルでは伝わりにくい細かいニュアンスも伝えやすくなったそうです。
同社が動画マニュアルをどのように活用したのか?詳細な内容は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
明治時代創業の繊維会社が挑む技術伝承!ITテクノロジーを駆使して伝統芸を若手へ伝達
トーヨーケム株式会社
トーヨーケム株式会社は、東洋インキグループにおけるポリマー/塗加工関連事業を担う中核事業会社で、新人からベテランまで700名以上の社員を抱える製造業の企業です。同社では、若手社員への技術伝承と属人的なOJTによる教育のムラが課題でした。
人や物の動きが伴う作業が多く、文字や静止画ではカンコツが伝わりづらいということに加え、OJTによる教育のみでは教え方の違いや業務ノウハウを言語化できずに新人の業務習熟度にバラツキが生じ、技術伝承や多能工化の教育がスムーズに進まないといった課題がありました。
そこで動画マニュアルを活用し、技術伝承の推進と教育のムラ削減を実現しています。映像編集未経験者でも簡単に作成ができるツールを導入したことで『この業務は伝わりにくいので動画マニュアル化したい』という声が自発的に上がり、ボトムアップによる業務改善が進んでいます。
トーヨーケム株式会社の改善事例を詳しく読みたい方は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
新人からベテランまで700名を超える組織教育のグローバルスタンダードを目指す
カンコツ作業の標準化で活用されているツール
今回ご紹介した2社の事例のように、カンコツ作業の標準化を推進するツールとして「動画マニュアル」の活用が効果的です。
動画の場合、熟練者の手の動きや作業の流れなど、文書や口頭では伝えにくい細かな技術やノウハウを具体的に示せます。そのため、動画はベテランや熟練者のカンコツ作業を「見える化」するのに非常に有効です。
さらに、動画でカンコツ作業の標準化を推進することで、以下のような効果も期待できるでしょう。
- 熟練者の教育負担を軽減できる
- ベテランと新人の違いを比較検証しやすい
- ナレッジ蓄積となり、技術伝承を進められる
- トレーナーによる教育内容のバラつきを防げる など
カンコツ作業の標準化を動画で推進し、このような効果を実感いただいているツールが、かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」です。
動画マニュアルを誰でもかんたんに作成できるマニュアルソフトです。実際に作業している様子をスマートフォンで撮影し編集するだけで、わかりやすく高品質な動画マニュアルを作れます。
▼かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」紹介動画▼
編集がかんたんなだけでなく、カンコツ作業の標準化に有効な周辺機能も豊富に揃っています。
- 字幕の自動生成機能
- 100ヵ国語以上に対応した字幕の翻訳機能
- AIによる字幕読み上げ機能(一部多言語対応)
- 全プラン動画のアップロード本数が無制限
- 「誰が・どのくらい・どの動画を視聴したか」確認できるレポート機能
- スキルマップによる業務の実態に基づいた力量管理
- 職場の教育計画の作成や教育実施の記録も可能
今回ご紹介している機能はあくまでも一例です。tebiki現場教育の詳細な機能やプラン、改善事例などはサービス概要資料で詳しくご紹介しています。以下のリンクをクリックして、概要資料をご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能やプラン、改善事例を資料で見てみる
まとめ
カンコツや暗黙知の伝達は、教える側と教えられる側の双方からのコミュニケーションが不可欠です。
カンコツの認識の難しさや教育のムラを減らすためには、作業手順の整理・分類と、動画を用いた可視化がおすすめ。動画化により、細かなニュアンスや技術が明確に伝わり、教育の均一化が達成できるでしょう。
tebiki現場教育の資料は以下の画像をクリックすると無料でご覧いただけます。ぜひこの機会に、カンコツ作業の標準化を推進する手段の1つとして、tebiki現場教育をご検討ください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。




