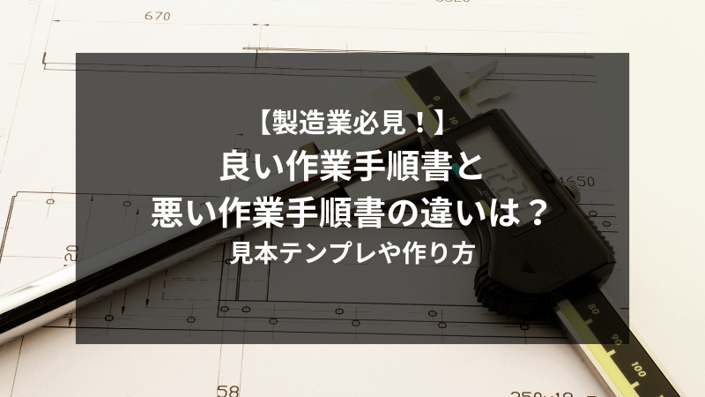

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開するTebiki株式会社です。
製造業において作業手順書は、品質の維持・向上、作業効率の最適化、作業者の安全を確保するための文書です。この記事をご覧になっている皆さんも作業手順書を作成したい/作成したことがあるかと思われますが、果たしてその手順書は「本当に伝わりやすい手順書」でしょうか?
この記事では、「良い作業手順書」と「悪い作業手順書」の違いを明確にし、製造現場で活用される作業手順書作成のポイントを詳細に解説します。
形骸化しない作業手順書の作り方は、「カンコツが伝わる!『現場で使われる』作業手順書のポイント」の資料でも詳しくご紹介しています。動画マニュアルを通じ、数多くの現場を支援してきたtebikiならではの作成ノウハウが凝縮された資料となっておりますので、是非本記事と併せてご覧ください。
>>カンコツが伝わる!『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
目次
- 1. 【無料DL可】製造業で使える!見本となる作業手順書のテンプレート例
2. 製造業における「良い作業手順書」と「悪い作業手順書」の違い
2-1. 製造業における「良い作業手順書」
2-2. 製造業における「悪い作業手順書」
3. 製造業における作業手順書の正しい作り方
3-1. 作業を洗い出し、手順化する対象業務を選定する
3-2. 業務内容を精査して区分する
3-3. 作業手順書の構成~内容を作成する
3-4. 定期的に見直して改善を重ねる
4. 製造業の作業手順書は「動画化」が効果的
4-1. 紙の手順書よりも多くの情報を伝えられる
4-2. 手順書を作成する手間を減らせる
4-3. 検索性に優れている
5. 製造業で作業手順書に動画を活用している事例
5-1. 株式会社神戸製鋼所
5-2. アサヒ飲料株式会社
5-3. テーブルマーク株式会社 - 6. 多くの製造現場で活用されるかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」とは
6-1. 専門知識不要!カンタンな映像編集
6-2. 手順書の更新も簡単にできる
6-3. 字幕生成/翻訳などの自動機能搭載
6-4. アクセス履歴・習熟度が一目でわかるレポート機能
7. 確実で正確な作業手順が求められる製造業だからこそ【まとめ】
【無料DL可】製造業で使える!見本となる作業手順書のテンプレート例
今回、無料でダウンロードできる、作業手順書のテンプレートをエクセル版/ワード版でご用意しました。
テンプレートの活用により、一から手順書を作成する手間を省けるだけでなく、誰でも同じ見た目と構造で作成できるため、ばらつきのない一貫した作業手順書が完成します。
書き方がわからないという方でも、テンプレートという見本に沿って内容を埋めるだけで簡単に高品質な作業手順書を作成できるため、是非ご活用ください。
.png?width=1000&height=675&name=%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%89%8B%E9%A0%86%E6%9B%B8%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BE%8B_%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%94%A8(%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD).png)
▼テンプレートDLフォーム▼
製造業における「良い作業手順書」と「悪い作業手順書」の違い
良い作業手順書とは、製造現場の効率と安全を高める文書だといえます。明確で理解しやすい内容が作業の質を一貫させて事故を防ぐことが可能な一方で、悪い手順書は作業の混乱を招きます。
ここでは良い作業手順書と悪い作業手順書の違いについて解説します。
製造業における「良い作業手順書」
誰が見ても理解できる書き方や内容である
良い作業手順書は、専門知識がない人でも理解できるように簡潔かつ明確な言葉遣いで書かれています。
作業手順書は新人からベテランまで幅広い方が利用するため、専門用語などの難しい言葉を減らし、読み手が作業内容を簡単にイメージできるわかりやすい表現を用いると良いでしょう。
また、言葉遣いだけではなく読みやすい文章を作成するために、5W1H(Who, What, When, Where, Why, How)を明確にするのも重要です。5W1Hを明確化することによって、作業者が必要な情報を瞬時に理解できます。
動画を使って視覚的にもわかりやすい
製造業の手順書は動作を伴う情報が多く、動きを理解するには、文章や画像を見てイメージするよりも動画を見た方が速いです。
たとえば作業服の着方に関する手順書で、「~に袖を通して、~の裾をとめて...」などと文章で長々と説明するより、動画でぱっと見せた方がすぐに理解できるでしょう。
六甲バター株式会社のサンプル動画
(再生時は音量にご注意ください)
「新日本工機株式会社」では、従来は紙マニュアルのみで作業手順の標準化が進まずに課題を抱えていたものの、手順書を動画にすることでよりわかりやすいマニュアルの作成が実現しています。1年間で作成した本数は1,500本以上にも登ります。
「紙マニュアルと比べて動画マニュアルの方が視覚的にわかりやすい」と語る、同社の動画活用事例を詳しく知りたい方は、こちらのインタビュー記事をご確認ください。
ご紹介した事例以外でも、製造業で動画マニュアルが活用されているケースが多くあります。どのような形で活用されているのか知りたい方は、以下のリンクをクリックして参考資料もご覧ください。
確認の基準や方法が明確に記載されている
明確な基準と作業方法が記載されている手順書は、誰が実施しても同じ品質で業務を遂行できます。これにより、業務の一貫性が確保され、結果として製品の品質や業務効率が安定します。
例えば、品質検査の作業手順書に検査基準や方法が詳細に記載されていることで、全ての検査員が同じ基準で製品を評価できるようになり、均一な品質の製品を市場に供給することができます。
また、基準や作業手順が詳細に明記されている手順書を整備することで、新しい作業者が手順を学ぶ際でも一定の水準を保ったまま、短期間で作業を習得できます。これにより、教育コストの削減や迅速な現場投入が見込めます。
「誰が実施しても同じ品質」を実現する明確な基準の伝達に最適な「動画マニュアル」について、その作り方を基礎から学べる入門ガイドをご用意しました。
作業の注意点や危険性が記載されている
作業手順書に注意点や危険性が記載されていれば、作業者がリスクを事前に認識して適切な予防措置を講じることができます。その結果、安全な作業環境を整備でき、労働災害の防止を実現できるでしょう。
たとえば、化学物質の取り扱いに関する手順書には、「化学物質を扱う際には必ず保護具を着用する」などの注意喚起を促すと良いでしょう。
ここまで紹介してきたように良い作業手順書には様々な特徴が共通しています。以下の資料では、実際の現場で活用される作業手順書の作成方法や作成のコツをご紹介しているので併せてチェックしてみてください。
>>カンコツが伝わる!『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
製造業における「悪い作業手順書」
作業者目線を意識して作成されていない
悪いとされる作業手順書は、作業者の立場や能力を考慮せずに作成されていることが多い傾向にあります。具体的には、新人だとわからない専門的な用語が多用されていたり、抽象的な言い回しが多くて内容がイメージしづらいといったことが挙げられます。
手順書は新人からベテランまで幅広い方が利用するものです。「ベテランしか理解できない」「書いた本人にしかわからない」、このような手順書は良い手順書とはいえないでしょう。
「そもそも作業手順書の作り方がよくわからない...」このようなお悩みを抱えている方は、以下の記事もご覧ください。
▼関連記事▼
【テンプレあり】作業手順書のわかりやすい作り方!作成例も紹介
全体の作業手順が見えず、わかりにくい
作業手順が不明瞭で全体の流れがつかみにくい手順書は、作業の効率と品質に悪影響を及ぼしたり、新人教育も進まずに業務が属人化してしまったりなどのリスクも十分に考えられます。
そのため、手順書の目的を明確化した上で不備なく記載することが必要です。手順書を閲覧する作業者が目的まで理解しておくことで、より責任を持って作業に取り組めるため結果として品質向上にもつながるでしょう。
わかりにくい手順書は現場で活用されず、そのまま形骸化してしまうことも珍しくありません。作業手順書が形骸化しないように、どのようにして作成をすればよいか?知りたい方は以下のリンクをクリックして、参考資料をご覧ください。
>>>「作業手順書が形骸化する原因|「本当に意味のある」手順書を作るには?」を見てみる
管理が行き届いておらず、現場が勝手に添削している
手順書に最新の作業状況や改善点が反映されていない場合、現場の作業者が独自に手順を変更することがあります。公式の手順書が実際の作業に合っていないと感じた作業者が、より効率的または安全な方法を模索してしまうからです。
しかし、独自の方法では作業の標準化が困難になり、結果として品質のバラつきや安全上の問題が生じる可能性があります。そのため作業手順書は定期的に見直し、現場の声を取り入れて更新することが重要です。定期的に更新することで作業手順書は常に最適な状態に保たれ、現場の作業者が安心して作業を行うことが可能です。
>>「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書を見てみる
どの段階で作業手順書を更新・見直すべきなのか詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
▼関連記事▼
作業手順書の見直しタイミングは?改訂手順や見直さないリスクを解説
作業手順の要点や注意点が強調されていない
要点や注意点が適切に強調されていないと、必要な情報を素早く把握しにくいです。そのため、重要な情報が見落とされ、作業ミスや安全事故につながるリスクが高まります。
作業手順書では、視覚的な工夫(太字や色分け、アイコンの使用など)を用いて要点や注意点を明確にすることがおすすめです。明確化することで作業者は重要な情報を瞬時に認識し、安全かつ効率的に作業を進められるようになります。
次章では、ここまでに紹介したポイントを踏まえ、製造業における正しい作業手順書の作り方を紹介していきます。
製造業における作業手順書の正しい作り方
製造業で正しく作業手順書を作成するための進め方は以下のとおりです。
- 作業を洗い出し、手順化する対象業務を選定する
- 業務内容を精査して区分する
- 作業手順書の構成~内容を作成する
- 定期的に見直して改善を重ねる
作業手順書の作り方をより詳しく知りたい方は、「準備編」「作成編」「運用編」「更新編」の4つのセクションに分けて手順書の作り方を説明している以下の記事も参考にしてみてください。
>>そのまま真似できる「見本」付き業務マニュアルの作り方完全ガイドを見てみる
▼関連記事▼
【テンプレあり】作業手順書のわかりやすい作り方!作成例も紹介
作業を洗い出し、手順化する対象業務を選定する
まずは日々の作業を洗い出し、その中でどの業務を手順化するべきなのか、対象となる業務の選定を行いましょう。なお、作業内容を洗い出す際には以下のようなポイントを踏まえて見てください。
- 従業員から作業内容をヒアリングする
- 部門ごとに作業内容を細かく書き出す
実態の作業に即した手順書でなければ、せっかく作成したものの利用されずに形骸化してしまうので注意が必要です。
業務内容を精査して区分する
作業の洗い出しが完了したら、作業ごとに細かい作業・大きな作業が混在している可能性もあるため、作業の粒度を揃えて区分していきましょう。なお、作業によっては特定の工程を経てから次の工程に移る必要があるもの、順番が前後しても良い作業など、作業ごとの付帯条件も踏まえる必要があります。
なお、区分した作業手順に沿って実際に作業しながら、本当に適切なのかを確認することも大切です。作業によってはイレギュラーが多かったり、前工程から待ちの時間が長かったりするケースがあるためです。この場合には、手順の追加・削除・並び替えなどを実施して手順を見直すことが大切です。
作業手順書の構成~内容を作成する
実際に作業手順書を作成する段階では、まず全体の骨組みとなる構成を作成しましょう。手順書に記載する項目や洗い出した作業をわかりやすく配置し、手順通りに並べていきます。作成した構成に沿って内容を作成していく際には、重要な箇所には「急所」「カンコツ」などのように注意喚起をしたり、適度に改行やスペースを利用して読みやすくなるような工夫を凝らしていきましょう。
また、作業手順だけが並べられていると「作業量がどの程度なのか」「作業の区切りはいつつくのか」など、作業者に不明点が生じてしまいます。全工程の流れが把握できるように目次をつけておくことも大切です。
構成の工夫や注意喚起で「カンコツ」をいかに伝えれば、現場で本当に「使われる」手順書になるのか、その具体的な作成ポイントを解説します。
>>カンコツが伝わる!『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
定期的に見直して改善を重ねる
作成した手順書は定期的な見直しを実施し、定期的な更新・改訂をして改善を重ねていくことが重要です。作業手順やルールの変更があったときはもちろん、定期的に手順書の内容を見直すことで、陳腐化の防止にもつながります。
なお、実際に手順書を利用する従業員の意見をヒアリングし、その意見をもとにして手順書を改善していくのも良いでしょう。手順書をいつ見直すべきなのか、具体的なタイミングを知りたい方は、「作業手順書の見直しタイミングは?改訂手順や見直さないリスクを解説」記事もご覧ください。
製造現場では長年の経験やスキルを要する「カンコツ」作業が多く、手順書だけでは作業者に伝わらずに形骸化するケースが非常に多く見受けられます。以下の資料では、「現場で使われる手順書作成・運用・管理のポイント」を詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。
>>カンコツが伝わる!『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
製造業の作業手順書は「動画化」が効果的
製造業で利用する作業手順書は、紙ではなく動画化することによって、より伝わりやすい作業手順書を作成することができます。ここでは、なぜ動画化が効果的なのかの理由を簡潔にご紹介します。
より詳しく知りたい方は、作業手順書の動画化(動画マニュアル)の有効性や作成方法を具体的に解説した記事もご覧ください。
紙の手順書よりも多くの情報を伝えられる
紙の手順書では伝わりにくい「作業のコツ」が、動画にすることで視覚的によりわかりやすく伝えることができます。力加減であったり、素早い動作のタイミングなど動画であれば一目でわかります。
また、動画を視聴できる端末があれば好きなタイミングでいつでも見返すことができるのもポイント。熟練者の技術を自発的に学習でき、新人教育につながることはもちろん、新人からベテラン社員に質問する時間を削減することにもつながります。
手順書を作成する手間を減らせる
動画で作業手順書を作成する場合、紙と比べて以下の通り少ないステップで完結します。
- スマートフォン、タブレットで撮影
- 字幕やカットなどの映像編集
- 公開
アサヒ飲料株式会社では、手順書の作成に3時間~10時間ほどかかっていましたが、動画化したことによって手順書の作成をおよそ30分で作成することに成功しています。同社の具体的な取り組み内容は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
>>>動画で手順書作成工数を大幅に削減したアサヒ飲料株式会社のインタビュー記事を読んでみる
検索性に優れている
紙の作業手順書の場合、作業工程が多ければ多いほど、必然的に冊数が膨大になります。そのため、必要な手順が掲載されている手順書を見つけるまでに時間がかかってしまい非常に手間が増えてしまうのです。
一方、動画であれば手順書のタイトルや本文に含まれているキーワードで検索をすれば、求めている手順書を見つけることができるため、紙と比べて検索性に優れています。
このように動画マニュアルには様々なメリットがあり、多くの製造現場で利用されています。実際に製造業でどのように動画マニュアルが活用されているのかをまとめた資料をご用意しておりますので、以下も併せてご覧ください。
製造業で作業手順書に動画を活用している事例
ここからは、作業手順書に動画を活用している企業事例を、3社厳選してご紹介します。
より多くの活用事例を知りたい方は、製造業以外の業界も網羅した動画マニュアル活用事例とサンプル動画を見れる記事がオススメです。
株式会社神戸製鋼所
「素材系事業」、「機械系事業」、「電力事業」の多岐に渡る事業を展開している株式会社神戸製鋼所。同社では、作業手順書を紙で作成していたものの、文字や写真だけで作業を伝えることが非常に難しく、人材教育の側面で課題を抱えていました。
そこで、動画編集のしやすさに着目して、動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入。導入により、紙から動画への置き換えが進んでおり、およそ400本ほどまで作成に成功しております。動画マニュアルの活用によって、OJTにかける時間が3割程度削減できたと語る同社のインタビュー記事は以下よりご確認ください。
▼インタビュー記事▼
動画を活用した現場の人材教育効率化と作業標準化
アサヒ飲料株式会社
アサヒグループにおける飲料の製造販売会社であるアサヒ飲料株式会社では、三ツ矢サイダーや十六茶、ウィルキンソンなどの飲料製品を製造しています。同社では、一つの作業手順書を作成するのに短くて3時間、長くて10時間ほどかかっていたことに加え、OJT教育にも課題を抱えていました。
その課題を解決すべく、動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入し、手順書作成の時間を30分まで短縮でき、OJTにかける時間も従来と比べて半分以下に削減することに成功しました。
今後は製造現場だけではなく、職場全体で動画マニュアルの活用が拡がれば良いと語る同社のインタビュー記事は以下よりご覧ください。
▼インタビュー記事▼
OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化
テーブルマーク株式会社
冷凍うどんを始め、ラーメンやチャーハンなどの冷凍食品の製造、常温のパックごはんや業務製品などの幅広い食品を製造販売しているテーブルマーク株式会社。
同社では、作業を教える担当者ごとの指導内容にバラつきがある点や、外国人労働者にうまく伝えることができないなどの課題を抱えていました。そこで教育工数・作業手順書作成工数の軽減を目的に動画を活用することを決断し、「tebiki現場教育」を導入。
導入後は教育工数を6時間から1時間まで削減することに成功し、指導者ごとのバラつきも軽減されたと語っています。同社のインタビュー記事は以下よりご覧ください。
▼インタビュー記事▼
属人化業務の指導工数を83%削減!標準化教育により安心安全な食品を提供
多くの製造現場で活用されるかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」とは
作業手順書の作成には、「tebiki現場教育」がおすすめです。
tebiki現場教育は、専門知識不要で誰でも簡単に動画マニュアルを作成できるツールです。現場教育の効率化、作業の安全性と品質向上といった効果が期待でき、紙のマニュアルの代替手段としても有効です。
専門知識不要!カンタンな映像編集
動画マニュアルのtebiki現場教育を使用する最大のメリットは、専門知識がなくても誰でも簡単にわかりやすい動画マニュアルを作成できる点です。スマートフォンやタブレットだけで撮影し、シンプルな編集を加えるだけで簡単に作業手順書を動画化できます。
また、tebiki現場教育で作成した動画マニュアルは、作業の注意点や危険性なども視覚的に示すことが可能です。例えば、化学工場での危険物質の取り扱いや高所作業の安全対策など、言葉だけでは伝わりにくい情報も動画なら直感的に理解できます。
手順書の更新も簡単にできる
紙の手順書だと更新を行うと特定の拠点でしか共有ができず、複数の拠点がある場合には拠点ごとに手順書を更新する手間がかかります。
一方、tebiki現場教育では更新が発生した場合に、1つの拠点で新たに動画を作成してアップロードすれば全ての拠点で手順書を更新することが可能です。
「tebikig現場教育」を活用している株式会社大商金山牧場では、拠点ごとに把握しきれなかった手順書を一元管理できるようになり、質の高い手順書を各拠点に展開できて教育レベルの底上げにつながっていると効果を実感しています。同社の事例を詳しく知りたい方は以下よりご覧ください。
字幕生成/翻訳などの自動機能搭載
tebiki現場教育では、撮影した動画の音声を最新の音声認技術で字幕に自動で変換することができ、撮影するだけでマニュアルの作成が完了します。なお、自動で作られた字幕は、編集する段階で自由に追加/編集も可能です。

また、字幕やタイトルはワンクリックで100ヶ国以上の言語に自動翻訳が可能。様々な国籍のスタッフがいる製造現場でも翻訳などの手間がかからずに外国語バージョンの動画マニュアルを作成できます。
アクセス履歴・習熟度が一目でわかるレポート機能

tebiki現場教育では作成した従業員ごとにアクセスした履歴であったり、作業に対しての習熟度を見える化できるレポート機能が充実しています。作成した動画マニュアルを見てほしい従業員がいる場合には、タスク機能を使って見てもらうように指示をすることも可能です。
現場教育でだれが何の作業ができるのかという点は非常に重要な指標となるため、tebiki現場教育を活用すればこの点をしっかりと把握することができます。
ここまで紹介してきたようにtebikiには製造業における様々なサポートに役立つ機能が豊富に搭載されています。より詳しく知りたい方に向けて、3分で理解できるtebikiのサービス資料をご用意しました。以下よりご覧ください。
確実で正確な作業手順が求められる製造業だからこそ【まとめ】
良い作業手順書は、誰もが理解できる明瞭な指示、視覚的な補助、明確な確認基準、危険性の警告を含むものです。対して、悪い作業手順書は作業者の視点を欠き、内容が不明瞭で、管理が不十分であり、重要な情報の強調が不足しています。
現場で実際に活用される作業手順書を作成するためには、目的と内容の具体化、定期的な見直し、テンプレートの活用などの様々な工夫が必要です。
特に「tebiki」のようなツールは専門知識が不要で、作業手順を伝える動画をカンタンに作成することができます。作業手順書の代替手段としてtebikiの導入を検討している方は、ぜひ以下より資料をダウンロードしてみてください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。




