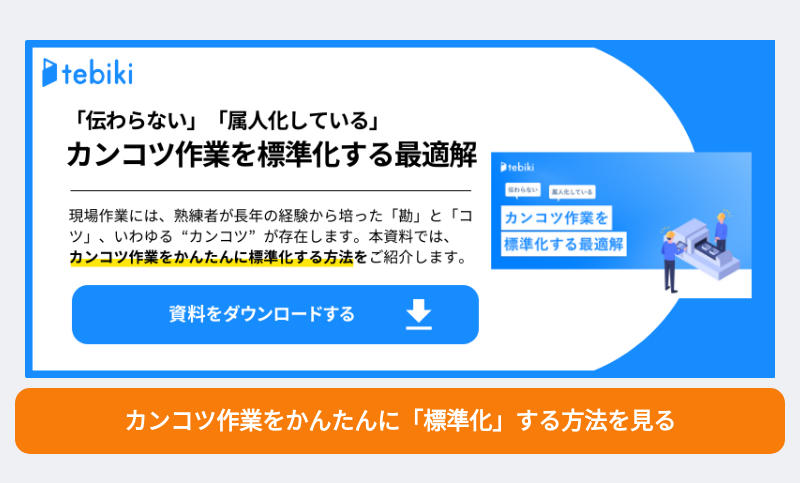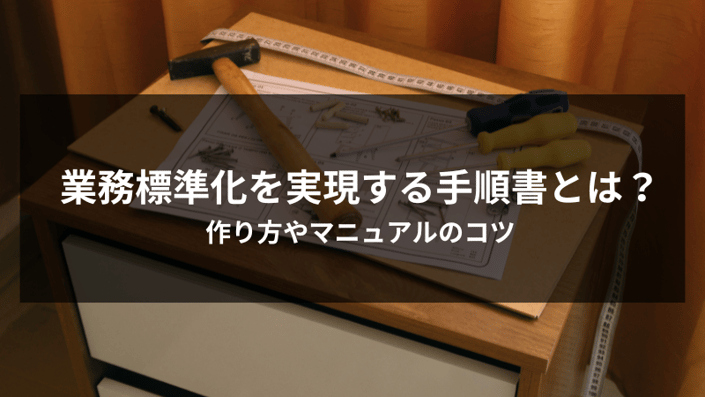

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、tebikiサポートチームです。
「特定の担当者しか業務内容を知らない」「人によって作業のやり方や品質がバラバラ」といった課題は、多くの企業で聞かれる悩みです。これらの課題解決の鍵となるのが業務標準化であり、その実現に不可欠なのが「マニュアル(手順書)」です。
本記事では、これまで数多くの企業や工場の現場教育を支援してきた弊社の知見に基づき、業務標準化の進め方から、標準化を実現するための手順書・マニュアル作成のコツまで実践的な情報をお届けします。
目次
- 1. 業務標準化が重要な理由や解決できる課題
1-1. 理由1:属人化による業務停滞・品質ばらつきのリスクを防止できるから
1-2. 理由2:教育コストの増大や非効率な新人教育を解消できるから
1-3. 理由3: 技術・ノウハウの喪失(技術伝承の停滞)を防げるから
2. 再確認しておきたい、業務標準化の目的とメリット
3. 業務標準化の実現に「マニュアル(手順書)整備」が不可欠な理由
3-1. 標準化された業務プロセスを「見える化」するから
3-2. 誰でも同じ品質で作業できる「共通言語」となるから
3-3. 教育・研修の効率化とOJTの質向上に貢献するから
3-4. 継続的な業務改善の土台となるから
4. 業務標準化を実現するマニュアル(手順書)作成の5ステップ
4-1. ステップ1:標準化する業務の選定と目標設定
4-2. ステップ2:現状業務の可視化と分析(業務フローの整理)
4-3. ステップ3:標準となる業務プロセスの設計
4-4. ステップ4:マニュアル(手順書)の作成
4-5. ステップ5:マニュアル(手順書)の導入・定着・継続的な改善
5. 失敗しない!現場で「使われる」標準化マニュアル作成の5つのコツ
5-1. コツ1:目的と対象者を明確にする
5-2. コツ2:5W1Hを意識し、具体的かつ簡潔に記述する
5-3. コツ3:専門用語を避け、平易な言葉で表現する
5-4. コツ4:図、写真、そして「動画」を効果的に活用する
6. 【事例】手順書刷新で業務標準化を実現した企業や現場
6-1. アサヒ飲料株式会社 - 熟練者の暗黙知を動画で形式知化
6-2. ASKUL LOGIST株式会社 - 多拠点・大人数での業務標準化と安全意識向上
7. 【課題解決の鍵】動画マニュアルが業務標準化を加速させる理由
7-1. 紙やテキストマニュアルでは伝わりにくい「カン・コツ」の可視化
7-2. 新人や外国人材でも理解しやすい直感的な分かりやすさ
7-3. マニュアル作成・更新の手間を大幅に削減
8. よくある失敗「マニュアルを整備したものの使われなくなった」を防ぐには?
8-1. マニュアルの保管場所とアクセス方法を明確にする
8-2. 定期的なレビューと更新プロセスを確立する
8-3. 現場からのフィードバックを収集し、改善に活かす仕組み
9. まとめ:効果的なマニュアルで業務標準化を実現し、生産性を向上させよう
業務標準化が重要な理由や解決できる課題
業務標準化が浸透していない職場や現場、つまり「業務の進め方が個人に依存」していたり、「手順が曖昧」だったりする職場や現場は、様々な問題が発生します。
ここでは、業務標準化によって解決できる代表的な課題(=標準化が重要な理由)を3つ挙げます。ここで紹介する項目はいずれも、弊社がご支援する中で特に耳にする内容です。
理由1:属人化による業務停滞・品質ばらつきのリスクを防止できるから
特定の担当者しかできない業務や、人によってやり方が違うといった属人化は、業務停滞や品質ばらつきのリスクとなります。
属人化は特に製造業や工場でよく問題視される経営課題です。例えば製造業の「大同工業株式会社」でも以前、属人化の課題に直面し、業務標準化が浸透されるためのマニュアル整備が急務でした。
基本的な内容は文書マニュアルに記載されていますが、実際に実務をおこなう時のちょっとしたコツやポイントは言語化しにくく、動作を見せて伝え、その実務を通じて担当者が会得するしかなく、しかも担当者によってコツやポイントに差があり、それゆえ業務手順も異なるという”我流化”(業務品質のバラつき)が起こっていました。
※同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
▼インタビュー記事▼
製造業の技術部門の業務を動画で標準化。品質評価に関わるヒヤリハットを8割削減して、多能工化を実現
業務標準化を図れると、こうした属人化や作業手順のバラつきが解消され、現場全体のパフォーマンス向上につながります。
理由2:教育コストの増大や非効率な新人教育を解消できるから
業務標準化がなされていないと、正しい手順を都度教育する手間が発生します。
よくあるケースとして、OJT(On-the-Job Training)頼みの教育体制になっている現場は少なくありません。教える側の負担が大きく、新人や異動者の立ち上がりに時間がかかります。また、教える人によって内容に差が出ることも多いです。
例えば 「タベル株式会社」では、教育の仕方が人によってバラバラであることが課題でした。
シフトの都合上、教える人が毎日変わるので、教え方がトレーナーによって違って新人スタッフが混乱してしまう、といったことも起きていました。
※同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
▼インタビュー記事▼
アルバイトスタッフの離職率が2割減って、管理者の仕事が大幅に効率化。
業務が標準化され、分かりやすいマニュアルがあれば、新入社員や異動者は基本的な業務内容を自律的に学ぶことができ、トレーナーはより実践的な指導や応用的な内容に時間を割くことができます。結果として、教育期間の短縮と教育の質の向上が期待できます。
理由3: 技術・ノウハウの喪失(技術伝承の停滞)を防げるから
標準化がなされていないとはつまり、「ベテラン社員や熟練者の技術・カンコツが、若手人材に継承されていない(継承される教育体制が整っていない)」とも言い換えられます。特に製造業や工場では、熟練者の持つ貴重な技術やノウハウが、言語化されずに暗黙知のままになっているケースも散見されます。
これは、退職などによる技術伝承の断絶リスクにつながります。
製造業の「株式会社神戸製鋼所」のように、動画を活用して熟練者の暗黙知を「見える化(形式知化)」し、技術伝承を進めている企業もありますが、多くの現場では依然として大きな課題です。
業務を標準化し、マニュアルという形に落とし込むプロセスは、暗黙知を形式知へと変換する重要な機会です。これにより、組織全体の知識レベルが向上し、貴重な技術やノウハウが次世代へと確実に受け継がれていく体制を構築できます。
熟練者のカンコツ作業をどのように標準化すればよいか、具体的な方法論を知りたい方は、「“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解(pdf)」が役立ちます。標準化を実現するための有効手段を紹介しています。下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
再確認しておきたい、業務標準化の目的とメリット
すでにご存知の方も多いかと存じますが、ここで業務標準化の主な目的とメリットを簡潔に振り返っておきましょう。業務標準化とは、誰が担当しても同じ成果を出せるように、最も効率的で質の高い手順やルールを定め、組織全体で統一し徹底することです。これにより、主に以下のようなメリットが得られます。
- 生産性の向上
- 品質の安定化・向上
- コスト削減
- 属人化の解消
- 人材育成・教育の効率化
- コンプライアンス強化・リスク管理
これらの目的・メリットを達成する上で、「マニュアル(手順書)」が極めて重要な役割を果たします。標準化された手順を明確に示し、組織全体に浸透させるための具体的なツールがマニュアルなのです。
業務標準化の実現に「マニュアル(手順書)整備」が不可欠な理由
業務標準化を進める上で、なぜマニュアル整備が重要なのでしょうか。その役割を具体的に見ていきましょう。マニュアルは単なる記録文書ではなく、標準化を推進し、定着させるためのエンジンとなります。
標準化された業務プロセスを「見える化」するから
どんなに優れた標準業務プロセスを設計しても、それが関係者に伝わらなければ意味がありません。
マニュアルは、決定された標準プロセスを、誰もが理解できる形(テキスト、図、写真、動画など)で具体的に示し、「見える化」します。これがなければ、標準を徹底することは困難です。
誰でも同じ品質で作業できる「共通言語」となるから
マニュアルは、作業者全員が参照する「共通のルールブック」であり、いわば業務上の「共通言語」です。
これにより、経験やスキルレベルに関わらず、担当者は定められた手順に従って作業を進めることができ、一定の品質を保つことが可能になります。人による解釈の違いや、やり方のばらつきを防ぐ役割を果たします。
教育・研修の効率化とOJTの質向上に貢献するから
新入社員研修やOJTにおいて、マニュアルは基本的な知識・スキルを体系的に伝えるための重要な教材となります。トレーナーは、マニュアルに沿って指導することで教える内容の抜け漏れを防ぎ、教わる側は予習・復習に活用することで理解を深められます。
これにより、教える側の負担軽減と教育の質の均一化、ひいては人材育成全体の効率化が図れます。
継続的な業務改善の土台となるから
マニュアルは、一度作ったら終わりではありません。それは、現時点での「ベストプラクティス」を記録したものです。
これをベースに、現場からのフィードバックや改善提案、あるいは外部環境の変化などを反映させてマニュアルを更新していくことで、継続的な業務改善のサイクルを回すことができます。マニュアルは、改善活動の出発点であり、その成果を記録・共有する媒体となるのです。
▼関連記事▼
マニュアルの意味とは?わかりやすく作るコツと流れを解説
【事例あり】マニュアル作成の3つの意味。「必要ない」は本当?
業務標準化を実現するマニュアル(手順書)作成の5ステップ
実際に業務標準化を進め、標準化が浸透するマニュアル(手順書)を作成するための具体的なステップを5段階で解説します。このステップに沿って進めることで、抜け漏れなく、質の高いマニュアル化を実現できます。
そのまま真似できる見本付きで、マニュアル作成の具体的な方法を学びたい方は、「そのまま真似できる「見本」付き 業務マニュアルの作り方完全ガイド(pdf)」が最適です。実践的な作成ノウハウが満載です。下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
ステップ1:標準化する業務の選定と目標設定
まず、組織内の全ての業務を一度に標準化しようとするのではなく、優先順位をつけて対象業務を選定します。例えば、以下のような観点で選定すると良いでしょう。
- 属人化が進んでおり、特定の担当者がいないと回らない業務
- ミスやクレームが発生しやすい業務
- 新人や異動者が習得するのに時間がかかっている業務
- 複数の部署や担当者が関わり、連携に課題がある業務
対象業務が決まったら、その業務を標準化することで「何を」「どこまで」改善したいのか、具体的な目標を設定します。目標は、「作業時間を現状から15%削減する」「不良品の発生率を5%以下にする」のように、できるだけ定量的で測定可能なものが望ましいです。
ステップ2:現状業務の可視化と分析(業務フローの整理)
次に、選定した対象業務が現在どのように行われているのかを詳細に洗い出し、「見える化」します。関係者へのヒアリング、実際の作業観察、既存の資料(もしあれば)の確認などを通じて、以下の情報を収集・整理します。
- 業務の開始から終了までの具体的な手順
- 各手順の担当者
- 各手順で使われているツールやシステム
- 各手順にかかる時間
- 判断基準や注意点
- 発生している問題や非効率な点
これらの情報を元に、業務フロー図などを作成すると、全体の流れや課題点が把握しやすくなります。この現状分析が、後の標準プロセス設計の重要なインプットとなります。
ステップ3:標準となる業務プロセスの設計
現状分析で見えてきた課題やボトルネックを踏まえ、最も効率的で品質の高い理想的な業務プロセス(=標準手順)を設計します。単に現状の手順をそのまま書き出すのではなく、「あるべき姿」を考え、無駄な手順の削除、手順の統合や順序変更、新しいツールの導入などを検討します。
この際、現場の担当者の意見を十分に聞き、実現可能かつ効果的なプロセスを設計することが重要です。関係者で議論を重ね、新しい標準プロセスに対する合意形成を図りましょう。
ステップ4:マニュアル(手順書)の作成
設計した標準プロセスに基づき、いよいよマニュアル(手順書)を作成します。このステップで重要なのは、「誰が読んでも理解でき、その通りに実行できること」です。後述する「作成のコツ」を意識しながら、具体的で分かりやすい記述を心がけましょう。
使用するフォーマット(Word, Excel, PowerPoint, マニュアル作成ツールなど)を選定し、文章だけでなく、図や写真、スクリーンショットなども効果的に活用します。特に複雑な手順や、言葉だけでは伝えにくい内容は、視覚的な要素を取り入れることが理解促進の鍵となります。
本記事よりもわかりやすい、かつ重要な要点だけをまとめたマニュアル作成ガイドは、下の画像をクリックしてご覧いただけます。早速作成に取り掛かりたい方は資料を参考にしてみてください。
ステップ5:マニュアル(手順書)の導入・定着・継続的な改善
作成したマニュアルは、現場に導入し、関係者に周知・教育を行って初めて価値を発揮します。説明会を開いたり、OJTで実際にマニュアルを使いながら指導したりするなど、確実に内容が伝わるように工夫しましょう。
そして最も重要なのが、導入後の運用と継続的な改善です。実際にマニュアルを使ってもらいながら、分かりにくい点や改善すべき点がないか、現場からのフィードバックを収集する仕組みを作ります。定期的にマニュアルの内容を見直し、業務内容の変更や改善点に合わせて更新していくことで、マニュアルが形骸化することを防止し、常に「生きたマニュアル」として機能させることが徹底のポイントです。
▼関連記事▼
マニュアルが形骸化する原因は?「更新されない問題」を解消する整備方法
マニュアルで現場のルールを定着させるには?効果的な周知方法や定着しないリスク
失敗しない!現場で「使われる」標準化マニュアル作成の5つのコツ
せっかく時間と労力をかけて作成したマニュアルも、現場で読まれ、活用されなければ意味がありません。「読みにくい」「分かりにくい」「情報が古い」といった理由で使われなくなってしまうケースは、残念ながら少なくありません。ここでは、現場で”本当に使われる”標準化マニュアルにするための具体的なコツを4つご紹介します。
コツ1:目的と対象者を明確にする
まず、「このマニュアルは、誰に、何を理解してもらい、どうなってほしいのか」という目的と対象者を明確に定義します。例えば、
- 新人向けに、基本的な作業手順を間違いなく覚えてもらうためのマニュアル
- 経験者向けに、特定の条件下での応用的な対応方法を伝えるためのマニュアル
- 管理者向けに、業務全体の流れと管理ポイントを理解してもらうためのマニュアル
このように対象者が異なれば、盛り込むべき情報、記述の詳しさ、専門用語の使用レベルなどが変わってきます。対象者に合わせた内容と表現を意識することが、分かりやすさの第一歩です。
コツ2:5W1Hを意識し、具体的かつ簡潔に記述する
マニュアルに記載する各手順について、「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」行うのかを具体的に記述します。「〇〇を××する」といった曖昧な表現ではなく、「〇〇システムの△△画面を開き、□□ボタンをクリックする」のように、誰が読んでも同じ行動が取れるレベルまで具体的に書くことが重要です。
ただし、具体的に書こうとするあまり、冗長にならないよう注意も必要です。一文を短くしたり、箇条書きを用いたりするなど、簡潔で読みやすい文章を心がけましょう。一般的な説明だけでなく、自社の状況に合わせた記述が必要です。
コツ3:専門用語を避け、平易な言葉で表現する
社内だけで通用する略語や専門用語は、新人や部署外の人には理解できません。できるだけ一般的で平易な言葉を選んで記述しましょう。どうしても専門用語を使う必要がある場合は、注釈を入れたり、巻末に用語集を設けたりするなどの配慮が必要です。読者の知識レベルを想定し、専門用語の壁で理解を妨げないようにしましょう。
コツ4:図、写真、そして「動画」を効果的に活用する
文章だけでは伝わりにくい業務内容や仕事の流れ、システムの操作画面などは、図(業務フロー図、画面キャプチャなど)や写真を効果的に活用することで、格段に分かりやすくなります。
特に、実際の作業の動き、手順の細かなニュアンス、言語化しにくい「カン・コツ」などを伝える場合には、動画が非常に有効な手段となります。動画であれば、一連の流れを視覚と聴覚で直感的に理解でき、誤解も生じにくくなります。
動画マニュアルが業務標準化に有効な理由は、「【課題解決の鍵】動画マニュアルが業務標準化を加速させる理由」で解説しています。
【事例】手順書刷新で業務標準化を実現した企業や現場
ここでは、実際にマニュアルや作業手順書を工夫して整備し、業務標準化に成功した企業の事例を3つご紹介します。各社が抱えていた課題と、それをどのように乗り越えたのかを見ていきましょう。
アサヒ飲料株式会社 - 熟練者の暗黙知を動画で形式知化
清涼飲料メーカーの「アサヒ飲料株式会社」では、製造ラインにおけるOJTの負荷増大や、紙の手順書作成・更新の手間、熟練者の暗黙知の継承などが課題でした。そこで「動画マニュアル」を現場の教育体制に導入。スマートフォンやタブレットで撮影した動画マニュアルを、簡単に編集・共有できる体制を構築しました。
結果として、OJT工数や手順書作成工数を大幅に削減。動画によって熟練者の作業の「カン・コツ」も見える化され、技術伝承と作業の標準化が進みました。同社の詳細な事例は以下の記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化
ASKUL LOGIST株式会社 - 多拠点・大人数での業務標準化と安全意識向上
物流サービスを提供する「ASKUL LOGIST株式会社」では、全国の拠点、3,500名超の従業員に対して、業務手順の標準化と安全教育の徹底が課題でした。特に新人や派遣スタッフへの教育に時間と手間がかかっていました。
そこで動画を活用し、庫内作業の手順や安全ルールなどを見える化・標準化しました。多拠点での教育内容の均質化を実現し、従業員の安全意識向上にも繋がりました。いつでも動画で復習できるため、教育効果も高まっています。
同社の詳細な事例は以下の記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
従業員数3,500名超・全国15拠点で 動画マニュアルtebikiを活用!
これらの事例から分かるように、分かりやすいマニュアル、特に動画を活用したマニュアルは、業種や規模を問わず、業務標準化とそれに伴う様々な効果(効率化、品質向上、技術伝承など)を実現する上で非常に有効な手段と言えます。
本事例の企業はいずれも、現場教育に特化した動画マニュアル「tebiki現場教育」で標準化を推進されています。tebikiの詳しい機能や活用事例については、「3分で分かる『tebikiサービス資料』でまとめられています。下の画像をクリックすると資料ダウンロードができるので、あわせて参考にしてみてください。
【課題解決の鍵】動画マニュアルが業務標準化を加速させる理由
標準化マニュアルを作成する際、特に「動き」や「手順のニュアンス」を正確に伝える上で、動画マニュアルは非常に強力なツールとなります。従来の紙やテキストベースのマニュアルが抱えていた課題を解決し、業務標準化を力強く推進する手段として、近年多くの企業で導入が進んでいます。その理由と効果を詳しく見ていきましょう。
紙やテキストマニュアルでは伝わりにくい「カン・コツ」の可視化
熟練者の細かな手の動き、作業のタイミング、力加減、姿勢、目線の配り方といった、いわゆる「カン・コツ」や暗黙知は、文章や静止画だけではどうしても伝えきれません。「適量」「素早く」「慎重に」といった言葉で表現しても、受け手によって解釈が異なってしまいます。
動画であれば、実際の業務の流れやポイントを映像と音声で正確に記録し、視覚的に伝えることができます。お手本となる作業をそのまま見せることで、見る人は具体的なイメージを掴みやすく、誤解なく手順を理解・習得することが可能です。
例えば「児玉化学工業株式会社」では、実際に以下のような動画マニュアルが活用されています。
▼ヤスリでバリをとる動画マニュアル(音量にご注意ください)▼
※tebikiで約10分で作成されました
こうした複雑な工程は文字では伝えにくく、OJTによる教育負担が大きい工程ですが、動画マニュアルによって作業イメージが明確に固まりやすくなります。
他にも、実際にどのような動画マニュアルが業務で使われているのか、具体的なサンプルを見てみたい方は、「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(pdf)」が役立ちます。様々な現場の動画サンプルがまとめられており、自社での活用イメージを膨らませるのに最適です。下のリンクをクリックして、ダウンロードしてみてください。
>>>「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」を見てみる
新人や外国人材でも理解しやすい直感的な分かりやすさ
文章を読むのが苦手な人や、業務経験の浅い新人にとって、長文のテキストマニュアルは読むだけで負担になりがちです。また、日本語の読み書きが得意でない外国人スタッフにとっては、言語の壁が理解をさらに難しくします。
動画は、視覚と聴覚に直接訴えかけるため、直感的に内容を理解しやすいという大きなメリットがあります。文字を読む必要が少なく、実際の作業を見ながら学べるため、新人や外国人材にとって非常に効果的な教育ツールとなります。
実際に、アメリカの工場で動画マニュアルを導入した「株式会社Archem」は、動画の効果について以下のように捉えています。
動画ならば、言語の壁を越えながら教育内容を標準化できる。教育のためにわざわざ日本から海外工場へ行かなくても、日本拠点のノウハウを動画で共有できる。
言語や文化の違いを乗り越えた人材育成に成功しています。字幕機能や自動翻訳機能を活用すれば、さらに多言語対応が容易になり、グローバルな標準化にも貢献します。
外国人社員の教育課題解決に関心のある方は、「外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!(pdf)」をご覧ください。動画が有効な理由が具体的にまとめられています。下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
マニュアル作成・更新の手間を大幅に削減
従来のマニュアル作成は、文章作成、図の挿入・編集、レイアウト調整、印刷、配布など、多くの工数がかかり、現場担当者にとっては大きな負担でした。特に、手順の変更があった場合の修正・再配布は非常に手間がかかります。
とはいえ「動画」と聞くと「紙マニュアルよりも難しそう」と思われがちですが、現場従業員が撮影から編集まで気軽にできるよう設計された動画マニュアルツールであれば、紙よりも短い時間でマニュアルが整備できるのです。
その例として、「株式会社タマムラデリカ」では、動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」導入後、1つの手順書を整備するのに15分ほどで完結しています。
※同社の詳しい事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
動画マニュアル作成時間が75%削減!教育体制を強化し、お客様に喜ばれる商品を提供したい
よくある失敗「マニュアルを整備したものの使われなくなった」を防ぐには?
マニュアルは作成して終わりではなく、現場で継続的に活用されてこそ、業務標準化の効果を持続させることができます。しかし、「作っただけで誰も見ていない」「情報が古くて役に立たない」といった理由で、マニュアルが形骸化してしまうのは「よくある失敗」です。
ここでは、そうした失敗を防止し、マニュアルを活かし続けるための運用・改善のポイントを解説します。
マニュアルの保管場所とアクセス方法を明確にする
まず基本的なことですが、誰でも必要な時にすぐにマニュアルを参照できるよう、保管場所とアクセス方法を明確にし、関係者全員に周知徹底することが重要です。
| 保管場所 | 全員がアクセスしやすい共有フォルダ、社内ポータル、情報共有ツール、あるいは動画マニュアル作成ツールのプラットフォーム上などが考えられます。 |
| アクセス方法 | どこに何のマニュアルがあるのかが一目で分かるように、フォルダ構成を工夫したり、検索しやすいようにファイル名を統一したりするルールを設けましょう。QRコードを現場に掲示して、スマホから直接アクセスできるようにするのも有効です。 |
「どこにあるか分からない」「探すのが面倒」という状態にしないことが、活用の第一歩です。
定期的なレビューと更新プロセスを確立する
業務内容、使用する設備やシステム、関連法規などは変化します。それに合わせてマニュアルの内容も更新しなければ、情報は古くなり、役に立たないどころか、誤った作業を招く原因にもなりかねません。
マニュアルを常に最新の状態に保つためには、定期的なレビューと更新のプロセスを確立することが不可欠です。
| レビュー頻度 | 例えば、「年に1回」「半年に1回」など、業務内容や変化のスピードに応じてレビュー時期を定めます。 |
| 担当者 | 各マニュアルの責任者(レビュー担当者、更新担当者)を明確にします。 |
| 更新プロセス | 現場からの修正依頼の受付方法、承認フロー、更新後の周知方法などをルール化します。 |
| 改訂履歴 | いつ、誰が、どの部分を、なぜ変更したのかが分かるように、改訂履歴を必ず記録します。 |
このプロセスを組織的に回していくことで、マニュアルの信頼性と実用性を維持できます。マニュアルの改訂方法や見直しのタイミングについては、以下の記事が参考になります。
▼関連記事▼
【マニュアル改訂方法】表紙の書き方から履歴の残し方まで!目的も解説
作業手順書の見直し・改訂のタイミングは?手順や見直さないリスクを解説
現場からのフィードバックを収集し、改善に活かす仕組み
マニュアルの分かりやすさや使い勝手は、実際にそれを利用する現場の担当者が一番よく知っています。「この部分の説明が分かりにくい」「実際の手順と少し違う」「もっとこうした方が良いのでは?」といった現場の声は、マニュアルをより良くするための貴重な情報源です。
現場からのフィードバックを積極的に収集し、改善に活かす仕組みを作りましょう。
| 収集方法 | 定期的なアンケート調査、ヒアリングの実施、意見箱の設置、マニュアルに対するコメント機能(ツールにあれば)の活用などが考えられます。 |
| フィードバックへの対応 | 寄せられた意見を検討し、マニュアルに反映するかどうかを判断し、その結果をフィードバック提供者に伝えることで、現場の改善活動への参加意欲を高めることができます。 |
現場を巻き込んだ継続的な改善こそが、マニュアルを形骸化させない秘訣です。
まとめ:効果的なマニュアルで業務標準化を実現し、生産性を向上させよう
本記事では、業務標準化の重要性の再確認から、その実現に不可欠なマニュアル(手順書)の作成方法、現場で使われるためのコツ、運用ポイント、そして標準化を加速させる動画マニュアルの活用まで、幅広く解説しました。
業務標準化は、属人化の排除、品質の安定化、生産性向上、人材育成の効率化など、企業に多くのメリットをもたらします。その成功には、分かりやすく、現場で活用されるマニュアルの整備と、継続的な運用・改善が不可欠です。「作って終わり」ではなく、常に最新の状態に保ち、現場の声を取り入れて進化させていくことが重要となります。
特に、動きやコツが重要な業務においては、従来のテキストベースのマニュアルに加え、動画マニュアルを導入することで、より早く、確実に標準化を進めるための鍵となります。視覚的に分かりやすく、言語の壁も越えやすいため、多様な人材が活躍する現代の職場環境において、その効果はますます高まっています。
動画マニュアルの導入や活用方法について、さらに詳しく知りたい方は、「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」や「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法(pdf)」をご参照ください。導入推進のステップや具体的なユースケースが分かります。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。