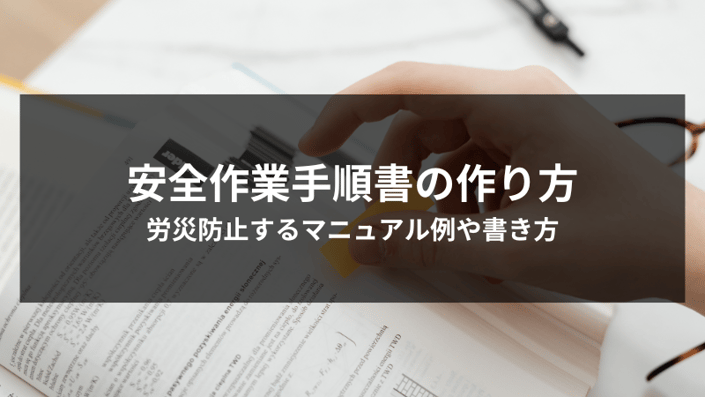

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
製造業や工場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、tebikiサポートチームです。
安全作業手順書(安全作業マニュアル)の作成や見直しは、現場の安全を守る上で不可欠ですが、構成や作り方がいまいち分からないという声はよく聞きます。
そこで本記事では、数多くの企業の現場教育を支援してきた弊社の実践的な経験と知見に基づき、法令遵守と現場での実用性を両立する安全作業手順書の作成方法、すぐに使えるテンプレート例、そして作成・運用における注意点を具体的に解説します。
このように、現場で実用的な安全作業手順書を作成することは、安全な職場環境を築くための第一歩です。
しかし、どれだけ優れた手順書を作成しても、それが現場の作業者に守られなければ意味がありません。「手順書通りにできない」あるいは「守られない」という問題は、多くの現場が抱える深刻な課題です。
手順書を作成した「後」の課題である、作業ルールをいかにして守らせるか。その効果的な方法について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法を見てみる
目次
- 1. 安全作業手順書(安全作業マニュアル)とは?
1-1. 安全作業手順書の重要性
1-2. 法的根拠と作成義務
1-3. リスクアセスメントとの関係
2. なぜ安全作業手順書が必要なのか?現場でよくある課題
2-1. 課題1:労働災害リスクの増大
2-2. 課題2:業務理解が浅い新人や外国人従業員の事故リスクが高い
2-3. 課題3:教育・指導の非効率化と負担増
2-4. 課題4:法令違反・コンプライアンス上のリスク
3. 安全作業手順書のマニュアル例(テンプレートあり)
3-1. 一般的な安全作業手順書に含めるべき項目
4. 分かりやすい安全作業手順書の書き方
4-1. 手順1:目的と対象作業の明確化
4-2. 手順2:作業の洗い出しとリスクアセスメントの再確認
4-3. 手順3:作業手順の分解と順序決定
4-4. 手順4:各ステップの具体的な作業内容を記述
4-5. 手順5:危険・有害要因と安全対策(急所)を明記
4-6. 手順6:図、写真、イラストの活用
5. 「安全作業」と「危険作業」が可視化された手順書が鍵
6. 安全作業手順書を作成・運用する際の注意点
6-1. 注意点1:現場の実態に合わせる
6-2. 注意点2:分かりやすさを追求する
6-3. 注意点3:定期的な見直しと改訂
6-4. 注意点4:周知徹底と教育・訓練の実施
6-5. 注意点5:外国人労働者にも対応できる手順書を作成する
7. まとめ
安全作業手順書(安全作業マニュアル)とは?
まず、安全作業手順書やマニュアルがどのようなものであり、なぜ重要なのか、基本的な知識を確認しましょう。
安全作業手順書の重要性
安全作業手順書の整備は、企業にとって多くのメリットをもたらします。
| 労働災害の防止 | 最も重要な効果です。危険な箇所や正しい安全対策を明記することで、ヒューマンエラーによる事故を防ぎます。 |
| 作業効率の向上と品質の安定化 | 標準化された手順を示すことで、無駄な動作をなくし、誰が作業しても一定の品質を保てるようになります。 |
| 教育・訓練の効率化 | 新人や未経験者に対する教育ツールとして活用でき、OJT(On-the-Job Training)の負担軽減や教育レベルの均一化につながります。 |
| 法的要求事項の遵守 | 労働安全衛生法などで求められる事業者責任(安全配慮義務など)を果たす一助となります。 |
法的根拠と作成義務
労働安全衛生法では、事業者は労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じる義務があると定められています。具体的には、第二十条 - 第三十六条にて以下のような内容が定められています(一部抜粋)。
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及 び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
出典:労働安全衛生法 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条-第三十六条)
また、リスクアセスメントの実施と、その結果に基づく措置の実施が努力義務(一部義務)とされており、安全作業手順書の作成・整備はその具体的な措置の一つとして位置づけられます。
特定の危険有害な作業(例:化学物質の取り扱い、特定の機械操作など)については、手順書の作成がより強く求められる場合があります。しかし、法的な義務の有無に関わらず、従業員の安全確保という企業の社会的責任を果たす上で、自主的な作成と運用が極めて重要です。
危険有害作業の手順書をはじめ、あらゆる「業務マニュアル」の作成に応用できる、そのまま真似できる「見本」付きの完全ガイドをご用意しました。
>>そのまま真似できる「見本」付き 業務マニュアルの作り方完全ガイドを見てみる
リスクアセスメントとの関係
安全作業手順書を作成するためには、リスクアセスメントの実施が不可欠です。リスクアセスメントとは、職場に潜む危険性や有害性(リスク)を特定し、それらのリスクの程度を見積もり、優先度を設定してリスク低減措置を決定する一連の手法です。
労働安全衛生法の第二十八条の二にも、リスクアセスメント(危険性または有害性等の調査)について言及されています。
粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
出典:労働安全衛生法 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条-第三十六条)
つまり安全作業手順書は、このリスクアセスメントを通じた調査結果に基づく対策実施の手段の1つとしても重要な役割を果たしているのです。「どの作業の」「どの部分に」「どのような危険があり」「どうすれば安全か」を具体的に落とし込んだものが、安全作業手順書なのです。
安全作業手順書があるにも関わらず繰り返される「不安全行動」を、行動科学の観点から根本的に防止するための具体的な方法を、チェックリスト付きで解説します。
>>"現場指導チェックリスト付"繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
なぜ安全作業手順書が必要なのか?現場でよくある課題
安全作業手順書の重要性は理解していても、「うちには必要ない」「作っても形骸化している」といった現場もあるかもしれません。しかし、手順書がない、または機能していない現場では、以下のような課題が発生しがちです。
課題1:労働災害リスクの増大
最も深刻な課題は、労働災害の発生リスクが高まることです。 手順が曖昧だったり、作業者によってやり方が異なったりすると、危険な状況を見落としたり、誤った操作をしてしまったりする可能性が高まります。特に、経験の浅い作業員や、久しぶりにその作業を行う作業員にとっては、安全な進め方を示す手順書がなければ、事故につながるリスクは格段に上がります。
特に製造業は労災の発生が多く、安全教育がより重要です。資料「製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育」では、安全意識を現場に浸透させる教育方法についてまとめられています。あわせて参考にしてみてください。
課題2:業務理解が浅い新人や外国人従業員の事故リスクが高い
特に安全作業手順書が重要になる場面は、「新人従業員」や「外国人従業員」の安全教育です。何が危険で何が安全なのかが理解できていないうちは、気が付かずに危険な作業手順を踏んでしまうことが多々あります。ゆえに安全作業手順書の整備は不可欠ですが、整備時間がなかなか取れないのも事実です。
例えば製造業の「トーヨーケム株式会社」は、安全作業手順書の一環として「現場作業の事故を再現し、動画におさめ、従業員全員で視聴する」ような教育体制を整えています。

安全教育は直接指導やOJT教育が不可欠なので、教育担当者の工数に負担が生じがちです。ゆえに、同社の取組のような工夫を通じて、効率的な教育を推進しつつ、新人や外国人スタッフの事故リスク低減に努めていかなければなりません。
同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事でご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
新人からベテランまで700名を超える組織教育のグローバルスタンダードを目指す
トーヨーケム社の事例のように、特に言語の壁がある「外国人社員」の教育課題は、視覚的に伝えられる「動画マニュアル」で解決できることを、以下の資料で詳しく解説します。
>>外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!を見てみる
課題3:教育・指導の非効率化と負担増
安全作業手順書がないと、新人教育やOJTは指導担当者の経験や勘に頼らざるを得ません。これにより、「教える人によって言うことが違う」「指導に時間がかかりすぎる」「担当者の負担が大きい」といった問題が発生します。
標準化された手順書があれば、教育内容を均質化でき、指導の効率も格段に向上します。新入社員や未経験者が安全に作業を覚え、早期に戦力化するための重要な基盤となります。
例えば、大手飲料メーカーの「アサヒ飲料株式会社」では以前、OJTに大きく依存する状態が続いていました。そこで、「一目見ればわかる手順書の整備」を決意し、「動画マニュアル」の導入に踏み切ったのです。結果的にOJTや手順書の作成工数が大幅に削減され、暗黙知を視覚的に伝えられるようになりました。
※同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
▼インタビュー記事▼
OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化
製造業の現場で、動画マニュアルがどのように活用され成果を上げているか、具体的な事例を知りたい場合は、「製造業における動画マニュアル活用事例集(pdf)」がおすすめです。多様な企業の導入事例がまとめられています。
課題4:法令違反・コンプライアンス上のリスク
万が一、労働災害が発生した場合、安全管理体制の不備、特に安全作業手順書の未整備や不備が、安全配慮義務違反として企業の法的責任を問われる要因となる可能性があります。 コンプライアンス遵守の観点からも、適切な安全作業手順書の整備は企業にとって重要な取り組みです。
安全作業手順書のマニュアル例(テンプレートあり)
ここでは、特定の業種・作業に特化しない、一般的な安全作業手順書に含めるべき基本的な項目(構成要素)を以下に示します。これをテンプレートとして活用し、自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。なお、作業手順書のテンプレートは以下の記事でダウンロード可能です。
>>>テンプレート:作業手順書のわかりやすい作り方!作成例も紹介
一般的な安全作業手順書に含めるべき項目
安全作業手順書には以下のような項目を踏まえると良いでしょう。
| ① 表紙・基本情報 | ・作業名(例:〇〇機械の清掃作業) ・手順書番号、版数 ・作成年月日、改訂年月日 ・作成部署、作成者 ・承認者 |
| ② 目的 | この手順書が何のために作られたのかを記載(例:〇〇作業における労働災害の防止) |
| ③ 適用範囲 | この手順書がどの作業、どの部署、どの作業員に適用されるのかを明確化 |
| ④ 作業に必要な保護具・設備・工具 | 安全に作業を行うために必須の保護具(ヘルメット、安全靴、保護メガネなど)や、使用する設備、工具をリストアップ |
| ⑤ 作業手順 | ・作業を具体的なステップに分解し、順を追って記述 ・各ステップで「誰が」「何を」「どのように」行うのかを明確に |
| ⑥ 各ステップにおける危険・有害要因と安全上の注意点(急所) | ・手順書の最も重要な部分 ・各ステップに潜む危険(挟まれ、巻き込まれ、感電、墜落、有害物接触など)と、それに対する具体的な対策、禁止事項、遵守事項を明記 ・「なぜその対策が必要なのか」理由も簡潔に記述すると理解が深まる |
| ⑦ 異常時の措置 | 作業中に異常が発生した場合(機械の故障、体調不良など)の連絡先や対応手順 |
| ⑧ 関連文書 | 関連する他のマニュアル、リスクアセスメント結果、点検表などがあれば記載 |
| ⑨ その他 | 必要に応じて、作業前の点検項目、作業後の片付け手順などを追加 |
上記に加え、図や写真、イラストを効果的に挿入することで、より分かりやすい手順書になります。
現場で確実に読まれ、活用される作業手順書の作り方のポイントを知りたい方は、「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント(pdf)」が参考になります。具体的な作成ポイントがまとめられているので、以下をクリックして、ダウンロードしてみてください。
>>カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
分かりやすい安全作業手順書の書き方
テンプレートや構成要素が分かったところで、次は実際に手順書を作成していく際の具体的な書き方と進め方を6つのステップで解説します。
ちなみに、手順書は、分かりやすい内容にするのも大事ですが、「定期的に更新される仕組みづくり」も同じくらい重要です。現場で使われ続ける(作業ルールが守られ続ける)体制になってはじめて、従業員の安全が守られることになります。
下の画像は、資料「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント(pdf)」から抜粋した、作業手順書が更新されるための仕組みを図解したものです。
このような手順書が使われるための重要なポイントもあわせて知りたい方は、下のリンクをクリックして資料をご覧ください。
>>>「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント(pdf)」を見てみる
手順1:目的と対象作業の明確化
まず、「何のための手順書か(例:新規導入設備の安全な操作方法の習得)」という目的と、「どの作業についての手順書か」を明確に定義します。対象範囲が広すぎると内容が曖昧になるため、具体的な作業単位で作成するのが基本です。
手順2:作業の洗い出しとリスクアセスメントの再確認
対象作業を構成する個々の単位作業を洗い出します。
「準備」→「機械操作」→「点検」→「片付け」のように、作業の流れに沿ってリストアップします。そして、関連するリスクアセスメントの結果を再度確認し、各単位作業に潜む危険性や有害性を漏れなく把握します。
手順3:作業手順の分解と順序決定
洗い出した単位作業を、さらに細かい具体的な手順(ステップ)に分解します。
作業者が実際に行う動作をイメージしながら、「〇〇のボタンを押す」「〇〇のレバーを引く」といったレベルまで具体化します。分解した手順を、論理的かつ安全な順序に並べ替えます。
手順4:各ステップの具体的な作業内容を記述
各ステップについて、「誰が」「何を」「どのように」行うのかを、具体的かつ簡潔な文章で記述します。
曖昧な表現(例:「適切に」「注意して」)は避け、客観的な事実や具体的な行動を示す言葉を選びます。「5W1H」(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると、記述内容が明確になります。
5W1Hで記述することが最も難しい、熟練者の感覚的な「カンコツ作業」をいかにして標準化するか、その最適解を以下の資料で解説します。
>>“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解を見てみる
手順5:危険・有害要因と安全対策(急所)を明記
ここが安全作業手順書の核心部分です。各ステップごとに、リスクアセスメントで特定された危険・有害要因(例:回転部への巻き込まれ、高温部への接触、有害物質の吸引)と、それに対する具体的な安全上の注意点や対策(急所)を、目立つように分かりやすく記述します。
「保護メガネを着用する」「スイッチを切ってから清掃する」「換気装置を作動させる」など、具体的な行動を指示します。「なぜ危険なのか」「なぜその対策が必要なのか」という理由も併記すると、作業者の安全意識向上につながります。
明確な安全指示と、現場で繰り返される「不安全行動」とのギャップを、行動科学の観点から埋めるための決定的な防止網の作り方を、チェックリスト付きでご紹介します。
>>"現場指導チェックリスト付"繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
手順6:図、写真、イラストの活用
文字だけでは伝わりにくい操作方法、危険箇所、正しい保護具の着用方法などは、図や写真、イラストを積極的に活用しましょう。視覚情報は直感的な理解を助け、特に経験の浅い作業者や外国人作業員にとって有効です。ただし、情報が多すぎると逆に分かりにくくなるため、ポイントを絞って効果的に使用します。
例えば、動画マニュアルによる安全意識の向上や教育は、多くの製造業で導入されています。何が安全で、何が危険な作業なのかが一目でわかるようになるからです。
動画マニュアルの例として、児玉化学工業株式会社が実際に撮影・編集を手掛けた作業手順書の動画マニュアルを、一部ご紹介します。
▼ヤスリでバリをとる動画マニュアル(音量にご注意ください)▼
※「tebiki」で作成
これらの工程は文字では伝えにくく、OJTによる教育負担が大きい工程ですが、動画マニュアルによって作業イメージが明確に固まりやすくなります。また、安全な作業手順もある程度の理解ができるようになるので、安全作業を可視化する手段としても有効です。
同社の動画活用事例に関する詳細は、以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
製造業の動画マニュアル導入事例 | 工場の作業手順や異常処置、安全指導を動画で作成。手順書作成の工数は紙の1/3に。自動翻訳で外国人教育にも活用。
製造業の現場で、動画マニュアルがどのように活用され成果を上げているか、具体的な事例を知りたい場合は、「製造業における動画マニュアル活用事例集(pdf)」がおすすめです。以下をクリックして、ダウンロードしてみてください。
「安全作業」と「危険作業」が可視化された手順書が鍵
安全な作業が遵守されるには、「なぜその作業プロセスでなければ危険なのか」「どうしてその手順を踏むと安全になるのか」が、手順書を見てある程度把握できる状態が不可欠です。そのためには、文字だけの手順書や紙マニュアルでは、なかなか教育が難しいと言えるでしょう。
そこで、「手順6:図、写真、イラストの活用」章で触れたように、分かりやすい手順書整備には「動画」が1つの有効手段と言えます。動画なら、一目で作業手順がある程度理解できるだけでなく、教育担当者が不在でも動画で作業手順を学習する教育体制が作れるので、教育工数の削減にもつながります。
動画マニュアルは撮影や編集が難しい印象があるかもしれませんが、現場作業に特化した動画マニュアル作成ツール(例:tebiki現場教育)であれば、従業員の稼働時間を圧迫することなく動画マニュアルを手軽に作成できます。実際、製造業の児玉化学工業株式会社が作成したこちらの動画マニュアルは、現場従業員によって10分程度で作成されています。
ここまでで少しでも動画マニュアルに興味があれば、現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料もあわせてご覧ください。詳細な機能や、安全教育の活用イメージ、活用事例等、動画マニュアルの効果やメリットについて体系的に知ることができます。
以下をクリックして、動画マニュアル作成ツールが現場の安全教育にどのように活用できるか、イメージを膨らませてみてください。
安全作業手順書を作成・運用する際の注意点
せっかく作成した安全作業手順書も、現場で活用されなければ意味がありません。形骸化させず、安全確保に確実に役立てるための運用上の注意点を解説します。
運用面での工夫はもちろん重要です。しかし、そもそもなぜ手順書は「形骸化」してしまうのでしょうか。
その根本的な原因に目を向け、作成段階から「本当に意味のある」手順書を作ることが、形骸化を防ぐ最も確実な方法です。
以下の資料では、手順書が形骸化してしまう原因を分析し、現場で本当に役立つ手順書を作成するためのポイントを詳しく解説しています。
>>作業手順書が形骸化する原因 「本当に意味のある」手順書を作るには?を見てみる
注意点1:現場の実態に合わせる
手順書の内容が、実際の作業現場の状況や設備、作業者のスキルレベルとかけ離れていては、守られることはありません。作成・改訂にあたっては、必ず現場の作業者の意見をヒアリングし、実態に即した、実行可能な内容にすることが重要です。机上の空論にならないよう注意しましょう。
>>実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集を見てみる
注意点2:分かりやすさを追求する
誰が読んでも理解できるよう、専門用語や難しい言い回しは避け、具体的で平易な言葉を選びましょう。一文を短くしたり、箇条書きを用いたりするのも効果的です。写真やイラストの活用はもちろん、文字の大きさや行間、レイアウトなども工夫し、視覚的な分かりやすさも追求しましょう。
まさに、今ご紹介した分かりやすさの工夫は、優れたマニュアルを作成するための大原則です。
しかし、これらの工夫を凝らしてもなお、文章や静止画だけでは伝えきることが難しい領域が存在します。それが、熟練者の感覚や経験に支えられた「カンコツ作業」です。
このカンコツの部分がうまく伝わらないと、マニュアルは「伝わらない」「属人化している」といった壁に突き当たります。
この最も伝達が難しい「カンコツ作業」をいかにして標準化するか。その最適解について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解を見てみる
注意点3:定期的な見直しと改訂
作業方法の変更、新しい機械・設備の導入、法規制の改正、ヒヤリハット事例や災害事例の発生などを踏まえ、手順書の内容は定期的に見直す必要があります。少なくとも年に1回、あるいは変化があった都度、内容が現状に適合しているかを確認し、必要であれば速やかに改訂しましょう。改訂履歴をきちんと記録・管理することも重要です。
>>「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書を見てみる
▼関連記事▼
作業手順書の見直し・改訂のタイミングは?手順や見直さないリスクを解説
注意点4:周知徹底と教育・訓練の実施
手順書を作成・改訂しただけで満足せず、その内容を対象者全員に確実に周知することが不可欠です。単に配布するだけでなく、朝礼での説明、講習会の実施、OJTでの実践などを通じて、内容の理解と遵守を徹底しましょう。「なぜこの手順が必要なのか」「守らないとどうなるのか」といった背景やリスクも合わせて伝えることで、安全意識を高めることができます。
手順書の背景やリスクを伝える安全教育を、さらに「ヒューマンエラー」の防止という観点から体系化した、効果的な進め方を以下の資料で解説します。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
▼関連記事▼
・マニュアルで現場のルールを定着させるには?効果的な周知方法や定着しないリスク
・手順書通りにできない7つの理由!作業ルールを守らせる方法とは
注意点5:外国人労働者にも対応できる手順書を作成する
特に製造業や工場、物流業では、外国人労働者の割合が増えてきています。ゆえに、多国籍人材に適応したマニュアルの整備も重要です。
とはいえ、外国人教育のために、母国語に翻訳したマニュアルを整備するのは非常に工数がかかり、現実的ではありません。そこでよく導入されているのが「非言語マニュアル」です。言葉がなくとも、見ただけである程度の内容が理解できるマニュアルの整備が、現場教育には必須だと言えるでしょう。
非言語マニュアルで推奨されているのは「動画マニュアル」です。例えば製造業の「株式会社Archem(アーケム)」は、3つのアメリカの工場で動画マニュアルを導入し、工場全体のパフォーマンスを向上させています。
※同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
▼インタビュー記事▼
アメリカ3工場にて言語の壁を乗り越え、製品品質と生産性を向上
ご紹介したArchem社の例のように、言語の壁を越えて直感的に作業内容を伝えられる動画マニュアルは、外国人労働者への教育において絶大な効果を発揮します。
Archem社以外にも、多くの企業が動画マニュアルを活用して外国人労働者への「伝わらない」という課題を解決しています。様々な企業の具体的な取り組みと成果をまとめた事例集を、以下の資料で詳しくご紹介します。
>>外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集を見てみる
まとめ
本記事では、安全作業手順書(安全作業マニュアル)の重要性から、具体的な作成例、分かりやすい書き方のステップ、そして運用上の注意点まで、現場教育のプロの視点から解説しました。
安全作業手順書は、労働災害を未然に防ぎ、従業員の安全を守るために不可欠なツールです。リスクアセスメントに基づき、現場の実態に即した、誰にでも分かりやすい手順書を作成・整備し、定期的な見直しと教育を徹底することが重要です。目的意識を持って、手順書の改善に取り組みましょう。
しかし、従来の紙媒体の手順書だけでは、動きやカン・コツといった重要な情報を伝えきれない場面も少なくありません。視覚的に分かりやすく、多言語対応も容易な動画マニュアルは、安全教育の効果を飛躍的に高める可能性を秘めています。紙の手順書を補完する、あるいは代替する有効な手段として、動画マニュアルの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
製造業や工場に特化した動画マニュアル「tebiki現場教育」なら、現場従業員が気軽に、スマホ1つで動画マニュアルを撮影できます。稼働時間を圧迫せずに、紙よりもわかりやすいマニュアルが整備可能です。少しでもtebikiに興味が湧いた方は、以下の画像をクリックして、tebikiのサービス資料をダウンロードしてみてください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。




