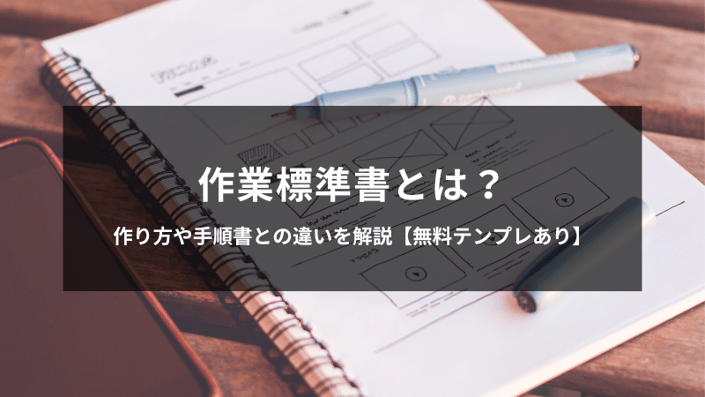

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開するTebiki株式会社です。
製造業や物流業、飲食業などで活用される作業標準書。作業をするうえで重要なルールやコツをまとめており、業務を標準化するために欠かせない文書です。この記事では、作業標準の作り方や作業手順書・マニュアルとの違い、作業標準書を動画で作る方法などを詳しく解説します。
現場で使われる作業手順書の作り方は、「カンコツが伝わる!『現場で使われる』作業手順書のポイント」でも詳しく解説しています。これまで何社もの手順書作成をサポートしてきたtebikiだからこそわかるノウハウをぜひご覧ください。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
目次
- 1. 作業標準書とは、作業方法の基準を定めたもの
1-1. 「作業標準書」と「作業手順書」の違い
1-2. 「作業標準書」と「マニュアル」の違い
2. 【無料DL】作業標準書のテンプレート
3. 作業標準書の作り方
3-1. STEP① 現行の作業内容の観察と改善を行う
3-2. STEP② フォーマットや作成ツールを決める
3-3. STEP③ 骨子を作成する
3-4. STEP④ 骨子をもとに肉付けする
4. 「わかりやすい作業標準書」にするには動画を活用する
4-1. 属人化しやすい複雑な作業を可視化できる
4-2. 教育内容を画一化できる
4-3. OK例/NG例を比較できる
4-4. 何度でも復習できる
4-5. 作成工数を大幅に削減できる
5. 作業標準書や手順書に動画を活用する企業事例
5-1. 導入1年で1,500本以上の動画を作成:新日本工機株式会社
5-2. 手順書作成の工数は紙の1/3に:児玉化学工業株式会社
5-3. 製造業の技術部門の業務を動画で標準化:大同工業株式会社
6. 作業標準書の動画マニュアル化には「tebiki現場教育」が有効
6-1. 誰でもカンタンな動画編集
6-2. 作成工数を削減するための工夫
6-3. 文書も動画もクラウド上へ無制限保存できる
6-4. オフライン環境での閲覧
6-5. 習熟度の把握などの教育管理
7. 【補足】作業標準書の必要性や導入効果
7-1. 品質の向上
7-2. 生産性の向上
7-3. 教育工数の削減
7-4. 事故やトラブルの防止
7-5. 属人化の防止
8. まとめ
作業標準書とは、作業方法の基準を定めたもの
作業標準書とは、作業についての標準的な内容をまとめたものを指します。どのやり方を基準とするのかなどの「標準」を決めることによって、やるべきことや作業の所要時間、必要な工数などが明らかになります。作業標準書は、SOP (Standard Operating Procedures)とも呼ばれています。
決まった様式や項目はありませんが、一般的には次のような内容が盛り込まれることが多いです。
- 作業名
- 作業目的
- 作業に必要な材料、部品、工具、機器など
- 作業に必要な資格や技能
- 作業手順
- 安全上の注意点
なお、作業標準書は「言語化しにくいカンコツが伝わらない」「更新や管理が手間で形骸化してしまう」など、作成~運用に様々な課題があります。その課題を解消し、現場で使われる作業標準書のポイントを説明している資料をご用意していますので、ぜひダウンロードしてみてください。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
作業手順書やマニュアルも似た存在ではありますが、それぞれどんな違いがあるのか以下で見ていきましょう。
「作業標準書」と「作業手順書」の違い
作業標準書と作業手順書の違いは、記載する内容が「総論か」「各論か」ということです。
作業標準書は標準的な作業内容を一通り述べ、作業手順書はその一つひとつの作業手順を展開するもの。作業標準書だけでも作業はできますが、作業者により細かいレベルのことに留意してもらうには作業手順書もあると望ましいでしょう。
以下の記事では、製造業における良い手順書と悪い手順書にどのような違いがあるのかという点や、活用される手順書作成のポイントをまとめているので併せてチェックしてみてください。
▼関連記事▼
製造業における「良い作業手順書」と「悪い作業手順書」の違い
「作業標準書」と「マニュアル」の違い
作業標準書とマニュアルの違いは、記載する内容が「標準的か」「多様なものを盛り込んでいるか」にあります。
作業標準書は、標準的な作業内容を一通り説明するものですが、マニュアルは基準となる作業だけでなくコツやノウハウ、過去の事例、トラブルシューティングなど、基準外のことも盛り込みます。つまり、マニュアルは多くのナレッジを集約し承継していくものとも言えます。
以下の記事では、作業標準書のほか作業手順書や手引書、マニュアル、取扱説明書といった似た概念のものについて定義をご紹介しています。ご興味のある方は併せてご覧ください。
▼関連記事▼
マニュアルとは:「作業手順書」「SOP」等の類語との意味の違いや英語の呼び方など
【無料DL】作業標準書のテンプレート
レイアウトや内容などを一から考えて作業標準書を作成すると非常に時間がかかるので、効率的に作成するためにもテンプレートの活用がおすすめです。作業標準書の作成に活用できるフォーマットをExcel/Word形式で多数ご用意しました。

以下のフォームからtebikiのメルマガにご登録いただくと無料でダウンロードできます。ぜひこの機会にテンプレートをご活用ください。
▼テンプレートDLフォーム▼
作業標準書の作り方
作業標準書は、わかりやすく作業内容を記載する必要があります。必要な情報を抜け漏れなく盛り込み、わかりやすい表現で記載するためには、以下4つの作成手順をもとに作ると良いでしょう。
STEP① 現行の作業内容の観察と改善を行う
作業標準書を作成するはじめのステップとして、標準書に落とし込む作業の観察と改善を行うことがおすすめです。標準とされているやり方がある業務であっても、すでにより良いやり方を行っている作業者がいるかもしれません。作業を経験している複数人で手順を洗い出して見直し、標準的なやり方を決めましょう。
また、一連の作業風景を撮影して、作業の異常/ヒヤリハット/不確かさ/を洗い出すことで、作業の注意点として盛り込むことができます。
作業風景を撮影して分析する手法は、言語化が最も難しい「カンコツ作業」の標準化において特に有効であり、その最適解を以下の資料で解説します。
>>“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解を見てみる
STEP② フォーマットや作成ツールを決める
作業標準書をどのようなフォーマットで作成するかを決め、それによって最適な作成ツールを検討しましょう。
>>動画マニュアルが作れる!無料の動画編集ソフト比較表を見てみる
紙で閲覧する場合は、Microsoft WordやPowerPointなどで作成し印刷します。パソコンやタブレットなどの端末で閲覧する場合は、WordやPowerPointなどのソフトのほか、マニュアル作成ツールや動画作成ツールなどで作成することができます。
標準化された作業手順を守ってもらうには、動画の活用がおすすめです。動画は聴覚情報も届けられるため、記憶に残りやすいという特徴などがあるためです。動画をおすすめする詳しい理由は、後述する『「わかりやすい作業標準書」にするには動画を活用する』で解説します。
なお、テンプレートに沿って作業標準書を作成したい方は「【無料DL】作業標準書のテンプレート」でダウンロードしてご利用ください。
STEP③ 骨子を作成する
作業内容をわかりやすく伝えられる構成を考え、作業標準書の骨子を作りましょう。
製品の組み立て作業であれば「準備/作業手順/機器操作方法」といった順序にするなど、初めて作業標準書を見る人にもわかりやすい順番で作ります。いきなり詳細から作り出すのではなく、構成の骨組みをまず作ることで、作業内容を抜け漏れなく盛り込むことができます。
また、”わかりやすさ”以外に「ECRSの視点」を持つことによって、手順書の内容を厳選できてより伝わりやすい手順書を作成できます。

「わかりやすい構成作成のポイント」や「読む気がなくなるマニュアルの目次構成例」などをご紹介している「マニュアルの「目次構成」の作り方5STEP!見やすい見出しを作るには?」の記事も併せてご覧ください。
なお、『「現場で使われる」作業標準書作成のポイント』をまとめた資料もご用意しております。「標準書が形骸化する理由」「標準書の作成/運用/管理」のポイントを詳しくまとめておりますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
STEP④ 骨子をもとに肉付けする
作業標準書の骨子に沿って、詳しい内容を肉付けしましょう。
肉付けする際は、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を意識して書くと作業者が迷わず作業できます。数値化できるものは数字を使い、写真や図を挿入します。ケガや事故のおそれがある作業では色を使い「危険!」と表示するなど、目立たせるとよいでしょう。
また、専門用語や難しい言葉が多いと標準書を活用する側は理解が深まらない可能性があるため、できるだけ平易な言葉を使うか、注釈で補足を記載するなど誰が見てもわかる工夫をしましょう。
標準書の内容を肉付けする際は、「【例文あり】マニュアル作成での正しい言葉遣いは?伝わる文章の書き方」を紹介している以下の記事をぜひご覧ください。
紙の作業標準書の場合には、骨子の作成や肉付けなどの手間が発生し、作成するうえでかなりの工数が発生してしまいます。少しでも作成する負担を軽減したいと考えている方は動画の活用がおすすめです。以下の資料では、現場で活用される作業標準書のポイント、動画を活用するメリットをご紹介していますので併せてご覧ください。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
「わかりやすい作業標準書」にするには動画を活用する
誰にとっても見やすくわかりやすい作業標準書を作成し、作業の標準化や品質向上を実現していくためには、動画が最も適しています。ここでは、作業標準書を動画にするメリットを5つご説明します。
属人化しやすい複雑な作業を可視化できる
「10年、20年と経験を積んだ熟練者しかできない作業」「言葉で説明するとかえってわかりづらい作業」など、作業現場には属人化しやすい作業が数多くあります。これらを動画化すると、作業者の姿勢や視点、音、動きなどたくさんの情報を可視化でき、他の作業者にも伝承していくことが可能になります。

業務の属人化に大きな課題を抱えていた「サッポログループ物流株式会社」では、動画マニュアルの活用で可視化・標準化を実現でき、教育コストの削減にも寄与しています。同社のインタビュー記事を読みたい方は以下のリンクをクリックしてください。
▼インタビュー記事▼
物流現場のノウハウを動画で可視化!ロジスティクスの生産性を上げるため人財教育の課題に挑む
教育内容を画一化できる
言葉の説明だけでは、人によって理解が異なることがあります。たとえば「レバーが停止する箇所まで回す」という作業では、自然に止まるところでやめる人もいれば、自然に止まるところからさらに強めに押し込む人もいるでしょう。動画でレバーが停止する様子を見れば、解釈の幅がなくなり、標準とする作業を画一化できます。
言葉による指示の解釈のズレを修正する手間こそOJT担当者の負担であり、その手間を動画で解消する「OJT教育の新常識」を以下の資料で解説します。
>>OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?を見てみる
OK例/NG例を比較できる
正しい手順は言葉で説明しやすくても、誤った手順によって発生する影響は言葉で説明しづらいものです。機器の異常が発生するとどんなアラームが鳴るのかなど、OK例とNG例を続けて見ることでわかりやすく伝えることができます。
▼OK例とNG例を示している動画マニュアル▼
(音量にご注意ください)
何度でも復習できる
人の動作や機器の操作などの「動き」は言葉では説明しづらいもの。そのため、作業標準書に加えOJT指導が行われるケースが多くありますが、OJT指導者に何度も同じ動きを見せてもらうことは現実的ではないでしょう。
動画の作業標準書であれば、何度でも視聴し正しい動きを理解できます。その結果、「この作業がよくわかっていないけど、先輩に聞きにくい」などの教育体制の問題も解決できるでしょう。
作業者が「何度でも視聴」できる動画は、「何度も同じ動き」を見せるOJT担当者の負担を激減させる「OJT教育の新常識」そのものです。
>>OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?を見てみる
作成工数を大幅に削減できる
わかりやすい作業標準書を作成するには、言葉選びや写真・イラストの追加などに多くの時間がかかります。しかし動画であれば、業務の様子を撮影するだけで済むため、作業標準書作成のための工数を大幅に削減できます。
1つの文書作成に3時間〜10時間かかっていたものの、動画化したことによって1本あたり30分ほどで作成できるようになり、作成工数の大幅な削減に成功している企業もあります。こちらの企業事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事も併せてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化
ここまで作業標準書を動画にすることで得られるメリットをご紹介してきました。次の見出しでは、実際に動画マニュアルを活用して作業の標準化を進めている企業の事例をご紹介します。
作業標準書や手順書に動画を活用する企業事例
作業標準書や作業手順書を動画で作ることにより、作成の工数を抑えながら標準化を進め、高い教育効果を得られている企業事例を3つご紹介します。
より多くの導入事例を知りたい方は26社の動画マニュアル活用事例を集めた記事か、以下のリンクをクリックしてtebiki現場教育を用いた動画マニュアル活用事例集もご覧ください。
>>>「tebiki現場教育を活用した動画マニュアル活用事例」を見てみる
導入1年で1,500本以上の動画を作成:新日本工機株式会社
▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:新日本工機株式会社▼
工作機械などの製造・販売を手がける新日本工機株式会社では、作業手順が標準化されていない業務があり、作業者や管理者により認識が異なるケースや作業のバラつき・手戻りが課題となっていました。
課題解決のため『標準化プロジェクト』を立ち上げるも、文字ベースの作業要領書では読まれないことが浮き彫りに。また、海外7カ国にある子会社へマニュアルを展開するための翻訳作業に膨大な時間がかかることも課題でした。
標準化プロジェクトへの負荷を軽減しつつ、誰もが標準手順通りに作業ができる体制構築を模索する中で出会ったのがtebikiでした。導入後1年で1,500本以上の動画マニュアルを作成。ワンクリックで瞬時に字幕を翻訳できるので、海外子会社の外国人スタッフに動画を共有するだけで情報伝達が完了するなど、紙マニュアルと比べて効率的にマニュアル整備できました。
新日本工機株式会社の詳しい事例は、以下からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
人が育つ環境づくりとして動画マニュアルtebikiを活用。技術の蓄積と作業品質の安定を実現。
手順書作成の工数は紙の1/3に:児玉化学工業株式会社
▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:児玉化学工業株式会社▼
住宅設備・自動車向け合成樹脂加工や産業機器の製造などを行う児玉化学工業株式会社では、膨大な量の紙の要領書や手順書がありました。しかし紙の手順書ではコツやノウハウを伝えきれず、さらに従業員の使用言語が多種多様で理解してもらいづらい課題を抱えていました。
「外国人従業員の教育に役立つ」「紙ではなくわかりやすい動画にする」「マニュアルが存在しない業務もマニュアル化する」を目指しtebikiを導入。スマートフォンで業務を撮影するだけの簡単作成で、手順書作成の工数は紙の1/3程度まで激減。行方不明になりがちな紙のマニュアルと違い「マニュアルはtebiki」と決めれば探すことがなくなり、標準化も進みました。
児玉化学工業株式会社でのtebiki活用の様子や効果は以下の記事で詳しくご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
製造業の動画マニュアル導入事例 | 工場の作業手順や異常処置、安全指導を動画で作成。手順書作成の工数は紙の1/3に。自動翻訳で外国人教育にも活用。
製造業の技術部門の業務を動画で標準化:大同工業株式会社
オートバイや自動車、産業機械などの部品・機器を製造する大同工業株式会社。文書マニュアルとOJTでの教育体制では、効率化を実現できないという問題を抱えていました。そこで、マニュアルの動画化を検討し、現場の従業員の使いやすさを考慮した結果tebikiを導入。
紙のマニュアルでは、1作業プロット分を作成するのに2時間以上かかっていたものが、tebikiでは1時間以下でできるように。業務の標準化だけでなく、マニュアル作成の過程で従業員からさまざまなノウハウが集まったことで業務の効率化・最適化も進みました。
「tebikiには動画マニュアルを活用した教育に必要な機能が揃っている」と語る大同工業株式会社の詳しい活用状況や導入効果については、次の記事をご覧ください。
▼インタビュー記事▼
製造業の技術部門での動画マニュアル導入事例|製造業の技術部門の業務を動画で標準化。品質評価に関わるヒヤリハットを8割削減して、多能工化を実現
作業標準書の動画マニュアル化には「tebiki現場教育」が有効
作業標準書を初めて動画化する場合は、「動画編集に時間がかかるのではないか」「動画はデータが重いから保存場所の確保が難しい」など、不安を抱える方もいると思います。
動画マニュアル作成ツールtebikiであれば非常にカンタンな操作で動画編集ができ、導入後もずっと続く動画作成サポート体制も受けられます。
▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼
ここでは、作業標準書を簡単に動画にできるtebikiの主な特徴を6つご説明します。
誰でもカンタンな動画編集
tebiki現場教育はとてもシンプルな動画編集画面であり、複雑な操作は一切不要で専門的なスキルや知識がなくても、直感的に動画の編集が可能です。作業の一連の流れを撮影し、重要なシーンでストップしたい・一部の不要なシーンをカットしたいなどの作業もワンクリックで行えます。
tebikiを活用している児玉化学工業株式会社では、導入後に紙の手順書作成時間と比べて1/3まで削減できたという事例もあります。tebikiは動画の作成・視聴がとてもかんたんにできると語る同社の様子は、以下のインタビュー記事を読んでみてください。
▼インタビュー記事▼
手順書作成の工数は紙の1/3になったと思います。動画で作るのはかんたんだし、学ぶ側にもわかりやすいですよね。
作成工数を削減するための工夫
tebikiでは、動画作成がスムーズにできるよう、工数を削減するさまざまな工夫をこらしています。たとえば、動画内の説明を自動で字幕に生成。生成された字幕は100カ国語へ自動的に翻訳されます。

外国人作業者の多い現場では、作業標準書を翻訳するのに多くの時間がかかりますが、ボタン1つで一瞬のうちに翻訳されます。
文書も動画もクラウド上へ無制限保存できる
動画マニュアルだけでなく、文書マニュアルの作成と保存も可能です。これにより、作業標準書の管理が一元化されます。
「文書の作業標準書も参照することがあるため、文書と動画の両方を保存したい」といった職場は少なくありません。tebikiを使えば、「作業標準書はtebikiを見る」というシンプルな動線が確立され、探す手間がなくなるでしょう。
また、tebikiではすべてのデータをセキュリティ対策済みのクラウドに無制限に保存できます。動画を何本作成しても月額の使用料金は変わらないため、作業標準書に加えて、詳細な作業手順書も多数作成できます。ユーザーからは、「自前で保存場所を用意しなくて済む」「導入後1カ月で1,300本のマニュアルを作成した」といった喜びの声も寄せられています。
オフライン環境での閲覧
tebikiはオフライン環境下での閲覧も可能なので、電波の届きにくい地下施設の現場でも作業標準書を見ることができます。YouTubeなどの動画再生ツールの場合、インターネット環境がある場所でしか動画を再生できませんが、tebikiならネット環境がなくても動画の再生が可能。スマートフォン/タブレット/パソコンなどあらゆるデバイスで閲覧でき、動画の読み込みも時間がかからず連続再生できる点でもストレスフリーなツールとなっています。
習熟度の把握などの教育管理
tebikiには動画作成の機能だけでなく、教育効果も確認できる以下の機能もあります。
- テスト作成 / 自動採点機能
- マニュアルの閲覧状況を可視化できる機能
- 個人のスキルを評価して表にできる機能
▼閲覧状況を可視化できるレポート機能▼

よく見られているマニュアルのデータから理解度の低い作業標準書の内容を見直すなど分析に活用し、教育効果の高い作業標準書を整備していく好循環も得られるでしょう。
tebikiにはまだまだ現場教育を効果的に行える機能が搭載されています。詳しくは、「3分でわかるtebikiサービス説明資料」をご覧ください。高い満足度を獲得している無料のサポート体制についてもご紹介しています。
【補足】作業標準書の必要性や導入効果
作業標準書で標準となる作業内容を定め、作業標準書を活用することで、以下のようなメリットが期待できます。
品質の向上
標準的な作業が決まっていれば、誰が手がけても一定の水準の生産物を生み出すことが可能です。さらに、各作業者の努力や工夫によってより良い作業内容を生み出せれば、元の作業標準をベースに新たな標準に改善していくことができます。
生産性の向上
作業標準が定められていない場合、人によってやり方が違ってしまうことがあります。生産物に影響がなければ結果オーライに見えても、後から影響が出て不良品が発生したり、作業の手戻りが発生したりするおそれも。
作業標準を定めることで、不良品や手戻りなどのムダを減らすことが可能になります。
教育工数の削減
作業標準書がない場合は、OJT指導などに頼ることになります。OJT指導は教わる側にわかりやすいメリットがありますが、教える側の教育工数が増えるデメリットもあります。かつ、教わる側は何度も同じことを聞きづらかったり、教える側次第で内容がバラついたりするおそれもあります。
作業標準書があれば、作業者同士の引き継ぎにおいても活用でき、「教える人」「教わる人」それぞれの工数の削減につながります。
事故やトラブルの防止
作業標準書に、詳しい手順とともにケガや事故などのリスクを記載することで、初めて作業を行う人に危険性を伝えることができます。また、問題が起こりやすい箇所やその対処方法について記載してあれば、作業者は万が一問題が発生しても適切に対応できます。
作業標準書で事故やトラブルの回避方法や対処方法を伝えることで、作業者が安心・安全に作業できる環境を提供できるでしょう。
作業標準書でリスクを伝えてもなお繰り返される「不安全行動」を、知識ではなく行動科学の観点から根本的に防止する方法を、チェックリスト付きで解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
属人化の防止
作業標準書で手順やノウハウを可視化し共有することで、それぞれの作業者が持つノウハウを組織全体で共有できるようになります。もし作業標準書がなければ、その作業者しかノウハウを持たない状況となり、業務が属人化していくおそれがあります。作業標準書で標準的な作業内容を示すことは、属人化の防止の観点でも有効です。
業務の属人化は、特に専門性が高い「設備保全」の領域で深刻な問題となりがちであり、その解消に特化した3つの秘訣を以下の資料で解説します。
>>設備保全の属人化、どう防ぐ? 属人化を解消する3つの秘訣を見てみる
まとめ
作業標準書は、標準的な作業内容をまとめたものであり、作業目的や手順、安全上の注意点などが盛り込まれるものです。企業として作業を標準化することで、作業品質や生産性の向上、事故やトラブルの防止につながります。
作業標準書を動画で作ると、作成工数を抑えながら属人化しやすい複雑な作業を可視化できるメリットがあります。
ここでは動画作成のためのツールtebikiをご紹介しました。tebikiでは、工数を抑えながらわかりやすい動画を作り、作成後も教育効果を上げる工夫が数多く用意されています。tebikiについての詳しい情報は、以下からぜひご覧ください。「簡単さ」を実感できる無料トライアルも受け付けております。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。




