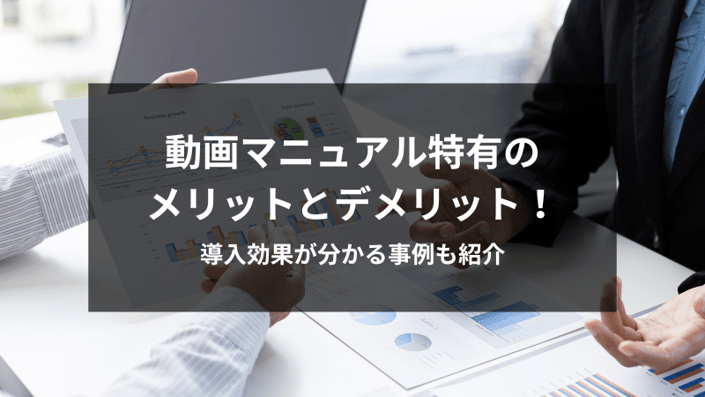

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開するtebikiサポートチームです。
動画マニュアルは多くの企業や現場で導入されつつあります。というのも、従来の紙マニュアルやOJTによる教育は、教育担当者の負担が大きく、本来リソースを使うべき業務に使えない事態が往々にしてあるからです。
動画マニュアルの導入メリットは多い反面、業界や職種によっては向き不向きが存在します。本記事を読むことで「動画マニュアルを導入するべきかどうか」の判断がつくよう情報をまとめているので、紙の手順書やパワーポイント等のマニュアルから脱却したい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
- 1. 動画マニュアルの導入が増えている背景や理由
2. 動画マニュアルの種類や特徴(サンプル動画あり)
2-1. 技術継承マニュアル
2-2. 安全教育マニュアル
2-3. 営業・接客マニュアル
2-4. 社内研修・新人教育マニュアル
2-5. 作手順・業務手順マニュアル
2-6. 製品チュートリアル
3. 紙にはない、動画マニュアル「特有」のメリット6つ
3-1. 「複雑な業務手順」が説明できる
3-2. 「誰が教えても同じ説明内容」になる
3-3. 教育工数/作成工数が削減される
3-4. 外国人スタッフの育成/雇用ができる
3-5. 同時更新/即時共有できる
3-6. マニュアルの管理コストが削減される
4. 動画マニュアルを活用する5つのデメリット
4-1. 動画編集ソフトを使いこなすのが難しい
4-2. 作成者によってマニュアルの質が左右される
4-3. 動画を作成/再生する端末やネット環境が必要
4-4. 閲覧状況や内容の習熟度合いを可視化できない
4-5. マニュアル管理に負担がかかる
5. 動画マニュアルが特に効果を発揮するケース
5-1. 複雑な動きを伴う業界・職種に属する場合
5-2. ベテラン社員の技術伝承を促進したい場合
5-3.グローバル化を見据えた人材育成・採用の予定がある場合
6. 動画マニュアル導入は「内製」と「外注」どちらがおすすめ?
7. 動画マニュアルの作り方
8. 動画マニュアル導入の判断ポイント
8-1. 必要な準備とリソース
8-2. 導入時によくある失敗とその防ぎ方
8-3. 紙マニュアルが適しているケース - 9. まとめ:動画マニュアルは「小さく」始めよう
動画マニュアルの導入が増えている背景や理由
ビジネスシーンで動画マニュアルの需要が高まる背景として、以下のような理由が挙げられます。
- スマートフォンやタブレットなどのデジタル端末が普及している
- テキスト媒体より動画媒体コンテンツが圧倒的に増えてきている
- 特に若い世代(人材)が動画による情報取得に慣れている
現在、業界を問わずさまざまな現場でデジタル端末が活用されており、動画を閲覧できる環境が整っています。
特に若い世代は幼少期からYouTubeやTikTokなどの動画を通じて情報を得ることに慣れているので、「動画で学ぶ」環境を受け入れやすいとも言えます。
この傾向は具体的な数字からも実証されています。現場改善のウェブメディア「現場改善ラボ」が調査したアンケート「動画マニュアル内製化の実態調査」では、製造業や建設業などのデスクレス領域に従事する100名のうち43%が「動画マニュアルの作成経験がある」と回答されました。
まだまだ現場DXの浸透の余地があるデスクレス業界において約半分が動画マニュアル作成経験がある、というのは、動画マニュアルの需要や重要性が高まってきていると言えます。
動画マニュアルの種類や特徴(サンプル動画あり)
では、動画マニュアルとは具体的にどのような種類があるのでしょうか?動画マニュアルの活用シーンや特徴も紹介しながら、代表的な動画マニュアルの種類について解説します。自社での活用イメージを掴んでみてください。
技術継承マニュアル
主に製造業や専門職において、熟練者が持つ高度な技術や長年の経験で培われた「カンコツ」といった、言葉や図だけでは伝えきれない「暗黙知」を、映像を通して次世代へ継承(形式知)するためのマニュアルです。
言語化しにくいカンコツは「動画教育」の相性が良く、特に製造業や物流業では動画マニュアルによる技術継承が一般的になりつつあります。
例えば「児玉化学工業株式会社」では、現場従業員が複雑な業務手順を動画マニュアル化し、若手人材への教育を推進しています。以下の動画は同社で実際に活用されている、「ヤスリでバリを取る」作業手順を解説した動画マニュアルです。
▼事故を動画化したマニュアル例(音量にご注意ください)▼
他のサンプル動画マニュアルも見てみたい方は、PDF資料「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」に多数の動画サンプルを掲載しているので、あわせてご覧ください。資料ダウンロード後、すぐその場で視聴可能です。
>>>PDF資料「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」を見てみる
安全教育マニュアル
労働災害や事故を未然に防ぐことを目的とし、危険が伴う作業の正しい手順や安全ルール、緊急時の対応方法などを教育するためのマニュアルです。
例えば、高所作業での安全帯の正しい装着方法、重機の安全確認手順、化学薬品の適切な取り扱い、火災・地震発生時の避難行動、過去のヒヤリハット事例とその対策を動画化したマニュアルが挙げられます。
とある総合物流会社では、実際に起きた事故を動画におさめ、再発防止の教育として動画マニュアルを活用しています。以下は実際の動画です。
▼事故を動画化したマニュアル例(音量にご注意ください)▼
文字ではなく動画で事故やヒヤリハットを共有することで、危険性を明確に周知できるのも、動画マニュアルの特徴です。
※上のような動画マニュアルの作り方は「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」でざっと知ることができます。
営業・接客マニュアル
営業担当者のスキルアップや、店舗・窓口での顧客対応品質の標準化を目的としたマニュアルです。先輩社員の実際のロールプレイを動画におさめ、動画マニュアルとして共有するような活用ケースが想定されます。
営業や接客はOJTによる教育が特に必要ですが、言い換えれば教育担当者の稼働時間を圧迫するというデメリットがあります。そのOJTを動画に置き換えることで、先輩社員の工数を確保できるのも動画マニュアルの特徴だと言えるでしょう。
例えば人材紹介事業を展開する「株式会社GEEKLY」は、新人育成のためのOJT教育が営業チームの工数を圧迫していたことが課題で、動画マニュアルを導入しています。結果的に教育担当者の工数を年間3,700時間の削減に成功しました。同社の詳しい動画マニュアル導入事例は、以下のリンクからご覧いただけます。
>>>「株式会社GEEKLY」営業職の動画マニュアル導入事例を読んでみる
社内研修・新人教育マニュアル
新入社員や既存社員に対し、業務に必要な知識、社内ルール、ビジネスマナー、企業文化といった、研修に必要な教育項目を動画マニュアルで伝達するケースもよくあります。
例えば、パワーポイントのプレゼン資料を画面録画しながら、ナレーションを入れて研修動画として内製するような作り方があるでしょう。
企業内の売店や食堂等の運営を手掛ける「心幸ホールディングス株式会社」の動画マニュアルを例に挙げると、飲食店経営や衛生管理に関する教育を動画マニュアルで進めています。
▼動画による研修マニュアルの例(音量にご注意ください)▼
こうした、パワーポイントのような資料を画面録画して動画マニュアルにする方法は手軽に推進できるため、小さく始めたいという場合はおすすめです。パワーポイントを活用した動画マニュアル作成手順は、PDF資料「パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順~現場ですぐ使えるコツ付き~」で解説されているので、あわせてご覧ください。
操作手順・業務手順マニュアル
特定の機械設備やツール、ソフトウェアの操作方法、あるいは日々行う定型的な業務の進め方を、誰が見ても同じように理解し、実行できるようにするためのマニュアルにも、動画マニュアルは活用されます。
例えば工作機械のセットアップ、検査機器の操作、社内システムのデータ入力、POSレジの精算作業、経費精算申請のフロー、報告書の作成手順、店舗の開店・閉店作業など。あらゆる動きが伴う操作や業務は、言葉で伝えるよりも動画で学んだほうが効率がいい場合が多いです。
▼関連記事▼
【見本画像あり】操作マニュアルとは?分かりやすく作る方法や手順、ポイントを解説!
製品チュートリアル
顧客または社内の営業・サポート担当者に向けて、自社製品やサービスの機能、使い方、設定方法、メンテナンス方法などを分かりやすく説明するためのマニュアルです。
例えばスマートフォンアプリの初期設定ガイド、ソフトウェアの新機能紹介、家電製品の操作方法のようなものが挙げられます。
紙にはない、動画マニュアル「特有」のメリット6つ
紙マニュアルにはない、「動画マニュアルだからこそ」のメリットを6つご紹介します。実際の企業事例や実例動画も適宜紹介しながら解説するので、動画マニュアルの導入効果がよりイメージできるでしょう。
- 「複雑な業務手順」が説明できる
- 「誰が教えても同じ説明内容」になる
- 教育工数/作成工数が削減される
- 外国人スタッフの育成/雇用ができる
- 全拠点で同時更新/即時共有できる
- マニュアルの管理コストが削減される
それぞれ1つずつ解説します。
「複雑な業務手順」が説明できる
動画マニュアルなら、文字や写真では表現しづらい内容を新入社員や中途社員に教育できます。
文字や写真、イラストなどの静止画像は二次元の表現であり、奥行きがあって立体的な様子などについては、言葉を尽くし多角度から何枚も写真を掲載しないと伝えにくいものです。
動画なら、手前から奥の方まで、あるいは対象物をぐるりと一周した様子をたった数秒の動画で表現でき、さらに音声情報も付加することが可能です。コマ送りではなく1つの動画の中で変化の様子を伝えることもでき、三次元の情報をそのまま届けられます。
複雑な業務手順を動画マニュアル化した例として、食肉販売専門店の「株式会社ジャンプ」が実際に作成した以下の動画マニュアルが挙げられます。
▼複雑な業務手順を動画化したマニュアル(音量にご注意ください)▼
※「tebiki」で作成
上のような動画マニュアルを作成する方法は、意外と難しくありません。スマホ1つで撮影が可能なので、動画マニュアルの導入推進を考えている方はPDF資料「はじめての動画マニュアル作成ガイド」を参考にしながら、動画マニュアル導入を検討してみてください。
>>>「はじめての動画マニュアル作成ガイド」を読んでみる
「誰が教えても同じ説明内容」になる
多くの職場では、業務ノウハウが「暗黙知」として属人化している状態が見られます。その結果、新人教育は「ベテラン社員によるOJT」が中心となり、以下のような課題が生じています。
- ベテラン社員が付きっ切りで指導しなければ、業務を理解できない
- 指導するベテラン社員によって教え方や重要視するポイントが異なる
- 結果的に新入社員間でスキルの偏りが発生する
紙マニュアルでは、こうした暗黙知を「形式知」に変換しきれません。文章による説明は読み手の解釈に依存するため、属人化を解消する決定打とはなりにくいのです。
一方、動画マニュアルは「動作」という客観的な情報を伝えるため、暗黙知の可視化と標準化を実現できます。ベテラン社員の経験とノウハウを、誰もが同じように理解し、再現できる形で残せることが大きな特徴です。
教育のバラつきを抑えて標準化を実現した事例として、「大同工業株式会社」の取り組みが挙げられます。同社は新人教育で動画マニュアル作成ツールを活用したことで、教育内容のバラつきを抑えつつも教育工数の8割削減しました。
動画で正しい内容を等しく伝えたことで、結果的に部内全体で標準化を行うことができ、部内で発生していた試験中のヒヤリハットや評価エラーも削減しています。大同工業株式会社の動画マニュアル活用事例や効果は、以下のインタビュー記事で詳しくご紹介しています。
▼関連記事▼
製造業の技術部門の業務を動画で標準化。教育工数を8割削減し、業務の効率化・最適化も実現。
教育工数/作成工数が削減される
これまで紹介した動画マニュアル特有のメリット「複雑な作業の説明ができる」「誰が教えても同じ内容を伝えられる」によって、以下のような恩恵が得られます。
- 新人が「見て理解→すぐ実践」できるため、指導者の付きっ切り時間が激減
- 複雑な動きや曖昧な手順が可視化されため、ベテラン社員の技術継承が促進
- スマートフォン1台で撮影から編集まで完結するため、マニュアル作成の負担が軽減
特に注目したいのは、これまで「口頭でしか伝えられなかった」暗黙知の部分も、動画なら簡単に記録できる点です。紙マニュアルでは「力加減」「スピード感」「細かな手順」を表現しきれず、結局はベテラン社員による実演が必要でしたが、動画マニュアルならベテラン社員不在でも熟練者の技術を見て学べます。
サッポログループ物流株式会社では、紙マニュアルを動画マニュアルに置き換えたことで「マニュアルの作成時間が2~3時間から30分までに削減」されました。マニュアル作成工数、OJTの削減による教育のコスト削減を金額で換算すると、月あたり30万円近くのコスト削減につながっています。
より具体的なサッポログループ物流株式会社の動画マニュアル導入効果は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
▼関連記事▼
物流現場のノウハウを動画で可視化!ロジスティクスの生産性を上げるため人財教育の課題に挑む
外国人スタッフの育成/雇用ができる
人手不足を背景に、多くの業界で外国人スタッフの採用が進んでいます。しかし言語の壁により、外国人スタッフに対する業務指導は多大な時間と労力がかかるのが現状です。
その点動画マニュアルなら、作業の様子を映像で見せることで、言語に頼らない直感的な理解が可能です。さらに、必要に応じて母国語の字幕を付けることで、より確実な理解を促すことができます。
例えば新日本工機株式会社では、海外子会社の外国人スタッフに対して「動画マニュアルを共有するだけで」ほとんどの情報伝達が可能になっています。動画マニュアル作成ツールは「tebiki」を利用しているので、日本語字幕をボタン1つで各国の言語に翻訳し、従来発生していたマニュアル/手順書の翻訳工数がゼロになっているとのことです。
同社が実際に作成した動画マニュアルを以下に掲載しますので、マニュアル作りの参考にしてみてください。
▼「シールテープの巻き方」動画マニュアル(音量にご注意ください)▼
※上のような動画マニュアルの作り方は「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」でざっと知ることができます。
同社のより具体的な動画マニュアル導入効果については、以下のインタビュー記事をご覧ください。
▼関連記事▼
人が育つ環境づくりとして動画マニュアルtebikiを活用。技術の蓄積と作業品質の安定を実現。
全拠点で同時更新/即時共有できる
デジタル共有ができない紙マニュアルは「同時更新・即時共有」が難しいので、以下のような不都合が生じます。
- マニュアル改訂の度に、印刷・配布・差し替え作業が発生
- 古いマニュアルの回収漏れにより、旧版と新版が現場に混在
- 結果として、拠点によって異なる手順で業務が行われ、品質にバラツキが生じる
複数の店舗や事業所、海外拠点を抱える企業ほど、これらのデメリットは無視できません。
一方で動画マニュアルは「クラウド上での一元管理」が可能です。クラウド管理環境を整備するには一般的にコストがかかりますが、本社で更新すれば全拠点が即座に最新版にアクセス可能になるので、差し替えコストや回収コストがゼロになります。
さらに重要なのは、「緊急の手順変更」にも即座に対応できる点です。製品不具合や品質トラブルなど、早急な対応が必要な場合でも、更新した動画データを全拠点へ即時展開できます。紙マニュアルでは難しかった「スピーディな是正対応」が可能になるのです。
マニュアルの管理コストが削減される
前述したように、動画マニュアルは「全拠点のマニュアルを一斉更新」「最新のマニュアルを全拠点に一斉共有」が可能です。つまり以下のような効果が期待できます。
- 印刷・配布のための工数とコスト削減
- 古いマニュアルの回収や廃棄作業が不要
- 各拠点でのバージョン管理の手間が減少
- 紙マニュアルの保管スペースが不要
もちろん、これらのメリットを享受するためには「クラウド一元管理のための環境整備」が必要です。しかし、動画マニュアル作成ツールによっては開発不要でクラウド管理が可能なものもあります。したがって、もし動画マニュアルサービスを導入する場合は、「クラウド管理が比較的容易なもの」を選びましょう。
例えば動画マニュアル作成ツール「tebiki」は、スマートフォン1つで動画マニュアルが作成できるだけでなく、そのままクラウド管理も可能なので、最新のマニュアルを全拠点でいつでも閲覧できます。マニュアルの一括更新・一括展開が可能なtebikiが持つすべての機能を知りたい方は、以下の「3分で分かるtebikiサービス資料」もあわせてご覧ください。紙マニュアルからの脱却に必要な機能が備わっています。
動画マニュアルを活用する5つのデメリット
動画マニュアルの活用にはメリットがありますが、デメリットもあります。特にデメリットが生じるシチュエーションが「無料の動画編集ソフトをお試しで使うとき」です。動画マニュアルの導入を検討する場合、まずは無料の動画編集ソフトをお試しで使ってみるケースが多いですが、基本的に以下のようなデメリットが生じることをあらかじめ把握しておきましょう。
とはいえ、いきなり有料の動画マニュアル編集ツールを導入するのは憚られる場合もあります。そこで、「比較的使いやすい無料動画編集ソフトを一覧化した比較表」を参考にしながら、無料ツールの導入を進めてみても良いでしょう。以下の画像をクリックすると比較表をダウンロードできます。
動画編集ソフトを使いこなすのが難しい
動画編集ソフトを使いこなすのが難しいというデメリットがあります。現場改善のヒントを発信するウェブメディア「現場改善ラボ」にて行ったアンケート調査「動画マニュアル内製化の実態調査(回答数100件)」では、以下のような結果になりました。
- 回答者のうち、50%の方が動画マニュアル作成が「うまくいっていない」と回答
- うまくいっていない方の80%が「一般的な動画編集ソフト」を使用している
動画マニュアルを作成するには、撮影と動画編集が必要となります。撮影はスマートフォン操作などで慣れていても、動画編集はソフトを使うため、スキルの習得が求められます。一方で現場改善ラボの調査結果からも分かる通り、編集ソフトの操作は誰もができるわけではなく、使いこなすことが難しいです。
例えば、冷凍食品の製造企業である「テーブルマーク株式会社」は、動画マニュアルを内製で作成・運用していました。しかしスムーズな作成方法が分からず、パソコンの編集ソフトの扱いが難しいことから時間も大幅にかかり、一時は頓挫してしまったのです。
私が工場で勤務していた頃、「わかりやすくて、とっつきやすい手順書」があればいいなという風に考えて、動画マニュアルを作成しようと試みました。実際に現場にデジカメを持って入って、撮影と動画編集をしてみようと。
……なんですけども、現場でいざ撮影するとなった際、「どのように区切って撮影していいかがわからない」というような問題に直面しました。あと編集の方でも、パソコンに入っている編集ソフトを使うと、時間も工数もとてもかかったので、動画マニュアルの作成は断念することに。
つまり動画マニュアル導入において重要なのは、「誰でも動画編集ソフトが扱える製品」を導入する点だと言えます。もっと言うと、「現場スタッフや現場作業員でも、撮影から編集まで手軽にできる動画マニュアル作成ツール」が理想です。
例えば動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、パソコンに慣れていない人でもかんたんに撮影~編集ができるよう設計されているので、マニュアルの整備工数を圧迫することはありません。tebikiの詳細資料は以下の画像からダウンロードできますが、必要最低限の機能のみで設計されていることが分かると思います。
作成者によってマニュアルの質が左右される
動画の撮影や編集を担当する人によって、マニュアルの品質が左右されるデメリットがあります。動画マニュアルは撮影するだけといっても撮影に入り、その手順に問題があった場合は業務標準化につながらないマニュアルが出来上がってしまいます。
撮影前にマニュアルの構成を検討しておくだけでなく、そもそもその手順に改善点はないか?作成する機会に見直しを行うことがオススメです。また編集時に使用する図形やスタンプ、機能など、予めルールを定めておくことで編集方法のバラつきを抑えることが可能です。
つまり動画マニュアル作成ツール選び方のポイントの1つとして、「無駄な機能は一切ない」「必要最低限の編集機能だけ備わっている」編集ソフトが望ましいです。その一例として挙げられる「tebiki現場教育」は、現場の従業員でもかんたんに撮影から編集できることに加え、企業単位に専任のカスタマーサポートが担当することになっており、動画マニュアルの導入から運用までスムーズに進行できるのが特徴です。
動画を作成/再生する端末やネット環境が必要
動画マニュアルを作成するには、作成するためのデバイスが必要です。それだけでなく、作成した動画を視聴するための端末も用意しなければなりません。
もし動画がクラウド上で管理されているのであれば、ネット回線と繋がっている端末でなければならないでしょう。
動画マニュアルの作成に取り掛かる前に、「マニュアル作成する端末のスペックは足りているか」「マニュアル閲覧環境は問題ないか」の確認も重要だと言えます。
上記のようなデメリットを解消するツール選びのポイントとして、「各端末に動画をあらかじめダウンロードし、ネット回線なしでも閲覧できる動画マニュアルツール」が1つ挙げられます。動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」なら、ネット回線がなくとも動画閲覧が可能な環境を構築できるので、導入のハードルを下げたい方にはおすすめです。
tebiki現場教育のサービス資料は以下のリンクからダウンロードできるので、あわせてご覧ください。
>>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見てみる
閲覧状況や内容の習熟度合いを可視化できない
一般的な編集ソフトで動画マニュアルを作成した場合、作成後『実際に使われているか?理解されているか?』という点を可視化することが出来ません。動画マニュアルの目的はただ作ることではなく、教育の改善にあるはずです。改善度合いを可視化できない限り、施策による改善効果を図ることもできず何となく運用が続いているという可能性もあります。
動画マニュアルを選ぶ際は、閲覧状況や習熟度合いを可視化できるツールを選ぶことで、より具体的な費用対効果を算出することができ、改善度合いを定量的に測ることが可能です。
例えば「従業員のスキルマップとマニュアルが紐づいたようなツール」だと、「誰がどんなスキルを習得できていなくて、そのためにどのマニュアルを理解してもらう必要があるのか」が可視化されます。以下はその画面の例です。
※スキルマップ機能がついている動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の実際の画面
動画マニュアルは作って終わりではなく、むしろ作った後が重要です。作成した動画マニュアルをいつ/誰が見ているかを把握し、スキルの習熟度を可視化することで、本質的な教育体制が整備できるようになるでしょう。動画マニュアル作成前後で成果やスキル状況の見える化が図れる「tebiki現場教育」のサービス資料は、以下のリンクからダウンロード可能です。よろしければご覧ください。
>>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見てみる
マニュアル管理に負担がかかる
文書マニュアルと比較し、動画マニュアルは1本あたりのデータ量が多くなります。そのため、動画でマニュアルを作成すると動画本数が増えるにつれて、社内サーバーを圧迫するなど管理の手間や保存場所の確保に負担がかかるデメリットがあります。
動画マニュアルを導入する場合は、管理の手間や保存場所の確保も省力化できるサービスを検討するとよいでしょう。
動画マニュアルが特に効果を発揮するケース
どんな場面でも動画マニュアルが優れている、とは言えません。場合によっては、紙マニュアルの方が適切な可能性もあります。動画マニュアルには向き不向きがあるので、ここからは動画マニュアルが特に効果を発揮しやすい場面について紹介します。動画マニュアル導入検討の判断材料として参考にしてみてください。
複雑な動きを伴う業界・職種に属する場合
業務内容が複雑な動きを伴う場合は、動画マニュアルの導入をオススメします。例えば以下のような業界は、見て学ぶ機会を設けた方が良いでしょう。
- 製造業・建設業・物流業
- 小売業・サービス業
- 医療・介護業界
いずれもデスクワークで完結しない職種が多く、一人前になるには、経験者の技術を見ながら学習しなければなりません。
ベテラン社員の技術伝承を促進したい場合
ベテラン社員に技術が偏りすぎている現場や職場では、動画マニュアルによる技術伝承がオススメされています。ベテラン社員による直接指導でも教育は可能ですが、ベテラン社員が指導中は他新入社員への教育が停滞するため、円滑な受入教育がなされません。
また、ベテラン社員それぞれの指導方法も異なれば、業務品質の均一化にも影響をおよぼします。一定の指導で一定の業務品質を保つには、ベテラン社員の業務の可視化が有効だと言えるでしょう。
動画マニュアルによる技術伝承の具体的な推進方法は、PDF資料「技術伝承を成功させるポイント」で分かりやすく解説されています。以下の画像をクリックしてダウンロードしてみてください。
グローバル化を見据えた人材育成・採用の予定がある場合
非言語マニュアルでもある動画は、外国人スタッフの育成や採用を可能にします。特に人材不足が叫ばれている業界では、外国人スタッフの受け入れも珍しくなくなってきており、効率的な教育が重要視されています。
現状は外国人スタッフがいなくとも、動画マニュアルによる教育環境が整備されていれば、外国人スタッフの採用余地が生まれることにもつながります。
例えば、タイのNavanakorn工業団地に拠点を置く「HOEI THAILAND CO.,LTD.」では動画マニュアルの活用が非常に進んでおり、半年で152本もの動画マニュアルが作成されています。こうした海外拠点の現場教育をスムーズに進める手段としても、動画マニュアルは大きく優れているのです。
外国人労働者の教育を動画マニュアルで進める具体的な方法については、PDF資料「外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる」を参考にしてください。以下のリンクからダウンロードが可能です。
>>>動画マニュアルによる外国人教育の進め方について知る
動画マニュアル導入は「内製」と「外注」どちらがおすすめ?
動画マニュアル導入のオススメは「内製」です。
外注の場合、本数が増えるにつれて制作コストが増えるのは勿論のこと、動画を作成した業務で手順変更が発生した場合、修正依頼のコストも追加で発生します。
一方で内製の場合は、ツール使用料以外のコストは発生しません。また、動画マニュアル作成における最重要ポイントは「業務のツボを押さえている現場の作業者が撮影/作成すること」であり、外注の場合はどうしても的を得たマニュアルが作成できず、結局使われなくなることが多いです。
外注より内製をオススメする理由について、より詳細な解説を知りたい方は以下の記事記事もご覧ください。
▼関連記事▼
動画マニュアルの制作は内製と外注/代行どちらがオススメ?
動画マニュアルの作り方
内製で動画マニュアル導入を推進したほうがいいとは言っても、具体的にどのように推進すべきか悩みますよね。
基本的には以下の流れで進められると、もれなく・ダブりなく導入が進められます。行き当たりばったりで作成し始めると結局手戻り等が発生するので、導入フェーズこそ慎重に進めましょう。
- 作成する目的/ゴールなど目標設定を明確にする
- 活用シーンを5W1Hで整理する
- 動画マニュアル化する優先度をつける
- 動画マニュアルを作成する責任者を決める
- 動画マニュアルの構成案/台本を作成する
- 必要な機材を準備する
- 動画を撮影する
- 動画を編集する
- 作成した動画を一元管理する
「【完全ガイド】動画マニュアルの作成手順と18のコツ!事例やソフト比較、選び方も」では、それぞれについて詳細に解説されているので、参考にしてみてください。
動画マニュアルの作成は一見、大変のように感じますが、まずは「小さく始める」と抵抗なく進められます。動画マニュアル化する業務範囲を小さく区切り、推進してみてはいかがでしょうか?試しに動画マニュアルを作成してみようと少しでも検討している場合は、以下の資料「はじめての動画マニュアル作成ガイド」を見ながら作成を進めてみてください。
動画マニュアル導入の判断ポイント
動画マニュアルの導入を検討する場合、事前に把握しておくべき項目がいくつかあります。予期せぬアクシデントに見舞われぬよう、以下のポイントは導入前に踏まえておきましょう。
必要な準備とリソース
動画マニュアルの導入には、いくつかの事前準備やリソースが必要です。
- 動画マニュアル作成ツールの導入費用
- 撮影者や実演者、編集者といった人的リソース
- カメラや三脚、マイクといった撮影機材
動画マニュアルプロジェクトを推進するのであれば、これらが確保できるかどうかを事前に把握しておかなければなりません。「ツールは導入できたものの、動画作成の担当者がいない」といった事態にならないよう、プロジェクトの推進体制は十分に考慮しておきましょう。
導入時によくある失敗
動画マニュアル導入時には、いくつかの典型的な失敗パターンがあります。以下のような轍を踏まないよう、今のうちから対策を練っておきましょう。
- 現場からの協力が得られない
- ツールが難しくて扱えない
- 動画を視聴できる環境がない
したがって、事前に現場への根回しや動画視聴の環境設計を考慮しておきましょう。
特に「ツールが難しくて扱えない」パターンは多く、現場の人でも簡単に撮影や編集ができるツールはほぼ必須と言えます。例えば、誰でも簡単に動画マニュアルが作成できる「tebiki」なら、現場スタッフがスマホで作業工程を撮影し、スマホで編集してすぐに動画マニュアルを公開できます。
紙マニュアルが適しているケース
現場によっては、動画マニュアルの作成が困難な場合もあります。以下に当てはまる場合は、紙マニュアルによる運用が望ましいかもしれません。
- デジタル端末の持ち込みが不可能な現場
- 設備の都合上、Wi-Fi環境が整備できない現場
- デバイスの故障リスクがある現場(高温・多湿環境など)
動画マニュアルツールを導入したとして、実際の撮影や編集が現環境で本当に可能なのかどうかを、今一度確認してみてください。
まとめ:動画マニュアルは「小さく」始めよう
本記事では、動画マニュアルの導入メリットと、効果的な活用方法について解説してきました。
動画マニュアルの最大の特徴は、「複雑な動作の可視化」と「教育品質の標準化」を同時に実現できる点です。特に以下のような課題を抱える製造現場で、大きな効果を発揮します。
- 文字や写真では伝えきれない、3次元的な動きの説明が必要
- 教育内容にバラつきが出て、品質にムラが生じている
- 多言語対応が必要な外国人スタッフの育成に苦心している
- 複数拠点での同時展開や、マニュアルの一括更新が必要
一方で、「編集の手間」や「ファイル管理の煩雑さ」といった運用面での課題も存在します。こちらは適切な動画マニュアル作成ツールの選択によって解消できますが、そのひとつの解決手段として動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」をご紹介いたしました。
いきなりすべての業務や研修を動画マニュアルで作成しようとすると、推進の難易度が非常に高くなります。まずは小さく始め、徐々に動画マニュアルのメリットを実感しながら、少しずつ現場改善を図っていく流れが望ましいです。その手段として、現場従業員でもかんたんに撮影から編集ができる動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」をおすすめしています。
「tebiki現場教育」の具体的な機能や、現場での導入事例については「3分で分かるtebikiサービス資料」にまとめました。動画マニュアルの作成から運用まで、どのように課題を解決できるのか、以下の画像をクリックしてご確認いただけます。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。









