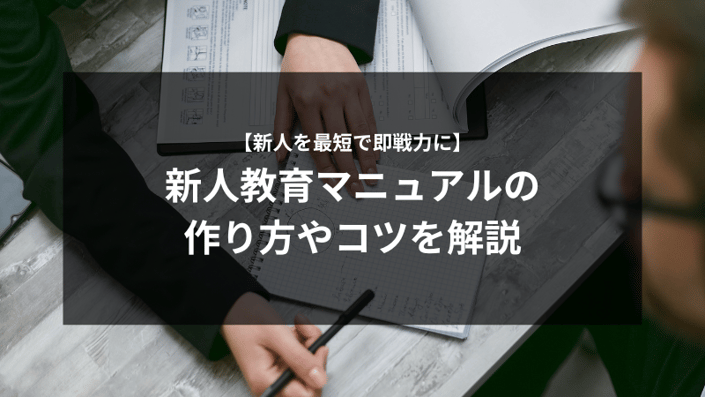
文章だけではなく図や写真を活用する
マニュアルを文章だけで作成してしまうと、見づらいのはもちろん、読む気力がなくなってしまい、伝えたいことが伝わらないリスクがあります。
文章では説明しにくい手順を紹介する箇所などは図や写真を活用し、視覚的にわかりやすくなる工夫を施しましょう。
なお、複雑な作業や業務については、写真や図で表現しようとすると膨大な枚数になることもあるので、動画の活用もおすすめです。動画を活用することで、動画を撮影して音声と字幕を入れるだけで文章よりもカンタンにマニュアルを作成できます。
はじめて動画マニュアルを作成する方に向けて、動画マニュアル導入のステップやメリットをわかりやすくまとめた「はじめての動画マニュアル作成ガイド」をご用意しています。ぜひ資料をご確認ください。
製造業など危険が伴う作業がある場合は伝えたいことを強調する
業界によっては危険が伴う作業が発生します。例えば、大型の機械を利用する製造業や食品業などが該当します。このような業界では、些細なミスや認識の相違が大事故に発展する可能性もあるので、事故や怪我のリスクがある作業については、伝えたいことを太字にしたり、赤字にしたりするなど、強調するようにしましょう。
特に、新人の場合には作業に慣れておらず、要領も掴めていないので事故が発生する可能性も考えられます。口頭の説明だけでは十分に伝わらないので、マニュアルでの注意喚起が必須と言えるでしょう。
定期的に新人社員の理解度を調べる
新人マニュアルは伝えたい情報の量が膨大になってしまう傾向があり、一度で全てを頭にいれることは難しい傾向があります。また、新人にマニュアルのインプットを任せっきりにしてしまうと、人によって理解度に大きな差が生まれてしまいます。
理解度を深めて定着させるためにも、定期的な理解度調査を実施しましょう。理解度調査は、口頭での確認やテストの実施など様々な方法があります。作成したマニュアルを定着させたいと考えられている方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
なお、様々な業界での導入実績がある動画マニュアル作成ツール「tebiki」では、作成した動画マニュアルをいつ / 誰が / どこで見たかを可視化でき、閲覧したマニュアルの理解度をテストでカンタンに確かめることができます。
「tebiki」のサービス内容や機能などについてもっと知りたい方は、以下よりサービス資料をご覧ください。
ビジネス作法やツールの使い方など「動き」は動画で伝える
新人教育において、文字や写真、図では伝えきれないことがあるため、動画を利用して説明するとよいでしょう。
例えば、お辞儀の角度や名刺の渡し方、PCの画面操作などの動きは文字では伝えにくい傾向があります。流動的な動きを写真や図で説明すると一部を切り抜いたものになり、その前後にある一連の流れが理解できません。動画であれば、流れを視覚的に分かりやすく伝えることが可能です。
新人教育の場面において、動画マニュアルを活用するケースは増えている傾向にあります。動画を活用するメリットについては、後ほど本記事内で詳しくご紹介します。気になる方は、以下よりクリックしてご覧ください。
>>新人教育で「動画マニュアルを活用するメリット」を知りたい方はこちら
新人教育マニュアルは「動画」での作成がオススメ
特に新人として入ってくるような2~30代の若手世代は、学生時代から携帯やスマートフォン、PCを介してYouTubeなどで動画に慣れ親しんできています。実際、YouTubeのようなプラットフォームは情報収集の手段として活用されており、これから受け入れる新人にとって「動画で学ぶ」というのは分かりやすい方法といえるでしょう。
実際、弊社が提供している動画マニュアル作成ツールの「Tebiki」がさまざまな業界/業種の教育課題を支援する中で、お客様の現場の声で『若手から文字や紙のマニュアルだと分かりにくい』と言われたことがあると教えていただきました。実際の声を踏まえても、分かりやすい新人教育マニュアルを作る手段として動画は有効ではないでしょうか。
動画マニュアルの活用による具体的な教育効果は、別紙のガイドブックで詳しくご紹介しているので、以下のリンクをクリックしてご覧ください。
>>「動画マニュアル」で新人教育の課題を解決する方法や効果を見てみる
動画マニュアルを活用するメリット
動画マニュアルは、現場作業の様子が文章よりも鮮明に伝えられます。文章や図面ではなかなか伝えられない微妙なカン・コツや新入社員にとって初見の業務でも、視覚的な理解が可能です。また、現場の臨場感を味わうことができるため、日本語が通じない外国籍の社員でも学習効果が得られます。複雑な作業や速度を伝えたい業務の場合も、文章より簡単に概要が分かります。

『動画のマニュアルは手間が掛かるのでは?』『動画の編集などが難しいのでは?』と感じるかもしれませんが、動画マニュアル作成に特化したツールを活用することで、動画編集未経験の方でもかんたんに作成が可能です。
実際、動画マニュアル作成ツール「tebiki」を活用している現場では、紙や文書ベースのマニュアルを作成していた時期と比べて、作成工数が1/3まで削減されている事例もあります。
そのため、新人教育マニュアルを動画化することで、新人の理解力向上や教育担当者の工数削減といったメリットが期待できます。 その他の代表的なメリットとして、以下のようなものも挙げられます。
- 繰り返し視聴できるため、自学自習に役立つ
- 教育担当のレクチャーが不要になるため、人員や時間のコストが削減できる
- 紙を紛失する心配がなくセキュリティが強化できる
- 理解度に個人差が生じにくい(読む・聴く・書くより理解がスムーズ)
動画の活用を検討するうえで『メリットとデメリットを比較したい』という方は、以下の記事も併せてご活用ください。
▼関連記事▼
【紙と比較】動画マニュアル特有のメリットとデメリット
動画マニュアルは「tebiki」での作成がオススメ
前述の「動画マニュアルを活用するメリット」でご紹介したように、動画で作成する場合は動画マニュアル作成に特化したツールの活用がオススメです。このようなツールで、製造業や物流業、サービス業など幅広い業界や業種で活用されているのが、私たちが展開する動画マニュアル作成ツール「tebiki」です。
専門知識がなくても簡単に作成できる
tebikiは実際の作業風景を撮影し、図形や一時停止機能など厳選されている編集機能を活用し、誰でもかんたんに動画編集が可能なクラウドサービスです。
一般的な動画編集ソフトはクリエイター向けゆえに「機能が豊富すぎて使える人が限られる」「高スペックのPCがないとスムーズに作業ができない」といった課題に直面するため、tebikiは教育に必要な機能を厳選したことでシンプルで分かりやすい操作性を実現しています。
また、動画の字幕は撮影時の音声が自動で文字起こしされるため、ゼロから編集して追加する必要もありません。
字幕を100を超える言語に翻訳できる
自動生成された日本語の字幕は、100を超える国や地域の言語に自動翻訳が可能です。実際にご活用いただいている方の声として『翻訳精度も問題なく伝わっている』『従来のマニュアルで行っていた翻訳工数がゼロになった』など、特に外国人従業員を多く抱える現場の方にオススメです。

また、外国人スタッフにとっても、業務の内容を母国語で学べるというのは心理的な不安が軽減されます。言葉や文化の違いから外国人スタッフの教育課題は起こりやすいので、動画マニュアルの活用がオススメです。具体的な効果や活動事例については、以下の資料で詳しくご紹介しています。
>>「外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!」の資料を見てみる
習熟度を可視化できる
新人教育マニュアルの目的は「新人の業務理解」にあります。そのため本来は、新人の習熟度をチェックする段階が必要ですが、なかなかそこまで整備することは現実的ではありません。
しかしtebikiなら、管理者は組織レポートでいつ/誰が/何のマニュアルを見ているかアクセス状況の確認が可能です。また、テスト機能も活用して内容が定着しているかチェックできるため、習熟度の進捗状況が一目で確認できます。
組織レポートの機能によって「マニュアルを作ったはいいものの活用されていない」状況も可視化できるため、組織内に視聴を促したり、該当のマニュアルをブラッシュアップして現場で使われるようにするという改善も可能です。
より詳しいtebikiのサービス概要を知りたい方は、「3分でわかるtebikiサービス説明資料」も併せてご覧ください。
動画マニュアル「tebiki」で新人教育マニュアルを整備している事例
ここまで、新人教育マニュアルに動画を活用するメリットや方法について詳しくご紹介しました。ここからは、実際にtebikiを活用して新人教育マニュアルを整備している企業事例をご紹介します。
より多くのtebikiによる動画活用事例を知りたい方は、さまざまな業界の事例をまとめて知れる以下の参考資料をご覧ください。
カルビー株式会社
カルビー株式会社は、ポテトチップスやじゃがりこといった日本を代表するスナック菓子メーカーで、製造技術や品質管理は業界内で高く評価されており、国内外での展開を積極的に進めています。
食品製造業としての成功の裏には、従来の座学による研修やOJTでは新人が「一気にすべてを覚えるのは難しい」「教育内容が教える人によって異なる」といった不安を感じる一方で、教育担当者も効率的な教育方法を模索し、その中で「教わる側の独り立ちが促進でき、かつ教える側の負担も軽減できる」システムの導入がカルビーの重要な取り組みとして浮上してきました。
そこで取り組みの手段として、tebikiを活用した「動画による新人教育の実証実験」を行った結果、新人スタッフはtebikiの動画マニュアルを非常に分かりやすく感じ、教育担当者からも動画を使用することで効率的に教育が行えるとの高い評価を受けました。
現在はカルビーの複数拠点でtebikiによる動画活用が進められ、新人教育やスキルアップを実現しています。カルビー株式会社の具体的な活用事例は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
▼インタビュー記事▼
カルビーが目指す製造現場の『効率的な多能工実現』と『新人の定着と早期独り立ち』。PoC検証を経て動画マニュアルtebikiを本格導入。
株式会社ハングリータイガー
株式会社ハングリータイガーは神奈川県横浜市を中心に、ハンバーグやステーキの専門店を複数展開しているチェーンレストランです。以前まで新人教育は紙マニュアルやOJTだったものの、接客の所作やキッチン業務など人の動きが伴う「業務ノウハウ」が伝わりにくいことに課題を抱えていました。
そこでtebikiを活用した動画マニュアルによる教育体制を構築したことで、アルバイトの方や調理未経験者への新人教育はtebikiを見るだけで、現場に出る一歩手前の水準までレベルアップさせることが可能になりました。同時にOJTやマニュアル作成といった工数も大きく削減されています。
株式会社ハングリータイガーの動画マニュアル「tebiki」活用事例は、以下のインタビュー記事で詳しくご紹介しています。
▼インタビュー記事▼
記事マニュアル作成やOJTの工数削減!接客の所作や業務の動きを伝えるには動画がベスト
株式会社GEEKLY
株式会社GEEKLYはIT業界に特化した人材紹介事業を行っている会社です。同社では、新人社員を受け入れるにあたりOJTの負担が大きく、トレーナーの負荷が月50時間ほどかかっていた課題がありました。また、トレーナーごとに教え方のバラつきが生じることで新人の理解度にも差が生まれ、結果的に営業数字にも影響を及ぼしていました。
そこでtebikiを活用した動画マニュアルによる新人教育を推進し、属人的になっていたOJT教育から脱却しトレーナーの教育工数を年間3,700時間削減しています。現在では基本的な教育はtebikiで行い、営業のロープレなど業務品質を高める部分でOJTや研修を取り組み、効果的かつ効率的な新人教育体制を構築しています。
より詳細な株式会社GEEKLYの動画マニュアル活用事例は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
▼インタビュー記事▼
年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!
ここまで、動画マニュアル「tebiki」を活用した実際の事例と具体的な効果をご紹介しました。tebikiを活用した、効果的かつ効率的な新人教育の実行/新人教育マニュアルの整備にご興味をお持ちの方は、以下よりお気軽にご相談ください。
【補足】新人教育マニュアルを作成するメリット
新人向けのマニュアルを作成する上では様々な手間がかかってしまいますが、その分得られるメリットも数多くあります。ここでは、新人教育マニュアルを作成するメリットについて紹介していきます。
基礎知識やノウハウをムラなく伝承できる
新人社員が現場で活躍する人材になるには、新人教育マニュアルを通して基礎知識やノウハウをムラなく共有し、独り立ちまでの期間をできるだけ短縮することから始めなければなりません。
多くの企業では、新人研修やOJTといった社内の上司や先輩が実際の業務を実践しながらスキルや手順を新人へと伝承する指導方法を採用しています。しかし、担当する講師や指導者によって仕事の質や内容がバラついてしまうことも。
正しい手順をバラつきなく正しく伝えるためにも新人教育マニュアルが必要です。新人教育マニュアルのカリキュラムに沿って均一的に教えることができれば、重要事項を漏れなく伝承することができるでしょう。
教育担当者の負担削減につながる
新人教育マニュアルがあると、教育担当者の負担削減につながるのもメリットです。教育担当者が定常業務やトラブル対応などで立て込んでいる時に、新入社員は新人教育マニュアルを使って自学自習することも可能です。新人教育マニュアルは、さまざまなシーンで教育担当者の負担軽減につながるでしょう。
新入社員の早期離職の防止につながる
一見、マニュアルと離職率には関係性がないようにも見えますが、教育環境の整備が早期離職の未然防止につながります。
参考として2023年10月に厚生労働省が公表した「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」を見てみましょう。新規学卒者の就職後3年以内の離職率は中学卒:52.9%、高卒37.0%、短大卒42.6%、大卒32.3%という状況になっています。これは、10人の新入社員のうち、3~4人が3年以内に辞めてしまうと言い換えることができます。
▼令和2年3月新規学卒就業者の離職率▼

【厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」より引用】
離職率だけではマニュアルとの関係性を把握できませんが、教育の重要性が高まっている理由を調べてみると新人教育マニュアルの重要性が分かります。
2023年2月に株式会社給与アップ研究所が中小企業(従業員数100名以上1,000名未満)の経営者104名を対象に実施した調査結果によると、教育の重要度が高まっている理由として最も選ばれているのが「社員の離職を防ぎエンゲージメントを向上させるため」という結果になっています。
▼社員教育・研修の重要度が高まっている理由▼
【株式会社給与アップ研究所「社員教育の課題に関する実態調査」より引用】
この結果を踏まえると、教育体制が整っていないことが社員の離職を招く原因の1つであることが浮かび上がってきます。
早期離職を防ぐためにも、新人教育マニュアルの整備が追い付いていない方はぜひ推進いただきたいと思います。
【補足】新人教育マニュアルに盛り込むべき6つの項目
ここでは、新人教育マニュアルに盛り込んだ方が良い項目を紹介していきます。項目漏れを無くすためにもぜひ参考にしてみてください。
- 会社の一員として把握しておくべき「企業理念」
- 社会人として必要な「ビジネスマナー」
- 会社独自の「社内ルール」
- 業務の全体像となる「業務の流れ」
- 業務で使用する「ツールや機械の使い方」
- 評価基準となる「目標設定」
会社の一員として把握しておくべき「企業理念」
企業理念は、会社の根幹となる価値観や考え方であり、社会における存在意義をわかりやすく明文化したものです。「何を目標に事業を行うのか」「なぜ企業が存在しているのか」などを示しています。新入社員の「この企業の一員として、仕事で社会に貢献しよう」という覚悟が芽生える効果が期待できます。
社会人として必要な「ビジネスマナー」
社会人経験がない新入社員には、ビジネスマナーをしっかりと理解してもらう必要があります。工数などに余裕がある企業は、新人教育マニュアルとは別に、ビジネスマナーのファイル(またはブック)を作っておいてもよいかもしれません。
最初の作成時は大変ですが、その後は何年も繰り返し利用できます。新人教育マニュアルに記載するとよいビジネスマナーの一例としては、以下の通りです。
- 挨拶の仕方(お辞儀の仕方)
- 身だしなみ
- 敬語と言葉の遣い方(社内外での敬称の言い換えなど)
- 名刺交換の仕方
- 電話の受話・発話の対話例
- メールおよびビジネス文書(よくあるパターンの定型文を提供)
会社独自の「社内ルール」
社内ルールは、全社員が見れる共用フォルダにまとめておくと便利です。新人教育マニュアル内には、そのフォルダにすぐ移動できるようにハイパーリンクを記載しておきます。共用サーバーがない場合は、保存先を表記しましょう。
新人教育マニュアルに記載するとよい社内ルールの参考例を、以下に挙げます。
- 企業倫理やコンプライアンス
- 社内組織図
- 社内座席表
- 業務ごとの担当者名簿(内線表・チャット・メールアドレスなども表示)
- 報連相(報告・連絡・相談)の徹底
- 出勤・有給・遅刻・早退・欠勤のルール
- 交通費や出張費の精算方法
- 経費精算の仕方
- 休暇申請の方法
- 会議室の予約方法
- 福利厚生についての説明(保養施設など)
- 評価制度
- 社内外でのセキュリティルール
- その他(備品の取り扱いや社内言語など)
業務の全体像となる「業務の流れ」
新入社員の配属先が決まっている場合は、新人教育マニュアルに業務の流れを掲載します。新人教育マニュアルに業務の流れを掲載する際には、以下を参考にしてみてください。
- 業務の名称や目的
- 業務の手順
- 業務の規則・注意事項・判断基準
- 業務に関わる情報(取引先および担当者・優良顧客・社内組織)
- 社内ツールの使い方
- ITに関する基礎知識(パソコン・社内ネットワーク・セキュリティなど)
業務で使用する「ツールや機械の使い方」
業務で使用しているツールや機械はマニュアル化するべきです。新人にとっては業務で使用しているツールを初めて触ることは珍しくないため、アカウント作成方法から基礎的な使用方法まで記載しましょう。
機械の使い方については、いくら中途社員でも職場によって機械の種類は異なります。そのため、誰でも分かるよう機械の使い方を細かくマニュアルに記載しましょう。
評価基準となる「目標設定」
新入社員が働く上でモチベーションとなる給与に直結する評価の基準となる目標設定についても、マニュアルに明記しておくと良いでしょう。
どのような基準で評価が決まるのか、評価を得るにはどのような目標を設定すればよいのかがわかれば、その目標を達成するための道筋となり業務にあたることができます。
新人教育でありがちな課題
ここまで新人教育の重要性やマニュアルの作成や運用方法などについて紹介してきました。しかし、新人教育を行う上では、様々な課題があるのも事実です。
- マニュアルが整備されておらずにOJTのみで指導している
- 担当者によって教え方や内容にムラがある
- 教育担当者の業務を圧迫してしまう
あらかじめ、どのような課題があるのかを理解しておくことで、よりよい新人教育につながることもあるのでチェックしてみてください。
マニュアルが整備されておらずにOJTのみで指導している
多くの企業では、新人教育マニュアルが完備されているわけではなく、新人が入社してくるたびにOJTのみで指導しているケースがあります。
OJTのみで教育してしまうと、業務を学ぶ時間が限定されてしまうために業務理解やスキルアップが遅くなってしまうことも。また、一度で覚えきれず何度も教える必要があるなど、新人・OJT担当それぞれに負担がかかってしまいます。そのため、OJTに頼るのではなく、この記事でご紹介した新人教育マニュアルを整備するなどの対策が重要と言えるでしょう。
弊社が提供している動画マニュアル作成ツールの「tebiki」を導入しているアサヒ飲料株式会社では、1日の半分以上をOJTに時間をかけていましたが、tebikiを導入してからOJTにかける時間が2時間ほどにまで短縮することに成功しています。同社の事例を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
▼インタビュー記事▼
OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化
担当者によって教え方や内容にムラがある
教育担当者ごとに業務のやり方が異なっていたり、教え方が標準化されていなかったりすることもあるため、新人社員も担当者によって業務のバラツキが発生する可能性があります。
新人のうちに覚えた業務を数年後に修正していくのは難しいため、従業員ごとに独自のやり方が浸透してしまい、いつまでも業務の標準化ができない状況になることも。業務標準化を目指すためにも、新人マニュアルの整備が必須と言えるでしょう。
教育担当者の業務を圧迫してしまう
担当者にとっては、日々の業務にプラスして教育業務が発生するため、必然的に業務内容が増加してしまいます。
新人教育は後回しにできない業務なので、通常業務を後回しにしてしまい、残業が増えてしまう可能性があるのです。場合によっては、全体の業務進行に影響が生じてしまうリスクも考えられるので、業務を整理するなどの対策が必要と言えるでしょう。
なお、紙のマニュアルから動画マニュアルのtebikiに移行したところ、作成時間が1時間から15分に大幅削減につながった「タマムラデリカ株式会社」の事例もあるように、動画でのマニュアル作成は担当者の業務負担軽減につながります。
tebikiのサービス概要をより詳しく知りたい方は、以下の資料もチェックしてみてください。
まとめ:tebikiを活用して新人教育マニュアルを充実させよう
今回は、トレーナーの負荷を軽減しつつも独り立ちを短縮させる新人教育マニュアルの作り方やコツを解説しました。ご紹介した実際の事例のように、新人教育マニュアルには動画を活用することが最も効果的です。
動画による新人教育マニュアルで教育担当の負担を減らし、新入社員の独り立ちをサポートする役割を果たします。また研修やOJTと合わせて利用することで、効果的に新人の業務品質向上も実現できるでしょう。
今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。








