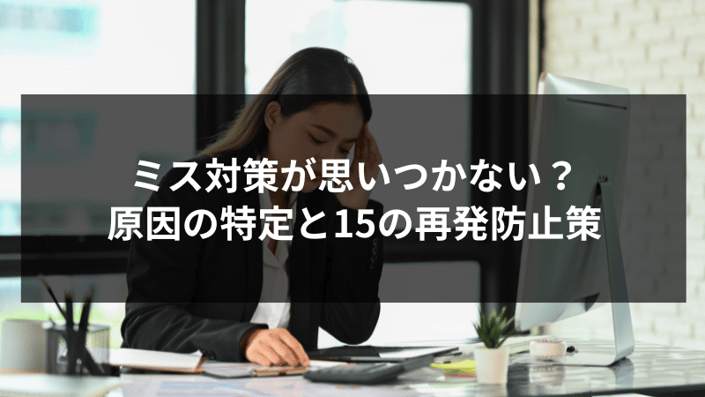

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開するTebiki株式会社です。
「また同じミスをしてしまった…」「何度言っても部下のミスが減らない…」
こうしたミスを未然防止するための対策を、本記事で解説しています。数多くの企業の現場教育を支援してきた弊社の実践的な知見に基づいた情報をまとめているので、原因分析から具体的な対策アイデア、そして組織的な取り組みまで、明日から実践できるヒントがつかめるはずです。
「何度言ってもミスが減らない」と感じる時、見直すべきは再発防止策そのものよりも、その「伝え方」と「守らせる仕組み」かもしれません。
その課題を動画マニュアルで解決した企業の事例を、以下の資料でご紹介します。
>>再発防止策の「伝わらない」「守られない」を解消する動画マニュアルの活用事例を見てみる
目次
- 1.なぜミス対策が思いつかないのか?3つの主な理由
1-1. 理由1:焦りや精神的な余裕のなさ
1-2. 理由2:ミスの原因分析が不十分
1-3. 理由3:対策の引き出し(知識・経験)不足
2.ミス対策を「思いつく」ための第一歩:原因分析で根本原因を探る
2-1. なぜなぜ分析:深掘りで真の原因にたどり着く
2-2. 4M分析:漏れなく原因を洗い出す視点
2-3. 事例3:【新人研修】OJT内容を動画化しトレーナー負荷軽減と早期戦力化を実現
3.【個人向け】具体的なミス対策アイデア10選
3-1. 業務の目的と全体像を理解する
3-2. 作業手順を明確にし、見える化する
3-3. タスクを細分化し、優先順位をつける
3-4. 時間管理を徹底し、余裕を持ったスケジュールを組む
3-5. 集中できる作業環境を整える
3-6. 指差し呼称やセルフチェックを行う
3-7. ダブルチェック・トリプルチェックの仕組みを取り入れる
3-8. コミュニケーションを密にし、不明点は必ず確認する
3-9. 十分な休息と睡眠をとる
3-10. 過去のミスから学び、記録に残す
4-1. 明確な指示と期待値の共有
4-2. 効果的な教育・研修体制の整備
4-3. ミスを報告しやすい心理的安全性の確保
4-4. 業務プロセスの見直しと標準化
4-5. 属人化の解消と情報共有の促進
5.根本的なミス対策の鍵は「分かりやすいマニュアル」にある
5-1. なぜマニュアルがミス防止に有効なのか?
5-2. 特に効果的な「動画マニュアル」という選択肢
6.まとめ:原因分析と適切な対策で、「ミス対策が思いつかない」状況を打破しよう
なぜミス対策が思いつかないのか?3つの主な理由
有効なミス対策を立てられない背景には、いくつかの共通した理由があります。まずは、ご自身もしくは部下、または組織がどの状況に近いか考えてみましょう。
以下の資料も併せてご覧ください。
>>再発防止策の「伝わらない」「守られない」を解消する動画マニュアルの活用事例を見てみる
理由1:焦りや精神的な余裕のなさ
ミスが続くと、「早くなんとかしなければ」という焦りが先行し、冷静な原因分析ができなくなっているケースです。
また、プレッシャーから精神的な余裕がなくなり、視野が狭くなって有効な対策が思いつかない、あるいは思考停止に陥ってしまうこともあります。
理由2:ミスの原因分析が不十分
発生したミスに対して、「不注意だった」「確認不足だった」といった表面的な理由だけで片付けてしまい、根本的な原因まで深掘りできていない場合があります。
原因が曖昧なままでは、的外れな対策しか立てられず、同じミスを繰り返すことになります。
理由3:対策の引き出し(知識・経験)不足
そもそも、どのようなミス対策の選択肢があるのかを知らない、あるいは知っていても自社の状況に合った方法が分からないというケースです。
特に、これまでにない種類のミスや、複雑な要因が絡むミスに対しては、既存の知識や経験だけでは対応が難しい場合があります。
ミス対策の「引き出し」を増やすためには、事故の根本原因である「ヒューマンエラー」について体系的に学ぶ安全教育が不可欠です。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
ミス対策を「思いつく」ための第一歩:原因分析で根本原因を探る
効果的な対策を立てるためには、なぜミスが起きたのか、その根本原因を正確に把握することが不可欠です。場当たり的な対策ではなく、本質的な改善を目指しましょう。ここでは、原因分析に役立つ代表的なフレームワークを2つ紹介します。
なぜなぜ分析:深掘りで真の原因にたどり着く
「なぜなぜ分析」は、発生した問題(ミス)に対して「なぜ?」という問いを繰り返すことで、表面的な事象の背後にある根本原因を突き止めるための手法です。
通常、5回ほど「なぜ?」を繰り返すと、真の原因が見えてくると言われています。
<分析を進める際のポイント>
|
事実に基づいて |
推測や憶測ではなく、客観的な事実を元に「なぜ?」を問いかけます。「たぶん」「おそらく」ではなく、実際に何が起きたのかを確認することが重要です。現場の状況をよく観察し、関係者からヒアリングしましょう。 |
|
「対策」で |
「〇〇しなかったから」で止めず、「なぜ〇〇しなかったのか?」とさらに深掘りします。安易な対策に飛びつかず、原因の本質を探求しましょう。対策は原因が特定できてから考えるべきです。 |
| 主語を 明確にする |
誰(何)が原因でその状況が起きたのかを明確にすることで、責任の所在や改善すべき対象が具体的になります。「~が悪い」という犯人探しではなく、改善点を見つける視点が大切です。 |
| 一つに 絞らない |
原因が複数考えられる場合は、それぞれに対して「なぜ?」を問いかけ、可能性を潰さないようにします。多角的に原因を探ることが重要です。 |
この分析を通じて、「個人の不注意」といった安易な結論に飛びつくのではなく、システムの不備や作業環境の問題など、より本質的な課題を発見することを目指します。
▼参考記事▼
なぜなぜ分析とは?進め方の具体例や注意点、現場での活用事例を紹介
4M分析:漏れなく原因を洗い出す視点
「4M分析」は、ミスの原因を「Man(人)」「Machine(機械・設備)」「Material(材料・部品)」「Method(方法・手順)」の4つの観点から網羅的に洗い出すフレームワークです。
これにより、原因分析のヌケモレを防ぎ、多角的な視点から問題をとらえることができます。
| Man (人) |
作業者のスキル、経験、知識、集中力、疲労度、思い込み、教育不足など、人的要因に関連する問題。「ヒューマンエラー」と片付けず、なぜそのエラーが起きたのかを考えます。 |
| Machine (機械・設備) |
使用している機械や設備の性能、老朽化、故障、メンテナンス状況、操作性など、設備要因に関連する問題。ツールの使いにくさなども含まれます。 |
| Material (材料・部品) |
使用する材料や部品の品質、仕様、保管状態、供給元、取り扱い方法など、材料要因に関連する問題。材料の欠陥や間違いがなかったかを確認します。 |
| Method (方法・手順) |
作業指示、作業手順書(マニュアル)の分かりやすさ・妥当性、作業のやり方、確認方法、連絡体制など、方法要因に関連する問題。作業手順そのものに問題がないか検討します。 |
現場によっては、これに「Measurement(検査・測定)」の精度や方法、「Environment(環境)」の整理整頓状況、温度、照明などを加えた「5M+1E」で分析することもあります。
このフレームワークを使うことで、ミスの原因が人的要因(Man)なのか、それとも設備や手順、環境といった他の要因(Machine, Material, Method, Environmentなど)にあるのかを整理しやすくなります。これにより、個人への責任追及だけでなく、仕組みや環境の改善といった、より建設的な対策を検討できるようになります。
▼参考記事▼
4M分析とは?現場改善に使える原因分析のフレームワーク【5M+1Eも解説】
【個人向け】具体的なミス対策アイデア10選
原因分析ができたら、具体的な対策を実行に移しましょう。ここでは、個人で取り組めるミス対策のアイデアを10個ご紹介します。ご自身に合ったものから試してみてください。焦らず、一つずつ着実に実践することが大切です。
1. 業務の目的と全体像を理解する
担当する業務が、全体のどの部分を担い、どのような目的を持っているのかを理解することで、作業の重要性や注意すべき点が明確になります。
ただ言われた作業をこなすだけでなく、その意味や前後の工程との繋がりを考えることで、状況に応じた適切な判断がしやすくなり、結果的にミス防止に繋がります。
2. 作業手順を明確にし、見える化する
作業の手順を一つひとつ書き出し、具体的な行動レベルまで落とし込みます。曖昧な記憶に頼らず、メモを取る、チェックリストを作成するなど、「見える化」することで、手順の抜け漏れや思い込みを防ぎます。
特に、言葉だけでは伝わりにくい複雑な作業や、身体の動き・タイミングが重要な作業の場合、静止画や文字だけでなく「動画」で手順を記録・確認することも非常に有効です。動画によって作業手順の「見える化」を進め、大きな効果を上げている事例があります。
例えば、アサヒ飲料株式会社では、従来OJT頼みだった熟練者の「暗黙知」や作業のコツを動画マニュアルで形式知化しました。これにより、作業手順書の作成工数を大幅に削減できたうえ、誰が見ても同じ解釈ができるようになったと評価されています。
※同社の詳細な課題と改善事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。
▼インタビュー記事▼
OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化
手順の「見える化」は、分かりやすいマニュアル作成の鍵です。これから初めてマニュアルを作成する方に向けて、その基本と「わかりやすいコツ」をまとめたガイドをご用意しました。
>>成功に導く「わかりやすいコツ」つき はじめてのマニュアル作成ガイドを見てみる
3. タスクを細分化し、優先順位をつける
複雑な業務や複数のタスクを抱えている場合は、一度に全てをやろうとせず、タスクをより小さな単位に分解します。そして、それぞれの重要度や緊急度に応じて優先順位を明確にします。
これにより、集中すべき作業が分かりやすくなり、混乱や抜け漏れを防ぎます。タスク管理ツールやアプリを活用するのも良いでしょう。
4. 時間管理を徹底し、余裕を持ったスケジュールを組む
各タスクにどれくらいの時間が必要かを見積もり、無理のないスケジュールに落とし込みます。締め切りギリギリではなく、予期せぬ事態にも対応できるようなバッファ(余裕)を持った計画を立てることで、焦りによるミスを防ぎます。
作業後の見直しやダブルチェックの時間も忘れずにスケジュールに組み込みましょう。
5. 集中できる作業環境を整える
作業に集中できるよう、デスク周りの整理整頓を心がけましょう。不要なものが視界に入るだけでも集中力は削がれます。
また、メールやチャットの通知を一時的にオフにする、周囲の騒音が気になる場合はノイズキャンセリングイヤホンや耳栓を使うなど、集中力を削ぐ要因を物理的・デジタル的に排除します。
6. 指差し呼称やセルフチェックを行う
特にミスが許されない重要なポイントや、間違いやすい箇所では、「〇〇ヨシ!」と声に出して指差し確認する「指差し呼称」が有効です。また、作業完了後には、あらかじめ作成したチェックリストに基づいてセルフチェックを行うことで、見落としや勘違いを効果的に防ぎます。
少しの手間に感じても、習慣化することで確実にミスを減らせます。
「指差し呼称」や「チェックリスト」が有効なのは、それが「不安全行動」を断ち切るための行動科学に基づいた手法だからです。その科学的なアプローチを、以下の資料で詳しく解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
7. ダブルチェック・トリプルチェックの仕組みを取り入れる
重要な業務やミスが許されない作業については、自分一人だけでなく、他の人にも確認してもらうダブルチェックやトリプルチェックの仕組みを取り入れることが望ましいです。
客観的な視点が入ることで、自分では気づけなかった個人の見落としや思い込みを発見しやすくなります。可能であれば、チームや組織のルールとして定着させましょう。
8. コミュニケーションを密にし、不明点は必ず確認する
少しでも疑問や不安に思うことがあれば、「これくらい大丈夫だろう」と曖昧なまま進めずに、必ず上司や同僚に報告・連絡・相談(報連相)を徹底します。認識のずれや思い込みによるミスを防ぐためには、積極的なコミュニケーションが不可欠です。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」と心得て、早めに確認する習慣をつけましょう。
9. 十分な休息と睡眠をとる
集中力や判断力の低下は、ヒューマンエラーの大きな原因となります。日々の疲れを溜め込まないよう、質の高い睡眠と適度な休息を確保し、心身のコンディションを整えることが、ミス防止の基礎となります。
疲れていると感じたら、無理せず短時間でも休憩を取り、リフレッシュしましょう。
10. 過去のミスから学び、記録に残す
起きてしまったミスは、単に反省するだけでなく、なぜ起きたのか(原因)、どうすれば防げたのか(対策)を具体的に記録に残しましょう。
そして、その記録を定期的に見返すことで、同じ過ちを繰り返さないための具体的な教訓とします。可能であれば、チーム内でミスの事例と対策を共有することで、組織全体の改善にも繋がります。失敗を次に活かすことが、個人と組織の成長の鍵です。
>>再発防止策の「伝わらない」「守られない」を解消する動画マニュアルの活用事例を見てみる
【リーダー/マネージャー向け】部下・後輩のミスを防ぐ組織的な対策5選
個人の努力だけでは、ミスを完全になくすことは困難です。リーダーやマネージャーは、ミスが起こりにくい体制や環境を整備する視点が求められます。部下や後輩の成長を支援し、組織全体のパフォーマンスを高めるための対策を考えましょう。
1. 明確な指示と期待値の共有
業務指示が曖昧だったり、求める品質レベルが不明確だったりすると、部下は「何をどこまですれば良いのか」分からず、ミスに繋がる可能性があります。
指示は具体的に、期待する成果や注意点を明確に伝えることが重要です。「5W1H」を意識して指示を出すと良いでしょう。
2. 効果的な教育・研修体制の整備
新入社員や異動者に対して、必要な知識やスキルを習得させるための教育・研修体制は不可欠です。OJT(On-the-Job Training)だけでなく、Off-JTやeラーニングなども組み合わせ、継続的な学びの機会を提供しましょう。
例えば、ブライダル事業などを展開する株式会社日本セレモニーでは、新入社員研修において、従来の方法に限界を感じていました。同社が重視する高い基準のおもてなしを実現するには、紙教材だけでは不十分だったのです。
レベルの高いおもてなしを実現するためには、声のトーンや間のとりかた、細やかな動きなど、ちょっとしたことの一つひとつの積み重ねが重要になります。それらを実現するには動画による教育システムが必要だと感じていた
同社では、新型コロナウイルスの影響で集合研修ができなくなったことを機に、Zoomと動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を組み合わせたオンライン研修を導入。tebikiで作成したマナーや立ち振る舞いの動画教材を活用し、オンラインでも効果的な新人教育を実現しました。
弊社の接客スタイルは手の角度などの細かいところまで、一つひとつ意味があり、動きが大事です。動画だと動きのタイミングで字幕を出し、同時に解説できます。(中略)研修の中で動きを見せて説明できることが効果的だと思いました。
動画を活用することで、場所を選ばずに質の高い教育を提供でき、社員は自分のペースで予習・復習を進めることが可能になります。このように、効果的な教育体制の構築において、動画マニュアルは強力なツールとなり得ます。
>>3分で分かる『tebiki現場教育サービス資料』を見てみる
同社の詳細な課題と改善事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。
▼インタビュー記事▼
ブライダルの新人教育動画マニュアル事例 | 結婚式場の接客新人研修をZoomと動画で実現!
3. ミスを報告しやすい心理的安全性の確保
ミスを隠したり、報告をためらったりする雰囲気は、問題の発見を遅らせ、より大きな問題へと発展させるリスクがあります。失敗から学び改善していく文化を醸成し、社員が安心してミスを報告できる組織を目指しましょう。
ミスを責めるのではなく、原因究明と再発防止に焦点を当てることが大切です。適切な対処法や謝罪の仕方を指導することもリーダーの役割です。
4. 業務プロセスの見直しと標準化
非効率な作業手順や、人によってやり方が異なり品質にばらつきが出るような状況は、ミスの温床となり得ます。定期的に業務プロセス全体を見直し、改善点がないか検討することが重要です。現場の意見も聞きながら、より安全で効率的な進め方を探求しましょう。
特に、作業手順の「標準化」はミス防止に不可欠です。誰が担当しても同じ手順で、一定の品質を保てるようにルールを明確化します。しかし、手順を文書化するだけでは不十分な場合もあります。言葉や文字だけでは伝えきれない細かなニュアンスが存在するためです。
例えば製造業の「大同工業株式会社」では、文書マニュアルはあっても、実際の作業におけるコツやポイントが言語化しきれず、担当者によって手順が異なる「我流化」が課題でした。
基本的な内容は文書マニュアルに記載されていますが、実際に実務をおこなう時のちょっとしたコツやポイントは言語化しにくく、動作を見せて伝え、その実務を通じて担当者が会得するしかなく、しかも担当者によってコツやポイントに差があり、それゆえ業務手順も異なるという”我流化”(業務品質のバラつき)が起こっていました。
同社はこの課題に対し、動画マニュアルを活用することで作業手順を分かりやすく「見える化」し、標準化を推進しました。結果として、品質に関わるヒヤリハットの削減にも繋がっています。
※同社の詳細な課題と改善事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。
▼インタビュー記事▼
製造業の技術部門の業務を動画で標準化。品質評価に関わるヒヤリハットを8割削減して、多能工化を実現
大同工業の事例のように手順を「見える化」して標準化しても、その後の更新を怠れば再び形骸化します。その「作って終わり」にしないためのマニュアル整備の教科書がこちらです。
>>「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書を見てみる
5. 属人化の解消と情報共有の促進
「あの人でなければ分からない」「担当者がいないと業務が進まない」といった業務の属人化は、担当者の不在時に業務が滞るだけでなく、知識やノウハウが組織に蓄積されないという問題も引き起こします。これは、ミスの原因特定や改善を妨げる要因にもなりかねません。担当者個人の負担が増大する原因にもなります。
属人化を解消するためには、個人の頭の中にしかない知識や経験(暗黙知)を、マニュアルなどを通じて誰もがアクセスできる形(形式知)にしていくことが重要です。これにより、組織全体で知識や情報をスムーズに共有できる仕組みを作ります。
「暗黙知」を「形式知」へ変換する、その一連の取り組みこそが「技術伝承」です。属人化を解消し、技術伝承を成功させるための具体的なポイントを解説します。
例えば東急リゾーツ&ステイ株式会社は、個々人に特有の業務やシフトが存在し、文字通り属人化の状態が続いていました。そこで、1つひとつの作業を動画によって可視化し、なるべく誰でも均等な業務品質がなされるよう仕組みを構築しています。
※同社の詳細な課題と改善事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。
▼インタビュー記事▼
従業員数2,500人超・全国100を超える施設で業務の平準化と多能工化を推進。
根本的なミス対策の鍵は「分かりやすいマニュアル」にある
様々なミス対策を講じても、作業手順そのものが分かりにくかったり、人によって解釈が異なったりすると、ミスを防止することは困難です。ここで重要になるのが「マニュアル」の存在です。
なぜマニュアルがミス防止に有効なのか?
分かりやすいマニュアルは、作業の標準化を実現し、誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できるようにするための基盤となるからです。
「何を」「どの手順で」「どこに注意して」行うべきかが明確になるため、思い込みや勘違いによるミス、手順の抜け漏れを大幅に減らすことができます。また、新人教育やスキルの平準化、業務の改善にも繋がり、組織全体の生産性向上に貢献します。
マニュアル整備の重要性や進め方については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
▼関連記事▼
マニュアル整備の必要性と具体的な進め方!成功事例も紹介
特に効果的な「動画マニュアル」という選択肢
近年、ミス対策として特に注目されているのが「動画マニュアル」です。動画は、文字や静止画だけでは伝えきれない作業の動きや複雑な業務プロセスを視覚的に、かつ正確に伝えることができます。
また、OJT教育やマンツーマン指導の工数を緩和させる役割もあるので、先輩社員・ベテラン社員の稼働時間を確保しながら教育体制を整備できるのもメリットです。新人スタッフが動画を視聴している間は、教育担当者のリソースが圧迫されることはないからです。
また、動画マニュアルは「非言語マニュアル」でもあるので、外国人教育にも強いのが特徴です。字幕や翻訳機能を活用すれば、言語の壁を越えて手順を伝えられます。株式会社Archemのように、アメリカの工場で従業員教育に動画マニュアルを活用し、言語の壁を乗り越えて品質と生産性を向上させた事例もあります。
以下の記事では、実際のサンプル動画マニュアルを記事上で再生・閲覧ができるので、動画マニュアルに少しでも興味がある方は参考にしてみてください。
▼関連記事▼
・【動画マニュアル事例集】業界別26社のサンプルを多数紹介
・動画マニュアル特有のメリットとデメリット!導入効果が分かる事例も紹介
実際にどのような動画マニュアルが業務で使われているのか、具体的なサンプルを見てみたい方は、「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(pdf)」が役立ちます。様々な現場の動画サンプルがまとめられており、自社での活用イメージを膨らませるのに最適です。
以下をクリックして、ダウンロードしてみてください。
>>実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集を見てみる
まとめ:原因分析と適切な対策で、「ミス対策が思いつかない」状況を打破しよう
仕事上のミスが続き、対策が思いつかないと悩んでいる方は、まず冷静にミスの原因を分析することから始めましょう。「なぜなぜ分析」や「4M分析」などを活用して根本原因を突き止め、個人でできる対策と組織的な対策の両面からアプローチすることが重要です。
特に、作業手順の標準化と共有に有効な「マニュアル」の整備は、根本的なミス防止に繋がります。中でも、動きや複雑な業務プロセスを分かりやすく伝えられる「動画マニュアル」は、現代の多様な働き方や教育ニーズに適した効果的なツールと言えるでしょう。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のようなツールであれば、ミスが発生する根本要因を取り除き、職場全体で正しい手順で業務が遂行されるような環境を作るお手伝いが可能です。動画マニュアルや「tebiki現場教育」についてまずは概要を知りたいという方は、「3分で分かる『tebikiサービス資料』」をご覧ください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。




