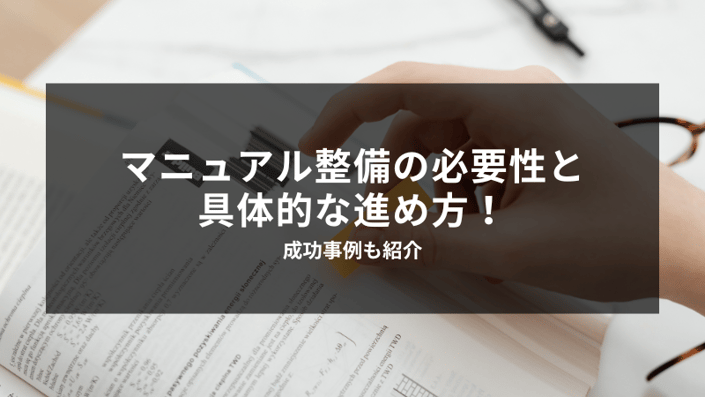

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開するTebiki株式会社です。
マニュアル整備は、業務標準化や新人教育の効率化に不可欠です。しかし、「どう進めればいいかわからない」「作ったきり形骸化している」という声も。
そこでこの記事では、マニュアル整備の目的設定から具体的な作成・改善手順、分かりやすいコツ、ツールの選び方まで網羅的に解説します。効果的な整備方法を知り、現場の生産性向上を実現しましょう。
目次
- 1. マニュアル整備の目的や5つのメリット
1-1. 業務品質の標準化と向上
1-2. 教育コスト・時間の削減
1-3. 業務の属人化防止とナレッジ共有
1-4. 新人・異動者の早期戦力化
1-5. 従業員の負担軽減と生産性向上
2. マニュアル整備の種類:新規作成と既存改善、どちらから着手すべき?
2-1. 新規マニュアル作成:ゼロから業務を標準化する場合
2-2. 既存マニュアル改善:形骸化・陳腐化したマニュアルを見直す場合
3. 失敗しないマニュアル整備の具体的な進め方
3-1. Step1:目的とゴールの明確化
3-2. Step2:対象業務の洗い出しと情報収集
3-3. Step3:構成案(目次)の作成
3-4. Step4:マニュアル本文の作成・執筆
3-5. Step5:レビューとフィードバックによる修正
3-6. Step6:社内への周知と運用ルールの設定
3-7. Step7:定期的な見直しと更新プロセスの確立
4. マニュアル整備で押さえておきたいコツ
4-1. テキストや図解だけでは伝わりにくい情報を補う工夫
4-2. 対象読者を具体的に想定する
4-3. 一目で内容がわかるタイトル・見出し
4-4. 専門用語を避け、簡潔・具体的に書く(5W1H)
4-5. 図・表・チェックリストを効果的に使う
5. マニュアル整備で検討したいツールの一覧
5-1. 動画マニュアル作成ツール
5-2. Officeツール(パワーポイントやワード等)
5-3. テキスト/Wikiベースツール
5-4. eラーニング連携型ツール
6. まとめ:継続的なマニュアル整備で、変化に強い組織をつくる
マニュアル整備の目的や5つのメリット
マニュアル整備は基本的に、以下のような目的のもとで実施されます。
- 業務品質の標準化と向上
- 教育コスト・時間の削減
- 業務の属人化防止とナレッジ共有
- 新人・異動者の即戦力化
- 従業員の負担軽減と生産性向上
これらは目的と同時に、マニュアル整備のメリットでもあります。ひとつひとつ、これから解説します。
業務品質の標準化と向上
明確な手順が示されることで、担当者の経験やスキルに左右されず、業務の質を一定に保つことができます。これにより、製品やサービスの品質向上、顧客満足度の向上につながります。特に多拠点で事業を展開している場合、全社的な品質均一化に大きく貢献します。
例えばブライダル事業等を展開する「株式会社日本セレモニー」では、動画やZoomによるマニュアルを整備し、集合研修を動画で実施しています。結果的に「研修の参加者全員が同じ教育品質を受けられる」ような体制が整備できており、標準化につながっています。
同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
新型コロナ緊急対応で、ブライダル接客の新人集合研修をZoomと動画で実現!
教育コスト・時間の削減
体系化されたマニュアルがあれば、OJT(On-the-Job Training)担当者の負担を軽減し、新人や異動者が自律的に学習を進めやすくなります。これにより、教育にかかる時間とコストを大幅に削減できます。逆に、整備されていないと、教える人によって内容が異なったり、何度も同じ質問に答えたりする非効率が生じがちです。
例えば物流企業の「ソニテック株式会社」は、新人の受入教育には3ヵ月間のマンツーマン指導が必須でしたが、マニュアル整備によってマンツーマン指導は一切行わなくなりました(詳細の事例はこちら)。同社は「動画」によるマニュアル整備を進めており、「一目見れば分かるマニュアル」で現場教育を効率化しています。
動画マニュアルは多くの現場で導入され始めていますが、具体的にどのように活用し、推進するのかについては資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」で詳しく解説されています。下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
業務の属人化防止とナレッジ共有
特定の担当者しか知らない業務手順やノウハウがマニュアル化されることで、業務の属人化を防ぎます。担当者の急な不在や退職による業務停滞リスクを低減し、組織全体で知識やスキル(ナレッジ)を共有・蓄積することが可能になります。
新人・異動者の早期戦力化
分かりやすいマニュアルは、新しい環境で業務を覚える従業員の不安を軽減し、早期の立ち上がりをサポートします。自信を持って業務に取り組めるようになることで、エンゲージメントの向上も期待できます。
例えば以下の動画は、製造業の「児玉化学工業株式会社」が作成した「バリの取り方」を動画マニュアル化したものです。こうした「複雑な動きが伴う業務プロセスや技術」を新人社員に教育することは非常に難しいですが、要所要所に字幕が入り、動画の内容をより理解しやすくなっています。
▼動画によるマニュアル整備の例▼
※本動画は「tebiki」で作成されています
業務を理解しやすいよう、字幕が流れるときは映像が停止する構成になっており、視聴者に配慮した品質の高い動画マニュアルです。
従業員の負担軽減と生産性向上
作業手順が明確になることで、従業員は「次に何をすべきか」「どうやるのが正しいか」と迷う時間が減ります。これにより、心理的な負担が軽減され、本来注力すべき業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上につながります。特に現場作業においては、正しい手順の遵守が安全確保にも直結します。
マニュアル整備の種類:新規作成と既存改善、どちらから着手すべき?
「マニュアル整備」と一言で言っても、その状況は様々です。「そもそもマニュアルが存在しない業務を対象とするのか」、それとも「既にあるマニュアルが古くなったり、使われなくなったりしているのを改善するのか」によって、アプローチは異なります。
自社の状況はどちらに近いかを確認し、適切なスタート地点を見極めましょう。これは、どちらか一方を選ぶというよりも、自社の現状を把握し、以降の整備ステップをより具体的にイメージするための状況整理と捉えてください。
新規マニュアル作成:ゼロから業務を標準化する場合
これまでマニュアルが存在しなかった業務について、新たに作成するケースが該当します。特に、新しく開始する業務がある場合や、属人化が進んでおり手順の標準化が急務な場合、あるいは複数の担当者が自己流で作業しており品質にばらつきがある場合などに有効です。
最初のポイントとしては、まずどの業務からマニュアル化するか、優先順位をつけることが重要になります。業務の重要度、発生頻度、標準化による効果の大きさなどを考慮して対象業務を選定しましょう。
既存マニュアル改善:形骸化・陳腐化したマニュアルを見直す場合
既にマニュアルは存在するものの、情報が古くて現状の業務内容と合っていなかったり、内容が分かりにくく誰も読まなかったり、保管場所が不明確だったりする問題を抱えている場合は、既存マニュアルの改善から着手します。
改善に着手する際の最初のポイントは、こちらも同様、どのマニュアルから手をつけるべきかを見極めることです。普段マニュアルを読んでいる(もしくは今後読んでもらいたいと思っている)部署の従業員と会話を通じて、優先順位をつけましょう。
また、またマニュアルが形骸化しないよう、定期的な見直し(例:年1回)や、業務プロセスに変更があったタイミングで見直すルールをあらかじめ決めておくことが鍵となります。
ちなみに、マニュアルが使われなくなる原因のほとんどが「読みにくい」「どこに保管されているか分からない」という理由です。多くの企業や現場では、使われるマニュアルとして「動画マニュアル」が整備されており、形骸化を防ぐ有効手段としてあらゆる職場で活用されています。
紙マニュアルよりも動画マニュアルが優れている理由や活用シーン、導入事例等がまとめられた資料「『使われないマニュアル』は卒業!動画マニュアルで実現した現場の効率化」も参考にすると、動画マニュアルの有効性を知ることができます。あわせて参考にしてみてください。
失敗しないマニュアル整備の具体的な進め方
目的と対象(新規作成か既存改善か)が決まったら、いよいよ具体的な整備作業に入ります。ここでは、効果的なマニュアル整備を進めるための標準的な7つのステップを解説します。
Step1:目的とゴールの明確化
最初のステップは、そのマニュアルが「誰のための」「何の業務に関する」「どのレベルの内容を伝える」ものなのか、目的とゴールを具体的に定義することです。
例えば、「新入社員が、〇〇業務を、独力でミスなく完了できるレベルになること」のように具体的に設定します。この定義が曖昧だと、マニュアルの内容がブレたり、情報に過不足が生じたりする原因になります。
Step2:対象業務の洗い出しと情報収集
次に、マニュアル化する業務の具体的な手順やノウハウを洗い出します。これには、業務フローの可視化(作業の開始から終了までの流れを図式化)や、担当者へのヒアリング(実際に業務を行っている熟練者と初心者の両方から手順、注意点、コツなどを詳しく聞き取る)といった方法があります。
特に現場作業の場合は、実際の作業風景を観察し、担当者の動きや判断プロセスを確認することも重要です。この際、写真や動画で記録しておくと、後で詳細を確認する際に役立ちます。
Step3:構成案(目次)の作成
収集した情報を整理し、マニュアル全体の骨子となる構成案(目次)を作成します。読者が業務の流れに沿って、あるいは知りたい情報を見つけやすいように、論理的で分かりやすい構成を心がけましょう。
大きな業務の括り(章)、具体的な作業ステップ(節)、補足情報や注意点(項)のように、階層構造を意識すると情報が整理しやすくなります。
Step4:マニュアル本文の作成・執筆
作成した構成案に基づき、具体的なマニュアルの本文を作成(または既存マニュアルを修正)します。
誰が読んでも理解できるよう、専門用語を避け、平易な言葉で記述することを意識しましょう。図や表なども効果的に活用します。(分かりやすい書き方の詳細は次章で解説します。)
もし、「そもそもマニュアルの作り方の基本から知りたい」「具体的な見本が欲しい」という場合は、マニュアル作成の全体像と実践的な方法をまとめた以下の資料「そのまま真似できる「見本」付き 業務マニュアルの作り方完全ガイド」が参考になるでしょう。そのまま真似できるテンプレートも含まれており、具体的な作成手順を理解するのに役立ちます。
Step5:レビューとフィードバックによる修正
作成したマニュアル(案)は、完成前に必ず複数の関係者でレビューを行いましょう。
実際の作業者には内容の正確性や手順の抜け漏れを、業務未経験者や新人には初心者でも理解できるか、分かりにくい点はないかを、そして上長や関連部署には全体的な構成や他の業務との整合性を確認してもらうのが理想です。
受け取ったフィードバックに基づき、内容を修正・改善することで、マニュアルの質は格段に向上します。
Step6:社内への周知と運用ルールの設定
完成したマニュアルは、関係する従業員全員に周知し、いつでもアクセスできるように環境を整える必要があります。ファイルサーバーや社内ポータル、マニュアル管理ツールなど、誰でもアクセスしやすい場所に保管場所を明確化しましょう。
周知方法としては、メールでの通知や社内イントラネットへの掲載、会議での説明などが考えられます。特に現場では、朝礼での共有や関連する場所への掲示といった工夫も有効です。
あわせて、マニュアルに関する質問窓口、更新担当者、利用に関するルールなどを明確にしておくことも、スムーズな運用のために重要です。
Step7:定期的な見直しと更新プロセスの確立
マニュアルは作って終わりではなく、継続的に見直し、更新していくことが最も重要です。これが「形骸化」を防ぐ鍵となります。業務内容の変化や、より良い方法の発見に合わせて内容をアップデートしていきましょう。
そのためには、誰が、いつ(例:半年に1回、業務プロセス変更時など)見直しを行うかという更新担当者と頻度を明確に定める必要があります。また、利用者からの意見や改善提案を収集する仕組み(例:コメント機能、目安箱など)を設け、それを更新に活かす体制も有効です。更新履歴(いつ、誰が、どこを修正したか)を残しておくと、変更内容の確認や差し戻しも容易になります。
「作ったマニュアルが現場で活用されず、形骸化してしまう」という悩みは多くの企業で聞かれます。マニュアルを本当に活きるものにするための整備方法や、形骸化を防ぐ具体的な仕組みづくりについて、より詳しく知りたい方は以下の資料「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書」もご参照ください。マニュアルが「作って終わり」にならないためのヒントが見つかるはずです。
下の画像をクリックするとダウンロード可能です。
マニュアル整備で押さえておきたいコツ
せっかく整備したマニュアルも、読まれなければ意味がありません。ここでは、利用者にとって「分かりやすい」「使いたい」と思われるマニュアルを作成するための5つのコツを紹介します。
テキストや図解だけでは伝わりにくい情報を補う工夫
実際の操作画面の動き、機械の操作方法、身体の細かな動作、作業のスピード感、言葉では表現しにくい微妙なニュアンスなどは、テキストや静止画(図、写真、イラスト)だけではどうしても伝えきれない場合があります。
特に現場作業における「カンコツ」と呼ばれるような暗黙知は、熟練者の実際の動きを見るのが最も理解への近道です。このような情報を効果的に伝える手段として、動画の活用が挙げられます。短い動画をマニュアルの一部として埋め込むだけでも、テキストや図だけの場合と比較して、利用者の理解度は格段に向上するでしょう。
例えば以下の動画は、物流企業である「株式会社近鉄コスモス」が作成した「フォークリフトの操作」に関連する動画マニュアルです。「正しいハンドリフト操作」を短く動画化し、シンプルかつ分かりやすい例になっています。
▼フォークリフトの操作を解説する動画マニュアル▼
※本動画は「tebiki」で作成されています
物流業に限らず、他にも具体的な動画マニュアルのサンプルを見てみたい方は、資料「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」が役立ちます。様々な現場の動画サンプルがまとめられており、自社での活用イメージを膨らませるのに最適です。
>>>「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」を見てみる
対象読者を具体的に想定する
誰に向けたマニュアルなのかを明確に意識することが最も重要です。
新入社員向けなのか、経験者向けなのか、特定の部署向けなのかによって、使用する言葉遣いや説明の詳しさ、前提知識のレベルは大きく異なります。常に読者の視点に立ち、「この表現で伝わるか?」「この情報は本当に必要か?」を自問しながら作成を進めましょう。
一目で内容がわかるタイトル・見出し
マニュアル全体や各章・各節のタイトル・見出しは、その内容を具体的かつ簡潔に表すものにします。
「〇〇の設定方法」「△△のトラブルシューティング手順」のように、読者が知りたい情報がどこに書かれているか、一目で判断できるように工夫することが求められます。タイトルや見出しにキーワードを含めることで、後で検索しやすくなるという副次的なメリットもあります。
専門用語を避け、簡潔・具体的に書く(5W1H)
専門用語や社内用語の使用は、読者が理解できない可能性があるため、できるだけ避けるか、必要な場合は注釈を加えるようにしましょう。また、文章は一文を短く(目安:50~60文字以内)し、「~である」「~すること」といった断定的な表現を基本とします。情報を整理する際には、箇条書きなどを効果的に活用するのも良いでしょう。
特に作業手順を説明する場合は、「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「なぜ」「どのように(How much/How long含む)」という5W1H(+2H)を意識することで、より具体的で誤解の少ない記述になります。
図・表・チェックリストを効果的に使う
文字だけの説明では理解が難しい内容は、図、表、フローチャート、スクリーンショットといった視覚的な要素を積極的に活用しましょう。複雑な手順や複数の判断基準、機能の比較情報などは、表形式にまとめることで格段に分かりやすくなります。
また、作業ステップが多い業務では、チェックリスト形式を採用することで、実施漏れを防ぐ効果も期待できます。
マニュアル整備で検討したいツールの一覧
マニュアル整備をより効率的に進める上で、専用のツールやシステムを活用することは非常に有効な選択肢となります。具体的にどのようなマニュアル作成ツールがあるのか、ここから紹介します。自社のマニュアルの内容や利用シーンに合わせて、最適なタイプを選びましょう。
動画マニュアル作成ツール
テキストではなく、動画を中心としたマニュアルの作成、共有、管理に特化したツールは1つの有効手段です。
動画マニュアルの大きな特徴は、実際の作業手順や機械の操作方法、身体の細かな動きなどを正確に伝えたい現場作業の教育や、熟練者の持つ暗黙知(カンコツ)の技術伝承、さらには外国人労働者向けの多言語対応が必要な場合に大きな効果を発揮します。
無料の動画編集ソフトはウェブ上でダウンロード可能なので、試しに何か使ってみるのは良いかもしれません。
ただ、無料版は高い編集技術が求められることが多いので、現場教育に特化した(現場作業員でもかんたんに撮影・編集が可能な)ツールがおすすめです。なかでも「tebiki現場教育」は、専門的な動画編集スキルがなくても、スマートフォンなどで撮影した動画をアップロードし、簡単な操作で不要部分のカット、テロップや図形の挿入、ナレーション追加などが行えます。
tebiki現場教育の詳細な機能や活用事例についてまとめられたサービス資料は、下の画像をクリックしてダウンロードできるので、あわせて参考にしてみてください。
Officeツール(パワーポイントやワード等)
多くの従業員が普段から使い慣れているMicrosoft Word、Excel、PowerPointといったOfficeソフトをベースに、マニュアル作成に便利なテンプレートを提供したり、版管理や共有機能を強化したりするタイプのツールです。
既存のスキルを活かせるメリットがありますが、Officeソフトのライセンス管理が必要な点や、大規模なマニュアル管理には専用ツールほどの効率性がない場合もあります。
ちなみにパワーポイントは通常のマニュアルに加え、簡易的な動画マニュアルも作成が可能です。パワーポイントを使ったかんたんな動画マニュアル作成方法は、資料「パワーポイントで実践する動画マニュアル作成ガイド」にまとめられているので、まずはパワポでマニュアルを整備してみたい方は参考にしてみてください。下のリンクから資料をダウンロードできます。
>>>「パワーポイントで実践する動画マニュアル作成ガイド」を見てみる
テキスト/Wikiベースツール
主にシンプルなテキストベースのマニュアル作成に適しています。特別な知識がなくても比較的容易に作成・更新できるのが特徴です。
社内Wikiツールや情報共有ツール(グループウェア、例えばMicrosoft TeamsやSlack、Notionなど)に組み込まれている機能を利用することも多く見られます。手軽に始めやすい反面、複雑な手順や視覚的な情報伝達には限界がある場合もあります。
eラーニング連携型ツール
作成したマニュアルを単なる手順書としてだけでなく、オンラインの教材(eラーニングコンテンツ)として活用することに主眼を置いたツールです。
従業員の学習進捗管理、理解度を確認するためのテスト機能、アンケート機能などを統合しており、体系的な教育・研修プログラムの一環としてマニュアルを活用したい場合に適しています。多機能な分、導入や運用にコストや手間がかかる傾向があります。
まとめ:継続的なマニュアル整備で、変化に強い組織をつくる
マニュアル整備は、単なる目先の教育を短縮化するためではなく、現場全体の教育改善に繋がる基本にして重要な施策です。まずは自社のマニュアルの現状を見つめ直し、本記事で解説したステップやコツを参考に、小さな範囲からでも整備に着手してみてはいかがでしょうか。
その際には、伝えるべき内容や対象者に合わせて、テキスト、図解、そして動画といった表現方法や、効率化のためのツール活用も柔軟に検討しながら、自社にとって最適なマニュアル整備のあり方を見つけていくことが成功への道筋となるでしょう。
マニュアル整備は、時間がかかりすぎてもいけないですし、簡単に作りすぎて現場に読まれないというパターンも避けなければなりません。双方の課題を解消できる有効手段の1つに「動画マニュアル」という選択肢があります。
これから動画マニュアルの作成や導入を具体的に検討される方、あるいはその基本から学びたいという方には、以下のガイドブック「はじめての動画マニュアル作成ガイド」がおすすめです。作成のステップから導入の推進方法まで、実践的なノウハウが分かりやすくまとめられています。ぜひダウンロードして、次の一歩にお役立てください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。








