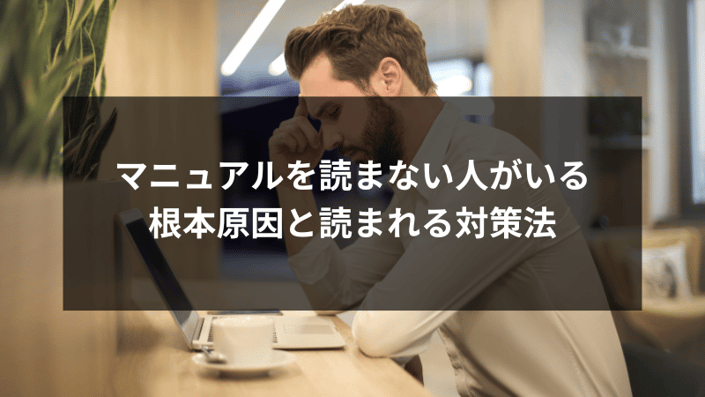

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、tebikiサポートチームです。
「時間をかけて作ったマニュアルが、現場でなかなか読まれない…」
多くの現場責任者や教育担当者が抱える悩みではないでしょうか。マニュアルが活用されないと、業務の属人化や新人スタッフごとの業務品質のばらつき、新人教育の非効率化など、様々な問題につながりかねません。
そこでこの記事では、なぜマニュアルが読まれないのか、その根本的な原因を深掘りし、現場で「読まれ、活用される」マニュアルにするための具体的な対策を解説します。
以下の資料も併せてご覧ください。
>>“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法を見てみる
目次
- 1. マニュアルが読まれないことによる現場の課題
1-1. 業務やサービスの品質バラつきと標準化の阻害
1-2. 新人教育・OJTの非効率化と負担増
1-3. 外国人教育の負担増
1-4. 特定の従業員への業務の属人化
1-5. ヒューマンエラーの増加
2. なぜマニュアルは読まれないのか?考えられる5つの原因
2-1. 原因1:従業員側の問題
2-2. 原因2:マニュアル自体の問題
2-3. 原因3:環境・仕組みの問題
3. マニュアルが「読まれる化」されるための7つのポイント
3-1. 1. 視覚的に分かりやすく、直感的に理解できる内容にする
3-2. 2. 読む目的とメリットを明確に伝える
3-3. 3. いつでも、誰でも、簡単に見つけられるようにする
3-4. 4. 常に情報を最新の状態に保ち、信頼性を維持する
3-5. 5. 実際に利用する従業員の意見を取り入れ、継続的に改善する
3-6. 6. マニュアルを活用する文化と時間的余裕を作る
3-7. 7. 汎用的なマニュアル作成ツールを活用する
4. 読まれるマニュアル作りに成功した企業や現場の事例
4-1. 【総合建設業】株式会社安藤・間:読まれない紙マニュアルを刷新
4-2. 【小売業】株式会社いなげや:新人に読まれない「分厚いマニュアル」から電子マニュアルへ
4-3. 【飲食業】株式会社ハングリータイガー:調理や接客の「動き」を動画で伝え、教育工数を削減
5. まとめ
マニュアルが読まれないことによる現場の課題
マニュアルが読まれない状態が続くと、具体的にどのような問題が発生するのでしょうか。マニュアルは一般企業のデスクワーカーでも現場業務(デスクレス領域)でも重要な役割を担いますが、特に工場や店舗、物流倉庫といったデスクレスワーカーが多く働く現場では、より重要な教育手段です。
そんなマニュアルが読まれない職場や現場では、以下のような課題に直面しがちと言えます。
マニュアルが読まれないことで過去の失敗から学ばず、同じ「不安全行動」が繰り返されるという課題が生じます。その連鎖を行動科学で断ち切る方法を解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
業務やサービスの品質バラつきと標準化の阻害
マニュアルが読まれない現場では、各々の従業員が自己流の手順や判断基準で業務が進んでいきます。
つまりサービスや作業の品質が安定しません。
例えば営業職であれば、クロージングするまでの流れに従業員間でバラつきがあると、成果のバラつきにつながり、チーム全体の成果がなかなか安定しないことになります。接客業であれば、言葉遣いやお客様の対応にバラつきが生じ、不信感を与える恐れもあります。
製造業や工場を例にするのであれば、作業品質のバラつきは、顧客からのクレームや信頼低下に直結するだけでなく、生産性の低下や材料ロス増加の原因にもなります。
まさにその「品質のバラつき」や「成果の不安定さ」こそが、企業が今すぐ「業務標準化」に着手すべき最大の理由です。
新人教育・OJTの非効率化と負担増
新入社員や部署異動者が配属されるたびに、OJT担当者がつきっきりで指導にあたるものの、なかなか独り立ちできない、という悩みもよく聞かれます。マニュアルが活用されない現場では、教える人によって指示内容が異なったり、新人が何度も同じ質問を繰り返したりしがちです。
結果として、新人の立ち上がりに時間がかかるだけでなく、OJT担当者は本来の業務に集中できず、残業が増えるといった負担増につながります。
新人の立ち上がりが遅れ、OJT担当者の負担が増える…その悪循環を断ち切る「OJT教育の新常識」を、以下の資料で詳しく解説します。
例えば、人材紹介業の「株式会社GEEKLY」では、トレーナーが新人教育の直接指導に多くの時間を割かれ、本来時間を割くべき営業活動にも影響が出てしまうという状況がありました。マニュアルが読まれず、OJTに依存した教育体制は、ベテラン社員の時間や工数もかかることに留意しなければなりません。
※同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
▼インタビュー記事▼
年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!
外国人教育の負担増
特に、外国人労働者がいる職場や現場では、マニュアルが読まれる環境構築がより急務だと言えるでしょう。外国人教育では、言語の壁も加わり、さらに困難になるケースも少なくありません。ゆえにOJT教育やマンツーマン指導の難易度は高いため、外国人にも読まれるマニュアル整備は非常に重要です。
外国人スタッフにマニュアルが読まれるためには「非言語マニュアル」の整備が重要ですが、その手段として「動画・映像」のマニュアルが挙げられます。動画マニュアルで外国人教育をスピーディに実施する具体的方法や活用イメージについては、資料「外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!(pdf)」で詳しく解説しています。
以下のリンクからダウンロードが可能です。
>>>「外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!(pdf)」を読んでみる
特定の従業員への業務の属人化
「この作業はAさんしかできない」「Bさんに聞かないと、どのように対応したらいいか分からない」といった、特定の従業員に依存する状況(属人化)は、多くの職場が抱える課題です。マニュアルが読まれない職場では、特定の従業員のみ把握している情報が徐々に増え、業務が進みにくい状況になります。
例えば接客業でお客様から何かしらの質問をされた際、属人化が進んでいる職場では、「先輩社員に聞かないと分からない」ような状態になってしまうでしょう。あるいは、特定の担当者しか知らないシステム操作や顧客対応ノウハウなども属人化の一例です。
製造業や工場のような現場であれば、貴重なノウハウや技術が形式知として蓄積されず、若手への技術伝承が進みません。これは、企業の持続的な成長や将来的な競争力低下にもつながりかねない、根深い問題と言えるでしょう。
従業員に読まれるマニュアルは、どれだけ分かりやすいマニュアルが整備できるかが重要です。分かりやすいマニュアルを1から整備したい方は、以下の資料「成功に導く「わかりやすいコツ」つき はじめてのマニュアル作成ガイド(pdf)」を参考にすると、読まれるマニュアルの整備が比較的カンタンに進められるはずです。
以下をクリックして、資料をダウンロードしてみてください。
>>成功に導く「わかりやすいコツ」つき はじめてのマニュアル作成ガイド
ヒューマンエラーの増加
「これくらい大丈夫だろう」「いつもこうやっているから」といった慣れや自己判断による手順の省略・変更は、ヒューマンエラーを引き起こす大きな原因となります。ヒューマンエラーは業務効率が低下する要因になるので、ヒューマンエラーが発生しない仕組みづくりを徹底しなければなりません。
マニュアルで定められた正しい手順やルールが守られないことで、業務上のミス、サービス品質の低下、場合によっては重大な事故につながるだけでなく、最悪の場合、従業員の怪我や生命に関わる重大な問題につながる危険性も高まります。特に、安全管理やコンプライアンスが厳しく求められる職場や、顧客満足度に直結する業務においては、「マニュアル通りに業務が遂行される」職場づくりが不可欠です。
マニュアル通りに業務が遂行される現場づくりのヒントについては、「“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法(pdf)」を参考にしてみてください。下のリンクをクリックすると、ダウンロードが可能です。
>>>「“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法(pdf)」を読んでみる
なぜマニュアルは読まれないのか?考えられる5つの原因
従業員や現場作業員がマニュアルを読まない背景には、様々な理由が考えられます。ここでは主な原因を「読まない人(従業員側)」「マニュアル自体」「環境・仕組み」の3つの側面から分析します。自社の状況に当てはまるものがないか、確認してみてください。
原因1:従業員側の問題
面倒・時間がないと感じている
日々の業務に追われる中で、「マニュアルを読む時間があったら、1つでも多く作業を進めたい」と感じるのは自然な心理かもしれません。特に、緊急性の高い業務が多い現場では、マニュアルを確認する優先順位が低くなりがちです。
また、「読まなくても、これまでの経験や勘で何とかなる」「困ったら聞けばいい」という意識が、読むことへの面倒臭さにつながっているケースもあります。
これらの心理こそが「不安全行動」を繰り返させる根本原因です。行動科学でその心理を解明し、対策する方法を解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
必要性を感じていない
マニュアルを読まなくても、先輩社員に聞けばすぐに教えてもらえる環境であったり、OJT(On-the-Job Training)中心の教育体制であったりする場合、従業員はマニュアルを読む必要性を感じにくいかもしれません。「マニュアルは形だけのもので、実際の業務では使わない」という認識が広がっている可能性もあります。
>>「使われないマニュアル」は卒業!動画マニュアルで実現した現場の効率化を見てみる
読んでも理解できないと思っている
過去に読みにくいマニュアルに触れた経験から、「どうせ文字ばかりで分かりにくい」「専門用語が多くて理解できない」といった先入観を持っている場合があります。一度このようなネガティブなイメージを持ってしまうと、新しいマニュアルが整備されても、読む前から敬遠してしまう可能性があります。
原因2:マニュアル自体の問題
情報が分かりにくい・探しにくい
マニュアルが読まれない最も大きな原因の一つが、マニュアル自体の品質です。以下のような問題点が挙げられます。
| 文章が難解・冗長 | 専門用語や社内用語が多く使われていたり、一文が長すぎたり、逆に説明が不足していたりすると、読む意欲が削がれます。 |
| 視覚情報が不足 | 文字ばかりが羅列されており、図や写真、イラストなどが効果的に使われていないマニュアルは、内容を直感的に理解しにくいです。 |
| 構成が複雑 | 目次や索引がない、どこに何が書かれているか分かりにくいなど、目的の情報にたどり着くまでに時間がかかるマニュアルは敬遠されます。 |
| 情報が古い | 業務内容や手順が変更されているにも関わらず、マニュアルが更新されていないと、信頼性が失われ、読まれなくなります。 |
分かりやすいマニュアルを作成するための大切なポイントは、資料「はじめてのマニュアル作成ガイド(pdf)」に凝縮してまとめているので、参考にしてみてください。
>>>「はじめてのマニュアル作成ガイド(pdf)」を読んでみる
作成者の自己満足になっている
マニュアルを作成する際、実際にマニュアルを利用する従業員が本当に必要としている情報や、どのレベルの知識を持っているかを考慮せずに、作成者の視点だけで作られてしまうことがあります。
「伝えるべき」という思いが先行し、情報過多になったり、逆に基本的な説明が抜け落ちたりすると、実際の業務では使えないマニュアルになってしまいます。
自己満足に終わらない、利用者の視点に立ったマニュアルを作る一番の近道は、良い「見本」を真似ることです。そのまま使える「見本」付きの完全ガイドがこちらです。
>>そのまま真似できる「見本」付き 業務マニュアルの作り方完全ガイド
原因3:環境・仕組みの問題
マニュアルの保管場所が不明確・アクセスしにくい
そもそもマニュアルがどこに保管されているのか分からない、保管場所は知っていても、書棚の奥深くや共有フォルダの階層の深い場所にあって探すのが手間、といった物理的なアクセス障壁も、マニュアルが読まれなくなる一因です。必要な時にすぐに手に取れない、開けない状態では、活用は進みません。
マニュアルを読む文化・習慣がない
組織として「業務の基本はマニュアルにある」「困ったらまずマニュアルを確認する」といった文化が醸成されていない場合、従業員が自発的にマニュアルを読むことは期待しにくいでしょう。また、業務時間内にマニュアルを読む時間が確保されていなかったり、読んでいると「暇なのか」と思われたりするような雰囲気があれば、なおさらです。
このような文化こそ、「不安全行動」を助長する根本原因です。行動科学でその文化を変革する方法を解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
更新・管理体制が整備されていない
マニュアルは一度作ったら終わりではありません。業務内容の変更、新しいツールの導入、法改正などに合わせて、定期的に内容を見直し、更新していく必要があります。
しかし、誰がいつどのように更新するのか、その体制やルールが明確になっていないと、情報はどんどん古くなり、形骸化してしまいます。古い情報しか載っていないマニュアルは、誰も読まなくなります。
>>「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書を見てみる
マニュアルが「読まれる化」されるための7つのポイント
マニュアルを「読まれない」状態から「読まれ、活用される」状態へと変えるためには、作成方法から運用体制、組織文化に至るまで、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、マニュアルを現場で読まれるようにするための具体的な7つのポイントを解説します。
1. 視覚的に分かりやすく、直感的に理解できる内容にする
文字ばかりのマニュアルは、読む気を削いでしまいます。図や写真、イラストを効果的に使用し、視覚的に分かりやすいデザインを心がけましょう。言語化しにくい複雑な手順や操作、実際の動きを伴う内容は、「映像」や「動画」を活用するのが非常に有効です。
映像や動画は、実際の動きやスピード感をそのまま伝えられるため、理解度が飛躍的に向上し、言語化しにくい業務プロセスや「勘所(カンコツ)」といった曖昧なニュアンスまで見える化します。一目見て直感的に内容が頭に入るような、分かりやすさを追求することが重要です。
例えば、自動車部品や住宅設備等のプラスチック成形品を手掛ける製造企業である「児玉化学工業株式会社」では、現場従業員が以下の動画マニュアル「ヤスリでバリを取る業務プロセスの解説」を作成し、技術をスムーズに共有しています。
▼直感的に理解できるマニュアルの例▼
※現場従業員が「tebiki」で作成
一目で「何をどうすればいいか」が把握でき、文字では伝えにくい動きもすべて理解できるようになっています。
実際に業務でどのような動画マニュアルが使われ、効果を上げているのか、具体的なサンプルを見てみたい方は、以下の資料「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」が参考になります。様々な現場のリアルな動画を見ることで、自社導入のイメージが掴めるはずです。
>>>「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」を見てみる
2. 読む目的とメリットを明確に伝える
従業員がマニュアルを読む動機付けとして、「なぜ読む必要があるのか」「読むことでどのようなメリットがあるのか」を明確に示すことが不可欠です。このマニュアルが「誰の」「どのような状況で」「何の役に立つのか」を冒頭で具体的に伝えましょう。
「この手順を習得すれば、作業時間が〇分短縮できる」「この知識があれば、お客様からの質問にスムーズに答えられる」など、読むことによる具体的な効果や、自身の仕事への貢献をイメージさせることで、自分ごととして捉えられ、読む意欲が高まります。
3. いつでも、誰でも、簡単に見つけられるようにする
マニュアルの保管場所は、ファイルサーバー、社内ポータル、情報共有ツールなどに一元化し、全従業員に周知徹底しましょう。ファイル名やフォルダ構成のルールを統一し、キーワード検索ですぐに目的の情報にたどり着けるようにすることも重要です。
PCだけでなく、現場で使うタブレットやスマートフォンからもアクセスしやすい環境を整えるなど、物理的・システム的なアクセス性を最大限に高める工夫が求められます。
誰でもアクセス可能なマニュアルの好事例として、冷凍食品の製造等を手掛ける「テーブルマーク株式会社」の取り組みが挙げられます。同社では、操作が複雑な機械にQRコードを貼り付け、タブレット等で読み込むだけで、誰でも簡単にその機械の操作方法を解説した動画マニュアルを閲覧できる仕組みを導入しています。
機械に動画マニュアルが閲覧できるQRコードを貼り付けて、わからないときにiPadでQRコードを読んでマニュアルが見られるような体制を作っています。QRコードを各機械に貼ることによって、自分で復習できるため、何度も繰り返し教育することがなくなりました。
同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
属人化業務の指導工数を83%削減!標準化教育により安心安全な食品を提供
4. 常に情報を最新の状態に保ち、信頼性を維持する
「このマニュアル、情報が古いんだよね」と思われた瞬間に、マニュアルの信頼性が薄れ、読まれなくなります。
業務手順の変更、新しいツールの導入、顧客からのフィードバックなどを反映し、定期的に内容を見直し、更新する体制を構築しましょう。誰がいつ更新するのか責任者を明確にし、改訂履歴も記録します。常に情報が最新かつ正確であることが、マニュアルが「使える」ツールとして信頼され、形骸化しないための大前提です。
「作って終わり」にせず、現場で本当に活きるマニュアルを整備し、維持していくための具体的な方法論や体制づくりについては、「『作って終わり』にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書(pdf)」で詳しく解説しています。マニュアルの形骸化にお悩みのご担当者様は、以下をクリックして、ぜひご一読ください。
>>「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書を見てみる
5. 実際に利用する従業員の意見を取り入れ、継続的に改善する
マニュアルは、作成者の自己満足であってはなりません。実際にマニュアルを使う従業員の意見こそが、最も価値のある改善のヒントです。「この部分が分かりにくい」「こういう情報も載せてほしい」「この手順は現状と違う」といったフィードバックを定期的に収集する仕組みを作りましょう。
アンケートやヒアリング、質問しやすい雰囲気づくりを通じて従業員の声に耳を傾け、それを反映して継続的にマニュアルを改善していくサイクルを回すことが、真に業務で役立つマニュアルへの近道です。
現場の意見を反映させることで、初めてマニュアルは自己満足を脱し、「現場で使われる」ものになります。そのための作成ポイントと、「カンコツ」を伝える秘訣がこちらです。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
6. マニュアルを活用する文化と時間的余裕を作る
どんなに優れたマニュアルを整備しても、組織に「マニュアルを見るのは当たり前」という文化がなければ、活用は定着しません。経営層や管理職が率先してマニュアルの重要性を発信し、自らも活用する姿勢を示すことが効果的です。
また、業務時間内にマニュアルを確認する時間を確保したり、新人研修にマニュアル学習を組み込んだりするなど、マニュアルに触れる機会を意図的に設けることも重要です。「困ったらまずマニュアル」が自然な行動となるような、組織的な後押しと心理的な余裕が必要です。
「困ったらまずマニュアル」という文化を育てることこそ、OJT担当者の負担を激減させる「OJT教育の新常識」の核心です。
>>OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識を見てみる
7. 汎用的なマニュアル作成ツールを活用する
分かりやすく、管理しやすいマニュアルを効率的に作成・維持するためには、適切なツールの活用も検討しましょう。WordやExcel、PowerPoint等、一般的に使われている汎用ツールを活用してマニュアルを整備するのは1つの手段です。
特にPowerPointは簡易的な動画マニュアルも作れるので、おすすめです。資料「パワーポイントで実践する動画マニュアル作成ガイド(pdf)」では、パワーポイントで動画マニュアルを作る方法について解説動画付きでまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。
>>パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順~現場ですぐ使えるコツ付き~を見てみる
読まれるマニュアル作りに成功した企業や現場の事例
ここからは、「もともとマニュアルが読まれない課題」を抱えていたところから、「マニュアルが読まれるようになった」企業や現場の成功事例を紹介します。具体的な改善方法もあわせて触れているので、参考にしてみてください。
以下も併せてご覧ください。
【総合建設業】株式会社安藤・間:読まれない紙マニュアルを刷新
総合建設業である「株式会社安藤・間」では、膨大なマニュアルが整備されていたものの、従業員に読んでもらえないという課題に直面していました。
数十〜数百ページと膨大になる紙マニュアルを熟読し理解する時間を確保することは非常に困難です。そのため、紙マニュアルでは「思うように浸透しない」「作成しても読んでもらえない」といった「紙マニュアルの限界」を感じていました。
そこで同社は、動画によるマニュアルに刷新し、現場で使われるマニュアル体制を実現しました。また、使用している動画マニュアル作成ツールも、必要最低限の機能のみが搭載されているツール(tebiki現場教育)を選定しており、マニュアルの作成工数自体も紙に比べて大幅に削減できています。
同社の「読まれるマニュアル作り」に関する詳細な事例は、以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
建設現場で使用するシステムの「利用者からの問合せ」や「新システムの普及展開」に関わる工数を8割削減!
【小売業】株式会社いなげや:新人に読まれない「分厚いマニュアル」から電子マニュアルへ
食品スーパーを手掛ける「株式会社いなげや」では、新入社員にマニュアルが読まれないことから、教育工数の圧迫に課題を感じていました。
新人トレーニング中は、教える側の人は業務ができなくなりますよね。時間がない中でトレーニングするのが大変なので「何か見るものがあれば便利だよね」という声はありました。紙の分厚いマニュアルはあったんですけど、新人さんには引かれちゃってました。「ちょっとレジ打ってくるから、自分で見といて」と分厚いマニュアルを渡されても、新人さんとしてもきついですよね。実際、うちの新人さんの離職率は高かったかもしれません・・・。
接客業の教育トレーニングは、どうしても動きが伴う業務プロセスを説明する必要があるため、同社は「文字や図解による手順書」よりも「映像によるマニュアル整備」が効果的であると考え、動画マニュアルを導入しました。結果的にスピーディなトレーニングが実現できているだけでなく、全店舗に同じ教育品質を展開できているので、従業員の標準化も図れています。
同社の「読まれるマニュアル作り」に関する詳細な事例は、以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
133店舗ある小売業の現場で動画を活用。スピーディな店舗教育を実現し、地域に愛されるスーパーであり続ける。
【飲食業】株式会社ハングリータイガー:調理や接客の「動き」を動画で伝え、教育工数を削減
ハンバーグ・ステーキレストランをチェーン展開する「株式会社ハングリータイガー」では、紙マニュアルでは調理手順や接客における細かな所作が伝わりにくく、教育の非効率性や品質のばらつきに課題を感じていました。
動画マニュアルtebikiを導入する以前は、紙マニュアルで社員やスタッフの教育をしていましたが、文字情報だけでは業務手順が伝わりにくく、接客における細かい所作、調理手順など人の動きである「業務ノウハウ」の部分が特に伝わらないなと感じていました。
伝わらない部分はOJTを行い、新しく人が入る度に同じOJTを繰り返して実施し、非効率だなと感じていましたし、また、人によって教え方や教え方の丁寧さなどにムラがあり、業務品質に不安を感じていました。
過去に動画マニュアルの内製化を試みたものの、動画編集スキルの問題や業務の属人化、共有リスクなどから断念した経験もあったといいます。
そこで、編集が容易で教育管理機能も備えた動画マニュアルツール(tebiki現場教育)を導入。結果、「動画を見ておいて」の一言でマニュアルが読まれるようになり、OJTの工数が大幅に削減されました。動画によって調理未経験のアルバイトスタッフでも業務をスムーズに習得できるようになり、スタッフの習熟度が向上。
従業員が自ら動画を見て予習・復習する動きも見られるようになったそうです。また、マニュアル作成自体の工数削減にも繋がりました。
同社の「読まれるマニュアル作り」に関する詳細な事例は、以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
マニュアル作成やOJTの工数削減!接客の所作や業務の動きを伝えるには動画がベスト
まとめ
マニュアルが読まれない状況は、単に従業員の意識の問題として片付けるのではなく、その根本にある原因を多角的に捉えることが重要です。「読まない人」がいる背景には、マニュアル自体の分かりにくさやアクセスの悪さ、そしてマニュアルを活用する文化や仕組みの欠如が存在する可能性があります。
この記事で解説した「読まれない原因」と「読まれる条件」、そして「具体的な対策」を参考に、ぜひマニュアル運用を見直してみてください。
特に、動きや手順、言葉にしにくい業務プロセスは、文字や図解だけでなく、動画マニュアルという手段を取り入れることが、理解を深め、マニュアルを「読まれる化」するための非常に有効なアプローチとなります。
動画マニュアルの具体的な推進方法や活用事例についてまとめられた資料「はじめての動画マニュアル作成ガイド」を参考に、読まれるマニュアル作りを検討してみてください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。




