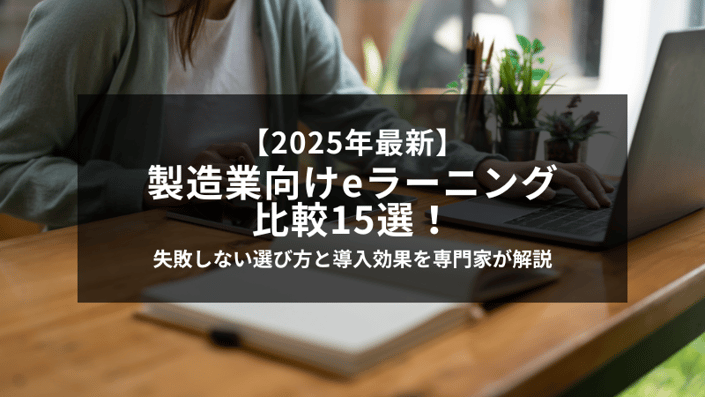

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
製造業向け動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開するTebiki株式会社です。
「製造現場の人材育成、何から手をつければいいのか…」 「熟練者の技術を、どうすれば若手にうまく伝えられるだろうか?」 「複数の工場で、教育レベルに差が出てしまっている…」
このような悩みを背景に、時間や場所を選ばずに効率的な教育を実現できる「eラーニング」や「教育ツール」に注目が集まっています。導入によって、教育コストの削減や内容の均質化、ひいては従業員のスキルアップや生産性向上といった効果が期待できるため、多くの製造業で活用が始まっています。
そこでこの記事では、製造業におすすめのeラーニングや教育ツールをまとめて紹介します。
本記事でおすすめする教育ツールの一つとして、まずご紹介したいのが、現場教育に特化したツール「tebiki」です。熟練者の技術伝承や教育の均質化といった、製造業ならではの課題解決に貢献します。
目次
- 1.【2026年最新】製造業におすすめのeラーニングシステム・教育ツール徹底比較15選
1-1. tebiki現場教育 (Tebiki株式会社)
1-2. Tech e-L (日本アイアール株式会社)
1-3. Cross Learning (株式会社クロスリンク)
1-4. TechラーニングPlat. (株式会社コガク)
1-5. 学び~と (SATT株式会社)
1-6. e-JINZAI for maker ((株)ビズアップ総研)
1-7. eラーニングライブラリ ((株)JMAM)
1-8. Cloud Campus ((株)サイバー大学)
1-9. Platon (ロゴスウェア株式会社)
1-10. Smart Boarding ((株)FCEトレーニングC)
1-11. Udemy Business (Udemy, Inc.)
1-12. AirCourse (KIYOラーニング株式会社)
1-13. schooビジネスプラン (株式会社Schoo)
1-14. learningBOX (learningBOX株式会社)
2.製造業におけるeラーニング・教育ツールの活用シーンと成功事例
2-1. 事例1:【技術継承】熟練工の暗黙知を動画マニュアル化し若手へ伝承
2-2. 事例2:【安全教育】映像による注意喚起で安全意識を向上
2-3. 事例3:【新人研修】OJT内容を動画化しトレーナー負荷軽減と早期戦力化を実現
3.製造業向けのeラーニングは「内製支援型」がおすすめな理由
3-1. パッケージ型eラーニングの限界:現場とのギャップ
3-2. 内製支援型がもたらす3つの大きなメリット
3-3. 内製支援型eラーニングのおすすめは「動画マニュアル」
4.なぜ今、製造業でeラーニング・教育ツールの活用が加速しているのか?
4-1. 人材育成・技術継承の深刻化する課題
4-2. DX化、コンプライアンス強化…変化への対応が急務
4-3. eラーニング・教育ツールが製造業の課題を解決する仕組み
5.製造業におけるeラーニング・教育ツール導入のメリット・デメリット
5-1. 導入で得られる主要メリット
5-2. 知っておくべきeラーニング導入のデメリットと注意点
6.【補足】製造業のeラーニングで使える無料の教材
6-1. 品質管理に関するeラーニング教材
6-2. 人材育成に関するeラーニング教材
6-3. 安全教育に関するeラーニング教材
6-4. 生産性向上に関するeラーニング教材
7.まとめ:最適な教育ツールで製造業の現場力を最大化する
【2026年最新】製造業におすすめのeラーニングシステム・教育ツール徹底比較15選
現在、製造業での活用が期待できる主要なeラーニングシステムおよび教育ツールは多岐にわたります。ここでは、その中から15のサービス・ツールを厳選し、比較形式でご紹介します。
選定のポイントは、教材があらかじめ用意されている「パッケージ型」と、自社で教材を作成・共有する「内製支援型」のどちらが自社にとって適切かを見定めることです。
製造業の場合、基本的には「内製支援型」のeラーニング・教育ツールがおすすめです。すでに用意されているeラーニング教材は、どの現場にでも当てはまる汎用性の高いコンテンツが収録されている分、「自社で応用がきかない」ことが多いからです。
|
サービス名 |
タイプ |
主な特徴 |
無料トライアル |
|
内製支援 |
スマホで簡単動画マニュアル作成・共有、自動翻訳、習熟度管理 |
あり |
|
|
パッケージ/カスタム |
製造業技術スキル特化、オーダーメイド教材作成可能 |
あり |
|
|
パッケージ/カスタム |
製造・物流特化、多言語対応、派遣向けにも強み |
あり |
|
|
パッケージ |
技術者育成実績豊富、2000超コンテンツ受け放題、多言語対応 |
あり |
|
|
パッケージ/内製支援 |
自社教材作成容易、柔軟な受講管理が可能 |
あり |
|
|
パッケージ |
DX、実務、階層別など製造業・メーカー向けコース多数 |
あり |
|
|
パッケージ/内製支援 |
大手企業導入多数、コースが豊富 |
あり |
|
|
パッケージ/内製支援 |
ユーザー数無制限プランあり、動画・アニメーション教材作成機能 |
あり |
|
|
パッケージ/内製支援 |
PowerPointから教材作成、多機能LMS、低価格プランあり |
あり |
|
|
パッケージ |
ライブ型オンライン研修、アウトプット重視、豊富な汎用コンテンツ |
あり |
|
|
パッケージ |
豊富なコース、最先端分野に強い、実績多数 |
あり |
|
|
|
パッケージ/内製支援 |
標準コース受け放題、動画マニュアル作成機能、簡単な操作性 |
あり |
|
パッケージ |
オンライン集合学習、ビジネス/DX系スキルコンテンツ豊富 |
要問合せ |
|
|
パッケージ/内製支援 |
低価格(無料プラン有)、教材作成自由度高い、機能豊富 |
あり |
比較表で概要を掴んだところで、各サービス・ツールの特徴をもう少し詳しく見ていきましょう。ここでは、特に注目度の高いサービスや特徴的なサービスを中心に解説します。
tebiki現場教育 (Tebiki株式会社)
自社で動画マニュアルが作成できるツール「tebiki現場教育」は、製造業向けeラーニングとして最もおすすめです。製造業の業務工程や安全に対する教育をすべて動画におさめ、動画マニュアル化し、新入社員が視聴するような活用イメージになります。
- タイプ:内製支援
- 主な特徴:スマホで簡単動画マニュアル作成・共有、自動翻訳、習熟度管理
- 無料トライアル:あり
パッケージ化されたeラーニング教材は、汎用性が高い分、どうしても自社の現場状況や業務内容と乖離が生まれてしまうことが多いです。そうすると、基本的な知識は身に付いたとしても、現場で即戦力を発揮できるかというとそうではありません。ゆえに、tebiki現場教育のような、自社でマニュアルや動画コンテンツを作成できる体制づくりが重要だと言えます。
tebiki現場教育の最大の特徴は以下のとおりです。
- 現場従業員が抵抗なく使える、圧倒的な「簡単さ」
- オンラインで全拠点から最新教材にアクセス可能
- 100か国以上の外国語に自動翻訳
- 学習状況やスキル習熟度の可視化
普段お使いのスマートフォンやタブレットで作業風景を撮影し、tebikiにアップロード。あとは、直感的な操作で不要部分をカットしたり、注目してほしい箇所に図形やコメントを入れたりするだけ。動画編集の経験や技術は一切必要ありません。
例えば化学メーカーの「児玉化学工業株式会社」では、tebiki現場教育を導入したことによって、手順書作成の工数が紙マニュアルに比べて3分の1になり、動画マニュアルを教育に組み込んで日々従業員が視聴するような教育体制を整備しています。
▼動画マニュアル導入企業のインタビュー▼
このように、tebikiは教材作成の容易さ、現場への即応性、スピーディな外国人教育、教育効果の可視化といった点で、従来のOJTやパッケージ型eラーニングが抱えていた課題を解決します。
特に、技術継承、新人教育の効率化、安全意識の向上、多拠点での標準化といった課題を持つ製造業にとって、強力な武器となるでしょう。費用面でも、パッケージ型に比べてコストパフォーマンスが高い点も魅力です。
動画マニュアル型eラーニング「tebiki現場教育」のサービス資料は、以下をクリックしてダウンロード可能です。参考にしてみてください。
Tech e-L (日本アイアール株式会社)
技術知識・業務知識の習得、実務スキル向上のための講座など、技術者向けの専門性の高いコンテンツから、研究開発、設計、生産技術、設備技術、品質保証、購買・調達、技術営業など、製造業に関わる職種を幅広くカバーしたコンテンツまで提供しているのが特徴です。
- タイプ:パッケージ/カスタム
- 主な特徴:製造業技術スキル特化、オーダーメイド教材作成可能
- 無料トライアル:あり
さらに、100以上の講座から、自社に必要な講座だけをピックアップして組み合わせすることが可能です。受講順も教育担当者様ご自身で決められます。特定の専門技術を深く掘り下げたい、あるいは市販の教材では対応できない独自の教育ニーズがある企業に適しています。
Cross Learning (株式会社クロスリンク)
製造業および物流業に特化したeラーニングサービスです。
- タイプ:パッケージ/カスタム
- 主な特徴:製造・物流特化、多言語対応、派遣向けにも強み
- 無料トライアル:あり
ヒューマンスキルやものづくり教育など、基礎的な内容が多い講座となっています。また、英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語に対応しているため、海外拠点を持つ企業や外国人従業員が多い企業にとっては有力な選択肢となるでしょう。派遣経験の長いスタッフにも対応しています。
TechラーニングPlat. (株式会社コガク)
55年以上の技術者育成実績を持つコガクが提供する、製造業技術者向けのeラーニング受け放題サービスです。
- タイプ:パッケージ
- 主な特徴:技術者育成実績豊富、2000超コンテンツ受け放題、多言語対応
- 無料トライアル:あり
製造業で必要とされる様々な技術分野を幅広くカバーしており、2000を超える豊富なコンテンツが強み。多言語対応に加え、講師に直接質問できるWebセミナーやオーディオブックなど、多様な学習スタイルを提供している点も特徴です。体系的かつ広範な技術教育を行いたい企業に向いています。
学び~と (SATT株式会社)
自社オリジナルの教材作成・活用を重視する企業向けのeラーニングシステムです。
- タイプ:パッケージ/内製支援
- 主な特徴:自社教材作成容易、柔軟な受講管理が可能
- 無料トライアル:あり
PowerPointなどの既存資料から簡単に教材を作成できます。パッケージ型の汎用コンテンツも用意されていますが、どちらかというと内製化支援に強みを持つサービスと言えます。
- 公式サイトリンク: https://www.manabeat.com/
e-JINZAI for maker ((株)ビズアップ総研)
製造業・メーカー向けに特化したeラーニングサービスです。
- タイプ:パッケージ
- 主な特徴:DX、実務、階層別など製造業・メーカー向けコース多数
- 無料トライアル:あり
DX研修、製造業実務研修(バリューチェーンなど)、階層別研修、課題別テーマ研修など、製造業で求められる知識・スキルに関するコースを幅広く網羅しているのが特徴です。体系的な知識習得を目的とする場合に適しています。
- 公式サイトリンク: https://www.ejinzai.jp/maker/
eラーニングライブラリ ((株)JMAM)
日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)が提供する、大手企業を中心に多くの導入実績を持つ総合eラーニングサービスです。
- タイプ:パッケージ/内製支援
- 主な特徴:大手企業導入多数、コースが豊富
- 無料トライアル:あり
ビジネススキル全般と製造業向けの技術系講座(生産管理、電気・制御、設備保全など)が豊富です。信頼性や実績を重視する企業に適しています。
Cloud Campus ((株)サイバー大学)
ソフトバンクグループのサイバー大学が提供するLMSです。
- タイプ:パッケージ/内製支援
- 主な特徴:ユーザー数無制限プランあり、動画・アニメーション教材作成機能
- 無料トライアル:あり
ユーザー数無制限で利用できる月額固定料金プランがあり、従業員数の多い企業にとってはコストメリットが大きいのが特徴です。動画やアニメーションを用いた教材を比較的簡単に作成できる機能も搭載しており、内製化支援の側面も持ち合わせています。
- 公式サイトリンク:https://cc.cyber-u.ac.jp/index.html
Platon (ロゴスウェア株式会社)
教材作成ツールと高機能なLMSを提供するシステムです。
- タイプ:パッケージ/内製支援
- 主な特徴:PowerPointから教材作成、多機能LMS、低価格プランあり
- 無料トライアル:あり
PowerPointから簡単にeラーニング教材を作成できるツールが特徴で、自社教材中心の運用を考えている企業に向いています。LMS機能も充実しており、低価格から利用できるプランも用意されています。製造業での導入実績もあります。
- 公式サイトリンク: https://platon.logosware.com/
Smart Boarding ((株)FCEトレーニングC)
録画された動画コンテンツだけでなく、ライブ形式のオンライン研修やディスカッションなど、アウトプットを重視した学習体験を提供しているのが特徴です。
- タイプ:パッケージ
- 主な特徴:ライブ型オンライン研修、アウトプット重視、豊富な汎用コンテンツ
- 無料トライアル:あり
全体としてはビジネススキルや階層別研修など、幅広い業界に対応した内容が中心です。
- 公式サイトリンク:https://www.smartboarding.net/
Udemy Business (Udemy, Inc.)
世界最大級のオンライン学習プラットフォーム「Udemy」の法人向けサービスです。
- タイプ:パッケージ
- 主な特徴:豊富なコース、最先端分野に強い、実績多数
- 無料トライアル:あり
IT、ビジネス、デザインなど豊富なコースが提供されており、製造業に関連するコースも含まれています。最新技術に関するコースが多いのも特徴です。従業員の自律的なスキルアップを支援する目的での導入に適しています。
- 公式サイトリンク:https://ufb.benesse.co.jp/
AirCourse (KIYOラーニング株式会社)
「スタディング」で知られるKIYOラーニングが提供する法人向けeラーニングです。
- タイプ:パッケージ/内製支援
- 主な特徴:標準コース受け放題、動画マニュアル作成機能、簡単な操作性
- 無料トライアル:あり
受け放題の標準コース(ビジネスマナー、コンプライアンス等)に加え、簡単な動画マニュアル作成機能も搭載されているのが特徴です。操作性のシンプルさも評価されています。標準的な知識習得と、簡易的な動画マニュアル作成の両方を行いたい場合に検討できます。
- 公式サイトリンク: https://aircourse.com/
schooビジネスプラン (株式会社Schoo)
オンライン集合学習が特徴的なサービスです。
- タイプ:パッケージ
- 主な特徴:オンライン集合学習、ビジネス/DX系スキルコンテンツ豊富
- 無料トライアル:要問合せ
ビジネススキルから政治・経済・金融・デザイン、プログラミング、 DX、AIから哲学まで全21カテゴリの幅広い領域を網羅しています。製造業に特化した内容は少ないですが、従業員のデジタルリテラシー向上やビジネススキル強化を目的とする場合に活用できます。
- 公式サイトリンク: https://schoo.jp/biz/
learningBOX (learningBOX株式会社)
低価格(無料プランあり)と教材作成の自由度の高さが特徴のLMSです。
- タイプ:パッケージ/内製支援
- 主な特徴:低価格(無料プラン有)、教材作成自由度高い、機能豊富
- 無料トライアル:あり
クイズやテスト、レポート、アンケート、認定証発行など、学習管理に必要な機能も豊富に備わっています。自社で教材を自由に作成・登録し、コストを抑えてeラーニングを始めたい企業に適しています。
- 公式サイトリンク: https://learningbox.online/
製造業におけるeラーニング・教育ツールの活用シーンと成功事例
eラーニングや教育ツールは、製造業が抱える様々な課題解決に具体的にどう役立つのでしょうか? ここでは、代表的な活用シーンと、それによって期待される効果を実際の事例に沿ってご紹介します。
事例1:【技術継承】熟練工の暗黙知を動画マニュアル化し若手へ伝承
eラーニングによって解消が期待できる課題の1つ目に、「技術継承」が挙げられます。
例えば、自動車部品や住宅設備等のプラスチック成形品を手掛ける製造企業である「児玉化学工業株式会社」では、現場従業員が以下の動画マニュアル「ヤスリでバリを取る業務プロセスの解説」を作成し、技術をスムーズに共有しています。
▼eラーニング(動画マニュアル)技術継承の例▼
※「tebiki」で作成されています
一目で「何をどうすればいいか」が把握でき、文字では伝えにくい動きもすべて理解できるようになっています。熟練工の動きをそのまま映像におさめることで、「技術の見える化」を実現しています。
事例2:【安全教育】映像による注意喚起で安全意識を向上
某食品製造会社の現場では、動画マニュアルによって安全意識を向上させる教育体制を整備しています。同社で実際に活用されている動画マニュアルを以下に掲載します。
▼eラーニング(動画マニュアル)による危険周知の例▼
※「tebiki」で作成されています
このように、作業の危険性や正しい手順を動画におさめ、教育することで、従業員の安全性を高めています。文字や画像だけでは危険性が伝わりにくいので、映像を使ったeラーニングは現場の安全度にも寄与するといえるでしょう。
事例3:【新人研修】OJT内容を動画化しトレーナー負荷軽減と早期戦力化を実現
eラーニングは、OJT教育の様子をそのまま映像に残すことで、教育担当者の教育工数を削減する、という活用方法も可能です。
例えば以下の動画は、工作機械や遠心力鋳造管・産業機械の製造/販売を手掛ける「新日本工機株式会社」の現場従業員が作成した動画マニュアルです。スマートフォンで撮影しています。
※「tebiki」で作成されています
このように、eラーニングによる教育体制が整備されていれば、教育担当者のOJTに大きく依存せずとも新人教育が可能になります。
OJT担当者に大きく依存しない教育体制の構築こそ、その負担を激減させる「OJT教育の新常識」です。
>>OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識を見てみる
製造業向けのeラーニングは「内製支援型」がおすすめな理由
さて、ここまでeラーニングや教育ツールの比較、活用シーンを見てきました。
その中で、「パッケージ型」と「内製支援型」という2つのタイプがあることに触れましたが、特に製造業の現場における実践的な教育においては、後者の「内製支援型」が非常に有効であると私たちは考えています。
ここからはその理由について、詳しくご紹介します。
パッケージ型eラーニングの限界:現場とのギャップ
パッケージ型は、ビジネスマナー、コンプライアンス、あるいは特定の専門分野に関する体系的な知識を効率よく学ぶには非常に便利です。多くの企業で共通して必要とされる内容であれば、自社で教材を作成する手間なく、質の高い教育をすぐに始められます。
しかし、製造現場の実践的なスキルやノウハウとなると、話は少し変わってきます。パッケージ型の教材は、どうしても一般的・汎用的な内容にならざるを得ません。そのため、以下のような「現場とのギャップ」が生じやすくなります。
設備や手順の違い
教材で説明されている機械や工具、作業手順が、自社のものと完全に一致しない場合があります。「うちのやり方とは違う」と感じた瞬間、学習効果は薄れてしまいます。
暗黙知の欠如
教科書的な説明は理解できても、現場で本当に重要な「この作業のコツ」「この異音は危険信号」といった、言葉にしにくい感覚や経験則(暗黙知)まではカバーしきれません。
変化への追随
日々改善が進む製造現場では、作業手順や使用する部品が変わることも珍しくありません。パッケージ教材の内容が、常に最新の現場状況を反映しているとは限りません。
当事者意識の希薄化
「どこか他人事」と感じてしまい、学習内容を自分自身の業務に結びつけて考える意欲が湧きにくい可能性があります。
もちろん、これはパッケージ型eラーニングを否定するものではありません。目的によっては非常に有効なツールです。しかし、現場のOJTを補完・代替したり、固有の技術を確実に継承したりするという目的においては、その限界も認識しておく必要があるでしょう。
パッケージ型では伝わらない、自社固有の手順や「暗黙知」。その課題を解決し、現場に最適化された教育を実現するツール「tebiki」の概要資料がこちらです。
内製支援型がもたらす3つの大きなメリット
そこでおすすめなのが、現場の担当者が主体となってeラーニング教材を作成する「内製化」です。
メリット1:圧倒的な実践性と納得感
最大のメリットは、自社の現場に100%マッチした教材を作れることです。自分たちが毎日使っている設備、実際に行っている作業手順、守るべき安全ルール、その全てをありのままに教材化できます。学習者は「これは自分の仕事の話だ」とすぐに理解でき、学んだことが即座に実践に活かされます。
さらに、現場で培われた改善ノウハウや、ベテランが持つ独自の工夫、過去の失敗から得た教訓なども、動画であれば具体的に記録し、組織全体の貴重な財産として共有できます。
メリット2:作成・更新のスピードと容易性
かつては「教材の内製化は時間もコストもかかる」というイメージがありましたが、今はツールによっては手軽に作成できるようになっています。
例えば「tebiki現場教育」のような動画マニュアル作成ツールは、現場の担当者がスマートフォン1つで撮影し、手軽に編集が可能なため、製造業の現場教育ツールとして多くの現場に導入されています。
これにより、現場での改善活動や手順変更にも迅速に対応できます。「手順が変わったから、すぐにマニュアルを修正して展開する」といったことが、現場レベルでスピーディに行えるようになるのです。
メリット3:高い費用対効果
パッケージ型eラーニングで多くのコースを利用したり、多数のIDを発行したりする場合と比較して、トータルコストを抑えられる可能性があります。内製支援ツールは、比較的安価な月額料金で利用できるものが多く、教材作成自体に追加費用はかかりません。(※初期費用やストレージ容量による変動はあります)
一度作成した動画マニュアルは、社内の資産として半永久的に、何度でも、何人でも活用できます。従業員数が多いほど、一人あたりの教育コストは低減していきます。
本文中でご紹介した、教材の内製化がもたらす3つのメリットを簡単に実現するツール「tebiki」について、その概要をまとめた資料をご用意しました。
内製支援型eラーニングのおすすめは「動画マニュアル」
なぜ、内製化の中でも特に「動画マニュアル」が製造現場に適しているのでしょうか? それは、動画が持つ「見てわかる」という圧倒的な情報伝達能力にあります。
「動画マニュアルで現場教育を改善したいが、具体的にどう推進すればいいか分からない」場合は、以下の資料「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」を参考にすると、導入推進のイメージがつきやすくなります。以下をクリックして、ダウンロードしてみてください。
暗黙知の見える化
熟練者の滑らかな手の動き、絶妙な力加減、視線の配り方、作業リズム… これらは文章や写真だけでは到底伝えられません。動画なら、これらの非言語的な情報、いわば「暗黙知」をそのまま記録し、伝達することが可能です。「見て学ぶ」ことの重要性が高い製造現場のスキル習得において、これ以上の教材はありません。
動画で「暗黙知」を見える化することこそ、「技術伝承」を成功させるための最も重要なポイントです。その具体的な進め方を以下の資料で解説します。
OJTの質の向上と効率化
動画マニュアルがあれば、OJT指導者は基本的な手順説明に時間を取られることなく、より高度な判断や応用的なスキル、個別指導に集中できます。また、指導者による教え方のバラつきをなくし、教育の標準化を実現します。結果として、OJT全体の質と効率が向上します。
OJTの質と効率を高めることこそ、OJT担当者の負担を激減させる「OJT教育の新常識」です。
>>OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識を見てみる
言語・経験の壁を超える
正確な作業手順を映像で示すことで、外国人従業員や経験の浅い新人でも、言葉の説明だけでは理解しにくい内容を直感的に把握できます。tebikiのような自動翻訳機能付きのツールを使えば、多言語対応も容易になり、グローバルな人材育成にも大きく貢献します。
言語の壁がある「外国人社員の教育課題」は、まさに「動画マニュアルで解決できる」ことを、以下の資料で詳しく解説します。
>>外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!を見てみる
反復学習と知識定着
わからない箇所があれば、いつでも、何度でも動画を見返すことができます。自分のペースで確実に理解を深められるため、学習効果が高まり、知識やスキルの定着につながります。
このように、動画マニュアルは、製造現場における教育のあり方を根本から変える可能性を秘めているのです。
「動画マニュアルで現場教育を改善したいが、具体的にどう推進すればいいか分からない」場合は、資料「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」を参考にすると、導入推進のイメージがつきやすくなります。下のリンクをクリックして、ダウンロードしてみてください。
>>>「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」を読んでみる
なぜ今、製造業でeラーニング・教育ツールの活用が加速しているのか?
記事の前半では、具体的なeラーニング・教育ツールの比較や、教材内製化のメリットについて解説しました。ここで改めて、なぜ多くの製造業がeラーニングや教育ツールの導入に踏み切っているのか、その背景にある根本的な課題を整理しておきましょう。自社が抱える課題と照らし合わせることで、ツール導入の目的意識がより明確になります。
人材育成・技術継承の深刻化する課題
多くの製造現場では、長年にわたり人材に関する課題が指摘されてきましたが、近年その深刻度は増すばかりです。
まず、多様化する働き方と教育の難しさがあります。工場が国内や海外に点在していたり、24時間稼働によるシフト勤務が常態化していたりすると、従来のように従業員全員を一箇所に集めて研修を行うこと自体が物理的に困難になっています。
次に、技術継承の危機です。日本の製造業を支えてきた熟練技術者の方々が次々と引退を迎える中で、彼らが長年の経験で培ってきた貴重な知識やノウハウ、いわゆる「暗黙知」が失われてしまうリスクが現実のものとなっています。これをいかに効率よく、そして確実に次世代へと引き継いでいくかは、多くの企業にとって喫緊の経営課題と言えるでしょう。
また、実践的なスキル習得に不可欠なOJTにも限界が見えています。指導を担当する従業員によって教え方や熱意に差が出やすく、教育の質が「属人化」してしまう傾向があります。結果として、体系的な知識や理論が十分に伝わらなかったり、間違ったやり方が受け継がれてしまったりする可能性も否定できません。加えて、指導者の業務負担が大きいことも課題です。
さらに、慢性的な人手不足の中で、新しく入社した人材には一日も早く現場で活躍してもらわなければなりません。そのためには、基礎的な知識やスキルを効率的かつ効果的に習得させ、スムーズに現場へ適応させるための早期戦力化の仕組みが強く求められています。
>>製造業の現場教育に「動画マニュアル」を活用すべき理由を見てみる
DX化、コンプライアンス強化…変化への対応が急務
加えて、製造業を取り巻く外部環境の変化も、新たな教育の必要性を生み出しています。
その筆頭がDX(デジタルトランスフォーメーション)の急速な進展です。工場のスマート化を目指し、IoTデバイスの導入、AIを活用した画像検査システム、生産ラインの自動化・ロボット化などが進められています。しかし、これらの新しい技術を導入するだけでは不十分であり、それを正しく理解し、使いこなし、さらにはデータを活用して改善活動につなげられる人材の育成が追いついていないという現実があります。
また、コンプライアンスに対する要求の高まりも見逃せません。安全衛生に関する規制は年々強化され、環境問題への配慮も企業にとって必須の取り組みとなっています。品質基準はより厳格になり、ハラスメント防止といった職場環境の整備も重要性を増しています。これら多岐にわたるルールや規範を、全従業員に正しく理解させ、遵守させるための教育は、今や企業の存続に関わる重要事項です。
さらに、グローバルな競争の激化と変化のスピードも、継続的な学習を不可欠にしています。国内外の競合他社に打ち勝つためには、常に生産性や品質レベルを向上させ続ける努力が必要です。また、市場のニーズや関連技術のトレンドは目まぐるしく変化するため、従業員も常に自身の知識やスキルをアップデートし、変化に柔軟に対応していく必要があります。
eラーニング・教育ツールが製造業の課題を解決する仕組み
このような複雑化する課題に対し、eラーニングや教育ツールは、その特性を活かして有効な解決策を提供します。
最大の利点は、インターネット環境さえあれば、時間や場所に縛られずに学習できる柔軟性です。これにより、多拠点展開やシフト勤務といった物理的な制約を乗り越え、全ての従業員に対して公平な学習機会を提供することが可能になります。
また、全員が同じ質の高い教材で学習することで、教育内容の標準化と質の担保が実現します。特に動画マニュアルなどを活用すれば、作業手順を誰が見ても同じように理解できるようになり、属人化を防ぎ、業務品質の安定化に貢献します。
さらに、言葉だけでは伝えきれない熟練者の技術や現場で培われたノウハウを、動画などのデジタルデータとして記録・蓄積できる点も大きなメリットです。これにより、貴重な知識が組織全体の共有財産となり、効率的な技術継承が進みます。
加えて、LMS(学習管理システム)を活用すれば、従業員一人ひとりの学習状況や理解度をデータとして正確に把握できます。これにより、個々のレベルに応じた適切なフォローアップや、効果測定に基づいた計画的な人材育成が可能になります。
そして、文章や静止画だけでは伝わりにくい複雑な作業手順や、危険箇所の注意喚起なども、動画、アニメーション、VR/ARといった多様な表現方法を用いることで、より直感的で分かりやすく、学習効果の高い情報伝達が実現します。
このように、eラーニングや教育ツールは、その機能と特性を活かすことで、製造業が直面する構造的な課題に対応し、人材育成をより効率的かつ効果的に、そして戦略的に進めるための強力な基盤となり得るのです。
製造業におけるeラーニング・教育ツール導入のメリット・デメリット
eラーニングや教育ツールの導入は、多くのメリットをもたらしますが、一方で注意すべき点も存在します。導入を成功させるためには、これらの両側面を事前にしっかりと理解しておくことが極めて重要です。
導入で得られる主要メリット
まず、導入によって企業が得られる主なメリットについて、具体的に見ていきましょう。
コスト削減効果
集合研修を実施する場合、会場費、外部講師への謝礼、参加者の交通費や宿泊費、資料の印刷費など、様々なコストが発生します。eラーニングや教育ツールを導入すれば、これらの直接的な費用を大幅に削減できます。さらに、従業員が研修場所へ移動する時間や、研修を受けている間の人件費といった間接的なコストも削減できるため、トータルで見ると非常に大きな費用削減効果が期待できます。
教育の効率化と質の向上
従業員は、業務の都合や自身の理解度に合わせて、自分の好きな時間に、自分のペースで学習を進めることができます。分からない箇所は納得できるまで何度でも繰り返し学習できるため、知識やスキルの定着率向上が期待できます。また、全ての従業員が標準化された同じ教材で学習するため、指導者による教え方のバラつきがなくなり、教育内容の均質化が図れます。これにより、組織全体のスキルレベルの底上げにつながります。特に動画マニュアルなどを活用すれば、従来時間のかかっていたOJTの効率化や質の向上にも大きく貢献します。
学習進捗管理の容易化
多くのeラーニングシステムや教育ツールには、LMS(学習管理システム)機能が搭載されています。これを活用することで、「誰が、どの研修(教材)を、いつ、どこまで学習したか」「テストの点数は何点だったか」といった情報を、データとして正確かつ簡単に把握・管理できます。これにより、教育計画全体の進捗管理はもちろん、個々の従業員の理解度に応じた適切なフォローアップや、次のステップとなる育成プランの立案などが、より客観的かつ効率的に行えるようになります。
技術・ノウハウ継承の促進
製造現場における最大の課題の一つが、熟練技術者が持つ貴重な技術やノウハウ、いわゆる「暗黙知」の継承です。eラーニング、特に動画マニュアル作成ツール(例:tebiki)を活用すれば、これらの暗黙知を映像や音声、テキストといった「形式知」としてデジタルデータ化し、プラットフォーム上で共有・蓄積することが可能です。これにより、退職による技術喪失のリスクを大幅に低減し、組織全体として効率的かつ確実に技術・ノウハウを次世代へ継承していく仕組みを構築できます。
コンプライアンス遵守と安全意識の向上
法令遵守や安全確保は、製造業にとって最重要課題の一つです。eラーニングを活用すれば、関連する法律、社内規定、安全作業手順などを、全従業員に対して漏れなく、かつ確実に伝達することができます。理解度を確認するためのテストを実施し、その受講履歴や結果を記録として残すことで、企業としてのコンプライアンス遵守体制や安全教育実施の証明にもなります。定期的な繰り返し教育も容易に行えるため、従業員の意識の維持・向上にも効果的です。
知っておくべきeラーニング導入のデメリットと注意点
一方で、メリットばかりに目を向けるのではなく、導入に伴う可能性のあるデメリットや注意点についても理解し、事前に対策を講じることが成功の鍵となります。
デメリット①:コストと手間
eラーニングシステムや教育ツールの導入には、初期費用や月額(または年額)の利用料が発生します。また、教材を自社で作成する「内製化」の場合は、その作成に時間と労力がかかります。これらの投資に見合う効果が得られるかを慎重に検討する必要があります。
したがって、導入前に、削減できるコスト(研修費用、移動時間など)と導入・運用にかかるコストを比較し、費用対効果を十分に試算することが大切です。また、国や自治体が提供するIT導入補助金などが活用できないかも確認しましょう。
デメリット②:従業員のモチベーション維持
集合研修とは異なり、eラーニングは基本的に個人学習となるため、本人の学習意欲に成果が左右されやすい側面があります。「忙しくてつい後回しにしてしまう」「一人で黙々と続けるのが苦手」といった理由で、学習が進まなくなってしまうケースも少なくありません。
したがって、なぜこの学習が必要なのか、学ぶことで本人にどのようなメリットがあるのか、学習の目的と意義を明確に伝え、動機付けを行うことが重要です。具体的な学習目標の設定を促し、LMSで進捗状況を可視化する、上司が進捗を確認し声かけを行う、学習成果を人事評価の一部に反映する、修了者を表彰するなどのインセンティブ設計も、モチベーション維持に有効です。
デメリット③:コンテンツの陳腐化
一度導入・作成した教材も、技術の進歩、法改正、社内ルールの変更、現場での改善活動などによって、内容が古くなってしまう可能性があります。古い情報のままでは学習効果が得られないばかりか、誤った知識を植え付けてしまうリスクもあります。
したがって、 定期的に教材内容を見直す計画を立て、担当者を明確にしておくことが重要です。特に教材を内製する場合は、現場で変更があった際にすぐに、簡単に更新できるような、メンテナンス性の高いツールを選ぶことがポイントになります。
デメリット④:ITリテラシーの差
従業員の中には、PCやスマートフォンの操作に苦手意識を持っている方もいるかもしれません。操作が複雑だと感じると、それだけで学習への心理的なハードルが高くなり、利用が進まない原因となります。
したがって、導入するシステムやツールは、年齢やITスキルに関わらず、誰でも直感的に使えるシンプルなインターフェースのものを選定することが極めて重要です。導入時には丁寧な操作説明会を実施したり、分かりやすいマニュアルを用意したりするだけでなく、困ったときに気軽に質問できる社内サポート窓口などを設けることも有効です。
これらのデメリットや注意点を事前に理解し、組織として対策を講じることで、導入後の「こんなはずじゃなかった」という失敗を防ぎ、eラーニング・教育ツールを最大限に活用するための土台を築くことができます。
操作が複雑でツールが使われないという失敗を防ぐには、「誰でも直感的に使える」ツール選定が不可欠です。
その思想に基づいて開発された現場教育ツール「tebiki」の概要資料をご用意しました。
【補足】製造業のeラーニングで使える無料の教材
ここでは、教材作成のヒントや従業員の学習コンテンツとして活用できる、無料で視聴可能な専門家のセミナー動画をご紹介します。これらは、私たちTebikiが運営するWebメディア「現場改善ラボ」で公開されており、製造業における重要なテーマを扱っています。
いずれも、eラーニングとして扱える無料教材となっているので、お試しで活用してみてください。
品質管理に関するeラーニング教材
品質管理の基本的な考え方から、QC7つ道具の具体的な使い方、不良品削減に向けたアプローチまで、品質向上に不可欠な知識を動画で学ぶことができます。自社の品質教育コンテンツを作成する際の参考にしたり、従業員の品質意識向上のための学習資料として活用したりできます。
人材育成に関するeラーニング教材
技術継承や多能工化、外国時労働者の即戦力化など、製造現場における人材育成には数多くの課題が存在しています。これらの課題を解消するためのノウハウや実践方法についてまとめられたセミナー動画も、無料で公開されています。現場責任者や管理者候補の方々に向けたeラーニング教材として、活用余地があるでしょう。
安全教育に関するeラーニング教材
労働災害ゼロを目指すために不可欠な安全教育に関するセミナー動画も、無料で公開されています。ヒューマンエラー対策、リスクアセスメントの実施方法、KYT(危険予知訓練)の実践、安全文化の醸成といったテーマを扱っています。
従業員の安全意識を向上させるeラーニング教材として活用できるでしょう。
生産性向上に関するeラーニング教材
ムダをなくし、効率的な生産体制を構築するための具体的な手法を学べます。5S活動の徹底、トヨタ生産方式の基本、リードタイム短縮の考え方などを解説しているセミナー動画が多数あるので、現場改善活動の推進や、改善提案を促すための教育に活用できます。
これらの無料動画リソースも活用しながら、自社の教育コンテンツの充実や、従業員のスキルアップを図ってみてはいかがでしょうか。
まとめ:最適な教育ツールで製造業の現場力を最大化する
本記事では、製造業におけるおすすめのeラーニングを紹介しました。
製造業向けeラーニングの一覧は「【2026年最新】製造業におすすめのeラーニングシステム・教育ツール徹底比較15選」にすべてまとめていますが、製造現場の教育改善におすすめなのは「内製支援型」のツールです。あくまで自社の環境に合った教材を用意することが、質の高い教育につながるからです。
内製支援型のなかでも特におすすめなのは、製造現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。現場従業員がスマホ1つで動画の撮影が可能なので、従業員のリソースを奪わずに教育体制を整備できます。
教育において最重要なのは、「現場を一番知る現場従業員が自ら教育資料を作成すること」であり、現場従業員が動画マニュアルを作成できるよう設計されたtebiki現場教育は教育の質にも寄与します。本ツールが気になる方は以下の画像をクリックして、サービス資料をダウンロードしてみてください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。





