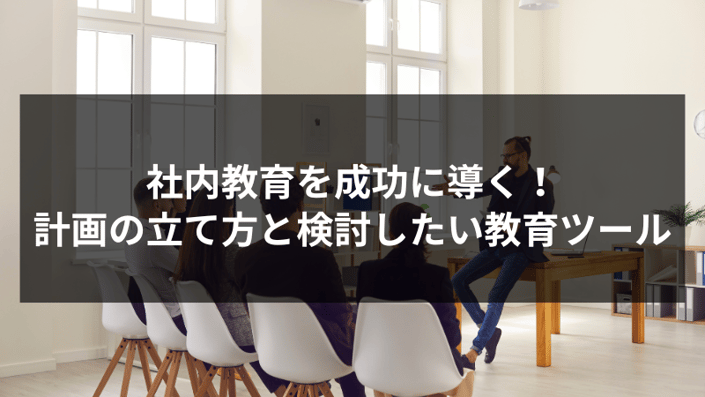

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、tebikiサポートチームです。
社内教育と一口に言っても、「何から手をつければ良いかわからない」「実施しているものの効果が見えない」といった悩みを抱える教育担当者の方は多いです。
この記事では、社内教育の基本的な考え方から、具体的な計画の立て方、効果を高めるためのポイントまでを網羅的に解説します。自社に合った社内教育を設計・実行するためのヒントが満載です。
目次
- 1. 社内教育とは?その目的と重要性を再確認
1-1. 企業が社内教育に取り組むべき理由
1-2. 社内教育の主な目的
2. 社内教育でよくある課題とは?
2-1. 教育担当者が直面する課題
2-2. 受講者側(社員)の課題
3. 社内教育の主な種類と方法一覧
3-1. 階層別研修
3-2. 職種別・テーマ別研修
3-3. OJT (On-the-Job Training)
3-4. Off-JT (Off-the-Job Training)
3-5. 自己啓発支援
4. 社内教育の計画を立てる実践ステップ
4-1. Step1: 現状分析と課題の特定
4-2. Step2: 教育目標の設定
4-3. Step3: 教育プログラムの設計
4-4. Step4: 実施と効果測定
4-5. Step5: 改善とフォローアップ
5. 社内教育の質を高める手段やツール
5-1. 動画マニュアルの活用:現場教育の効率化と標準化を実現
5-2. マイクロラーニング:短時間で効率的に学習
5-3. ゲーミフィケーション:学習意欲を高める工夫
5-4. ブレンデッドラーニング:オンラインとオフラインの融合
5-5. LMS(学習管理システム)の導入
6. 社内教育を成功させるためのポイント
6-1. 経営層のコミットメントを得る
6-2. 教育体系図を作成し、全体像を可視化する
6-3. 受講者のモチベーションを高める工夫
6-4. 現場との連携を強化する
6-5. 教育効果を持続させるためのフォロー体制
7. まとめ
社内教育とは?その目的と重要性を再確認
社内教育とは、企業が従業員に対して、業務遂行に必要な知識、スキル、マインドなどを習得させるために行う教育活動全般を指します。単なる福利厚生ではなく、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現するための重要な経営戦略の一つとして位置づけられています。
変化の激しい現代において、社員一人ひとりの能力向上と組織全体の活性化を図る社内教育の重要性はますます高まっています。
企業が社内教育に取り組むべき理由
企業が社内教育に注力すべき理由は多岐にわたります。弊社が日々の支援活動を通じて目の当たりにしてきた、実際に聞いた声や事例をもとに解説します。
スキルアップによる生産性向上
第一に、社員のスキルアップによる生産性の向上です。業務効率の改善や新たな価値創出に繋がり、企業業績への直接的な貢献が期待できます。
例えば、ある小売業の現場では、社内の教育体制を見直したことでOJTや関連書類作成にかかる工数を大幅に削減したという事例があります。また、別の高度な技術を要する製造現場では、教育プログラムの改善により、人員や労働時間を変えずに特定の工程の生産性を数十パーセント向上させたという報告も受けています。
これらは、効果的な教育が単なる知識習得にとどまらず、現場の生産性という具体的な数値に結びつくことを示しています。
従業員エンゲージメントの強化と離職率の低下
第二に、従業員エンゲージメントの強化と離職率の低下です。学習機会の提供は、社員の「成長したい」という意欲に応え、企業への貢献意欲や仕事への満足感を高めます。自身の成長を実感できる環境は、結果的に人材の定着にも繋がります。
実際に、ある食品製造の現場では、新人スタッフへの教育体制を整備した結果、アルバイトスタッフの離職率が目に見えて低下したという声も聞かれます。適切な教育は、従業員が安心してスキルを習得し、前向きに業務に取り組めるようになるための重要な基盤であり、定着率改善に貢献するケースは少なくありません。
企業文化や理念・コンプライアンス順守意識の浸透
第三に、企業文化や理念、コンプライアンス順守意識の浸透です。研修などを通じて企業が目指す方向性や価値観を共有することは、組織の一体感を醸成します。
特にコンプライアンス順守意識は、従業員の安全を守ることにもつながります。例えば、ある製造現場では、作業手順の標準化と教育の徹底により、品質に関わる重大なヒヤリハットの発生件数を大幅に削減した事例があります。また、別の衛生管理が重要な工場では、標準作業手順書の理解と遵守を促す教育を強化することで、作業の均一化が進み、製品の安全性と品質の向上に繋がったという報告もあります。
これらは、教育がリスクを低減し、企業の信頼性を支える上で欠かせない要素であることを物語っています。
社内教育の主な目的
社内教育の目的は、企業の状況や課題に応じて様々ですが、一般的には以下のようなものが挙げられます。
| 業務遂行能力の向上 | 担当業務に必要な専門知識や技術、スキルを習得させ、パフォーマンスを高める。 |
| 階層別能力開発 | 新入社員、中堅社員、管理職など、それぞれの役割に応じたマネジメント能力やリーダーシップ、専門性を育成する。 |
| コンプライアンス・リスク管理意識の徹底 | 法令遵守や情報セキュリティ、ハラスメント防止など、企業活動に伴うリスクを低減するための知識と意識を向上させる。 |
| 企業理念・ビジョンの浸透 | 企業が大切にする価値観や目指すべき方向性を社員に深く理解させ、行動に繋げる。 |
| キャリア開発支援 | 社員一人ひとりのキャリアプラン実現を支援し、長期的な成長を促す。 |
| 組織風土の醸成 | コミュニケーション活性化、ダイバーシティ推進、イノベーション創出など、目指す組織文化を醸成する。 |
これらの目的を明確に設定することが、効果的な社内教育を計画・実施する上での第一ステップとなります。
社内教育でよくある課題とは?
多くの企業が社内教育の重要性を認識しつつも、その実践においては様々な課題に直面しています。弊社が日々、教育担当者や現場の従業員の方々から直接おうかがいしてきた声をもとに、代表的な課題を「教育担当者」と「従業員」の双方の視点から深掘りしてみましょう。
教育担当者が直面する課題
教育担当者や人事部門は、社内教育の企画・運営において以下のような課題を抱えがちです。
リソース不足
最も頻繁に聞かれるのが、教育に割けるリソースの制約です。限られた予算内で効果的なプログラムを企画・実施することは容易ではありません。
また、特に現場のOJT指導者は、自身の通常業務を抱えながら教育も担当することが多く、「教えたくても時間がない」「教育に専念できる人員がいない」という状況に陥りがちです。結果として、教育が場当たり的になったり、十分なフォローができなかったりするケースが見られます。
人材紹介業を展開する「株式会社GEEKLY」も、新入社員が入社するたびにOJTを実施する教育体制が原因で、本来リソースを費やすべき業務になかなか取り掛かれず同様の課題を抱えていました。同社の課題の詳細や改善までの事例は、以下のインタビュー記事で紹介しているので、あわせてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!
効果測定の難しさ
「教育に投資した結果、具体的にどのような成果があったのか?」を客観的かつ定量的に示すことの難しさも、多くの担当者が抱える悩みです。研修後のアンケートで満足度を測ることはできても、それが実際の行動変容や業績向上にどう結びついたのかを明確に証明するのは困難な場合が多いです。
指標の設定、データの収集、教育と成果の因果関係の特定など、クリアすべきハードルは高く、経営層に対して教育投資の費用対効果を十分に説明できず、予算確保に苦労するという声も少なくありません。
内容の陳腐化への対応と教材作成の負担
事業環境の変化が激しい現代においては、求められるスキルや知識も常にアップデートされます。そのため、一度作成した教育プログラムや教材も、定期的な見直しと改訂が不可欠です。
しかし、その都度、最新の情報を取り入れ、質の高い教材(テキスト、マニュアル、手順書など)を作成・修正する作業は、非常に大きな負担となります。特に、改訂内容を全社・全部署に正確かつ迅速に周知徹底させること、例えば紙媒体の手順書を差し替え・配布・管理する手間に、多くの担当者が頭を悩ませています。
実際に、大手コンビニエンスストアの専用工場を展開する「タマムラデリカ株式会社」は以前、膨大な紙マニュアルの作成工数に加え、作成しても読まれないという課題を抱えていました。同社の課題の詳細や改善までの事例は、以下のインタビュー記事で紹介しているので、あわせてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
マニュアル作成時間が75%削減! 教育体制を強化し、お客様に喜ばれる商品を提供したい
講師・教育の質担保の難しさ
教育の質は、講師のスキルや教材の分かりやすさに大きく左右されます。しかし、社内の特定分野に詳しい従業員が必ずしも「教えるプロ」であるとは限らず、社内講師の育成や質の均一化は大きな課題です。
また、外部講師に依頼する場合も、コストの問題や、自社の実情に完全にマッチする講師を見つけることの難しさがあります。結果的にあまり教育体制が整備できず、「見て覚えてください」式の非効率な指導が続けられたり、新入社員の理解度にバラつきが生じるリスクがあります。
受講者のモチベーション管理
どんなに良い教育プログラムを用意しても、受講者である社員に「学びたい」という意欲がなければ効果は半減します。しかし、社員の学習意欲を引き出し、維持することは容易ではありません。
「なぜこの忙しい中で研修を受けなければならないのか」という疑問や反発を招いたり、研修の意義やメリットを十分に伝えきれなかったりすることに、多くの担当者が苦心しています。単なる義務感による参加では、主体的な学びは期待しにくいのが現実です。
受講者側(社員)の課題
一方で、教育を受ける側の社員も、以下のような課題を感じていることがあります。
学習時間の確保
「学びたい気持ちはあるけれど、時間がない」という悩みはよく聞かれる声です。日々の業務に追われ、研修に参加するための時間を捻出すること自体が困難であったり、業務時間外での自己学習を求められることに負担を感じたりするケースは少なくありません。学習機会が一部の社員に限られてしまい、不公平感に繋がることもあります。
学習内容と実務の乖離
研修で学んだ内容が、実際の自分の仕事とかけ離れている、あるいは抽象的すぎて、どう活かせば良いのか分からないと感じる社員は少なくありません。「研修のための研修」という印象を受けてしまうと、学習意欲は大きく削がれてしまいます。
また、学んだことを職場で実践しようとしても、周囲の理解や協力が得られなかったり、試す機会そのものがなかったりすることも、学習内容が身につかない一因となります。
モチベーションの維持
研修内容そのものに興味を持てない、自分にとっての必要性やメリットを感じられない、あるいは、一方的に話を聞くだけの退屈な講義形式に集中力が続かないといった理由で、学習モチベーションを維持できない社員もいます。
特に、内容が難しすぎたり、逆に簡単すぎたりする場合や、自分のレベルに合っていないと感じる場合に、学習意欲は低下しがちです。「わかる」「できる」という手応えが得られないと、学び続けることは苦痛になります。
学習効果の定着
「研修中は分かったつもりになったけれど、時間が経つと忘れてしまった」「一度教わっただけでは、なかなか覚えられない」というのは、多くの人が経験することです。特に複雑な業務手順や専門知識は、一度学んだだけで完璧に身につけるのは困難です。
しかし、効果的な復習の機会がなかったり、困った時に参照できる分かりやすい資料が手元になかったりすると、せっかく学んだ知識やスキルも定着せず、「学びっぱなし」の状態に陥ってしまいます。現場でのフォロー体制が整っていないことも、定着を妨げる要因となります。
例えば食品スーパーを展開する「株式会社Olympic」では以前、新人スタッフが1人前になるまで何年もかかる状態が続いており、学習内容を効率的に定着させ、1人前になるまでの期間を短くすることが当面の課題でした。
同社の課題の詳細や改善までの事例は、以下のインタビュー記事で紹介しているので、あわせてご覧ください。
▼インタビュー記事▼
違いはOJTの回数です。動画で復習できるようになってものすごく効率化しました。
社内教育の主な種類と方法一覧
社内教育には様々な種類と方法が存在します。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や課題、対象となる社員に合わせて最適な方法を組み合わせることが重要です。
階層別研修
社員の役職やキャリア階層に応じて実施される研修です。それぞれの階層で求められる役割やスキル、マインドセットの育成を目的とします。
| 新入社員研修 | 社会人としての基礎、ビジネスマナー、企業理念、基本的な業務知識などを習得させ、早期戦力化と組織への適応を促します。 |
| 若手・中堅社員研修 | 主体性、問題解決能力、後輩指導力、専門スキルの深化など、組織の中核として活躍するための能力を向上させます。 |
| 管理職研修 | リーダーシップ、チームマネジメント、目標管理、部下育成、人事評価など、管理職としての役割遂行に必要なスキルと知識を育成します。 |
職種別・テーマ別研修
特定の職種に必要な専門スキルや知識を深める研修や、全社員または特定の部門に共通して求められるテーマに関する研修です。
| 職種別研修 | 営業力強化、技術者向け専門講座、マーケティング戦略、人事労務知識など。 |
| テーマ別研修 | コンプライアンス、情報セキュリティ、ハラスメント防止、ダイバーシティ&インクルージョン、DXリテラシー、ロジカルシンキング、コミュニケーションスキル、企業理念の再浸透など。 |
OJT (On-the-Job Training)
職場での実際の業務を通じて、上司や先輩社員が指導役(トレーナー)となり、必要な知識やスキル、仕事の進め方を教える教育方法です。
実務に即したスキルが身につく、教育コストを抑えられるといったメリットがある一方、指導者のスキルや熱意によって教育の質にばらつきが出やすい、体系的な知識を学びにくいといったデメリットもあります。効果的なOJTを実施するには、明確な育成計画、トレーナーへの支援、定期的なフォローアップが必要です。
Off-JT (Off-the-Job Training)
職場や通常の業務から離れて行われる教育方法です。体系的な知識や専門性の高いスキルの習得、あるいは異なる視点や考え方を学ぶ機会を提供します。
集合研修の特徴とメリット・デメリット
特定の場所に受講者を集めて行う研修形式です。講師から直接指導を受けられ、受講者同士の交流やディスカッションを通じて学習を深められる点がメリットです。一体感や連帯感も醸成しやすいでしょう。
一方で、参加者のスケジュール調整、会場費や交通費などのコストがかかる点、場所や時間の制約がある点がデメリットとして挙げられます。近年では、オンラインでの集合研修も増えています。
例えばブライダル事業等を手掛ける「株式会社日本セレモニー」は、新人研修を「Zoom」と「動画」で行っており、集合研修を効率化しながらも質の高い社内教育を実現しています。
▼動画でオンライン研修を実施する様子▼
※動画は「tebiki」で作成されています
ブライダル業や接客業といったサービス業は、動きを伴う業務プロセスが多く、他業界に比べて教育のハードルが高い側面があります。そこを動画で見える化し、映像のマニュアルで教育を行う現場は増えてきています。
動画マニュアルの活用イメージや具体的な推進方法については、資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」で解説されているので、あわせて参考にしてみてください。以下のリンクをクリックすると、ダウンロードできます。
>>>資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」を読んでみる
eラーニングの特徴とメリット・デメリット
PCやスマートフォン、タブレットなどを利用し、オンライン上で学習を進める方法です。時間や場所に縛られずに自分のペースで学習できる、反復学習が容易、教育コストを抑えられるといったメリットがあります。
一方で、受講者のモチベーション維持が課題となりやすい、実技や対面でのコミュニケーションが必要な内容には不向き、学習環境(デバイスやネットワーク)が必要といったデメリットも考慮する必要があります。
外部セミナー・研修の活用
自社だけでは対応が難しい高度な専門知識や最新の技術動向、あるいは社外の視点を取り入れたい場合に、外部機関が提供するセミナーや研修を活用する方法です。
社外の人気講師から学べる、他社社員との交流が刺激になるといったメリットがあります。ただし、内容が自社の現状やニーズに合っているか、慎重に見極める必要があります。
自己啓発支援
社員が自発的に学び、能力開発に取り組むことを支援する制度です。書籍購入費用の補助、資格取得奨励金、外部セミナー参加費の補助、通信教育講座費用の補助などが挙げられます。
社員の学習意欲(モチベーション)を高め、自社の教育体系を補完する役割を果たします。
社内教育の計画を立てる実践ステップ
社内教育の効果を最大化するためには、場当たり的な対応ではなく、戦略に基づいた計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、効果的な社内教育計画を立案するための基本的なステップを解説します。
Step1: 現状分析と課題の特定
まず、自社の現状を正確に把握することから始めます。
経営目標や事業戦略を踏まえ、組織全体や各部門、階層における人材育成上の課題は何かを明確にします。社員アンケート、人事データ(評価、異動、離職率など)の分析、経営層や現場管理職へのヒアリングなどを通じて、現状と理想像とのギャップを特定します。
Step2: 教育目標の設定
特定された課題に基づき、社内教育を通じて何を達成したいのか、具体的な目標を設定します。目標は、「SMARTの原則」に沿って設定すると良いでしょう。
| Specific(具体的) | 誰に、何を、どのレベルまで? |
| Measurable(測定可能) | 効果をどのように測るか? |
| Achievable(達成可能) | 現実的に達成できる目標か? |
| Relevant(関連性) | 経営課題や事業戦略と関連しているか? |
| Time-bound(期限) | いつまでに達成するか? |
明確な目標設定は、プログラム設計の指針となり、効果測定の基準にもなります。
Step3: 教育プログラムの設計
決定した教育目標を達成するために、具体的な教育プログラムを設計します。以下の要素を具体的に検討・決定していきます。
| 対象者 | どの部門の、どの階層の社員か?(新入社員、若手、中堅、管理職など) |
| 学習内容 | 目標達成のために必要な知識、スキル、マインドセットは何か? |
| 実施方法 | OJT、集合研修(対面/オンライン)、eラーニング、外部セミナーなど、最適な方法は何か? |
| 期間・時期 | いつ、どのくらいの期間で実施するか? |
| 講師 | 社内講師か、外部講師か? |
| 教材 | どのような教材(テキスト、資料、動画など)を使用するか? |
| 評価方法 | 学習の理解度や効果をどのように測るか? |
Step4: 実施と効果測定
計画に基づいて教育プログラムを実施します。実施後は、必ず効果測定を行います。効果測定の方法としては、以下のようなものが考えられます。
- 受講者アンケート: 満足度、理解度、内容の有用性など(反応レベル)
- 理解度テスト・レポート: 学習内容の習得度(学習レベル)
- 行動観察・評価: 研修後の行動変容(行動レベル)
- 業績指標の変化: 生産性、品質、顧客満足度など、教育が業績に与えた影響(業績レベル)
教育目標に合わせて適切な測定方法を選び、効果を客観的に評価します。
Step5: 改善とフォローアップ
効果測定の結果を分析し、教育プログラムの内容や実施方法に改善点がないか検討します。受講者のフィードバックも参考に、次回以降の計画に反映させ、継続的にプログラムの質を向上させていくことが重要です。
また、研修で学んだことを現場で活かし、定着させるためのフォローアップも欠かせません。定期的な面談、実践報告会、関連するOJTの機会設定などが考えられます。
社内教育の質を高める手段やツール
従来の社内教育方法に加えて、テクノロジーの進化などを背景に、より効果的で効率的な教育手法やツールが登場しています。これらを上手く取り入れることで、社内教育の質をさらに向上させることができます。
動画マニュアルの活用:現場教育の効率化と標準化を実現
特に製造現場やサービス業などのOJTや、具体的な作業手順の教育において、動画マニュアルは非常に効果的なツールとして注目されています。
文字や静止画だけでは伝わりにくい作業の細かな動き、力加減、タイミングといった「カンコツ」を視覚的に分かりやすく伝えることができます。受講者はスマートフォンなどからいつでもどこでも動画を繰り返し確認できるため、学習効果が高まり、指導者の負担も軽減されます。 さらに、作業手順を標準化しやすく、教育の質を均一化できる点も大きなメリットです。
例えばソフトクリーム総合メーカーの「株式会社日世」は、動画マニュアルの導入により、新入社員研修にかかる時間が従来の1/10に削減されただけでなく、外国人スタッフの理解度テスト正答率が100%になるという目覚ましい効果を上げています。
また、人材紹介事業を手掛ける「株式会社Geekly」では、動画による新人研修で教育工数が大幅に削減され、トレーナーが営業成績向上に時間を割けるようになったという成功事例もあります。
実際にどのような動画マニュアルが業務で使われているのか、具体的なサンプルを見てみたい方は、資料「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(pdf)」が役立ちます。様々な現場の動画サンプルがまとめられており、自社での活用イメージを膨らませるのに最適です。下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
マイクロラーニング:短時間で効率的に学習
マイクロラーニングは、1つのテーマを5分~10分程度の短いコンテンツに分割して提供する学習スタイルです。スマートフォンなどを活用すれば、通勤時間や休憩時間などの隙間時間を使って手軽に学習できます。
多忙な社員でも取り組みやすく、学習内容の定着率向上も期待できる方法として注目されています。
ゲーミフィケーション:学習意欲を高める工夫
ゲーミフィケーションは、学習プロセスにゲームのデザイン要素(ポイント、レベル、ランキング、バッジ、競争など)を取り入れ、受講者の学習意欲(モチベーション)やエンゲージメントを高める手法です。
退屈になりがちな学習も、ゲーム感覚で楽しく取り組めるように工夫することで、より主体的な参加を促し、学習効果を高めることが期待できます。
ブレンデッドラーニング:オンラインとオフラインの融合
ブレンデッドラーニングは、eラーニングなどのオンライン学習と、集合研修などの対面学習(オフライン)のメリットを組み合わせた教育方法です。例えば、基礎知識の習得はeラーニングで行い、集合研修ではディスカッションや実践演習に集中するといった活用が可能です。
それぞれの学習方法の長所を活かし、短所を補い合うことで、より高い学習効果を目指します。
LMS(学習管理システム)の導入
LMS(Learning Management System)は、eラーニングコンテンツの配信、受講者の登録・管理、学習履歴や進捗状況の把握、テストの実施、アンケート収集などを一元的に行えるシステムです。教育担当者の運用負荷を軽減し、学習データの分析を通じて教育プログラムの効果測定や改善に役立てることができます。
多くのLMSが登場しており、自社の目的や規模に合ったシステムを選ぶことが重要です。
社内教育を成功させるためのポイント
効果的な教育計画を立て、注目すべき手法を取り入れたとしても、社内教育を真に成功させるためには、さらに押さえておくべき重要なポイントがいくつかあります。
経営層のコミットメントを得る
社内教育は、単なる人事部門の施策ではなく、企業全体の成長戦略に関わる重要な投資です。経営層がその重要性を理解し、積極的に関与・支援する姿勢を示すことが不可欠です。
経営層からのメッセージ発信や、研修への参加などが、社員のモチベーションを高め、教育への意識を組織全体に浸透させる上で大きな力となります。予算やリソースの確保においても、経営層の理解と協力は欠かせません。
教育体系図を作成し、全体像を可視化する
企業としてどのような人材を育成したいのか、そのためにどのような教育プログラムを、どの階層・職種の社員に、どのタイミングで提供するのかを示した「教育体系図」を作成することが有効です。
これにより、教育施策の全体像が明確になり、社員は自身のキャリアパスと学習の機会を関連付けて理解しやすくなります。計画の網羅性や一貫性のチェックにも役立ちます。
受講者のモチベーションを高める工夫
社員が「受けさせられる」のではなく、「学びたい」と思えるような工夫が重要です。学習内容を人事評価や昇進・昇格、キャリアパスと連動させる、研修成果に応じたインセンティブ(表彰や報奨金など)を用意する、学習コミュニティを形成して学び合いを促進するなど、社員の学習意欲を引き出す仕組みづくりを検討しましょう。
研修内容自体を、現場の課題解決に直結するものにする工夫も効果的です。
現場との連携を強化する
研修(Off-JT)で学んだことを実務(OJT)で活かせなければ、教育効果は半減してしまいます。教育担当者と現場の管理職やOJTトレーナーが密に連携し、教育内容と現場での実践を結びつけることが重要です。研修前に現場のニーズをヒアリングしたり、研修後に現場での実践状況をフォローしたりするなど、連携体制を構築しましょう。
フィードバックを奨励する文化を醸成することも、学習と成長を促進します。
教育効果を持続させるためのフォロー体制
研修は実施して終わりではありません。学習した内容を忘れず、実務で活用し続けるためのフォローアップ体制が教育効果を持続させる鍵となります。定期的な復習セッションの開催、関連するテーマのeラーニング提供、学習内容の実践報告会の実施、上司との面談でのフォローなどが考えられます。
継続的な学習を支援する環境を整えることが大切です。
まとめ
社内教育は、企業の持続的な成長と社員一人ひとりの育成に不可欠な、未来への投資です。その成功のためには、場当たり的な研修ではなく、自社の経営戦略や課題に基づいた明確な目的設定、綿密な計画策定、そして効果的な実施方法の選択が重要となります。
OJTや集合研修といった従来の手法に加え、新しい教育DXツールも積極的に活用し、教育の質と効率を向上させていく視点が求められます。特に、社内教育の効率化や現場作業の標準化、技術伝承、新人教育の効率化といった課題に対しては、動画マニュアルが有力な解決策となり得ます。
動画マニュアルの導入を少しでも検討されている方は、まずは最近の動画マニュアル作成ツールにはどういった機能や実装されているのか、サラッとご覧いただくのが良いと思います。気軽に撮影から編集までできる動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の機能や活用事例は、「 3分で分かる『tebikiサービス資料』」で紹介しているので、参考にしてみてください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。






