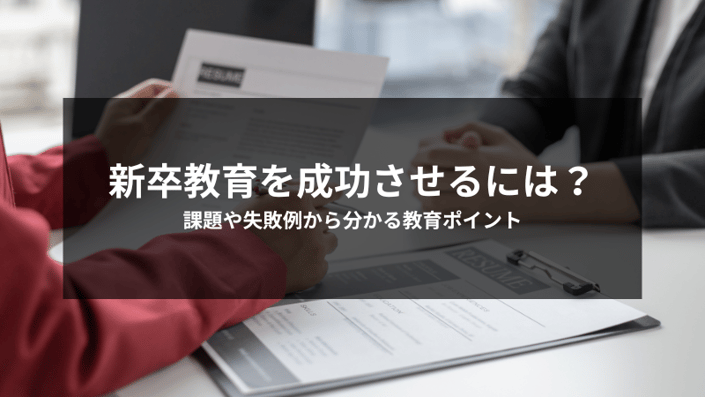

執筆者:tebikiサポートチーム
製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開するTebikiサポートチームです。
新卒教育は、企業の将来を左右する重要な投資ですが、その進め方には多くの課題も存在します。なるべく全員に均等な教育を提供し、均等な成長を促す教育体制を整備するのは非常に難易度が高いです。
そこでこの記事では、新卒教育の基本的な考え方から、現場で直面しがちな課題、効果的な教育手法、そして成功のための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。
目次
- 1.新卒教育でよくある課題と失敗例
1-1. 新卒教育における具体的な課題
1-2. 新卒教育で避けたい失敗例
2.新卒教育の主な手法とその特徴
2-1. OJT(On-the-Job Training):実践を通じた育成
2-2. Off-JT(Off-the-Job Training):職場外での学習
2-3. 手法の組み合わせと計画の重要性
3.新卒教育を進めるために押さえたいポイント
3-1. 明確な教育目標の設定
3-2. 新卒社員の特性理解
3-3. 段階的な教育計画の策定
3-4. OJT担当者の適切な選定と育成
3-5. コミュニケーションの活性化と心理的安全性の確保
3-6. 定期的なフィードバックと評価
3-7. マニュアルやツールの整備・活用
3-8. 多様な教育手法の組み合わせ
3-9. 教育効果の測定と改善
4.新卒教育の課題解決に「動画マニュアル」が選ばれる理由
4-1. 現代の若手人材は「動画」「映像」媒体の情報収集が主流
4-2. 新卒教育における動画マニュアルの具体的なメリット - 5.まとめ
新卒教育でよくある課題と失敗例
多くの企業が新卒教育の重要性を認識している一方で、現場では様々な課題や悩みに直面しています。
ここでは、新卒教育でよく聞かれる具体的な課題と、陥りやすい失敗例について見ていきましょう。これらを把握することが、自社の教育体制を見直す第一歩となります。
新卒教育における具体的な課題
新卒の教育では以下5つの課題がよく挙げられます。
- 教育内容・レベルのばらつき
- OJT担当者の負担が大きい
- 新卒社員のモチベーション維持の難しさ
- 教育体制・計画の不備
- マニュアルや教育資料の形骸化
教育内容・レベルのばらつき
特にOJT(On-the-Job Training)を中心に行っている場合、指導担当者の経験やスキル、あるいは指導への熱意によって、教える内容の深さや質が異なってしまうことがあります。
これにより、新卒社員間で習得する知識やスキルにばらつきが生じるという課題は頻繁に聞かれます。例えば、ステンレス鋼の加工を行う「MSSステンレスセンター株式会社」では、現場でのOJTに頼る中で、教育担当者ごとの教育品質のばらつきが課題となっていました。 このように、指導方法が個々の担当者に依存し、属人化してしまうと、標準的な育成が困難になります。
同社は結果的にマニュアルの整備に成功し、教育品質のばらつき解消を実現しましたが、その詳細な事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
▼インタビュー記事▼
ステンレス鋼の加工業務に動画マニュアルを導入し、現場教育のバラつきを削減
OJT担当者の負担が大きい
OJT担当者は、自身の通常業務と並行して新人の指導にあたることがほとんどです。「日々の業務が忙しく、十分な指導時間を確保できない」「新人指導のための準備に時間がかかる」「そもそも効果的な教え方が分からない」といった負担感は、担当者のモチベーション低下を招き、結果として指導の質の低下に繋がる可能性があります。
実際に、人材紹介業の「株式会社GEEKLY」では、トレーナーが新人教育に多くの時間を割かれ、自身の営業活動にも影響が出てしまうという状況がありました。 教育に時間を取られすぎることで、本来の業務成績に影響が出てしまうケースは少なくありません。
同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
▼インタビュー記事▼
年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!
新卒社員のモチベーション維持の難しさ
入社当初は高い意欲を持っていた新卒社員も、指導が一方的なものになったり、適切なフィードバックが得られなかったり、自身の成長を実感できなかったりすると、徐々にモチベーションが低下してしまうことがあります。
「放置されている」と感じたり、自分が担当する業務の目的や意義が見出せない状況も、働く意欲を削ぐ原因となり得ます。
教育体制・計画の不備
場当たり的なOJTや思いつきの研修になってしまい、体系的な教育計画が存在しない、あるいは計画が策定されていても実際には形骸化してしまっているケースも見られます。
育成すべき目標が曖昧であったり、評価制度と教育内容がうまく連動していなかったりすると、効果的な人材育成は難しくなります。
マニュアルや教育資料の形骸化
新卒教育のためにマニュアルを整備している企業は多いですが、そのマニュアルが十分に活用されていないという声も少なくありません。
例えば、「分厚すぎて読む気が起きない」「情報が古く、実際の業務内容と合っていない」「専門用語が多くて新人には理解しにくい」といった理由が挙げられます。マニュアルの作成や更新作業自体に多大な手間がかかることも、形骸化を招く一因と言えるでしょう。
マニュアルが形骸化してしまう原因と、現場で本当に活きるマニュアル整備の方法については、資料 「作って終わり」にしない!現場で本当に活きるマニュアル整備の教科書で詳しく解説しています。マニュアル活用に課題を感じている方は、下の画像をクリックして資料をダウンロードしてみてください。
新卒教育で避けたい失敗例
上記のような課題を放置すると、新卒教育において以下のような失敗につながる可能性があります。
一方的な知識の詰め込み
座学中心の研修などで、ただ一方的に知識を教え込むだけでは、新卒社員は受け身の姿勢になりがちです。
学んだことを実際に試す機会が少なかったり、自ら考えて行動する場面がなかったりすると、知識はなかなか定着せず、実践的な応用力も身につきません。
放置・受け身のOJT
OJT担当者が自身の業務多忙などを理由に、「まずは見て覚えなさい」「分からないことがあったら質問して」というスタンスで、実質的に新人を放置してしまうケースがあります。
積極的な関与や具体的な指示、そして適切なフィードバックがないOJTは、新人の不安を増大させ、育成効果も薄れてしまいます。
精神論・抽象的な指導
「とにかく頑張れば何とかなる」「気合で乗り切ることが大事だ」といった精神論や、「もっと主体的に考えて行動してほしい」のような抽象的なアドバイスだけでは、新卒社員は何を具体的に改善すれば良いのか理解できません。
行動レベルでの具体的な指導やアドバイスが必要です。
質問しにくい雰囲気
「忙しそうな先輩に話しかけづらい」「こんな初歩的なことを聞いて呆れられないか」といった心理的なハードルが存在すると、新卒社員は疑問点を解消できないまま業務を進めてしまいがちです。
これは、ミスや誤解、学習の遅れにつながる可能性があります。心理的安全性が低い職場環境は、新人の成長を大きく妨げる要因となります。
評価とフィードバックの欠如
自身の頑張りや出した成果が適切に認められなかったり、具体的なフィードバックを得られる機会がなかったりすると、新卒社員は自分の成長を実感することが難しくなり、モチベーションを維持することが困難になります。
定期的な評価と、成長を促すための建設的なフィードバックは、育成において不可欠な要素です。
新卒教育の主な手法とその特徴
新卒教育には様々な手法があります。代表的なものとして、職場内で行うOJTと、職場外で行うOff-JTがあり、それぞれに特徴があります。自社の状況や教育目的に合わせて、これらの手法を理解し、効果的に組み合わせることが重要です。
OJT(On-the-Job Training):実践を通じた育成
OJT(On-the-Job Training)とは、実際の業務が行われている職場で、上司や先輩社員(OJT担当者)が指導役となり、具体的な仕事を通じて新卒社員に必要な知識やスキル、業務の進め方などを直接指導・育成していく手法です。
一般的には、「まず指導者が見本を示す(Show)」、「次にその内容を説明する(Tell)」、「そして新人に実際にやらせてみる(Do)」、「最後にその結果を評価しフィードバックを行う(Check)」という一連のサイクルを繰り返すことが基本とされています。
Off-JT(Off-the-Job Training):職場外での学習
Off-JT(Off-the-Job Training)は、日常の業務が行われている現場(職場)を離れて実施される教育や研修の総称です。
OJTが実際の業務を通じた実践的な学びを重視するのに対し、Off-JTは、業務から一旦離れた環境で、体系的な知識や専門スキル、社会人としての基礎などを集中的に学ぶことを目的としています。
集合研修
新入社員などを一定期間、特定の場所に集めて実施する研修スタイルです。ビジネスマナー、コンプライアンス、自社の理念などを学ぶ目的で実施されることが多く、同期同士の連帯感を醸成する機会にもなります。
eラーニング
パソコンやスマートフォン、タブレットといったデバイスを利用し、インターネットなどを通じて提供されるオンライン教材を用いて学習を進める形式です。時間や場所に縛られずに自分のペースで学習できる点が特徴です。
その他のOff-JT(外部研修、通信教育など)
上記以外にも、特定の専門知識や高度なスキルを習得するために外部の専門機関が開催するセミナーに参加したり、自己学習を促す手段として通信教育プログラムを活用したりする方法もあります。
手法の組み合わせと計画の重要性
OJTとOff-JTは、それぞれに異なる役割を持っています。どちらか一方に偏るのではなく、育成目標や教育内容、新卒社員の状況に応じて、これらの手法を効果的に組み合わせることが極めて重要です。
最も重要なのは、場当たり的に研修を実施するのではなく、明確な育成目標に基づいた年間教育計画を策定し、それぞれの教育手法を計画的に実施していくことです。これにより、体系的かつ効果的な人材育成を実現することができます。
新卒教育を進めるために押さえたいポイント
新卒教育を真に成功させるためには、単に研修プログラムを用意するだけでは不十分です。
育成に関わる様々な要素を総合的に考慮し、計画的に、かつ継続的に取り組む必要があります。ここでは、新卒教育を実現するために大切なことを以下の9つに絞って解説します。
- 明確な教育目標の設定
- 新卒社員の特性理解
- 段階的な教育計画の策定
- OJT担当者の適切な選定と育成
- コミュニケーションの活性化と心理的安全性の確保
- 定期的なフィードバックと評価
- マニュアルやツールの整備・活用
- 多様な教育手法の組み合わせ
- 教育効果の測定と改善
明確な教育目標の設定
まず基本となるのは、「自社としてどのような人材に育てたいのか」という具体的な人物像と、「入社してからどのくらいの期間で、どのレベルのスキルや知識を身につけてほしいのか」という到達目標を明確に設定することです。
目標が具体的であればあるほど、それに応じた教育プログラムの内容や評価基準も具体化しやすくなります。また、この目標は人事部だけでなく、受け入れ部署も含めた組織全体で共有しておくことが、一貫した育成を行う上で重要となります。
新卒社員の特性理解
現代の新卒社員は、幼い頃からインターネットやデジタルデバイスに慣れ親しんだデジタルネイティブ世代であり、情報収集能力が高い一方で、失敗を極度に恐れる傾向や、他者からの承認を強く求める傾向が見られることも指摘されています。
また、時間対効果、いわゆるタイムパフォーマンスを重視する価値観を持つ人も少なくありません。もちろん、こうした傾向を一方的に決めつけてレッテル貼りをするべきではありません。
世代的な背景や価値観を理解しようと努め、一人ひとりの個性を見極めながら、彼らに合ったコミュニケーション方法や指導法を取り入れていく視点が、効果的な育成には不可欠です。
段階的な教育計画の策定
新卒社員に対して、入社直後からいきなり高い目標を設定しても、プレッシャーを感じてしまったり、何から手をつければ良いか分からず戸惑ってしまったりすることがあります。
例えば「入社直後の導入期」「OJTが本格化する基礎習得期」「徐々に独り立ちを目指していく実践期」といったように、成長段階に応じたフェーズを設定し、それぞれの期間で達成すべき具体的な目標と、それに合わせた教育内容を盛り込んだ育成計画を立てることが有効です。
適切な教育計画を立てるには、新入社員のスキル状況の明確な可視化が鍵を握ります。新入社員それぞれのスキル習熟度や理解度に応じて、教育内容も柔軟に変化するような体制が理想的だからです。
スキル可視化の有効手段として「スキルマップ」が挙げられます。以下の画像は、スキルマップの例です。
▼スキルマップのイメージ例▼

【「クラウド型スキルマップ - tebiki現場教育」より抜粋】
こうしたスキルマップは客観的評価の透明性や納得感にも寄与するので、新卒の教育体制を整備するうえで導入を検討したいツールになります。
OJT担当者の適切な選定と育成
OJTの成否は、指導を担当するOJT担当者の質に大きく依存すると言っても過言ではありません。担当者を選定する際には、単に業務遂行能力が高いだけでなく、指導に対する熱意があり、円滑なコミュニケーション能力を備えている社員を選ぶことが理想的です。
しかし、担当者個人の資質だけに頼るのではなく、会社としてOJT担当者の役割や責任範囲を明確に定義し、指導スキル向上のための研修機会を提供するなど、担当者を組織的に支援し、育成していく体制を整えることが極めて重要です。
コミュニケーションの活性化と心理的安全性の確保
新卒社員が安心して業務に取り組み、健やかに成長していくためには、オープンで良好なコミュニケーションと、心理的安全性が確保された職場環境が欠かせません。
日々の報告・連絡・相談をしやすい雰囲気づくりはもちろんのこと、定期的に1on1ミーティングなどを実施し、業務の進捗状況だけでなく、抱えている悩みや不安に耳を傾け、対話する機会を設けることが大切です。
「分からないことは、いつでも、何度でも聞いて良いんだよ」というメッセージを明確に伝え、新人が安心して質問できる環境を意図的に作っていくことが求められます。
定期的なフィードバックと評価
新卒社員の成長を効果的に促す上で、フィードバックは極めて重要な役割を果たします。指導者は、新人の行動に対して、良かった点や改善すべき点を、具体的な事実に基づいてタイムリーに伝えることを心がけましょう。
その際、「頑張りが足りない」といった漠然とした指摘ではなく、「先日の〇〇の場面での△△という行動は、顧客への配慮が感じられてとても良かった」「次は□□という点を意識して取り組んでみると、さらに良くなるだろう」といった、具体的な行動に言及したフィードバックが、本人の気づきと次の行動改善につながります。
また、定期的に面談等を実施し、設定した目標に対する達成度を確認し、次のステップに向けた具体的なアドバイスを行うなど、評価と育成をしっかりと結びつける仕組みを構築することも重要です。
マニュアルやツールの整備・活用
業務の手順や必要な知識を標準化し、誰もが一定の品質で業務を行えるようにするためには、分かりやすいマニュアルの整備が不可欠です。特に新卒社員にとっては、分からないことや忘れてしまったことを自分自身で確認できるマニュアルが存在すると、学習効率が格段に高まり、結果としてOJT担当者の負担軽減にもつながります。
ただし、マニュアルは「作ったが読まれない」「膨大なマニュアルで読む気が起きない」といったデメリットもあります。そうした形骸化が起きないよう、「動画によるマニュアル」は有効手段の1つです。特に接客業や工場、営業活動といった、動きを伴う現場では特に動画マニュアルが教育の効率化に貢献します。
現場教育が動画マニュアルによってかんたんになる理由や活用イメージは、以下の短編マンガ「動画マニュアルで現場の教育をカンタンにする方法」でわかりやすく解説されているので、参考にしてみてください。
多様な教育手法の組み合わせ
育成の効果を最大化するためには、OJTだけに依存するのではなく、集合研修やeラーニング、あるいは読書推奨制度や資格取得支援制度など、利用可能な様々な教育手法を戦略的に組み合わせることが有効です。
それぞれの教育手法が持つメリット・デメリットを正しく理解した上で、設定した教育目標や習得させたい内容、そして対象となる新卒社員の状況に合わせて、最適な組み合わせを検討し、多角的なアプローチで育成を進めていきましょう。
教育効果の測定と改善
実施した教育プログラムや研修が、実際に新卒社員の成長や業務パフォーマンスの向上にどの程度貢献しているのかを、定期的に測定・評価することが極めて重要です。
例えば、研修後のアンケート調査、理解度を確認するテストの実施、配属後の行動観察、OJT担当者や本人へのヒアリングなどを通じて、教育の効果を客観的に検証します。そして、その検証結果をもとに、教育プログラムの内容や手法を継続的に見直し、改善していく、いわゆるPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回していくことが、新卒教育の質を持続的に高めていくための鍵となります。
新卒教育の課題解決に「動画マニュアル」が選ばれる理由
ここまで新卒教育の重要性や手法、成功のポイントを解説してきましたが、多くの企業が抱える「指導のばらつき」「OJT担当者の負担」「マニュアルの形骸化」といった根深い課題を解決する有効な手段として、「動画マニュアル」が挙げられます。
なぜ動画マニュアルが、現代の新卒教育においてこれほど有効視されているのでしょうか。その具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
現代の若手人材は「動画」「映像」媒体の情報収集が主流
スマートフォンでの動画視聴が日常生活の一部となっているデジタルネイティブ世代の新卒社員にとって、動画は非常に馴染み深く、情報をインプットしやすい形式であると言えます。多くの場合、テキストを読み込むよりも、実際の映像と音声で説明される方が、内容を直感的に、かつ短時間で理解しやすいと感じるでしょう。
一方で、従来の主流であった紙媒体のマニュアルは、そのボリュームから読むのに時間がかかったり、文字や静止画だけでは実際の作業の動きや微妙なニュアンスが伝わりにくかったり、さらには情報の更新や配布に手間がかかったりといった課題を抱えていました。
また、口頭での説明も、担当者によって内容に差異が生じたり、一度聞いた内容を正確に記憶しておくことが難しかったりするという側面があります。 動画マニュアルは、こうした従来の教育手法が持っていた弱点を効果的に補い、新卒教育の効果と効率を飛躍的に高める大きな可能性を秘めているのです。
新卒教育における動画マニュアルの具体的なメリット
動画マニュアルを新卒教育のプロセスに積極的に活用することで、企業や教育担当者、そして新卒社員自身にとっても、以下のような多くのメリットが期待できます。
圧倒的な分かりやすさ
動画の最大の強みは、実際の作業手順や機械の操作方法、あるいは顧客対応時の表情や身振り手振りといった細かな所作まで、ありのままを映像として見せられる点にあります。
これにより、テキストや静止画だけでは伝えきることが難しかった複雑な内容や、言語化しにくい「カン・コツ」と呼ばれるような暗黙知も、視覚を通じて直感的かつ具体的に伝えることが可能になります。結果として、新卒社員の理解度が格段に向上することが期待できます。
いつでもどこでも反復学習が可能
一度作成された動画マニュアルは、スマートフォンやタブレット、あるいはパソコンがあれば、時間や場所の制約を受けることなく、いつでも視聴することが可能です。
これにより、新卒社員は、自身の都合の良いタイミングで、理解が曖昧な部分や忘れてしまった箇所を、納得いくまで何度でも繰り返し確認することができます。これは、新人の自律的な学習を促進すると同時に、OJT担当者が何度も同じ内容を説明する手間を省き、指導時間の削減にも大きく貢献します。
教育内容の標準化と均質化
動画マニュアルを用いれば、全ての新卒社員に対して、常に同じ内容、同じ品質の情報を提供することができます。
これにより、OJT担当者の経験やスキル、あるいは指導スタイルによって生じていた教育内容のばらつきを防ぎ、全社あるいは全部署で標準化された、均質なレベルの教育を実施することが可能になります。これは、組織全体のスキルレベルの底上げにも繋がる重要な要素です。
OJT担当者の負担軽減
基本的な業務手順の説明や、新人から頻繁に寄せられる質問への回答などを動画マニュアル化しておくことで、OJT担当者はそれらの対応に費やしていた時間を大幅に削減できます。
その結果、創出された時間を、より個別性の高い指導や、応用的な内容のレクチャー、あるいは新卒社員とのコミュニケーションやメンタルフォローといった、人でなければできない付加価値の高い業務に充てることができるようになります。
例えば、人材紹介事業を展開する「株式会社GEEKLY」では、新人教育の多くを動画マニュアルに置き換えた結果、教育工数が大幅に削減され、年間3,700時間削減された事例もあります。
実際にどのような動画マニュアルが業務で使われているのか、具体的なサンプルを見てみたい方は、下の画像をクリックして「 実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」をダウンロードしてみてください。様々な現場の動画サンプルがまとめられており、自社での活用イメージを膨らませるのに最適です。
外国人社員や多様な人材への対応
特に工場や物流業のようなデスクレス領域では、グローバル化の進展に伴い、外国人社員を採用する企業も増加しています。動画マニュアルは、視覚的な理解を促す「非言語マニュアル」でもあるので、外国人教育にも向いています。言語の壁という大きな障壁を乗り越え、外国人社員に対してもスムーズかつ正確に業務内容やルールを伝えることが可能になります。
外国人社員への教育に動画マニュアルが有効な理由や活用事例について、より詳しく知りたい方は以下の資料をご覧ください。具体的な活用方法や効果がまとめられています。
>>>「外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!」を読んでみる
教育ノウハウの蓄積と技術伝承
熟練社員が長年の経験を通じて体得した高度な技術や、独自のノウハウといったものは、しばしば言語化して伝えることが難しい「暗黙知」となりがちです。動画であれば、実際の作業風景を撮影し、重要なポイントをテロップやナレーションで補足解説することで、こうした貴重な技術やノウハウを、誰にでも分かりやすい形で記録し、組織全体の知識資産として蓄積・共有することができます。
これは、特定の個人に依存しがちな業務の属人化を防ぎ、将来に向けた円滑な技術伝承を実現する上でも、極めて有効な手段となります。
動画マニュアルを活用した技術伝承のポイントについて解説した資料もご用意しています。製造業など、熟練者の技術継承に課題をお持ちの場合に役立ちます。 以下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
動画マニュアル導入で新人教育の効果を高めた企業事例
動画マニュアルは、実際に多くの企業で新卒や新人教育の課題解決に貢献しています。ここでは、現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入して教育効果を高めた2社の事例をご紹介します。
事例1:株式会社日本セレモニー(ブライダル)
同社は、新入社員研修を紙のマニュアルで行うことに限界を感じ、動画マニュアル「tebiki現場教育」を導入。
オンラインMTGツール「Zoom」で動画を画面共有しながら研修する体制を整えており、教育ツールを駆使しています。
▼動画マニュアルを画面共有して教育する様子▼

テキストや紙マニュアルに比べて、動画は飽きにくく、集中力が維持されている様子もうかがえているとのことです。同社が活用している動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の詳細は、以下のリンクからご覧いただけます。どういった機能があり、どういった活用例があるのか気になる方は、あわせて参考にしてみてください。
>>>動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス資料をダウンロードする
事例2:ソニテック株式会社(物流業)
同社はもともと、新入社員には3ヶ月間のマンツーマン指導が必須である教育体制でした。しかし、膨大な教育工数やコストに課題を感じ、動画マニュアルの導入によって「マンツーマン指導をゼロ」にしたのです。
物流業は複雑な業務プロセスが伴うため、特に先輩社員からの直接指導に依存しがちですが、直接指導はお互いの時間が必要になるのでコスト面での課題が大きくなりがちです。そんな教育コストを削減できるのも動画マニュアルの強みと言えます。
これらの事例からも分かるように、動画マニュアルは業種や企業の規模を問わず、新卒・新人教育における様々な課題解決に有効なツールと言えます。
様々な業種・業界での動画マニュアル活用事例をもっと知りたい方は、以下のリンクから、動画マニュアルの活用事例をご覧ください。自社に近い課題を持つ企業の取り組みが参考になります。
まとめ
新卒教育は、単なる初期研修ではなく、企業の未来を担う人材を育成するための極めて重要な投資活動です。その成功のためには、まず教育を通じて何を達成したいのかという目的を明確にし、新卒社員一人ひとりの成長段階に合わせた、計画的かつ体系的な育成プログラムを設計・実行することが不可欠となります。OJTやOff-JTといった従来からの教育手法を効果的に組み合わせることはもちろん、指導担当者の育成、円滑なコミュニケーションの促進、そして適切なフィードバックの提供といった、運用面での細やかな配慮も欠かせません。
そして、多くの企業が直面している教育内容のばらつきや指導者の負担増、あるいはマニュアルの形骸化といった根深い課題に対して、本記事でご紹介した動画マニュアルは、非常に有効な解決策となり得ます。その圧倒的な分かりやすさ、学習効率の向上、教育内容の標準化といった多くのメリットを最大限に活かすことで、新卒教育の質と効果を大きく向上させることが可能です。
現場教育の効率化や動画マニュアルの活用に関心をお持ちの方は、動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料もご覧ください。詳細な機能や活用事例がまとめられているので、自社にどのように活用できるかがイメージしやすくなっています。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。








